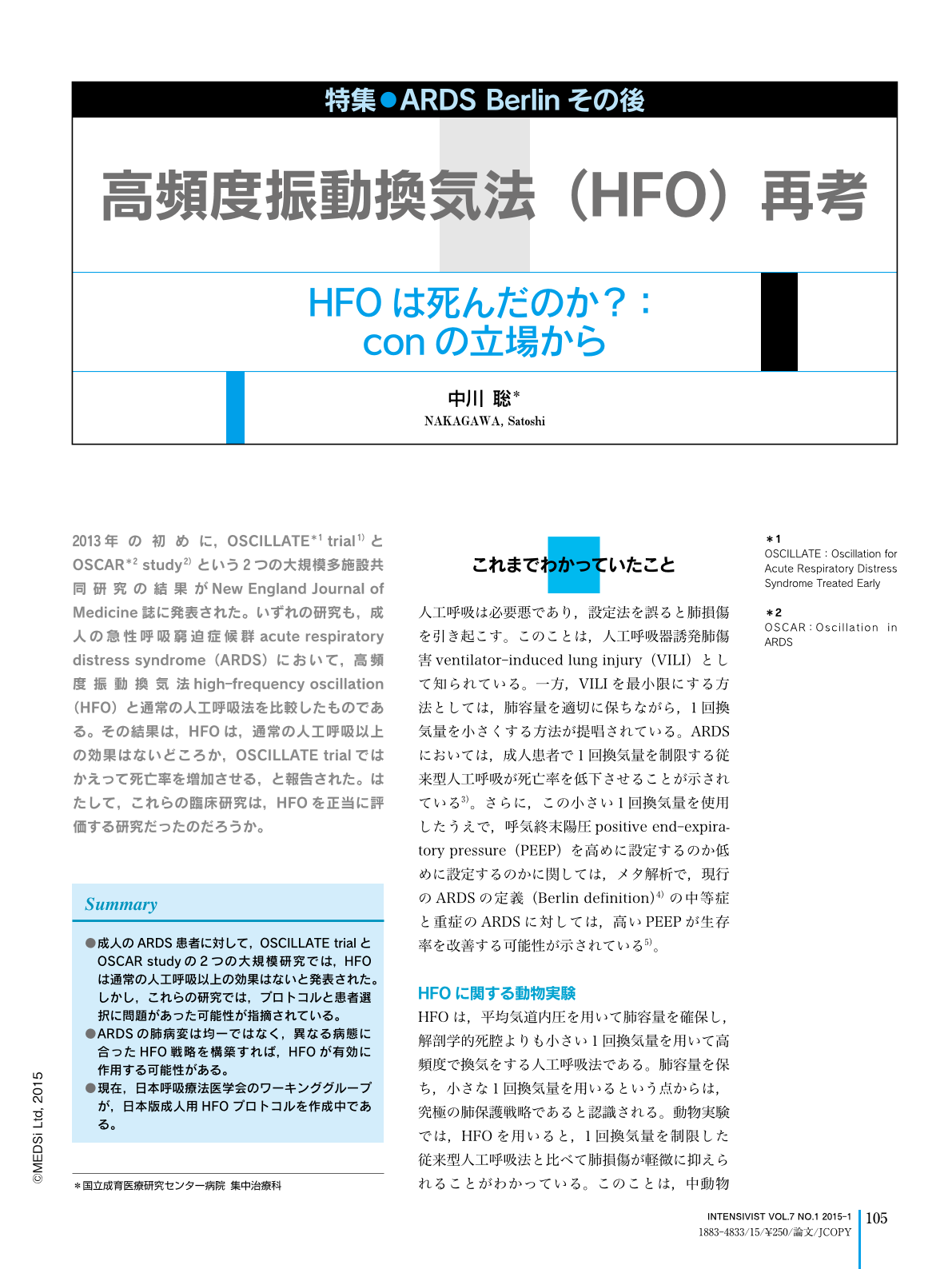5 0 0 0 OA 「地域の教育力」を育てる新しいパートナーシップの形成に関する調査研究
- 著者
- 古市 勝也 中川 聡 ブストス ナサリオ
- 出版者
- 九州共立大学
- 雑誌
- 九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学・生涯学習研究センター紀要 (ISSN:13421034)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.111-128, 2002-03-31
新たな青少年育成のための「地域の教育力」を培うには,地域・家庭・学校において学校を取り巻く人・物・行事等と,どのような方法で連携・融合したらいいか等,新しいパートナーシップの在り方を解明する必要がある。そこで,地域・家庭・学校において「地域の教育力」を育てる新しいパートナーシップ形成のメカニズムを規範意識の獲得の現状から考察してきた。その結果,地域では,「地域行事」や「子ども会等の少年団体活動」等や「子ども会」,「公民館の行事」で,「少年団体の指導者」や「地域のおじさん・おばさん」等から規範意識を獲得していることが浮き彫りにされた。また,家庭では,「家族の団らんの中で」「食事をしながら」「家事や家業の手伝いをしながら」の場面や「お正月」「お盆」「墓参り」「年末の年越し行事」「敬老の日」等の家庭行事で,「父」「母」「兄・姉」「祖母」「祖父」等から規範意識を獲得していることがわかった。さらに,学校では,「道徳の授業で」「学級活動・クラスタイム」「生活指導」の場面や「学年集会・全校集会」「修学旅行」「入学式」等の学校行事で「担任の先生」「同じ学年の友だち」「上の学年の先輩」「クラブ・部活動の先生」等から,規範意識を獲得していることが浮き彫りにされた。これらの地域・家庭・学校の場面・人・行事の組み合わせが「地域の教育力」を育てる新しいパートナーシップ形成の核(要因)になると思われる。
3 0 0 0 OA 小児周産期専門施設における静注アセトアミノフェン過量投与10件の検討
- 著者
- 土金 真人 壷井 伯彦 西村 奈穂 窪田 満 宇田川 恵里子 中舘 尚也 中川 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.547-548, 2021-11-01 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 7
3 0 0 0 OA 二重連結動詞構文についての一考察
- 著者
- 中川 聡
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学校
- 雑誌
- 豊田工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02862603)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.131-142, 2014-01-31 (Released:2017-04-27)
2 0 0 0 OA 関係代名詞を伴う分詞構文の衰退について
- 著者
- 中川 聡
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学校
- 雑誌
- 豊田工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02862603)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.115-124, 2015-01-30 (Released:2017-04-27)
2 0 0 0 IR みかん価格の変動とオレンジの輸入自由化
- 著者
- 中川 聡司 田渕 泰匡 草苅 仁
- 出版者
- 神戸大学農学部農業経済経営研究室
- 雑誌
- 神戸大学農業経済 (ISSN:02860473)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.33-40, 2006-03
1 0 0 0 OA 日本版敗血症診療ガイドライン2016 CQ8 敗血症性ショックに対するステロイド療法
1 0 0 0 国立成育医療研究センターにおける小児肝移植医療
- 著者
- 笠原 群生 阪本 靖介 福田 晃也 藤野 明浩 金森 豊 菱木 知郎 堀川 玲子 野坂 俊介 宮入 烈 鈴木 康之 中川 聡 西村 奈穂 植松 悟子 小野 博 今留 謙一 入江 理恵 義岡 孝子 石黒 精 松本 公一 李 小康 絵野沢 伸 深見 真紀 阿久津 英憲 斎藤 博久 梅澤 明弘 石川 洋一 松谷 弘子 松原 洋一 斉藤 和幸 賀藤 均 五十嵐 隆
- 出版者
- 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 = Japanese journal of National Medical Services : 国立医療学会誌 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.99-104, 2018-03
1 0 0 0 OA タイからドイツへの国際結婚移動 ―移動者および送り出し世帯へのアンケート調査より―
- 著者
- 中川 聡史
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2008年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.309, 2008 (Released:2008-12-25)
タイからドイツへの結婚を目的とした国際人口移動に関して,ドイツでの移動者への調査,送り出し地域であるタイ東北部における送り出し世帯への調査をもとに国際結婚移動の意義と課題を検討する。
1 0 0 0 OA 東京大都市圏における年齢別居住パターンの分析
- 著者
- 中川 聡史
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.34-47, 1990-06-30 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 2
本研究は東京大都市圏における5歳毎の年齢別居住パターンの特徴とその近年の変化を記述し,それらを人口移動に関連づけて説明することを目的とした。分析手法として多変量解析を用いずコーホート分析を利用し,以下の諸点を明らかにした。 5歳毎の14の年齢階級の居住パターンを1960年から1985年まで検討すると,大半が同心円的であり,一般に0~14歳と30~44歳は大都市圏内の外圏において相対的に高い構成比率を示し, 15~29歳と45歳以上は内圏で構成比率が高くなる。 1980年以降はこの傾向に多少変化が見られ, 15~19歳と45~49歳はむしろ外圏で, 30~34歳は内圏で高い構成比率を示すようになった。 2) 東京大都市圏をめぐる人口移動の主要な流れとして,大都市圏外から大都市圏の内圏への10歳代後半から20歳代前半の若者の移動と,大都市圏の内圏から外圏への20歳代後半から30歳代とその子供たちの家族の移動の2つが見いだせた。これらの2つの人口移動が前述の基本的な年齢別居住パターンの傾向を形成している。 3) 応用的なコーホート分析の結果,東京大都市圏では近年,若者全体に占める圏内育ち者の構成比率が急速に上昇していることが明らかになった。その要因として,圏外からの若者の流入数の減少とともに, 1950年代, 60年代に東京大都市圏に大量に流入した人々の子供にあたる世代が1980年頃から10歳代後半に達し始めたことが挙げられる。圏内育ちの若者の近年の居住パターンは,彼らの親世代の郊外への移動を反映して,外圏で高い比率を示す。こうした郊外の成熟が1980年以降にみられる年齢別居住パターンの変化を引き起こしていると考えられ,年齢別のセグリゲーションは少なくとも東京大都市圏の内圏・外圏というレベルでは,今後弱まっていくと予想できる。
1 0 0 0 OA 変容する海外で働く日本人 : 現地採用者に着目して
- 著者
- 丹羽 孝仁 中川 聡史 ティモ・ テーレン
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.205-222, 2016
- 著者
- 中川 聡
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.105-111, 2015-01-01
2013年の初めに,OSCILLATE*1 trial1)とOSCAR*2 study2)という2つの大規模多施設共同研究の結果がNew England Journal of Medicine誌に発表された。いずれの研究も,成人の急性呼吸窮迫症候群 acute respiratory distress syndrome(ARDS)において,高頻度振動換気法high-frequency oscillation(HFO)と通常の人工呼吸法を比較したものである。その結果は,HFOは,通常の人工呼吸以上の効果はないどころか,OSCILLATE trialではかえって死亡率を増加させる,と報告された。はたして,これらの臨床研究は,HFOを正当に評価する研究だったのだろうか。Summary●成人のARDS患者に対して,OSCILLATE trialとOSCAR studyの2つの大規模研究では,HFOは通常の人工呼吸以上の効果はないと発表された。しかし,これらの研究では,プロトコルと患者選択に問題があった可能性が指摘されている。●ARDSの肺病変は均一ではなく,異なる病態に合ったHFO戦略を構築すれば,HFOが有効に作用する可能性がある。●現在,日本呼吸療法医学会のワーキンググループが,日本版成人用HFOプロトコルを作成中である。
1 0 0 0 OA 日本版敗血症診療ガイドライン2016 CQ9 輸血療法
1 0 0 0 OA 日本版敗血症診療ガイドライン2016 CQ6 免疫グロブリン(IVIG)療法
1 0 0 0 OA 21世紀を創造力発揮の舞台に
- 著者
- 中川 聡子
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.2, pp.127-130, 2001-02-01 (Released:2008-04-17)
1 0 0 0 OA 深海底熱水活動域における糖鎖を介した生物間相互作用の分子的解明
本研究は、磁性流体の粘性が外部磁場によって可変となる性質を用いたセミアクティブダンパ構築の可能性について検討を行ったものである。本セミアクティブダンパは、従来の空気圧もしくは油圧タイプのアクティブダンパと異なり、メカニズムは単なる磁性流体封入シリンダ中のピストン運動であるため、一旦制御が破綻してもシステムの安定性が保持でき、また、装置自体が単純な液体封入シリンダと電気設備のみによって構築できるという大きな利点をもつ。ここに本研究の成果および今後の研究課題について以下にまとめる。〈平成8年度〉磁性流体の粘性が、電磁石によって生みだされる磁場に対して可変となる性質をモデル化し、本ダンパを含むシステムの運動方程式を記述した。これが強い非線形システムであることを示し、非線形H無限大制御理論による補償器の設計法を提案、計算機シミュレーションによってその効果を確認した。〈平成9年度〉8年度の研究によって、磁性流体セミアクティブダンパの有効性が確認されたことから、実際に磁性流体セミアクティブダンパを設計・製作した。その後磁性流体の基礎特性を実測し、電磁石電流によって磁性流体粘性がダイナミックに変化することを確認した。〈平成10年度〉種々の振動実験を繰り返す事により、システムモデルの修正を行い、本非線形制御の優位性を確認した。〈今後にむけて〉電磁石の軽量化や、電磁石電流の制御に対して電圧制御から電流制御方式への移行を行い、装置の軽量化や、即応性の改善を行っていきたい。
1 0 0 0 GABA含有はっ酵乳製品の正常高値血圧者に対する降圧効果
- 著者
- 梶本 修身 平田 洋 中川 聡史 梶本 佳孝 早川 和仁 木村 雅行
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 : Nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi = Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.79-86, 2004-02-15
- 被引用文献数
- 13 43
WHO/ISHの血圧の定義・分類で正常高値に該当する者を対象として,FMGのプラセボを対照とした12週間の2重盲検長期摂取試験を実施したところ,以下のことが明らかとなった.<br>被験飲料群では,収縮期血圧が摂取8週間後に有意に低下し,摂取12週間後まで継続して安定した降圧が認められた.また,拡張期血圧は摂取12週間後に有意に低下した.<br>試験期間中,血液および尿検査値の異常はみられず,また,診察所見および自覚的所見において,被験飲料摂取によると思われる重篤な副次的作用は認められなかった.<br>したがって,FMGは,正常高値血圧者に対して,収縮期血圧および拡張期血圧の降下作用を有し,かつ高い安全性を有することが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 二相性の経過をたどる小児急性脳症の検討
- 著者
- 榎本 有希 六車 崇 久保田 雅也 中川 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.10, pp.828-834, 2010-10-15 (Released:2010-12-04)
- 参考文献数
- 11
目的:小児二相性脳症の臨床経過とその特徴を明らかにし,二相目の発症前における単相性脳症との鑑別の可能性について検討する。対象・方法:2007年4月から2009年8月の間に国立成育医療研究センター集中治療室に痙攣・意識障害で入室した患者について,診療録を後方視的に検討した。単相性脳症群26例と,てんかん・熱性痙攣群 10例を対照群として,第3病日までのlactate dehydrogenase(LDH),fibrin/fibrinogen degradation products(FDP),Dダイマーの最大値を各群間で比較した。結果:脳症と診断された患者は36症例で,そのうち二相性脳症は10例(28%)であった。痙攣重積で発症した脳症22症例中,二相性脳症は8例(36%)で,一相目の痙攣が重積した症例が8例,重積しなかった症例が2例だった。二相目発症の中央値は第5病日(最小第4病日-最大第8病日)だった。ステロイドパルス療法,低体温療法,頭蓋内圧センサー挿入下の脳圧管理などが施行された。10症例中2例で一相目から積極的な治療を施行したが,二相目の発症を予防できなかった。転帰は全例生存で,後遺症なし 1例,軽度の神経障害 5例,重度神経障害 4例であった。 LDHの最大値はてんかん・熱性痙攣と単相性脳症,二相性脳症との間で有意差がみられた(p=0.017,0.002)。FDP,Dダイマーの最大値はてんかん・熱性痙攣と二相性脳症との間に有意差がみられた( p=0.018,p=0.033)が,いずれのマーカーも単相性脳症と二相性脳症の間に有意差は認められなかった。結語:小児では痙攣後,一過性の症状改善の後に再度痙攣や意識障害を来す転帰不良な疾患群が存在する。発生頻度が少なくないにもかかわらず,その発症予測は現時点では不可能である。小児の痙攣後には神経学的症状が軽度であっても二相目発症の可能性を視野に入れた管理が必要である。