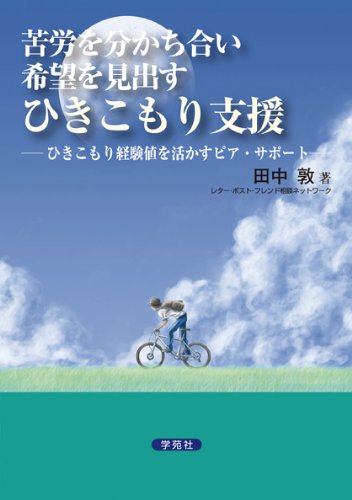- 著者
- 水野 孝彦
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ベンチャ- (ISSN:02896516)
- 巻号頁・発行日
- no.246, pp.132-135, 2005-03
「鍵の専門店」を全国展開したカリスマ経営者は、加盟店向けの債務保証に足を取られた。数値管理を「苦手」と敬遠した"逃げ"の経営が、致命的な判断ミスを生んだ。
1 0 0 0 サイトカインシステムにおけるシグナル伝達と遺伝子発現機構の解析
サイトカイン系におけるシグナル伝達の機構を解析するため、インタ-ロイキンー2(ILー2)系をモデルとして抱え、昨年度にはすでにILー2受容体β鎖の構造解明を行ったが本年度は更にこのβ鎖の下流に位置し、β鎖と共役するシグナル伝達分子の存在について解析を行った。その結果、ILー2受容体β鎖と相互作用を持つ分子としてリンパ球に特異的に発現するsrcファミリ-チロシンキナ-ゼであるp56^<eck>を同定することに成功した。更にβ鎖とp56^<eck>分子の相互作用に必要な領域を両分子において同定することにcDNA発現法を用いることによって成功した。またILー2刺激によってp56^<eck>のチロシンキナ-ゼ活性が上昇することも明らかにした。サイトカインの遺伝子発現機構の解析をインタ-フェロン系において推進した。すでにこの系を制御する転写調節因子IRFー1、IRFー2を同定、構造解明に成功しているが本年度はEC細胞へのcDNA導入実験によってIRFー1がインタ-フェロン遺伝子やインタ-フェロン誘導遺伝子の転写活性化因子としてIRFー2が抑制因子として機能することを明らかにした。
1 0 0 0 仲原善忠と沖縄史研究 : 郷土から生まれる歴史観
- 著者
- 並松 信久
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.239-278, 2014-03
1 0 0 0 東アジアにおける戦争記憶の保存と表象
本共同研究では、2003(平成15)年度から2005(平成17)年度までの3ヵ年の研究期間において、東アジアにおける戦争記憶の保存と表象のあり方に関して、歴史学を中心軸にしながら博物館学・植民地教育史学・言語学・哲学などの学術的視点をも援用し学際的かつ総合的な解明を行なった。特に調査研究の遂行にあたっては、日本のみならず中国・韓国・沖縄の研究者とともに行う国際的な研究体制を堅持した。研究期間内に、中国・韓国・沖縄・日本における戦争博物館・戦争遺跡の調査・研究を各年度の計画に基づいて実施したが、全体として、海外実地調査を5回、国内実地調査を6回、国内研究会を4回、海外での研究報告を3回、海外(中国・重慶)での特別講演会を1回実施することができた。その結果、これまで日本国内では、その存在さえも十分に認知されていなかった戦争遺跡等のいくつかを調査することができ、現地研究者との研究・情報交流を踏まえて、各地域における戦争記憶が、遺跡や博物館という形を取りながらどのように保存され、表象されているのか、またどのような歴史的背景存在するのかなどを具体的に解明することができた。また本研究成果の特色として、中国・韓国など海外、また沖縄などにおいて、日本が起こした近代以降の侵略戦争による加害・被害の史実認識、歴史認識共有化を目的とした現地研究者との学術研究交流を活発に実施したことをあげることができる。戦争記憶に関する歴史認識共有は今後の東アジアにとって極めて重要な課題であり、平和実現への欠かすことのできないステップでもある。研究代表者および分担者・協力者は、その目的達成のため、研究期間内での諸議論を踏まえて、本共同研究の研究成果発表の一環として、君塚仁彦編著『平和概念の再検討と戦争遺跡』(明石書店、2006年)を上梓し、その成果をより広く共有されるようにした。
1 0 0 0 OA 企業社会の変化と家族
- 著者
- 木本 喜美子
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.27-40, 2000-07-31 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 3 6 2
本稿は、戦後日本の家族と企業社会との関係を「家族賃金」という概念から分析することにある。日本において性別分業を組み込んだ〈近代家族〉モデルは、終身雇用、年功賃金、企業福祉を柱とする日本的経営のもとで、強固な基盤が据えられた。とくに「生活給」賃金思想に支えられた大企業の労働者家族は、物質的生活基盤とひきかえに、夫を競争的な「企業内人生」へと駆り立てていった。「減量経営」を経た1970年代以降こうした動向は明確化し、家族と企業社会とは強い絆で結ばれるところとなった。だが同時に1970年代以降のスクラップ・アンド・ビルドの進展のもとで地域間移動をともなう配置転換、出向等が多発するなかで、家族の側から「家族帯同」を拒否する傾向が強く現れ、1980年代以降単身赴任が社会現象として注目されるにいたった。物質優先主義が、「家族成員相互の情緒的関係」を欠いた〈近代家族〉の中心軸になっており、この傾向は1990年代にも基本的にひきつがれている。
1 0 0 0 壁の白とページの白--ウィーン分離派館と『ヴェル・サクルム』
- 著者
- 浅井 麻帆
- 出版者
- オ-ストリア文学研究会
- 雑誌
- オ-ストリア文学 (ISSN:09123539)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.18-28, 2009
- 著者
- 中河 隆仁 森 友則 朝香 卓也 高橋 達郎
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. NS, ネットワークシステム (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.457, pp.411-416, 2009-02-24
- 被引用文献数
- 3
Unstructured型P2Pネットワークにおいて,コンテンツごとに人気度が異なり,コンテンツのリクエスト数分布やコンテンツのネットワーク上の存在数分布がべき乗側に近い性質を持っていることが報告されている.これにより,フラッディングを用いてコンテンツの検索を行うと,人気度の高いコンテンツは発見しやすいが,人気度の低いコンテンツは発見しにくいという問題がある.さらに,人気度の高いコンテンツを検索する際に無駄なメッセージが多く発生するという問題が生じる.そこで,本稿では,コンテンツの人気度に応じて検索時のTTL(Time To Live)を制御する方式を提案する.本方式では,コンテンツの人気度を過去にそのコンテンツを検索したメッセージが通過した回数で計算し,人気度の高いコンテンツを検索する際には,TTLを小さく設定し,人気度の低いコンテンツを検索する際には,TTLを大きく設定する.これにより,人気度の高いコンテンツを検索する際に,高いヒット率を維持しながら無駄なメッセージが減少し,かつ人気度の低いコンテンツのヒット率が向上する.結果として,P2Pネットワーク全体で高いヒット率を維持させながら,メッセージ数を減少させる効果が期待できる.また,本稿では,シミュレーションによる評価を行い,提案方式の有効性を示す.
1 0 0 0 OA 江戸八景 愛宕山の秋の月
1 0 0 0 IR 前近代における広島湾頭地域の開発とその進行(前)
- 著者
- 東 晧傳
- 出版者
- 広島修道大学
- 雑誌
- 修道商学 (ISSN:03875083)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.1-28, 2003-02-28
1 0 0 0 喜多源逸と京都学派の形成
- 著者
- 古川 安
- 出版者
- 化学史学会
- 雑誌
- 化学史研究 (ISSN:03869512)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.1-17, 2010-03-15
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 乾 善彦
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.59-65, 2007
1 0 0 0 アレルギー性気道炎症における気道温度の測定とモニタリングの開発
気管支喘息に代表されるアレルギー性疾患は,アレルギー性炎症疾患として捉えられている.古典的な炎症の定義から考察するとアレルギー性炎症として「発熱」という現象に対する検討はまだされていない.そこで,気道炎症の「発熱」を呼気温度の測定にて捉え得るのではないかと着目し,基礎的検討を行った.フローボリウム測定と瞬時に温度変化を捉えられる高感度温度計を組み合わせ,はじめに安定した測定条件の検討を行った.最大吸気から呼出までの条件,最大呼気条件による呼気測定の温度センサーの位置をマウスピースの中央,マウスピースより咽頭側,鼻マスクで検討を行った.この結果最大吸気後ゆっくりとゆっくり呼出させる方法で,温度センサーをマウスピースを咽頭側で測定した際,最も安定した測定値が得られた.次に単位面積当たりの熱エネルギー量(W/cm^2)を表す呼気熱流速と呼気温度のピーク値の体温補正値(呼気温度測定値と体温の比で表したもの)を健常者の各条件で比較した.その結果,呼気熱流速は呼気温度に比べて温度変化に敏感な値を示した.さらに呼気温度のピーク値は性別や喫煙の有無で差が認められたが,熱流速には差を認めなかった.呼気温度と呼気熱流速の両方を用いることで気道炎症の新しい指標になりうると考えられた.
1 0 0 0 OA ヒノキ林化した都市近郊二次林における小面積伐採後初期の木本種組成の変化
- 著者
- 今西 亜友美 柴田 昌三 今西 純一 寺井 厚海 中西 麻美 境 慎二朗 大澤 直哉 森本 幸裕
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.641-648, 2008 (Released:2009-11-30)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1 1
ヒノキ林化した都市近郊二次林をアカマツまたは落葉広葉樹主体の林相に転換させることを目的として,母樹を残した小面積 (0.06~0.09 ha) の伐採を行った。3 つの伐採区 (上部,中部,下部) のいずれにおいても伐採後に消失した種はなく,伐採後3 年目には10 種以上の種数の増加が確認された。中でも,落葉広葉樹林の主要構成要素を含むブナクラスの種が上部と中部では6 種,下部では4 種増加し,林相転換に一定の効果が得られたと考えられた。前生稚樹は伐採後にほとんどの個体が枯死し,伐採後の林相には大きく寄与していなかった。散布種子についてはその大部分がヒノキで占められており,風散布種であるヒノキはプロット内に多量の種子を散布することで伐採後の林相に大きな影響を与えると考えられた。また,伐採後3 年目には新たな種の出現がほとんどみられなかったことから,林相が単純なヒノキ林では周囲からの新たな種の供給は少ないと考えられた。伐採面積の最も大きかった上部の伐採区 (0.09 ha) では,相対日射量が60% 以上あり,ヒノキの発芽と生存率が抑制されたと考えられ,アカマツとヒノキの混交する林相への転換が期待された。一方,中部と下部の伐採区では,全実生個体数のうちヒノキが50% 以上を占めており,今後,選択的除去などの人為的な管理が必要であると考えられた。
1 0 0 0 OA 人口分布特性によるメガシティの類型化に関する研究
- 著者
- 内山 愉太 岡部 明子
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.883-888, 2011-10-25 (Released:2011-11-01)
- 参考文献数
- 13
一般にメガシティは人口規模によって定義されるが、人口規模は都市の一属性にすぎない。既往の研究において、人口規模が同規模のメガシティであっても、抱える問題は大きく異なることが示されている。それには、人口規模以外に多様な要因が考えられるが、都市が空間的な広がりを持っていることと関係があると思われる。メガシティの異なる空間特性を客観的に把握し、メガシティを空間特性により類型化することは、各都市の特性を把握し、その抱える問題や潜在的な可能性を考察する上で有用であると考えられる。本研究では、空間的な人口分布が都市の空間特性を一定程度示していると考え、人口分布特性によりメガシティの類型化を行った。その結果、対象35都市について、人口の特定の人口密度の地域への偏在傾向に関して四類型化でき、人口密度の異なる地域の空間的分布状況によっても四類型化できることがわかった。特に、最も複雑な人口分布特性を持つメガシティがアジアに集中していることが明らかとなった。各都市の空間特性を生かした将来に向けた再編を検討するにあたり、本研究の空間特性によるメガシティ類型を活用できると考えられる。
1 0 0 0 OA 簡易柔術実用形 : 附・活法銃丸除
- 著者
- 山本柳道斎 (正道) 著
- 出版者
- 藤谷崇文館
- 巻号頁・発行日
- 1907
1 0 0 0 OA 墓制の変遷からみた家族とコミュニティの変容に関する研究
本研究は省エネルギーを前提として国連が計画中の、国際植物遺伝子銀行設立に際してコンサルタントを依頼され、それを実現に導くための基礎的な種子の貯蔵条件を解明するために実施された。その結果、遺伝資源としての植物種子の長期間に亙る貯蔵を、永久凍土の年平均-3.5℃で行うためには、従来各国で採用されてきた方法を適用することは妥当ではなく、種子の劣化を招く主要因となっている水分と代謝生産物であるカルボニル化合物を除去することが必要なことが判明した。そのための最も簡便な方法として、定期的な真空脱気法の導入が望ましいことが明かになった。ただ、残念ながらこの場合には完全なエネルギーコスト消減は不可能ということになり、初期の目的には沿わないことになる。また、施設費も相当嵩むことになることから、相当長期に亙る運用を前提とした経済的な検討が、実際に建設に踏み切る場合にはなされる必要がある。ただ、そうだとしても、将来の化石燃料枯渇の時代を予測するならば、本計画は実行に移されるべき性質のものと私は判断する。幸運なことに、本研究の過程で、種子の老化機構についての実体が解明され、種子の貯蔵湿度に対応して二種類の劣化の道が作動することが判明した。一つは、高い湿度下でのみ進む補酵素群の消耗、ミトコンドリア発達能の低下によるものであり、通常採用されている乾燥種子の保存の場合には殆ど問題とはならないと思われる。二つめの種子老化の仕組は種子自らが貯蔵期間中に生成・放出するカルボニル化合物、主としてアセトアルデヒドと種子中の機能蛋白質のアミノ基との間でシッフ反応の結果、蛋白質の変成を来して老化する機構であり、この反応率も高湿度下で高いものの前者とは違って、通常用いられる低湿度下でも進行するものである。後者の仕組みは植物の老化に一般的に当てはまるものと推定され植物の老化の研究に新たな展望を与えることになった。