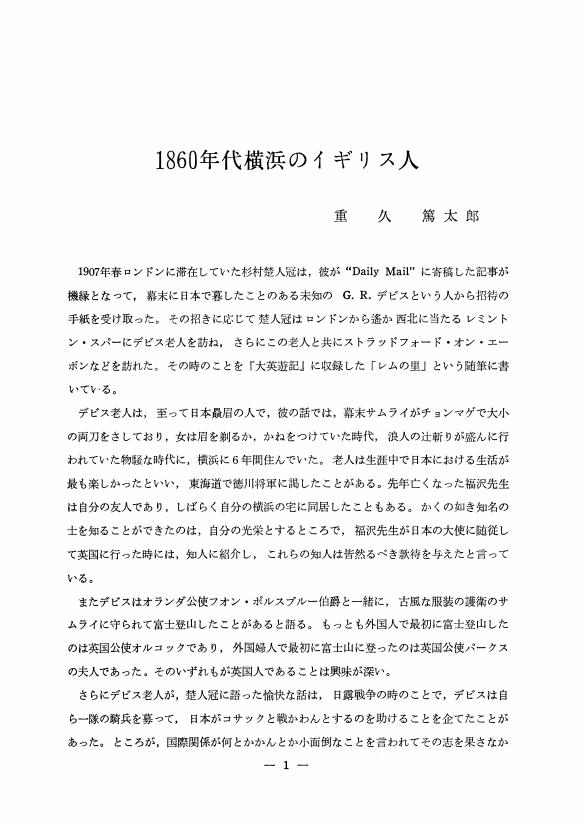1 0 0 0 OA 胎生期環境と生活習慣病発症機序
- 著者
- 福岡 秀興
- 出版者
- 日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.37-40, 2016 (Released:2016-01-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3
Worldwide, lifestyle-related diseases such as type 2 diabetes and cardiovascular diseases are presently the leading causes of death and disability, and their incidences tend to increase. A lifestyle-related disease has been considered mainly to be induced by specific disease susceptibility genes and lifestyle after birth. However, the steep increase in the incidences of lifestyle-related diseases is difficult to be explained only by specific genes. Presently, a new theory has been proposed. Epidemiological and animal studies have disclosed the intimate links between malnutrition in the developmental stage and lifestyle-related chronic diseases. Such studies provide the foundation and framework for a new life science, that is, the theory of developmental origins of health and diseases (DOHaD). Although much research has been carried out to elucidate the putative concepts and mechanisms that relate specific exposures in early life to the risk of chronic diseases, a complete picture still remains obscure. Historically, the world has experienced severe famines, for example, the Dutch Winter Famine, the Chinese Great Leap Forward Famine, the Leningrad Siege and the Biafran Famine. These famines showed that malnutrition in utero poses higher risks of lifestyle-related diseases. The main research point has been focused on periconceptional and perinatal undernutrition and specific nutrient deficiencies. However, presently, the number of people who are overweight and obese has been increasing. Therefore, perinatal overnutrition and specific nutrient excesses should also be examined. In addition, psychological stress, environmental chemicals and artificial reproductive techniques are other important research fields in DOHaD.
1 0 0 0 OA 実験的鞭打ち損傷の研究(III)
- 著者
- 瀧川 勝雄 国分 信彦 梶原 大義 土肥 美恵 田原 溶夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.489-493, 1972 (Released:2010-07-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 15 15
Using rabbits and rats injured in experimental Whiplash, changes in glycolysis and enzyme activities of the cervical cords, and the effects of Pantui extracts, Pantocrin were investigated in detail. In the cervical cords, depressed glycolysis and lowered activities of aldolase, GOT, and alkaline phosphatase were noted. Cervical injuries were greater in rats than rabbits while hexokinase, glycerokinase and GPT were inhibited. Three enzymes in the rabbits were also inhibited. This enzymological difference between the two species appeared to be dependent on the extent of injury. Pantocrin remarkably improved abnormal glycolysis and the lowered enzyme activities of cervical cords from both injured animals.
1 0 0 0 OA 実験的鞭打ち損傷の研究(II)
- 著者
- 瀧川 勝雄 国分 信彦 田原 溶夫 土肥 美恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.473-488, 1972 (Released:2010-07-30)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 4 4
Physical, morphological and pharmacological studies of an experimental Whiplash Injury were done, using rabbits, to elucidate the injury mechanism and the effects of Pantui extracts, Pantocrin, on the injury. A device of rotary type, which is capable of producing concentrated exterior force effectively to the cervical region, was used to simulate experimental Whiplash Injury. The injured caput and cervical regions were physically, roentgenologically and pathologically examined and the requirement for producing Whiplash Injury of no serious damage was established, i.e., acceleration of 20G to the device and a weight of 300g an the rabbit head. In addition, a new method for optokinetic stimulation was employed to study nystagmus reactions on injured rabbits. Abnormally exaggerated patterns and lowered frequencies in the ENG were noted 3 to 21 days after the injury accompanying depressed glycolysis in cerebrospinal regions. Pantocrin, administered to the injured rabbits at an intramuscular dose of 1ml (ca. 1.5mg as a dry wt.) per kg daily from the 3rd to 21st day after injury, was markedly effective for improving the abnormalities in both ENG patterns and cerebrospinal glycolysis.
1 0 0 0 OA 大学生におけるペットとペットロスに関する意識調査
- 著者
- 得丸 定子 川島 名美子
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集 第48回日本家庭科教育学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.36, 2005 (Released:2006-01-13)
【目的】ペットロスは正常な適応反応であるが、飼い主が受けるストレスは様々で、情緒的・身体的症状が現れることもある。日本ではペットロスに関する一般の理解はあまり進んでおらず、文献や研究論文等も少ない。ペットロス・ケアに関しても、欧米諸国の知識や方法を直訳的に取り入れている現状である。 そこで本研究では、個人の性格・価値観・ペットの飼育経験等の観点から、ペットへの接し方・ペットロスの諸症状・対処法等について分析し、日本人の感性に合ったペットロス・ケアや学校教育における「いのち教育」の取り組みに資することを目的とした。【方法】本調査『ペットとペットを失うことに関するアンケート』(無記名、自記式)は、2004年4月_から_同年6月に実施した。調査対象は、新潟県・群馬県・千葉県・大阪府から各1大学、合計4大学679名である。調査内容は、「心理尺度に関するもの」82項目を中心に、「属性と信仰している宗教の有無に関するもの」「ペットの飼育経験に関するもの」「ペットの位置づけ・価値観に関するもの」「ペットを失った時の状況と対応に関するもの」の、計116項目と自由記述である。分析は因子分析(主成分分析、バリマックス回転)、分散分析、多重比較、比率の差の検定、KJ法を行った。 【結果・考察】1.因子分析結果心理尺度に関する質問項目について因子分析を行い、8因子を抽出。各因子名は第1因子“抑うつ型”、第2因子“協調・努力型”、第3因子“理解・共感型”、第4因子“自信型”、第5因子“宗教肯定型”、第6因子“情緒型”、第7因子“個性尊重型”、第8因子“内向型”とした。2.因子とペットロスとの検討各因子により、ペットの位置づけ・価値観、ペットロス時の心身の状況、対処法の違いが明らかになり、心理傾向により、具体的なペットロスへの対処法の手がかりが示された。3.「性別」「宗教」「飼育経験」とペット・ペットロスとの検討“性別”では、女性の方が男性よりも情緒的なペットロス反応を示した。ジェンダーバイアス的な価値観や子育てが影響し、感情を認めたり表出したりする段階で男女差が生じているものと考えられる。“信仰心”では、信仰心の高い人はペットロス時に悲嘆が身体症状として表れたり、他に傾聴を求めたり、ペットの安楽死反対論が示された。 “ペットの飼育経験の有無”では、飼育経験がある者の方が、ない者よりもペットを「守るべき存在」、「心の安らぎ」と捉えていた。これらの結果は、ペットの飼育を実際に経験することが、ペットの存在感を認識させることを示している。“ペットの喪失経験の有無”では、ペット喪失経験により「後悔」を覚え、ペットが自分にとって「心の安らぐ大切な存在」であったことに気付き、「守るべき存在」であると認識していることが示された。また、ペットの喪失経験者の方が未経験者よりも代わりのペットを欲している結果が示されたが、「代わりが欲しい」とは、なくしたペットと外見や習性などが同じ代替のものではなく、ペットという存在や、そこから得られる安らぎが欲しいと感じているものと考えられる。 以上の結果は、日常生活で死別経験が乏しくなっている現在の子どもにとって、ペット飼育や死別で経験する出来事、心理体験は「いのち」の重さを実感できる重要な教育内容を持つことを示している。4.自由記述の検討ペットを亡くした時の感情については「悲しみ」や「怒り」などの情緒的反応が回答の約半数を占めた。次に否定的反応が多く、内容は後悔と罪悪感の反応が大部分であった。ペットを亡くした悲しみから立ち直ったきっかけについては「時間の経過」が最も多かった。
1 0 0 0 OA アメリカの大学生におけるペットロス意識調査
- 著者
- 得丸 定子 川島 名美子
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集 第49回日本家庭科教育学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.10, 2006 (Released:2007-02-11)
【目的】 近年ペットロスという用語は一般化してきたが、わが国における学術研究論文数は一桁以内でまだ少ない。欧米では1984年から学術論文が発表されているが、ほとんどが米国の学術誌である。ゆえに、本研究では昨年本研究大会で発表した日本の大学生対象の調査項目と同一の調査を米国中西部の大学生を対象に行い、「いのち教育」を実践するための資料を得ることを目的とした。 【方法】 アイオワ大学の共同研究者の多大な援助を得て、調査「Questionnaire Concerning Pet and Pet Loss」を、2004年3月~同年6月にかけて、アイオワ州の3大学、ミズーリ州1大学の合計4大学の学生194名(有効回答率78.4%)対象に実施した。調査内容は「心理尺度に関するもの」82項目を中心に、「属性、信仰する宗教とその有無」「ペットの飼育経験」「ペットの位置づけ・価値観」「ペット喪失時の状況と対応」の計116項目と自由記述である。分析は因子分析(主成分分析、バリマックス回転)、分散分析、多重比較、比率の差の検定、KJ法を行った。 【結果】 1.因子分析結果 心理尺度に関する質問項目について因子分析を行い5因子抽出された。因子名は第1因子”自尊・自信型“、第2因子”努力・前進型“、第3因子”共感・協力型”、第4因子”抑うつ型“、第5因子”宗教肯定型”とした。 2.因子とペットロスの関連性の検討 心理傾向を表す上記5因子を高群と低群にわけ、それらの高低群と「ペットの位置づけ・価値観」「ペットを失った時の状況」「ペットを失ったときの自分自身の対処法」とを多重比較を行い、有差を検討した。その結果、心理傾向とペットの位置づけやペットロスの状況、対処法との関連性が得られ、各人に応じたペットロス対処を行うことへの手がかりが示唆された。詳細な結果は口頭発表で行う。 3.「性別」VS「ペットの位置づけ・価値観、喪失時の状況・対応」 性別では、女性のほうが男性よりもペットを失ったとき「誰かに話を聞いてほしい」「我慢せずに泣けばよい」「普段と変わらず接してほしい」の項目で有意に高い結果を示した。 4.「信仰心」VS「ペットの位置づけ・価値観、喪失時の状況・対応」 調査対象者の約9割が信仰する宗教を明確に持っており、信仰心の低い人のほうが「ペットを飼えなくなった場合、捨ててしまいたい」と答えた人が多く、信仰心の高い人の方が「ペットを失った時、代わりのペットを飼いたい」と答えた人が多かった。 5.「飼育経験」VS「ペットの位置づけ・価値観、喪失時の状況・対応」 本調査ではペット飼育経験者150名、未経験者2名であり、検定が成立しなかった。 6.「ペット喪失経験」VS「ペットの位置づけ・価値観、喪失時の状況・対応」 ペットを亡くした経験のある人のほうがない人よりも「安楽死をさせる」が有意高く、「ペットを亡くした時、新しいペットの飼育を勧めてほしい」は有意に低かった。 7.自由記述 ペットを亡くした時の思いは「悲しみ、驚き、怒り、寂しさ」の情緒的な反応が72%で最も多かった。悲しみから立ち直ったきっかけは「新しいペットを飼った、他のペットを大切にする」が23%で最多であった。 【考察】 心理尺度では日本は8因子、米国は5因子であり、そのままの単純比較はできなく、日米比較の詳細は次発表で行う。米国では信仰を持つ割合や飼育経験が高いこと、ペットロス研究は日本と異なり約20年も前から取り組まれていることがペットロスとその対処との関連性に影響を与えていると考えられる。日米比較は次回行う。
1 0 0 0 OA 1860年代横浜のイギリス人
- 著者
- 重久 篤太郎
- 出版者
- 日本英学史学会
- 雑誌
- 英学史研究 (ISSN:03869490)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, no.9, pp.1-9, 1976-09-01 (Released:2009-09-16)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA Weblogにおける文書作成支援のためのエゴセントリック検索
- 著者
- 沼 晃介 大向 一輝 濱崎 雅弘 武田 英明
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第18回全国大会(2004)
- 巻号頁・発行日
- pp.131, 2004 (Released:2006-02-11)
本発表では,Weblogにおける文書作成のための情報検索および提示システムについて述べる.関連文書の検索手法として自分を中心としたネットワークを利用するエゴセントリック情報検索を提案する.
1 0 0 0 OA IoT環境下の「考える工場」実現を目指す実仮想融合型生産システム
- 著者
- 貝原 俊也
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.53-58, 2016-01-10 (Released:2016-01-30)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA バス床用制振合板の開発
- 著者
- 濱野 信之
- 出版者
- The Institute of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.28-31, 1992-02-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 1.仮面高血圧―病態と治療―
- 著者
- 苅尾 七臣
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.1, pp.79-85, 2007 (Released:2009-12-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
近年,診察室血圧が正常で,診察室以外の血圧が高値を示す「仮面高血圧」が注目されている.仮面高血圧は未治療者の10~15%,治療中高血圧患者の20~25%に存在する.その心血管リスクは正常血圧より2~3倍高く,診察室と診察室以外の血圧レベルが共に高い持続性高血圧と同程度かそれ以上である.仮面高血圧の表現型には,早朝血圧,ストレス性高血圧,夜間高血圧があり,その治療には個々の背景病態を把握する必要がある.早朝高血圧をターゲットにした降圧療法が,仮面高血圧治療の最初の第一歩である.
1 0 0 0 OA (書評)木庭顕著「デモクラシーの古典的基礎」
- 著者
- 小川 浩三
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.54, pp.197-204, 2005-03-30 (Released:2010-05-10)
1 0 0 0 OA ヒト外耳道から分離した新規Candida属酵母の分類
- 著者
- 佐藤 一朗 槇村 浩一 蓮見 弥生 西山 彌生 内田 勝久 山口 英世
- 出版者
- 日本医真菌学会
- 雑誌
- 日本医真菌学会総会プログラム・抄録集 第52回 日本医真菌学会総会・学術集会 (ISSN:09164804)
- 巻号頁・発行日
- pp.73, 2008 (Released:2009-03-06)
【目的】真菌症は免疫力の低下した患者にとって重篤な症状を起こす病害である。そのため、免疫力の低下した患者における微生物叢とその薬剤耐性を定期的に把握する必要がある。我々は外来患者の外耳道から新規Candida属酵母を得たので報告する。【材料および方法】国内病院での外来患者の外耳道から採取した耳漏スメアを分離源とした。純粋分離菌株の26S rDNA D1/D2領域(26S)および ITS1+5.8S rDNA+ITS2領域(ITS)を用いた分子系統分類を行った。そのほかの試験項目はThe Yeasts 4th edに順じた。【結果および考察】純粋分離菌JCM15448株は26Sの相同性がCandida haemulonii CBS5149T とは85.7%、C. pseudohaemulonii CBS10099Tとは83.0%であった。ITSはそれぞれ84.9、81.4%であり、系統樹ではCandida属に分類されたが同一な種は認められなかった。本菌株は42℃およびビタミンフリー培地で生育陽性であり、Candida属としては特徴的な培養性質を示した。その他の培養性質から本菌株はグループ VI(イノシトール・硝酸カリウム・エリスリトール陰性、40℃陽性)に分類された。本グループはC. albicansをはじめ病原性が報告されている種が複数属しているが、本菌株の病原性は不明である。ボリコナゾール・イトラコナゾール・フルコナゾール・フルシトシンに対する感受性は既知の種と差が認められなかった。これらの結果から本菌株をCandida属の新種と判断した。
- 著者
- 宇津木 弘 西村 成興 堀越 英生
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.238, pp.673-679, 1973-07-15 (Released:2009-06-03)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
The surface of silica gel was treated in an autoclave by the solution of alcohol or phenol with some functional groups in hexane or acetone, and their surface properties were investigated by determining their preferential dispersion into the media consisting of two immiscible components such as n-hexane and water. Furthermore, the identification of the surface groups and their thermal and chemical natures were examined through the infra-red spectra, differential thermal analysis (DTA), thermogravimetry (TGA) and qualitative analysis.The conclusions obtained are as follows: (1) The silica gels treated by diethylene glycol, 3-chloropropanol, phenol, or salicylic acid were hydrophilic whereas the ones treated by o-, m-, or p-cresol and hydroxybenzol were hydrophobic (lipophilic). (2) The characteristic absorptions due to alcoxy or phenoxy groups were observed in the infra-red spectra of the surface-treated silica gels. Since the intensity of the absorption at 950cm-1 due to bending vibration of Si-OH was almost the same for both the untreated and phenol-treated silica gels, it is still questionable whether silanol combines chemically with phenol or not. (3) DTA showed the exothermic due to dissociation and oxidation of the surface groups at 250°C, which is higher than the normal boiling point, and the remarkable exothermic due to oxidation of deposited carbon. Therefore, the surface groups are considered to combine with silanol chemically, except phenol. (4) These surface groups are confirmed to be alcoxy or phenoxy, since they were dissolved into boiling water or boiling dil. H2SO4 and, furthermore, from the qualitative analysis of dissolved solution, they were confirmed being alcohol or phenol used in this study.
- 著者
- Ryota Matsuoka Norio Takayashiki Yusuke Chino Yasuharu Tokuda
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.15, pp.1733-1734, 2014 (Released:2014-08-01)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 北海道幌満かんらん岩体から発見された新鉱物・苣木鉱
- 著者
- 北風 嵐
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.32-33, 2010 (Released:2010-03-27)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 新鉱物・宮久石の誕生について
- 著者
- 浜根 大輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.57-59, 2015 (Released:2015-03-05)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 山口県萩市高山斑れい岩からのNiに富む幌満鉱の新発見
- 著者
- 北風 嵐 小松 隆一
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.133-137, 2016 (Released:2016-11-02)
- 参考文献数
- 14
Ni-rich horomanite is found from the chalcopyrite-bearing (1.0-1.5 mode%) layer in the Kouyama gabbroic body, Hagi city, Yamaguchi Prefecture, western Japan and as second occurrence in the world. It occurs as inclusions in chalcopyrite interspaced with silicate minerals, vanadium-bearing magnetite and ilmenite. It is often associated with siegenite and is secondarily replaced by violarite. Chalcopyrite associating with Ni-rich horomanite commonly shows the polysynthetic twin. Analytical data for horomanite obtained by EPMA are Cu: 0.56-2.19, Fe: 23.01-25.32, Ni: 37.45-41.35, Co: 1.56-4.03 and S: 32.85-33.32 wt%. Their variations are small for inner grain or another grain. The atomic ratio of (Cu + Fe + Ni + Co): S correlates well with ideal formula of 9:8 for horomanite. In addition, Ni content in metal ratio for (Cu + Co): Fe: Ni (at%) ranges from 52 to 59 and is Ni-rich than that of original horomanite from the Horoman peridotite. Horomanite might be considered to be continuous solid solution ranging from 3.0 to 5.5 in terms of Ni(+Co) content. Therefore, general formula for horomanite is thought to be (Fe + Cu)6 − x(Ni + Co)3 + xS8(0 < x < 2.5).
1 0 0 0 OA 敗血症を併発した歯性感染症による非クロストリジウム性頭頸部ガス壊疽の1例
- 著者
- 立石 晃 天野 裕治 相田 高幸 福田 仁一
- 出版者
- 社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.8, pp.423-426, 2002-08-20 (Released:2011-04-22)
- 参考文献数
- 10
A case of non-clostridial gas gangrene with sepsis in the maxillofacial region and neck caused byodontogenic infection is reported.A 74-year-old woman consulted our department because of painful swellingof the head and neck region.She had been treated for depression for about 20 years.Her general conditionwas classified as I-2 coma according to the Japan coma scale.Blood examination revealedleukocytosis, hepatopathy, nephropathy, hypoalbuminemia, and hyperglycemia.A computed tomographicscan showed gas accumulation with abscess formation in the temporal, buccal, submandibular, and cervicalregions.Administration of antibiotics (PAPM/BP) and gamma-globulin was followed by emergencysurgical drainage under general anesthesia. Microbiological examinations revealed Streptococcus pneumoniae in the abscess and Peptococcus asaccharolyticus in venous blood on the 1st disease day. Aftertreatment, the swelling disappeared and the results of blood tests became normal.However, a secondmicrobiological examination of venous blood also revealed Peptococcus asaccharolyticus on the 9 th diseaseday. Antibiotics (CLDM) were given from the 17th to 20th disease days.Hyperglycemia was controlledby insulin.She was discharged on the 53rd disease day.Rapid diagnosis by computed tomography, rapid surgical drainage, appropriate chemotherapy, and examinationsof blood cultures and for DIC are required to save patients'lives.
1 0 0 0 OA 新潟県西部からのナガレタゴガエルの記録
- 著者
- 下山 良平
- 出版者
- 日本爬虫両棲類学会
- 雑誌
- 爬虫両棲類学会報 (ISSN:13455826)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.1, pp.6-7, 2002-03-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 5.尿細管性アシドーシスの分類と診断
- 著者
- 冨田 公夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.10, pp.1891-1896, 1997-10-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 2
尿細管性アシドーシスとは糸球体濾過量が正常か軽度低下にもかかわらず代謝性アシドーシスがみられる場合で尿細管からの酸排泄の低下が原因である.障害部位により,近位尿細管性アシドーシスと遠位尿細管性アシドーシスに分けられる.近位尿細管性アシドーシスは低K血症を呈するが,遠位尿細管性アシドーシスには低K血症を呈するものと高K血症を呈するものとがある.炭酸水素ナトリウム負荷試験,酸負荷試験,フロセミド負荷試験,硫酸ナトリウム負荷試験,中性リン酸ナトリウム負荷試験などにより障害部位および機序を鑑別する.