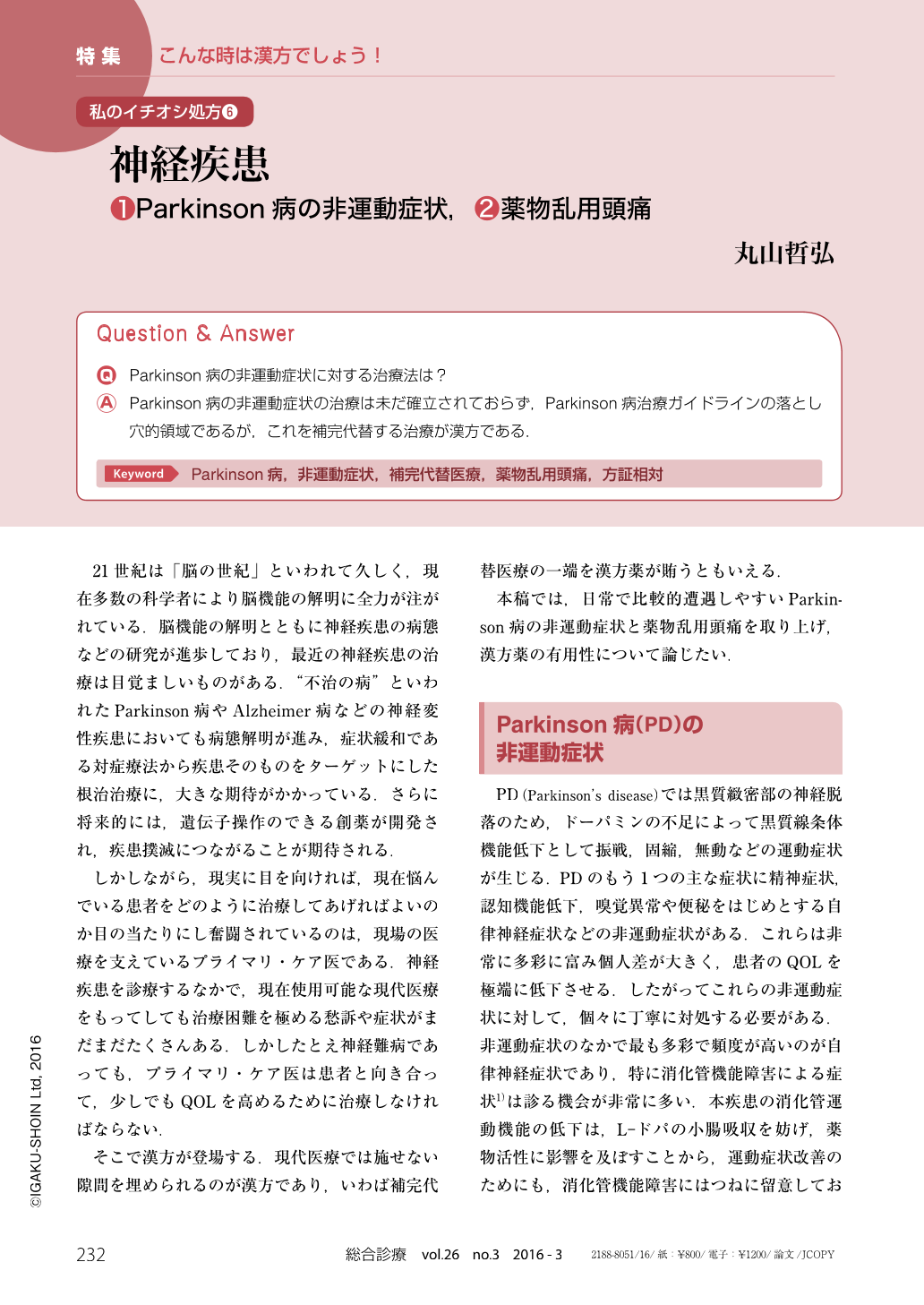4 0 0 0 OA 冷え感を有する健康人におけるカイロ加温の部位別検討試験
- 著者
- 嶋 良仁 渡邉 あかね 井上 暢人 國友 栄治 丸山 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- pp.2330, (Released:2020-07-28)
- 参考文献数
- 9
【目的】「冷え」は正常な体温であるにもかかわらず,手または足が冷えている状態である.疾病の有無に関係なく,高齢者を中心に多くの人がこの「冷え」に悩まされている. 冷えを和らげる方法のひとつに使い捨てカイロで手を温めることがあるが,この方法では手が塞がり日常の作業を妨げる.そこで,カイロで上肢の別の部分を加熱することで,手の冷えを緩和できるかどうかを調査した. 【方法】インフォームド・コンセントの後,脈管異常の指摘がこれまでない冷えを自覚する30名に頸部,肘,手首の加温の検討を行った.18名はそれぞれ1週間のインターバルをあけて3ヶ所を指定された順に1週間ずつカイロで加温を行った.残りの参加者は,カイロ固定用ホルダーの影響を観るためにホルダーだけを装着した.すべての参加者は,10cmのvisual analog scaleによる手の冷え評価を連日記録させた. 同様にカイロやホルダー装着が日常作業に差し障ったかを連日評価させた.1週間の加温の治療効果を観るために,カイロまたはホルダーのみを使用した期間終了翌日に,サーモグラフィーとlaser speckle contrast analysis(LASCA)を使用して,24℃20分間の室温順応後に両手の表面温度と血流を計測した. 【結果】頸部と肘部のカイロ加温中に冷えVASの有意な低下が観察された.日常への差し障り度評価は3ヶ所間で差がなかった.手の表面温度・血流はカイロ(あるいはホルダーのみ)の使用で上昇は観察されなかった. 【結語】手を温めなくても手の冷えを改善できることと,加温部位によってその効果が異なることが判明した.この研究は,「冷え」を改善する新しい方法につながると考えられる.サーモグラフィー等の客観的評価は,外気温等の測定条件の影響が非常に大きく,評価方法の検討が必要と考えられた.
2 0 0 0 IR 仏教のグローバル化と開教 : 「グローバル文化論」のための覚書(3)
- 著者
- 丸山 哲央 山本 奈生
- 出版者
- 佛教大学
- 雑誌
- 社会学部論集 (ISSN:09189424)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.17-31, 2010-03-01
社会学や人類学における文化理論では,宗教は文化の普遍的項目あるいは普遍的類型(universal pattern)として扱われてきた。しかし,文化のグローバル化との関連で宗教に言及する場合,宗教の包括的な定義をもってしては,そのグローバル化の実態を捉えることは困難である。なぜなら,グローバルなレベルでの宗教的実践が周知の事実として確認されると同時に,宗教の本質には身体性と地域性という時間・空間に規定されたローカルな実存的(existential)要素が不可欠なものとして含まれている。本稿では,世界宗教とされる仏教のグローバル化について,特に浄土宗の布教活動である海外開教を事例として取り上げ,その理論的分析方法について考察する。この際に,仏教の教義,教理を含む文化の認知的および評価的要素とともに,具体的な宗教的実践にかかわる実存的要素と宗教芸術や娯楽的行事(仏教の「花まつり」等)を捉えるための表出的要素とを分析概念として設定することの有効性が確認された。
1 0 0 0 OA 冷え感を有する健康人におけるカイロ加温の部位別検討試験
- 著者
- 嶋 良仁 渡邉 あかね 井上 暢人 國友 栄治 丸山 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.105-112, 2020-10-31 (Released:2021-02-10)
- 参考文献数
- 9
【目的】「冷え」は正常な体温であるにもかかわらず,手または足が冷えている状態である.疾病の有無に関係なく,高齢者を中心に多くの人がこの「冷え」に悩まされている. 冷えを和らげる方法のひとつに使い捨てカイロで手を温めることがあるが,この方法では手が塞がり日常の作業を妨げる.そこで,カイロで上肢の別の部分を加熱することで,手の冷えを緩和できるかどうかを調査した. 【方法】インフォームド・コンセントの後,脈管異常の指摘がこれまでない冷えを自覚する30名に頸部,肘,手首の加温の検討を行った.18名はそれぞれ1週間のインターバルをあけて3ヶ所を指定された順に1週間ずつカイロで加温を行った.残りの参加者は,カイロ固定用ホルダーの影響を観るためにホルダーだけを装着した.すべての参加者は,10cmのvisual analog scaleによる手の冷え評価を連日記録させた. 同様にカイロやホルダー装着が日常作業に差し障ったかを連日評価させた.1週間の加温の治療効果を観るために,カイロまたはホルダーのみを使用した期間終了翌日に,サーモグラフィーとlaser speckle contrast analysis(LASCA)を使用して,24℃20分間の室温順応後に両手の表面温度と血流を計測した. 【結果】頸部と肘部のカイロ加温中に冷えVASの有意な低下が観察された.日常への差し障り度評価は3ヶ所間で差がなかった.手の表面温度・血流はカイロ(あるいはホルダーのみ)の使用で上昇は観察されなかった. 【結語】手を温めなくても手の冷えを改善できることと,加温部位によってその効果が異なることが判明した.この研究は,「冷え」を改善する新しい方法につながると考えられる.サーモグラフィー等の客観的評価は,外気温等の測定条件の影響が非常に大きく,評価方法の検討が必要と考えられた.
1 0 0 0 OA キンモクセイ花の成分研究 (第1報)
- 著者
- 石黒 武雄 古賀 直文 高村 恭治 丸山 哲生
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.7, pp.781-785, 1955-07-25 (Released:2010-02-19)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 8 8
The flowers of Osmanthus fragrans Lour. var. aurantiacus Makino were soaked in petroleum ether immediately after collection, digested for one week, and filtered with pressing. The aqueous layer of the filtrate was extracted with ether. The residual flowers were then digested with warm dehydrated ethanol for 16 hours.1) The portion soluble in petroleum ether is composed of concretes amounting to 0.214% of the original flowers and its treatment with cold dehydrated ethanol separates it into 0.163% of absolutes and 0.043% of flower wax, which is chiefly composed of triacontane, C30H62.2) The ether solution was chromatographically purified and p-hydroxyphenethyl alcohol C8H10O2, was isolated.3) The ethanol-soluble portion yielded D-mannitol.4) The water-soluble portion was fractionated with lead acetate and basic lead acetate. D-Mannitol was isolated from the filtrate and the presence of D-glucose and D-fructose was detected by paper chromatography. The precipitate obtained by lead acetate and the portion soluble in ethanol, yielded succinic acid.
- 著者
- 甲南大学久保ゼミ 丸山 哲 甲南大学久保ゼミ 久保 はるか
- 出版者
- 甲南大学法学部久保ゼミ
- 雑誌
- 「大学周辺地域の歴史を知る」シリーズ
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-10, 2017-05
1 0 0 0 OA 子宮内膜症・腺筋症における幹細胞の役割の解明
- 著者
- 丸山 哲夫 内田 浩 升田 博隆 小野 政徳 BULUN Serdar SCIARRA John J.
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2012-04-01
本研究では、子宮内膜症および子宮腺筋症の発生・進展における幹細胞の役割を明らかにするために、ヒト内膜細胞を用いた腹膜内膜症モデルマウスの開発を行い、磁性体により内膜症様病変をマウス壁側腹膜の任意の位置に局在させ得る戦略が可能で有ることを示した。同時に、新たに幹細胞標識追跡法を開発することで、組織(病変)再構成過程における幹細胞の振る舞いを検証できるin vivoシステムを構築し得た。さらに、子宮腺筋症の類縁疾患である子宮平滑筋腫の病因メカニズムに幹細胞とWNT/β-Catenin経路が関与することを明らかにした。
1 0 0 0 進行舌癌治療後に発症した治療関連骨髄異形成症候群の1例
- 著者
- 仁村 文和 丸山 哲昇 村橋 信 丸山 修幸 新崎 章
- 出版者
- 一般社団法人 日本口腔腫瘍学会
- 雑誌
- 日本口腔腫瘍学会誌 (ISSN:09155988)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.91-96, 2019
- 被引用文献数
- 2
骨髄異形成症候群は,造血幹細胞の異常により,血球3系統に量的および質的異形成を来した病態であり,白血病に移行しやすい。同疾患は悪性腫瘍に対する化学療法や放射線治療の後に発症することがあり,治療関連骨髄異形成症候群(therapy-related myelodysplastic syndrome,以下t-MDS)と呼ばれる。今回われわれは,舌扁平上皮癌患者に対して化学放射線療法後にt-MDSを発症した1症例を経験したので報告する。症例は52歳男性,舌癌(T4aN2bM0 stage Ⅳ)でTPF療法による導入化学療法後に手術を施行した。頸部転移リンパ節の節外浸潤を認めたため術後化学放射線療法を施行した。一次治療終了後から3年3か月後,t-MDSを発症し死亡した。化学療法および放射線療法を施行した口腔癌症例ではt-MDSの発症を考慮し,長期の経過観察が必要と考えられた。
1 0 0 0 神経疾患—❶Parkinson病の非運動症状,❷薬物乱用頭痛
- 著者
- 丸山 哲弘
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.232-238, 2016-03-15
21世紀は「脳の世紀」といわれて久しく,現在多数の科学者により脳機能の解明に全力が注がれている.脳機能の解明とともに神経疾患の病態などの研究が進歩しており,最近の神経疾患の治療は目覚ましいものがある.“不治の病”といわれたParkinson病やAlzheimer病などの神経変性疾患においても病態解明が進み,症状緩和である対症療法から疾患そのものをターゲットにした根治治療に,大きな期待がかかっている.さらに将来的には,遺伝子操作のできる創薬が開発され,疾患撲滅につながることが期待される. しかしながら,現実に目を向ければ,現在悩んでいる患者をどのように治療してあげればよいのか目の当たりにし奮闘されているのは,現場の医療を支えているプライマリ・ケア医である.神経疾患を診療するなかで,現在使用可能な現代医療をもってしても治療困難を極める愁訴や症状がまだまだたくさんある.しかしたとえ神経難病であっても,プライマリ・ケア医は患者と向き合って,少しでもQOLを高めるために治療しなければならない.
1 0 0 0 OA 機械学習向けプログラミング言語の使い分け
- 著者
- 丸山 哲太郎
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 日本計算機統計学会大会論文集 日本計算機統計学会 第30回大会実行委員会 (ISSN:21895821)
- 巻号頁・発行日
- pp.87-88, 2016 (Released:2017-03-10)
1 0 0 0 IR 日本仏教のグローバル化と南米開教 : 「グローバル文化論」のための覚書(4)
インドから中国,朝鮮・韓国を経て移入され,日本化された仏教(Japanized Buddhism)は日本固有の要素にすべての時代,地域に通底する普遍的要素を付加し,独自の体系を形成してきた。日本仏教に固有の要素でありながら新たな普遍性を備え,逆に外部に再発信しうる要素とは何かということの解明が,文化のグローバル化現象の根幹をなす問題である。本稿では,日本仏教のグローバル化について,特に布教活動である南米での海外開教を事例として取り上げ,その理論的分析方法について考察する。この際に浄土宗と浄土真宗の開教活動に焦点を当て,見仏体験にかかわる文化の実存的要素の伝播可能性についての究明を試みたが,文化伝播のメディアとの関連での分析が必要なことが明らかになった。
- 著者
- 丸山 哲史 小島 祥敬 林 祐太郎 渡辺 秀輝 郡 健二郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会
- 雑誌
- 日本小児外科学会雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, 2000
昨年度に引き続き本年度は、哺乳類胚発生のメカニズムならびに胚の個体発生能を含めた質的ポテンシャルを、非侵襲的に解明し評価することを目的とした。そのために、マウス胚発生過程において培養液中に分泌されるタンパク質のプロファイル(secretome)を明らかにし、そのデータベース構築を目指すとともに、agingや機械的受精操作などがsecretomeにどのような影響を及ぼすかについて検討するための実験システムの整備を行った。まず、secretomeと胚発生・発育の関連を検討する際に、十分な胚盤胞到達率が得られなければならない。一方、プロテインチップ解析に供するためには、出来るだけ少量の培養液で行う必要があり、これは胚発生・発育にとって厳しい環境となる。このように、両者は相反するため、至適条件の確立が極めて重要である。そこで、培養液の変更など種々の検討を行った結果、60μ1の培養液量で約90%の胚盤胞到達率を再現性良く得られる培養システムを確立し、引き続いてその実験システムにより得られた各時期の培養液をプロテインチップ解析に供した。その結果、コントロール培養液に比較して、胚存在下の培養液では、複数の特異的蛋白ピークが検出され、また時期に応じてそのプロファイルは変化した。これらの一連のsecretomeのプロファイリングと胚盤胞到達率との関連を検討するとともに、今回検出された複数の特異的蛋白の同定を目指し、MALDI/TOF-MS質量分析計への解析に供するに必要な実験システムの更なる構築を行った。昨年度より引き続いて本年度得られた上記の成果は、マウスのみならずヒト胚のqualityの非侵襲的評価システムを確立するうえで、重要な基盤データになると考えられる。