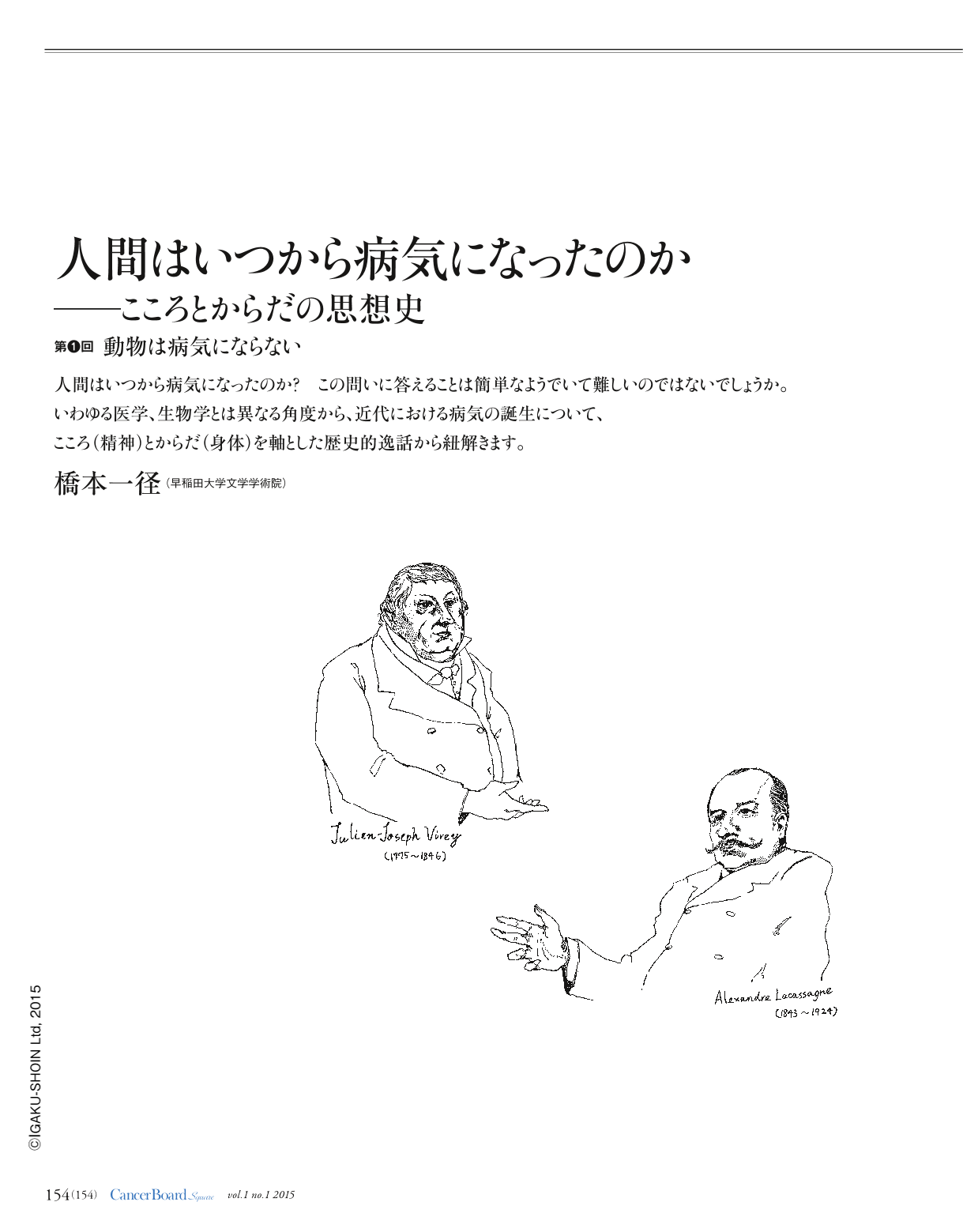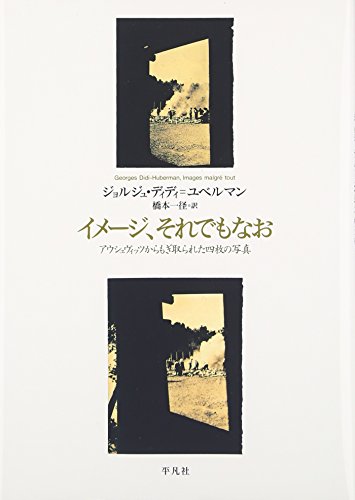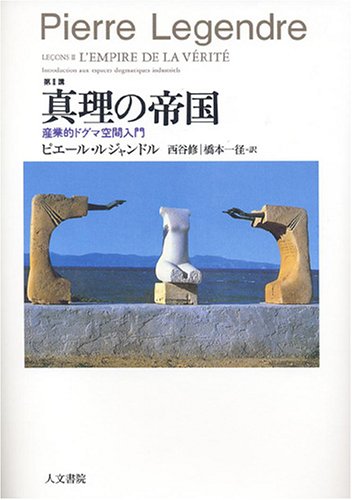12 0 0 0 動物は病気にならない
「動物は病気にならない」 病気になるのは人間だけで、動物、とりわけ野生動物は、めったに病気になどならないし、なったとしても自然に治る。このように述べるのは、フランス革命期から19世紀初頭にかけて活躍した医師であり博物学者のジュリアン=ジョゼフ・ヴィレー(Julien-Joseph Virey, 1775-1846)である。「動物は(…中略…)野生状態では通常は病気にならないⅰ」。1801年に2巻本の大著として刊行され、1824年にさらなる増補版の出された主著『人類の自然史』においてこう記すヴィレーは、動物に比べて人間があまりにも多くの病気に脅かされていることを嘆く。「なんと多くの病を人間は持ち合わせていることか、自分では引き受けきれないほどにⅱ!」。動物が病気にならないというのなら、獣医の商売は上がったりのようにも思われるが、もちろんヴィレーとて、当時すでに大学で講じられる立派な学問として成立していた獣医学の存在を知らなかったわけではあるまい。獣医学がもっぱらその対象としてきた、豚や羊や馬などの家畜動物が病気になることは、ヴィレーも認めているからである。 ヴィレー曰く、彼らが病気になるのは、「自然の秩序から遠ざかってⅲ」しまったから、つまり人間に近づいてしまったからだ。それでも人間に比べれば彼らの病気など取るに足らないものである。世界のあらゆる生き物のなかで、人間が「もっとも病弱な動物ⅳ」であることは、ヴィレーにとって自明のことであった。病気とは、自然を離れて文明化した人間だけに襲いかかる災難であり、言ってみれば“持てる者の悩み”なのだ。
1 0 0 0 IR イメージの権利 : 19世紀フランスにおける写真の著作権・肖像権 (特集 身体と同一性)
- 著者
- 橋本 一径
- 出版者
- 神戸大学文学部芸術学研究室
- 雑誌
- 美学芸術学論集 (ISSN:18801943)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.27-37, 2013
- 著者
- ジョルジュ・ディディ=ユベルマン著 橋本一径訳
- 出版者
- 平凡社
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 真理の帝国 : 産業的ドグマ空間入門 : 第II講
- 著者
- ピエール・ルジャンドル著 西谷修 橋本一径訳
- 出版者
- 人文書院
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 法的人間ホモ・ジュリディクス
- 著者
- アラン・シュピオ著 橋本一径 嵩さやか訳
- 出版者
- 勁草書房
- 巻号頁・発行日
- 2018
- 著者
- 橋本 一径
- 出版者
- 国立新美術館
- 雑誌
- NACT review : bulletin of the National Art Center, Tokyo : 国立新美術館研究紀要 (ISSN:21890129)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.264-272, 2015