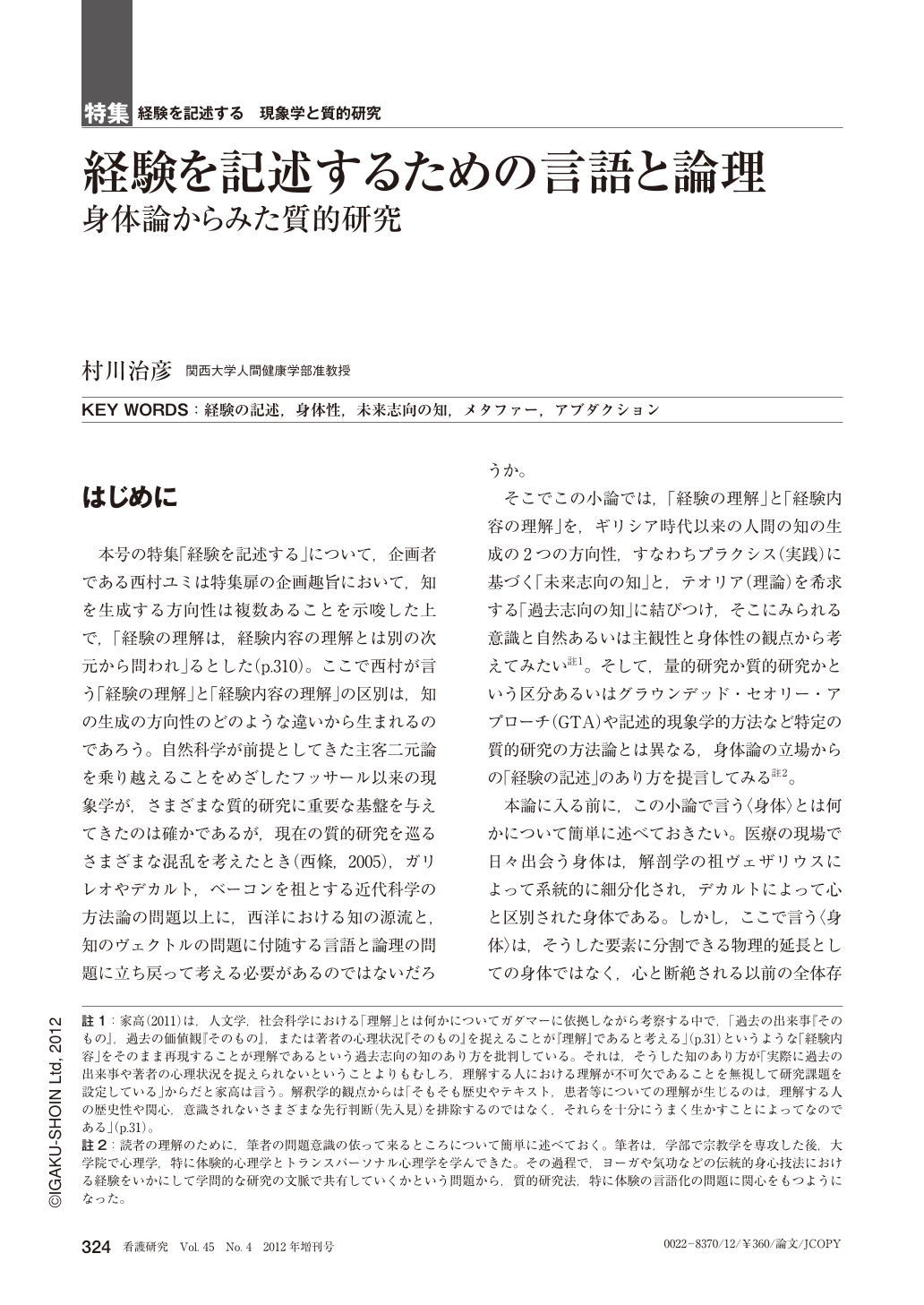1 0 0 0 経験を記述するための言語と論理―身体論からみた質的研究
はじめに 本号の特集「経験を記述する」について,企画者である西村ユミは特集扉の企画趣旨において,知を生成する方向性は複数あることを示唆した上で,「経験の理解は,経験内容の理解とは別の次元から問われ」るとした(p.310)。ここで西村が言う「経験の理解」と「経験内容の理解」の区別は,知の生成の方向性のどのような違いから生まれるのであろう。自然科学が前提としてきた主客二元論を乗り越えることをめざしたフッサール以来の現象学が,さまざまな質的研究に重要な基盤を与えてきたのは確かであるが,現在の質的研究を巡るさまざまな混乱を考えたとき(西條,2005),ガリレオやデカルト,ベーコンを祖とする近代科学の方法論の問題以上に,西洋における知の源流と,知のヴェクトルの問題に付随する言語と論理の問題に立ち戻って考える必要があるのではないだろうか。 そこでこの小論では,「経験の理解」と「経験内容の理解」を,ギリシア時代以来の人間の知の生成の2つの方向性,すなわちプラクシス(実践)に基づく「未来志向の知」と,テオリア(理論)を希求する「過去志向の知」に結びつけ,そこにみられる意識と自然あるいは主観性と身体性の観点から考えてみたい註1。そして,量的研究か質的研究かという区分あるいはグラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)や記述的現象学的方法など特定の質的研究の方法論とは異なる,身体論の立場からの「経験の記述」のあり方を提言してみる註2。 本論に入る前に,この小論で言う〈身体〉とは何かについて簡単に述べておきたい。医療の現場で日々出会う身体は,解剖学の祖ヴェザリウスによって系統的に細分化され,デカルトによって心と区別された身体である。しかし,ここで言う〈身体〉は,そうした要素に分割できる物理的延長としての身体ではなく,心と断絶される以前の全体存在としての〈身体〉である。メルロ=ポンティに依拠する西村(2001)はこの〈身体〉を,「生きられた世界経験の具体的な出発点」であり,「世界とのつながりであり,〈身体〉があるからこそ,世界との対話が可能となる」と表現している。この小論で言う〈身体〉も,メルロ=ポンティが示したこの世界とのつながりとしての〈身体〉であり,それはたんにデカルト以前の心とひとつになった身体ではなく,主体と客体という二元論によって人間存在を理解するはるか以前,ギリシア時代に主観性の哲学が立ち現われる以前の〈存在〉を指している。 では,この主観性の哲学以前の〈存在〉とはいかなるものであろう。ギリシア哲学者の日下部吉信(2005)は,「西洋形而上学は全体として主観性の哲学」であり「存在の真理を隠蔽してきた」という反省から,ソクラテス以前のギリシア自然哲学に着目し,根源概念としての〈自然概念〉(ピュシス)を見いだした。日下部はこの「ピュシス」が「ギリシア人にとっては意識の対象ではなく,ある意味性を帯びた意識そのものであった」(p.78)とし,それを主観性の哲学によって説明することは「原則不可能」であることを強調している。そして,「にもかかわらず,そういった根源概念である自然概念(ピュシス)の解明がなお可能だとするなら,それはその概念が自ら現れ出る現場を差し押さえる現象学的方法によって以外ではありえないであろう」(p.75)とした。このピュシスが「自ずから現れ出る現場」こそが,古代ギリシア人にとってはテクネー(技術)の世界であった。日下部によれば,「テクネーの志向性は物事に即したそれである。ギリシア的テクネーの知はいわば物事との応答の内に開示される存在の思索なのである」(p.55)。 このように,ソクラテス以前のギリシア自然哲学の特徴は,テクネー性の重視にあり,その特徴を日下部は,「技術は物事の本質に対して無関心なのである。テクネーをベースとする命題には原理・本質に対する無関心性,冷淡さがつきまとう。というより,それがテクネーの本性なのであって,テクネーは物事の本質には係わらない。そのありように係わるだけである」註3としている。テクネーの人の代表者であるプロタゴラスが示した「絶対的・客観的知識の穏やかな,しかし断固とした拒否」と「神に関しては判断停止」の態度がこうしたテクネー性そのものであり,「プロタゴラスもまた存在の一表現となった人物」としている。このように私たちの〈身体〉は,ギリシア時代に主観性原理が確固たる地位を占める以前に人々が依拠した存在(自然概念)へと導いてくれる。 東西の身体論についての第一人者であった湯浅泰雄(1993)もまた,ギリシア時代のプラクシス(実践,行動)に対するテオリア(理論,観察)の優位こそが,近代がもたらした問題の根源にあることを次のように指摘している。「技術の進歩が科学を追い抜いたという現代の状況は,日常性と科学性の関係について,あらためて考え直す必要をわれわれに教えている。というのは,技術は本来,日常的経験の場面に根拠をもつ営みであるからである。言いかえればわれわれは,近代とは逆に,日常的経験の立場から出発して科学的認識というもののあり方について考えてゆかなくてはならない」(pp.63-64)註4。 日下部の言う存在としての〈自然概念〉(ピュシス)の喪失から主観性原理の確立,湯浅が言うプラクシスに対するテオリアの優位が成立した経緯は,知の方向性という観点からは,哲学者の大出晃(2004)の言う「未来志向の知」から「過去志向の知」への転換と位置づけられるだろう。この小論では,古代オリエントからギリシア時代にかけて起こった知の方向性の転換におけるこの2つの知のあり方,つまり技術的な知恵を主とする「未来志向の知」と事象の依って来る由縁に関心をもつ「過去志向の知」を,西村の言う「知を生成する複数の方向性」と捉えてみる。そして,存在としての〈身体〉が生み出す「未来志向の知」という観点から,「経験の記述」のあり方について考えてみる。
言及状況
外部データベース (DOI)
Twitter (1 users, 1 posts, 0 favorites)
「テクネーの志向性は物事に即したそれである。ギリシア的テクネーの知はいわば物事との応答の内に開示される存在の思索なのである」
看護研究 45巻4号 (2012年7月)
特集 経験を記述する 現象学と質的研究
経験を記述するための言語と論理―身体論からみた質的研究
https://t.co/B1JihznKBr