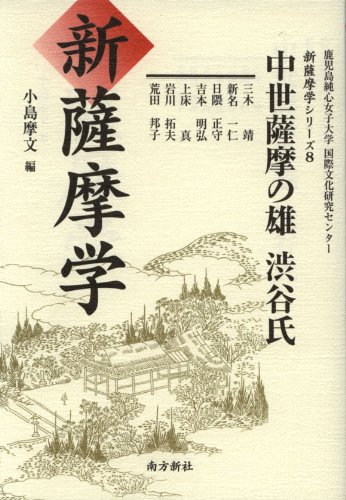5 0 0 0 IR 鹿屋市笠之原につたわる高麗餅「シロ」に関する調査研究
- 著者
- 森中 房枝 浮中 菜々子 小島 摩文
- 出版者
- 鹿児島純心女子大学看護栄養学部
- 雑誌
- 鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀要 = Bulletin of Faculty of Nursing and Nutrition, Kagoshima Immaculate Heart University (ISSN:13484303)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.57-64, 2015
鹿児島では法事菓子の主役として高麗餅を使用することが多い。「これがし」とか「これもち」と呼び,小豆餡と米の粉をこね合わせた蒸し菓子である。高麗餅が鹿児島に伝わったのは,慶長3年(1598年)朝鮮の役により,豊臣秀吉の命を受けて出兵した島津義弘が,李朝の陶工たちを南原(ナモン)から捕虜として連れ帰った折に一緒に伝えたとされている。鹿児島県鹿屋市笠之原地域では,この高麗餅を「シロ」と呼び,地域の玉山宮では祭事や行事の際に高麗餅「シロ」を奉納し"餅返し"の儀式を行っていた。同様に薩摩焼窯元日置市東市来町美山でも,高麗餅を作っていたという記録が残されている。鹿児島における高麗餅の歴史・文化を探る目的で調査を行った。本研究では,鹿屋市笠之原地域玉山宮に伝わる口伝を,宮司を務めていた川元家が書き留めた記録を元に川元アキエ氏が「シロ」を再現しており,聞き取り調査を行った。さらに薩摩焼14代陶工沈壽官氏に聞き取り調査,沈壽官氏所蔵「玉山宮由来記」等を参考に高麗餅の由来や歴史的背景を探り,「シロ」との比較を試みた。韓国の伝統菓子「パッシルトッ」と鹿屋市笠之原の玉山宮に代々伝えられてきた高麗餅「シロ」を再現して比較してみると,類似性が多く美山の記録も同様であった。南原から連れてこられた陶工たちは串木野の島平に上陸後,東市来町美山に移り住み,一部は時を経て笠之原に移住している。笠之原には陶土が少なく陶芸文化は廃れたが,望郷の為に「玉山宮」を建立し,高麗餅を作って"餅返し"儀式を伝えたと推察される。