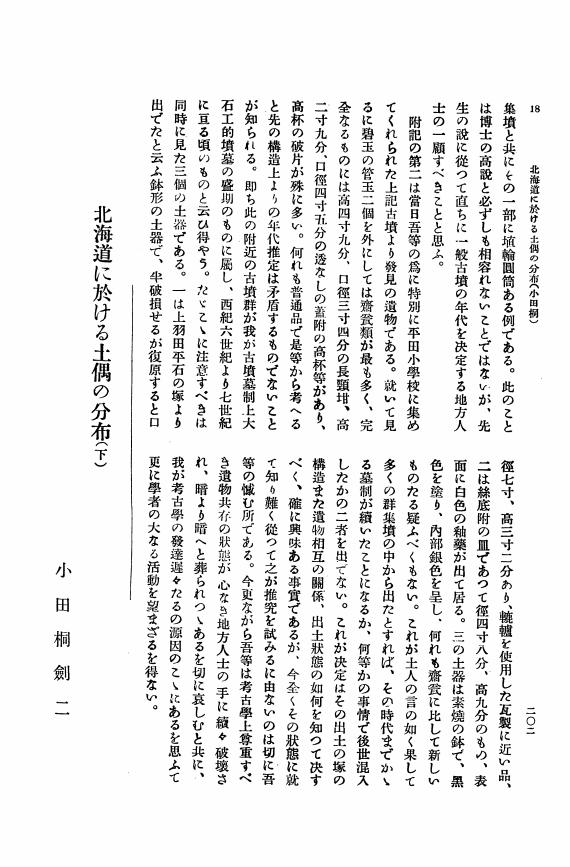1 0 0 0 OA 結縄、書契の例
- 著者
- 坪井 正五郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 東京人類學會雜誌 (ISSN:18847641)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.66, pp.403-413, 1891-09-28 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 樺太亜庭灣沿岸小満別遺跡に就いて
- 著者
- 新岡 武彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.227-236, 1935-06-15 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 北海道石狩國濱益村岡島洞窟遺跡
- 著者
- 杉山 壽榮男
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.348-360, 1938-07-25 (Released:2008-02-26)
1 0 0 0 OA 北海道に於ける土偶の分布 (下)
- 著者
- 小田桐 劍二
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.7, pp.202-205, 1917-07-25 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 北部九州の縄文~弥生移行期に関する人類学的考察
- 著者
- 中橋 孝博 飯塚 勝
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.1, pp.31-53, 1998 (Released:2011-07-01)
- 参考文献数
- 77
- 被引用文献数
- 3 5
弥生文化がいち早く開花した北部九州において, 縄文から弥生への変革を担ったのは土着の人々か, それともこの時期に大陸から渡来した人々なのか, この点について出土人骨に関する形態学的, 人口学的な観点から考察を加えた。当地域の弥生人骨の出土は中期に集中しており, 縄文晩期~弥生初期の住人については資料欠落のため, 直接的な検討ができない。しかし, 中期人骨を判別分析した結果によると, その中に含まれる縄文系弥生人の比率は10~20%に留まり, 殆どが渡来系弥生人で占められている。中期の前半と後半でも人骨形質に変化はなく, こうした人口構成は遅くとも中期初めまでに形成されたと考えられる。もし, 水稲耕作を柱とする弥生社会の出現と発展が土着の縄文系弥生人に依るものだとすると, 200~300年後の同地域に, 形質の大きく異なる渡来系の人々が大多数を占めるような社会が出現することは説明困難である。考古学的諸事実から, 初期渡来人の数は土着集団に較べて少数であったと考えられるが, 土着系集団と渡来系集団の間に人口増加率で大きな差があったと想定すれば, 弥生中期に至るまでの人口比の逆転現象は説明可能である。弥生文化の開花とその発展は, 当初より渡来系集団が牽引者となり, 急速に自身の人口を増やしていった可能性が高い。
1 0 0 0 OA 圖版考説
- 著者
- 大野 雲外 柴田 常恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 東京人類學會雜誌 (ISSN:18847641)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.207, pp.352-371_17, 1903-06-20 (Released:2011-02-23)
1 0 0 0 日本における歯の人類学史
- 著者
- 金澤 英作
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- pp.201110, (Released:2020-12-05)
日本における歯の人類学は,戦後隆盛期を迎えたがその萌芽は明治時代からあった。小金井良精をはじめとする人類学者がむし歯や抜歯風習の研究を始めていた。昭和になってから藤田恒太郎が現れ,歯の解剖学を確立するとともに,歯のもつ様々な形態の研究を通して歯の人類学の可能性を示した。その門下からは多くの歯の人類学者が出たが,その一人が埴原和郎であった。埴原は特定の歯の変異形質がアジア人に多く出現することを示し,これをモンゴロイド・デンタル・コンプレックスと呼んで発表した。埴原に続く世代では,縄文人や弥生人のような日本の古人骨やアジア太平洋地域の様々な集団の歯の形質が調べられ,日本人の成立過程やアジアにおける人の移動に関する仮説などが出された。1990年代は歯の人類学が最も盛んな時期であり,メトリックやノンメトリック形質ばかりでなく,三次元形態,古病理学,霊長類の歯,咬耗,咬合,遺伝など様々な観点から人類学的研究が行われたが,2000年以後になると次第に研究者は少なくなってきている。歯の持つ情報は無限であると思われるが,そこから何を引き出すかが今後の課題であろう。
1 0 0 0 OA 星に關するアイヌの傅説
- 著者
- 吉田 巖
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.7, pp.396-401, 1911-10-10 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 葦船に關する研究
- 著者
- 西村 眞次
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.204-214, 1916-06-25 (Released:2010-06-28)
- 著者
- 片山 一道 土肥 直美
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.2, pp.149-153, 2008 (Released:2008-12-27)
- 参考文献数
- 26
ポリネシア人の祖先となったと考えられるラピタ人など,オーストロネシア系オセアニア諸語グループが,そもそもは台湾あたりに出自したとする出台湾(Out of Taiwan)仮説,あるいは‘Express Train to Polynesia’(ETP)仮説は,言語学や考古学の分野で有力視されている。その仮説を人類学的方法で検証するための試論を展開した。台湾先史時代の墾丁寮人骨と,ラピタ人骨など,太平洋の先史時代人骨との間で頭骨形態を予備的に比較することにより,前者がラピタ人などの変異内に収まることを示した。今後,詳細な研究が期待できる。
1 0 0 0 OA 歯科人類学におけるカラベリー結節
- 著者
- 近藤 信太郎 金澤 英作 中山 光子
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.1, pp.63-73, 2006 (Released:2006-06-23)
- 参考文献数
- 78
ヒトの上顎大臼歯と第二乳臼歯に見られるカラベリー結節は最もよく知られた歯冠形質のひとつである。この形質に関しては様々な観点から多数の研究が行われてきた。本稿では最近の研究を紹介するとともに,この形質が歯の人類学に与えた多くの課題を3つのキーワード「分布」,「遺伝」,「系統と発生」にしたがって検証した。「分布」の項では形質の基準,集団間の違い,ヨーロッパ人にカラベリー結節が多く見られる理由を検討した。「遺伝」の項ではカラベリー結節の遺伝,左右側の非対称性,性染色体とカラベリー結節,性差について考察した。「系統と発生」の項ではカラベリー結節の系統発生と個体発生,カラベリー結節は大きい歯にみられるのか,に関して検討した。歯の内部構造の研究方法の開発や分子生物学的な研究によりカラベリー結節は多方面からより詳細に研究され,未解決の課題が解明されることであろう。