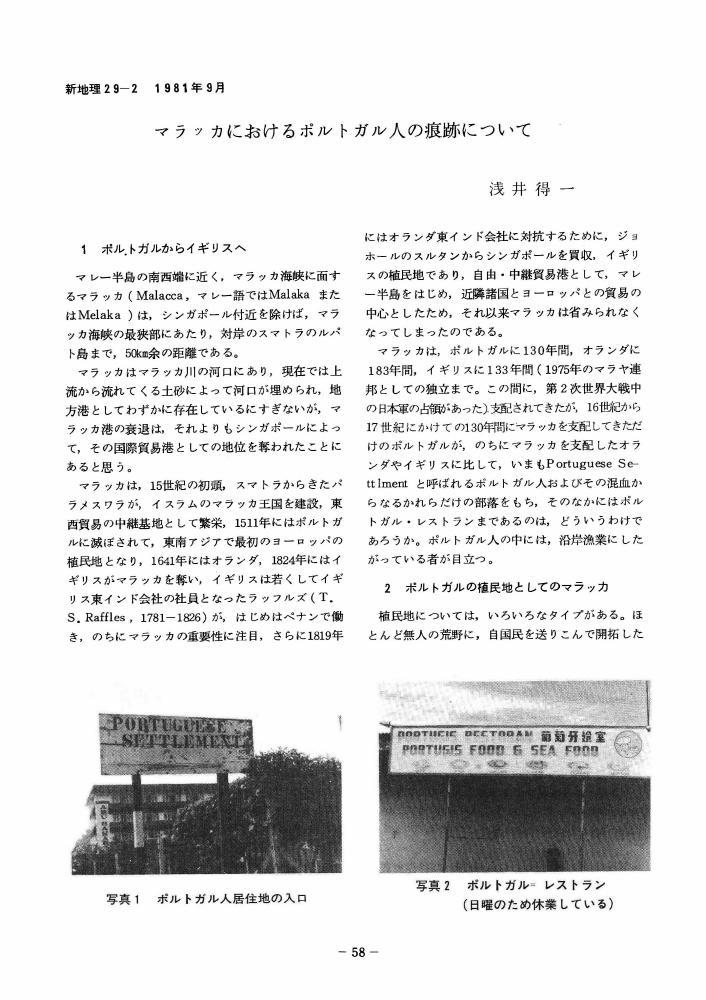10 0 0 0 OA マラッカにおけるポルトガル人の痕跡について
- 著者
- 浅井 得一
- 出版者
- 日本地理教育学会
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.58-61, 1981-09-25 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 6
5 0 0 0 OA わが国における耳垢型の地域的分布について
- 著者
- 浅井 得一
- 出版者
- 日本地理教育学会
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.27-30, 1988-09-25 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 13
4 0 0 0 OA 粟島共同調査報告 (その1)
3 0 0 0 OA 「日本の国土」 についてのいろいろな疑問
- 著者
- 浅井 得一
- 出版者
- 日本地理教育学会
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.1-9, 1977-12-25 (Released:2010-02-26)
The writer researches several kinds of text books of the social study, and finds some confusion of expression and understanding as follows:1. Japan is called Nippon or Nihon in Japanese, but it depends upon teachers'choice which term they use in teaching.2. Some text books contain the south of Chishima islands as the territory of Japan, on the other hand, the others negrect them.3. Each text books indicates the total area of cultured field of Japan dependent on different sources.4. Japan is not an empire, kingdom or republic after the War.The category of Japanese national structure is now obscure. The course of study by the Ministry of Education does not show any indication about it.The writer shows in this paper the problems mentioned above.
3 0 0 0 OA 泰緬鉄道補遺
- 著者
- 浅井 得一
- 出版者
- 日本地理教育学会
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.1-31, 1963-03-25 (Released:2010-02-26)
泰緬鉄道については, はじめて耳にする人もあると思うので, 正編とやや重複のきらいはあるが, その概要についてしるすことにする。泰緬鉄道は太平洋戦争中に日本軍がタイとビルマの間に建設した延長415kmにおよぶ鉄道である。日本軍は昭和17年5月のビルマ全土の占領をもって, 南方進攻作戦を成功のうちに終了した。しかし連合軍の日本軍占領地域に対する反攻は, インド洋方面においてまず開始され, 昭和17年の後半になると, ラングーン-シンガポール間の航路は, 連合軍の航空機と潜水艦による攻撃のために危険となって, ほとんどとだえてしまった。このため17年6月から安全な陸路としての鉄道の建設が始まったのである。ビルマとタイを結ぶ鉄道の建設は, イギリス側でも調査をしたことがあり, トングーからチェンマイに至るもの, モールメンからビサヌロークに至るもの, メルギーからチュンポンに至るものなどのルートが考えられていたが, のちに日本軍が鉄道を建設したサム・オン峠 (いわゆるThree Pagodas' Pass) を越えるタンビザヤ-ノンブラドック間のルートについては, 工事が困難であるとして, 具体的な計画は何も立てていなかったようである。 (第1図) タンビザヤ-ノンブラドックのルートは, 地形的に見ればそれほどけわしいものではなく, 最高点のサム・オン峠も海抜450mしかない。イギリス側が困難なりとしたのは, おそらくここが世界的に名高い悪性マラリアの浸淫地であつたからではなかろうか。そして日本軍がここを選んだのはこのルートがビルマ側およびタイ側の既設の鉄道を結ぶ最短距離であったからである。このルートのタイ側はメクロン川およびその支流ケオノイ川の谷に沿っており, 雨期には川を利用すればビルマ国境に近いところまでさかのぼることができる。ジャングルの主体は竹で, 株をつくってはえているから, 株と株の間は自由に通行できるが, 1つの株の竹と他の株の竹は上方で互にからみ合っていて, 道を開くために下方を切っても, 竹は倒れず, また焼いても燃えない。工事にはこのような思わぬ困難が待っていたのである。雨量は年に3,000mm内外であるが, その2/3は5月から9月までの雨期に降るから, ケオノイ川は氾濫の危険があり, またビルマ側は多くの川がこのルートを横切っているので, 流木を伴う急流のために, 橋が流失するおそれがある。工事はビルマ側およびタイ側から同時に始められ, 昭和18年10月17日に東西の軌道がタイのコンコイターで連接され, 1年余りで完成した。日本軍の鉄道2個連隊を基幹とする部隊のほか, ジャワ, シンガポール, ビルマから集めたオランダ, オーストラリア, イギリスなどの連合軍の俘虜と, タイ, ビルマ, マライ, ジャワ, 仏印などの現地人の労務者がこの工事に従った。俘虜は昭和18年8月には47,737名 (うち患者27,053名, 就業率42%) に達し, 現地人労務者は多いときには10万名ぐらいいた。工事に従う者の多くがマラリアにたおれたほか, 昭和18年の初めにはコレラがビルマ側で発生し, 4月にはタイ側に波及, マラリアやコレラのために日本軍1千, 俘虜1万, 現地人労務者3万の死者を出している。雨期には食料の輸送が不円滑となり, 奥地方面約100kmの間は, 栄養失調のための犠牲者も出た。軌間はlmで, 日本からC56型機関車および貨車 「トム」 が送られビルマ, タイ, マライ, 仏印からも機関車, 貨車が集められた。軌条はラングーン-マンダレー間の複線およびイェ線の一部をはずしてもってきたり, マライの東部線をはずすなどおもに現地のものを利用したが, サイゴンに集結してあった大本営手持ちのもの120kmも使った。鉄道は完成したが, 最初の計画の1日の輸送量1方向3,000tは, 工事をいそいだためその1/3の1,000tに変更された。すなわち1列車100t (10t貨車10両), 10往復20列車という案で, これは5個師団分の常続補給量であり, 絶対に欠くことができないものであった。しかし開通後間もなく空襲が始まって, 昼間輸送は困難となり夜間を主として1日に3列車の運転がせいいっぱいというところであった。停車場には必ず密林内に待避線をつくり, 昼間は列車をここへいれておくのである。また輸送は主として貨物と患者のみに限り, 健康な兵員は線路に沿って歩かせた。列車の時速も20kmにすぎなかったが, 航空路を除けば, これはビルマ-タイ間の唯一の連絡路となり, ビルマにおける20万の日本軍への補給は, 細々ながらこの1本の鉄道によってささえられていたのである。敗戦後は日本軍の引揚げに使われたのち, こんどはイギリス軍に指揮された日本軍の俘虜の手によって, その大部分が撤去されてしまった。シンガポールの繁栄を守るため, あるいはビルマ, タイ2国の接近を警戒するためにイギリスがとった処置は, 大きな犠牲をはらって建設したこの鉄道をふたたびジャングルの中にうずめてしまったのである。
2 0 0 0 泰緬鉄道補遺
- 著者
- 浅井 得一
- 出版者
- The Geographic Education Society of Japan
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.1-31, 1963
泰緬鉄道については, はじめて耳にする人もあると思うので, 正編とやや重複のきらいはあるが, その概要についてしるすことにする。<br>泰緬鉄道は太平洋戦争中に日本軍がタイとビルマの間に建設した延長415kmにおよぶ鉄道である。<br>日本軍は昭和17年5月のビルマ全土の占領をもって, 南方進攻作戦を成功のうちに終了した。しかし連合軍の日本軍占領地域に対する反攻は, インド洋方面においてまず開始され, 昭和17年の後半になると, ラングーン-シンガポール間の航路は, 連合軍の航空機と潜水艦による攻撃のために危険となって, ほとんどとだえてしまった。このため17年6月から安全な陸路としての鉄道の建設が始まったのである。<br>ビルマとタイを結ぶ鉄道の建設は, イギリス側でも調査をしたことがあり, トングーからチェンマイに至るもの, モールメンからビサヌロークに至るもの, メルギーからチュンポンに至るものなどのルートが考えられていたが, のちに日本軍が鉄道を建設したサム・オン峠 (いわゆるThree Pagodas' Pass) を越えるタンビザヤ-ノンブラドック間のルートについては, 工事が困難であるとして, 具体的な計画は何も立てていなかったようである。 (第1図) タンビザヤ-ノンブラドックのルートは, 地形的に見ればそれほどけわしいものではなく, 最高点のサム・オン峠も海抜450mしかない。イギリス側が困難なりとしたのは, おそらくここが世界的に名高い悪性マラリアの浸淫地であつたからではなかろうか。そして日本軍がここを選んだのはこのルートがビルマ側およびタイ側の既設の鉄道を結ぶ最短距離であったからである。<br>このルートのタイ側はメクロン川およびその支流ケオノイ川の谷に沿っており, 雨期には川を利用すればビルマ国境に近いところまでさかのぼることができる。ジャングルの主体は竹で, 株をつくってはえているから, 株と株の間は自由に通行できるが, 1つの株の竹と他の株の竹は上方で互にからみ合っていて, 道を開くために下方を切っても, 竹は倒れず, また焼いても燃えない。工事にはこのような思わぬ困難が待っていたのである。雨量は年に3,000mm内外であるが, その2/3は5月から9月までの雨期に降るから, ケオノイ川は氾濫の危険があり, またビルマ側は多くの川がこのルートを横切っているので, 流木を伴う急流のために, 橋が流失するおそれがある。<br>工事はビルマ側およびタイ側から同時に始められ, 昭和18年10月17日に東西の軌道がタイのコンコイターで連接され, 1年余りで完成した。日本軍の鉄道2個連隊を基幹とする部隊のほか, ジャワ, シンガポール, ビルマから集めたオランダ, オーストラリア, イギリスなどの連合軍の俘虜と, タイ, ビルマ, マライ, ジャワ, 仏印などの現地人の労務者がこの工事に従った。俘虜は昭和18年8月には47,737名 (うち患者27,053名, 就業率42%) に達し, 現地人労務者は多いときには10万名ぐらいいた。<br>工事に従う者の多くがマラリアにたおれたほか, 昭和18年の初めにはコレラがビルマ側で発生し, 4月にはタイ側に波及, マラリアやコレラのために日本軍1千, 俘虜1万, 現地人労務者3万の死者を出している。雨期には食料の輸送が不円滑となり, 奥地方面約100kmの間は, 栄養失調のための犠牲者も出た。<br>軌間はlmで, 日本からC56型機関車および貨車 「トム」 が送られビルマ, タイ, マライ, 仏印からも機関車, 貨車が集められた。軌条はラングーン-マンダレー間の複線およびイェ線の一部をはずしてもってきたり, マライの東部線をはずすなどおもに現地のものを利用したが, サイゴンに集結してあった大本営手持ちのもの120kmも使った。<br>鉄道は完成したが, 最初の計画の1日の輸送量1方向3,000tは, 工事をいそいだためその1/3の1,000tに変更された。すなわち1列車100t (10t貨車10両), 10往復20列車という案で, これは5個師団分の常続補給量であり, 絶対に欠くことができないものであった。しかし開通後間もなく空襲が始まって, 昼間輸送は困難となり夜間を主として1日に3列車の運転がせいいっぱいというところであった。停車場には必ず密林内に待避線をつくり, 昼間は列車をここへいれておくのである。また輸送は主として貨物と患者のみに限り, 健康な兵員は線路に沿って歩かせた。列車の時速も20kmにすぎなかったが, 航空路を除けば, これはビルマ-タイ間の唯一の連絡路となり, ビルマにおける20万の日本軍への補給は, 細々ながらこの1本の鉄道によってささえられていたのである。<br>敗戦後は日本軍の引揚げに使われたのち, こんどはイギリス軍に指揮された日本軍の俘虜の手によって, その大部分が撤去されてしまった。シンガポールの繁栄を守るため, あるいはビルマ, タイ2国の接近を警戒するためにイギリスがとった処置は, 大きな犠牲をはらって建設したこの鉄道をふたたびジャングルの中にうずめてしまったのである。