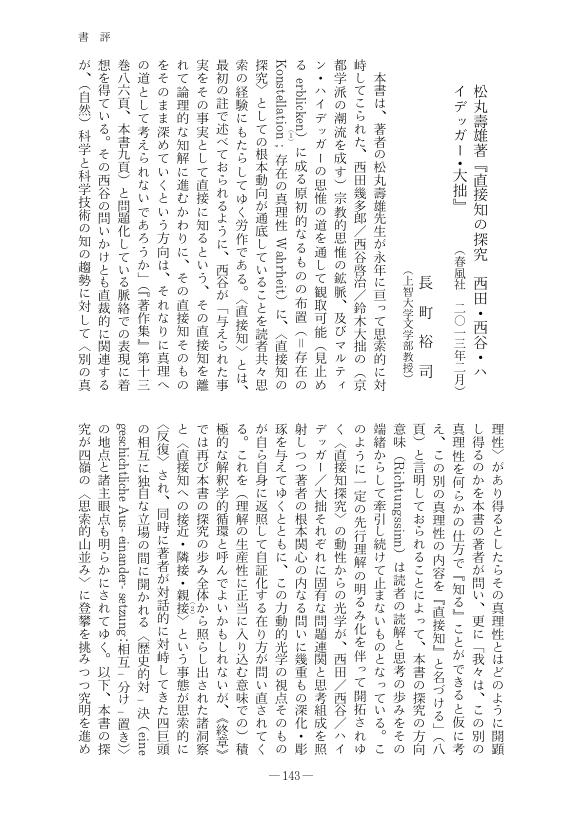5 0 0 0 中世後期アリストテレス哲学受容における知性・霊魂論の発展
- 著者
- RIESENHUBE K. 長町 裕司 オロリッシュ J?C 荻野 弘之 川村 信三 佐藤 直子 大谷 啓治
- 出版者
- 上智大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 1999
本研究は西欧ラテン中世盛期・後期スコラ学におけるアリストテレスの知性論・霊魂論の受容・解釈史を解明することを課題とした。方法的に、アリストテレス『霊魂論』解釈の手がかりとなったそのアラブ哲学註解、特にアヴィセンナとアヴェロエス、また多大な影響を及ぼした新プラトン主義的精神理解、特に『原因論』、さらにアウグスディヌスの意識論的精神論との関係を研究の視野に入れることになった。本研究では『霊魂論』の解釈史の中で以下の諸段階と諸学派を区別することができた。1.13世紀前半ではアリストテレスの知性論は、アヴィセンナに従って理解され、能動知性が拒否されることもあれば、アウグスティヌスの照明説と結びつけて能動知性が神と同一視される(オックフォード学派)など広く異なった試みが見られる。2.1250〜70年代、1252年パリ大学学芸学部で『霊魂論』が教材として採用される時点から始まるラテン・アヴェロエス主義の、そのパリでの禁令書に至る、この中心的な時期において、(1)アルベルトゥス・マグヌス、(2)ブラバンのシゲルス、(3)ボナヴェントゥラ、(4)特にトマス・アクィナスにおける能動知性・可能知性の諸解釈の発展と絡み合って身体と霊魂の差異がアウグスティヌス主義的に理解される一方、知性と霊魂が同一視され、霊魂と身体の実体的一致が積極的に新しい人間論に向かって展開されるが(アルベルトゥス、トマス)、その際アヴェロエスの新プラトン主義的な知性単一説との討論が原動力となった。3.1280〜1300年の過渡期においてラテン・アヴェロエス主義的知性論が至福論との関係において初めて体系的に発展する。4.1300〜30年ではアヴェロエス主義の知性論がパリからパドヴァとボローニャへと移り、知性単一説を基盤にした統一的なアリストテレス解釈が推し進められる一方、ケルンのドミニコ会学派でフライベルクのディートリヒによって能動知性論とアウグスティヌスの心理学的精神論が結びつけられた上、エックハルトが魂の造られざる根底という概念を基盤にドイツ神秘思想を知性論的に基礎づける。5.14世紀半ばから15世紀前半では形而上学的能動知性論の前提たる抽象説は、一方で唯名論的・経験論的に平面化され解消され、他方で15世紀前半のプラトン受容に伴って自己認識論によって乗り越えられ、近世の主体概念の先駆的形が見られる。6.16世紀前半のイタリアのアヴェロエス主義とトマス学派の間に霊魂不滅が議論の新しい焦点となる。
2 0 0 0 OA 西洋中世における「美」の概念--新プラトン主義の受容と変容の史的解明
- 著者
- 樋笠 勝士 荻野 弘之 佐藤 直子 長町 裕司 O'LEARY Joseph 川村 信三 児嶋 由枝 竹内 修一 HOLLERICH Jean-c 村井 則夫
- 出版者
- 上智大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2006
本研究は、平成18年度から21年度にわたる4年間の研究計画により、西洋中世における「美」の概念を、とくに新プラトン主義の受容と変容という課題に絞って、歴史研究を行うものである。本研究の独創性は「美」の概念について、古代末期思想家プロティノスに始まる新プラトン主義美学思想が、西洋中世キリスト教思想にどのような影響を与えたのかを解明する点にある。その思想の影響系列は、「美」を「光」と関係づけるキリスト教の伝統的な形而上学思想の原型をつくりだし、また典礼芸術等の芸術現象に展開する文化的基礎となる概念形成にも展開している。さらに中世の神学思想における超越概念にも影響を与える基本思想にもなっていることから、美学研究のみならず西洋中世思想研究の基礎研究にとって、本研究課題は思想史研究上の大きな意義を有するものとなる。
- 著者
- 長町 裕司
- 出版者
- 上智大学哲学科
- 雑誌
- 哲学科紀要 (ISSN:0286925X)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.1-58, 2012
1 0 0 0 OA 書評 松丸壽雄著 『直接知の探究 西田・西谷・ハ イデッガー・大拙』
- 著者
- 長町 裕司
- 出版者
- 西田哲学会
- 雑誌
- 西田哲学会年報 (ISSN:21881995)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.143-147, 2014 (Released:2020-03-22)
- 著者
- 長町 裕司
- 出版者
- 西田哲学会
- 雑誌
- 西田哲学会年報 (ISSN:21881995)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.51-68, 2013 (Released:2020-03-22)
Den Versuch zu unternehmen, das Verständnis des ‘Nichts’ sowohl in der philosophischen Ideengeschichte des Abendlandes als auch im ostasiatischen Denken zu ergründen und ans Licht zu bringen, ist das grundsätzliche Hauptanliegen dieser Abhandlung. Um dies zu ermöglichen, ist zunächst einerseits die Problematik in Bezug auf das ‘Nichts’ bei Meister Eckhart, dem Begründer der deutschen Mystik im Spätmittelalter, zu untersuchen; andererseits sollte das Gedankenfeld Nishida Kitarōs im Kontext der Problematik des ‘Nichts’ erneut in seiner Gesamtkonstellation zur Darstellung gebracht werden. Dabei ist auch eine mögliche dialogische Dynamisierung zwischen den jeweils eigenen Verständnishorizonten beider Denker positiv in Betracht zu ziehen. Das ‘Nichts’-Verständnis Eckharts ist zwar in mindestens drei kontextbezogenen Dimensionen konzipiert, zugleich aber in seiner eminent onto-theologischen Denkrichtung als einheitlich einzusehen: nämlich, die relationale Nichtigkeit des innerweltlich-kreatürlichen Seienden in seiner Abgetrenntheit von der einzigen Seinsfülle Gottes, das ‘nihil’ des ‘intelligere’ durch seine ontisch nicht unendliche Offenheit, und das ‘Nichts’ Gottes in seiner formlos-universalen Gottheit ― diese drei kontextuell differenzierten Aspekte lassen sich im Eckhartschen Gedankenkern ausfindig machen. Im zweiten Teil dieses Traktats werden die Entwicklungsphasen des Hauptgedankens Nishidas in Bezug auf das Nichts skizzenhaft dargelegt. Ausgehend von den frühen Schriften Nishidas ist die entscheidende Gründung des topologischen Standpunktes beim späten Nishida herauszukristallisieren. Darauf abzielend ist die genaue Untersuchung des »Ort«-Traktats(1926)und der darauf folgenden Vertiefung des topologischen Gedankens im religiösen Standpunkt des ‘absoluten Nichts’(seit 1931)von großer Bedeutung.