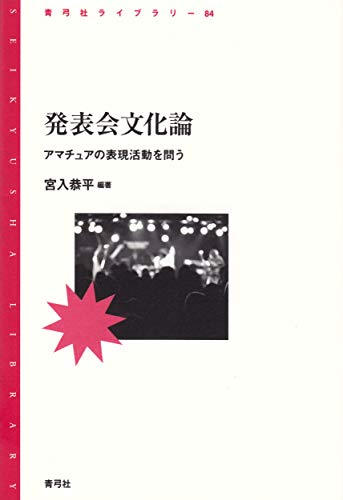- 著者
- 宮入 恭平 歌川 光一
- 出版者
- 音楽文化創造
- 雑誌
- 音楽文化の創造 : cmc
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.15-18, 2014-07
2 0 0 0 若きカート・コバーンの悩み
- 著者
- 宮入 恭平
- 出版者
- 国立音楽大学紀要編集委員会
- 雑誌
- 研究紀要 = Kunitachi College of Music journal (ISSN:02885492)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.165-174, 2019
2 0 0 0 団塊世代によるノスタルジアとしての音楽消費
- 著者
- 宮入 恭平
- 出版者
- 日本余暇学会
- 雑誌
- 余暇学研究 (ISSN:1882269X)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.28-39, 2010-03
1 0 0 0 OA シティポップ再評価の背景 : ノスタルジア、反時間性、そして憑在論
- 著者
- 宮入 恭平
- 出版者
- 国立音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 = Kunitachi College of Music journal (ISSN:02885492)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.115-125, 2022-03-31
シティポップが再評価されている。シティポップとは、1970年代以降の日本のポピュラー音楽を系譜とする音楽ジャンルとして一般的に容認されている。シティポップをめぐっては、これまでに数多くの議論がなされてきた。とは言え、その定義は曖昧で漠然としたものだ。そこには、多かれ少なかれ、恣意的な評価が加味されていることは否めない。シティポップは2000年代になって国内で散見されるようになり、そこで再定義や再解釈がおこなわれるようになった。さらに、2010年代にはインターネットを介して世界的に認知されるようになり、昨今のシティポップ再評価へと結びついたのだ。シティポップは、ある特定の音楽ジャンル概念というよりはむしろ、記号的な意味合いが強い。本稿では、シティポップそのものに関する議論というよりはむしろ、シティポップが再評価される背景に注目しながら、社会・経済・政治との関係を明らかにする。
1 0 0 0 3.11が日本のポピュラー音楽シーンに与えた影響
- 著者
- 宮入 恭平
- 出版者
- 国立音楽大学
- 雑誌
- 国立音楽大学研究紀要 (ISSN:02885492)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.115-126, 2011
ポピュラー音楽は、音楽産業という文化産業がつくりだす商品として消費されている。しかし、2011年3月11日に発生した東日本大震災は、日本のポピュラー音楽シーンにさまざまな影響をもたらすことになった。平穏な日常生活のなかでは自明のものだったポピュラー音楽シーンにおける規範-音楽産業がつくりだす商品としてのポピュラー音楽の消費-は、3.11によって改めて問い直されることになったのだ。3.11が発生してから半年が経過したポピュラー音楽シーンは、3.11以前と比べて、何かが変わったのだろうか?あるいは、何も変わっていないのだろうか?本稿では、時間の経過-3.11以前、3.11発生直後、そして3.11以降-とともに変化を見せてきた日本のポピュラー音楽シーンについて検証しながら、自明のものとなっていたポピュラー音楽シーンの規範について考察する。
1 0 0 0 ライブハウス概念の再考
- 著者
- 宮入 恭平
- 出版者
- 国立音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 = Kunitachi College of Music journal (ISSN:02885492)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.163-172, 2018-03-31
興隆するライブ・エンタテインメント市場の一翼を担っているライブハウスは、ライブハウス概念の一側面といえるだろう 。その一方で、ライブハウスが広く認知されはじめたのは、ビジネス化にともなうシステム化が確立した1980年代半ばだった。そして、この時期のシステム化したライブハウスは、ライブハウス概念のもうひとつの側面としてとらえることができるだろう。本稿では、多様化する日本のライブハウスの現状を検討したうえで、ライブハウス概念の再考を試みる。まず、ライブハウスに関するデータを更新したうえで、ライブハウスを取り巻く現状を確認する。そして、物議をかもすことになったブログの記事から、既存のライブハウスに対する認識を読み解く作業を試みる。そのうえで、システム化したライブハウスの特徴でもあるノルマ制度に注目しながら、現状のライブハウスに対する認識について検討する。そこから、ライブハウス概念が明らかになる。
1 0 0 0 抵抗の音楽 : 日本のポピュラー音楽シーンにおける反原発運動
- 著者
- 宮入 恭平
- 出版者
- 国立音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:02885492)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.117-127, 2012
2011年3月11日に発生した東日本大震災によって引き起こされた東京電力の福島第一原子力発電所事故は、日本国内における原子力エネルギー政策を根本から問い直す契機になった。3.11が発生してから時間の経過とともに、「絆」や「がんばろう!日本」といった言説は希薄になった。その一方で、TwitterやFacebookといったソーシャルメディアを中心に叫ばれてきた反原発の声は、テレビや新聞といったマスメディアからも聞かれるようになった。チャリティに偏向していたポピュラー音楽シーンにも、反原発を掲げる政治性に注目する動きが見られるようになった。 第二次世界大戦後の日本では、商品としてのポピュラー音楽に偏向するあまり、音楽の政治性が可視化されづらい状況にあった。しかし、ポスト3.11の原発問題によって、音楽と政治の関係は無視できないものになっている。本稿では、日本のポピュラー音楽シーンにおける反原発運動を検証しながら、音楽の存在意義について考える。
1 0 0 0 発表会文化論 : アマチュアの表現活動を問う
- 著者
- 宮入 恭平
- 出版者
- 国立音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:02885492)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.159-169, 2014
〈右傾化〉が囁かれる日本社会において、J-POPはどのような立ち位置をとっているのだろうか。表面的には政治と乖離しているはずのポピュラー音楽が、政治と近接しながら〈右傾化〉する社会でのプロパガンダとして利用される可能性がある。ここで重要になるのは、音楽に政治的な意味が含まれるかどうかではなく、政治性の希薄な音楽が無自覚的に政治利用されてしまうことへの懸念だ。もちろん、ポピュラー音楽は商品として消費されるものだが、その一方で、人びとの意識を変革させるだけの影響力をも持ち得ている。したがって、たとえ音楽そのものに政治的な意図が含まれていなかったとしても、音楽家(作詞家、作曲家や歌手)、および楽曲そのものの意志とは無関係に、音楽が政治的に利用されてしまうこともあり得るのだ。