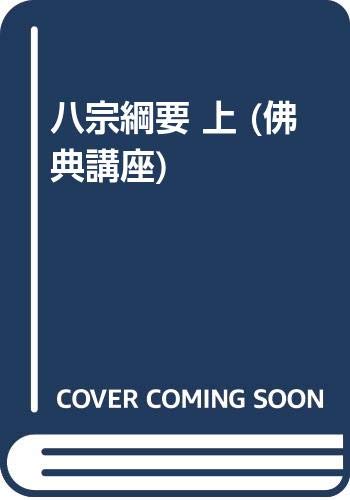2 0 0 0 OA 律蔵とカルマン
- 著者
- 平川 彰
- 出版者
- 大谷大学佛教学会
- 雑誌
- 佛教学セミナー = BUDDHIST SEMINAR (ISSN:02871556)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.26-44, 1974-10-31
2 0 0 0 OA 禅と戒律
- 著者
- 平川 彰
- 出版者
- 愛知学院大学
- 雑誌
- 禅研究所紀要 (ISSN:02859068)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.363-378, 1976-12-28
1 0 0 0 OA 大乗仏教の興起と文殊菩薩
- 著者
- 平川 彰
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.580-593, 1970-03-31 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 大乗経典の発達と阿闍世王説話
- 著者
- 平川 彰
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1-12, 1971-12-31 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 般若と識の相違 (平成六年十月十二日 提出)
- 著者
- 平川 彰
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.1-25, 1995 (Released:2007-06-22)
In my paper I discuss the difference between prajña and vijñana from various angles. Firstly, I examine Majjhima-nikaya No. 43, Mahavedalla-sutta, the sutta expounding the difference between prajña and vijñana. This sutta points out that prajña and vijñana exist within the same mind framework, at the same time; and act upon the same objects at the same time; however, they are different ways of understanding because prajña is‘to become aware of something’whereas vijñana is‘to recognize something by distinguishment, ’and thus, while prajna can be strengthened by training, our perception of vijñana must be re-examined.
1 0 0 0 OA 説一切有部の認識論
- 著者
- 平川彰
- 出版者
- 北海道大學文學部
- 雑誌
- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-19, 1953
1 0 0 0 IR 説一切有部の認識論
- 著者
- 平川 彰
- 出版者
- 北海道大學文學部
- 雑誌
- 北海道大学文学部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.3-19, 1953-03
On the basis of the Double Truth (二諦)the Sarvastivadins adopt, the preasent writer tries to prove that the epistemology and the ontology, both making out their Dharma-theory, Stand in intimate relations to each other. According to the Abhidharmakosasastra and Yasomitra's commentary on it, paramarthasatya (勝義諦)and samvrtisatya(世俗諦)advocated by the Sarvastvadins mean respectively paramarthasat(勝義有)and samvrtisat(世俗有), thus these two kinds of sat are equally recognised by them as satya, ie, as truth. Svabhava dharmah of the school belong to paramarthasat which, however, presupposes samvtisat, both being established on the mutual relationship. The Sarvastivadins are strongly opposed by the Sunyavadins who insist upon the nihsvabhavata of the dharmas and interpret the svabhavas of the Sarvastivadins only as svo bhavah. But this opposition should be regarded as merely one-sided, because according to the Sarvastivadins svabhava may be interpreted both as substance and as attribute so that dharma presupposes dharmin which is samvrtisat sc. prajnaptisat(仮有) In this respect the relation between paramarthasat and samvtrtisat is, stricly speaking, different from that between guna and dravya of the Vaisesika school. Namely the Sarvastivadins teach that dharma is an attribute inasmuch as it has an owner (dharmin) and that it is at the same time a dravya, inasmuch as the owner of the dharma is Prajnapti (conventional). Thus in this point that the dharma has the double meaning consist, the present writer believes, the characteristics of the Dharma-theory of the Sarvastivadins and only by interpeting it in the way, we can understand the reason why the Savrastivadins insist upon the anatmavada and the ksanabhngavada on the one hand, while they accept the svabhava of the dharmas on the other.
1 0 0 0 コンゼ仏教 : その教理と展開
- 著者
- エドワード・J.D.コンゼ著 平川彰横山紘一訳
- 出版者
- 大蔵出版
- 巻号頁・発行日
- 1975
1 0 0 0 戒壇の原意
- 著者
- 平川 彰
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.680-700, 1962
1 0 0 0 仏教研究の諸問題 : 仏教学創刊十周年記年特輯
1 0 0 0 仏教思想の諸問題 : 平川彰博士古稀記念論集
- 著者
- 平川彰博士古稀記念会編
- 出版者
- 春秋社
- 巻号頁・発行日
- 1985
平成13年度以来同16年迄の4年間、幸い科学研究費補助金の支給を受け、研究協力者の助言を得ながら研究を続行し得た成果を以下に報告する。近時ジェンダー研究が盛んで本邦に於いても社会学者を中心に所謂「女性差別」「男女平等」を学問的に研究しようとする気運が昂まった。筆者はこの問題を自らが専攻する古代インドの文献に徴して学問的に研究しようと試み、方法論を筆者の専攻する文献学に取り、斯学の世界的リーダーとして令名の高かったロンドン大学のJ.Lisley博士の精神的支持を得てその研究に従事した。不幸にして同博士は昨年急逝したが、同種の研究に従事する「ギリシャの女たち」の著者桜井万里子氏(東大教授)やタイ国の法制史を研究し比丘尼の生活規範を纏め上げた石井米雄氏(文化功労者、京大名誉教授)の助言を得ながら同学のインド古典研究者、仏教学者を研究協力者として研究を進めた。ここに提示するものは過去四年間に亘って研究代表者が発表したもの中心に同類の「女性」に関する過去の研究を一括したものである。その結果分量が大部となり、従って研究協力者の論文は今回見合わせざるを得ず、それらは別の機会に発表する事とした。古代インドの「貞女」「烈女」「淫女」の諸相、「妻」「娘」の地位を中心に「男尊女卑」の系譜を辿ると共に、「貞節」「不倫」の諸問題を系統的に文献に徴して整理したものである。