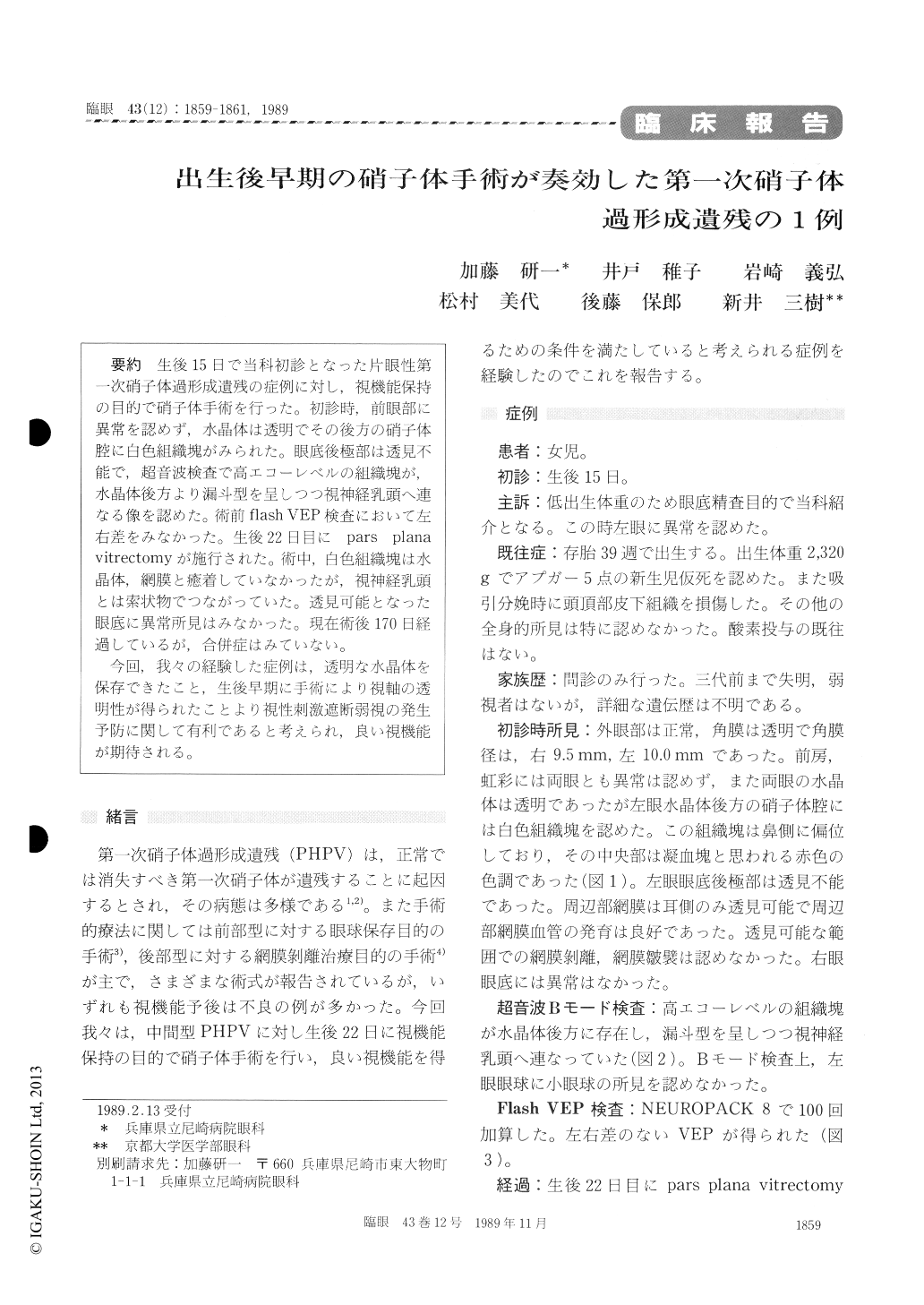1 0 0 0 出生後早期の硝子体手術が奏効した第一次硝子体過形成遺残の1例
- 著者
- 加藤 研一 井戸 稚子 岩崎 義弘 松村 美代 後藤 保郎 新井 三樹
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床眼科 (ISSN:03705579)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.12, pp.1859-1861, 1989-11-15
生後15日で当科初診となった片眼性第一次硝子体過形成遺残の症例に対し,視機能保持の目的で硝子体手術を行った。初診時,前眼部に異常を認めず,水晶体は透明でその後方の硝子体腔に白色組織塊がみられた。眼底後極部は透見不能で,超音波検査で高エコーレベルの組織塊が,水晶体後方より漏斗型を呈しつつ視神経乳頭へ連なる像を認めた。術前flash VEP検査において左右差をみなかった。生後22日目にpars planavitrectomyが施行された。術中,白色組織塊は水晶体,網膜と癒着していなかったが,視神経乳頭とは索状物でつながっていた。透見可能となった眼底に異常所見はみなかった。現在術後170日経過しているが,合併症はみていない。 今回,我々の経験した症例は,透明な水晶体を保存できたこと,生後早期に手術により視軸の透明性が得られたことより視性刺激遮断弱視の発生予防に関して有利であると考えられ,良い視機能が期待される。
1 0 0 0 網膜内層の電気生理学的研究
本年度の研究は人体で計測した臨床電気生理学的実験とネコ、ニワトリ網膜を用いて行った動物網膜の電気生理学的実験を行った。臨床電気生理学的には正常者と網膜内層の異常があると考えられる緑内障眼において、多局所網膜電図(Sutterら)を測定した。緑内障眼では有意に多局所網膜電図各波の振幅の低下、頂点潜時の延長が認められたが、これが網膜内層の変化を反映しているのか、視細胞など外層の変化を反映しているのかは、来年度以降の基礎実験が必要である。基礎実験の内、M波については薬理学的手法を用いて行った。TTXを用いてナトリウム依存性活動電位を抑制するとM波は変化しないがERGのoff反応は減少した。M波のon反応はAPB投与により極性が反転し、この反転した波はaspartateによって消失した。また網膜電図のSustained negativer responseはAPBによって変化しなかった。この様にM波の臨床的ERGへの関与は小さいが、パターン刺激のように小さい刺激野で刺激する場合などでは関与する可能性が考えられた。Scotopic threshold response(STR)に関しては、微少電極でこの波のdepth profileを調べることができたが、STRは内網状層付近で最大となり、網膜中心付近(60%の深さ)で極性が逆転した。このことは、この点より近位側に電流のsinkが存在することが推定され、電流のsourceはさらに遠位側にあると考えられた。またカリウム選択性電極を用いてカリウム変化を測定した結果ではカリウム濃度の変化と網膜電図の変化に密接な関係がみとめられた。
1 0 0 0 視覚誘発電位を用いた他覚的視機能評価
パターン視覚誘発電位(PVEP)は眼科領域では眼底黄斑部や視神経の機能評価に用いられ、病変による機能障害の判定などに利用される。PVEPのうち刺激の反転頻度が早い、8ヘルツ以上のものをsteady-statePVEPという。刺激の空間周波数を変化させるとPVEPの振幅はある空間周波数で最大となり、その空間周波数より高いものでも低いものでも振幅は低下する。この現象を空間周波数特性と呼ぶが、この特性を利用して他覚的に視力を測定することができるようにしたものがスイープPVEPである。この方法で得られた視力(PVEP視力)と通常の視力表を使った自覚的視力検査との違いをみるために正常者の眼前にアクリルフィルターをおき視力を低下させてPVEP視力と通常の視力を測定し比較した。フィルターなしの状態で通常の視力検査での視力が1.0以上のときでもPVEP視力は0.6から0.7を示した。アクリルフィルターの数を増やすと通常の視力検査による視力が低下するよりも早くPVEP視力は低下を示した。通常の視力検査とPVEP視力は0.3で一致したが、1.0から0.3のあいだでも両視力検査の値は1オクターブ以上離れることはなかった。実際の臨床ではどれくらい視力が障害されているのかを評価することに使用するため、視力が良い状態での両視力検査の乖離はあまり問題にならないと思われる。また、各種眼疾患による視力障害をもつ80例に対しても両視力検査を行い相関をみた。通常の視力検査では0.3より良い症例ではPVEP視力は低くなり、反対に通常の視力が0.3以下になるとPVEP視力はよくなる傾向がみられた。両視力検査の間の相関係数は0.66であった。特に黄斑疾患の症例で両者の相関は高かった。乳幼児に対してもPVEP視力測定を行う予定である。