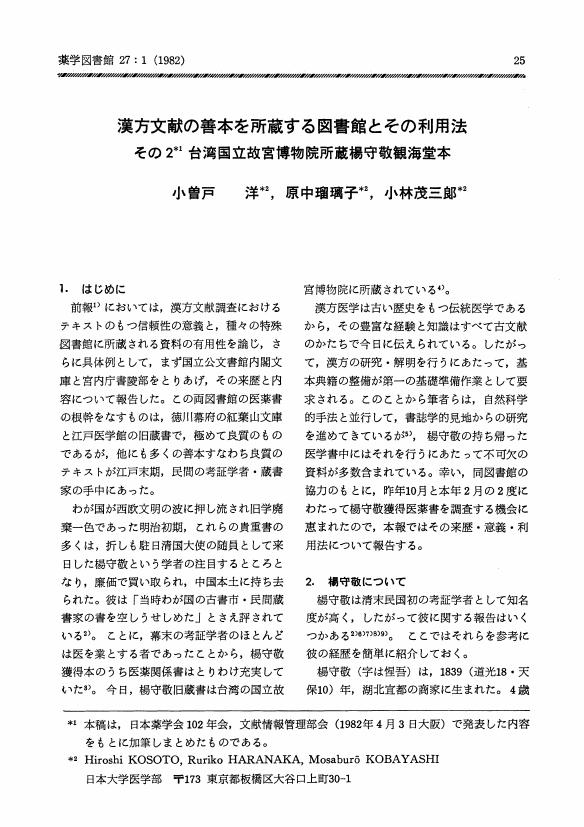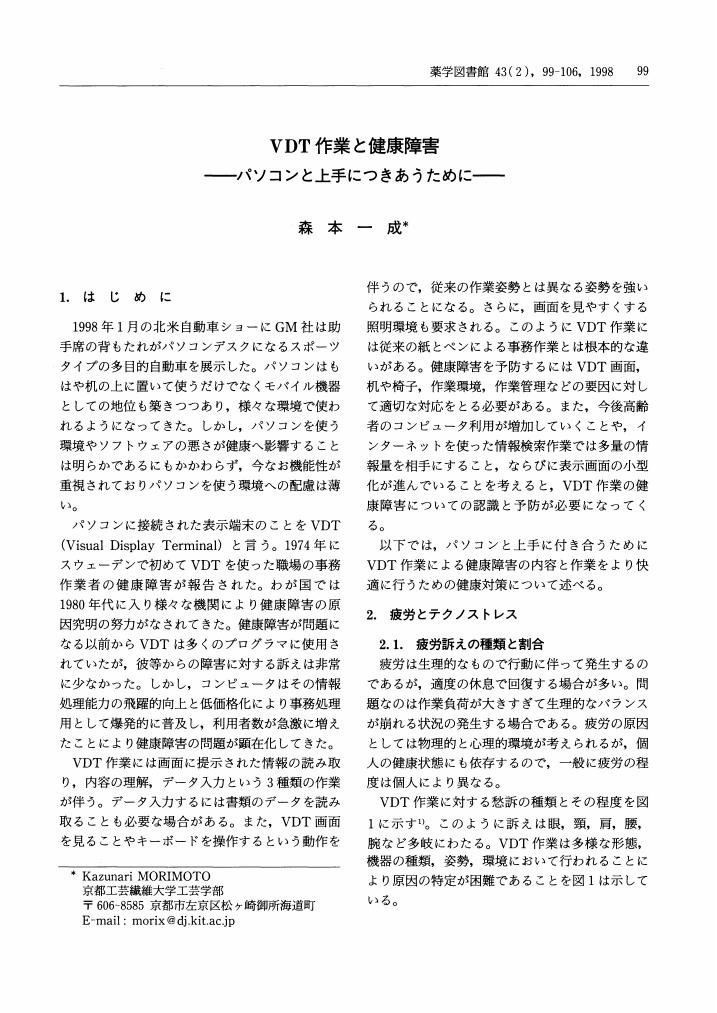- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.103-106, 1992
1 0 0 0 図書館員から見た科学者の生態―大学編
- 著者
- 高田 真一
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.97-99, 1993
1 0 0 0 OA 医薬品名の「つけ方」と「つき方」
- 著者
- 川田 恒康
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.395-399, 1999-10-31 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 小曽戸 洋 原中 瑠璃子 小林 茂三郎
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.25-32, 1982
- 著者
- 小山 政子
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.15-21, 2008
財団法人日本医薬情報センター (JAPIC) 附属図書館では1997年に図書館システムを導入し, 2005年12月より所蔵情報, 新着情報などを「図書館検索メニュー」として公開しています。また, 2006年9月には, 医学・薬学関係の学会・地方会などの開催予定情報を収載した「医学・薬学関連学会開催情報検索」を追加公開しました。今回はJAPICのホームページの中から, 附属図書館が管理している上記のサイトについて, 公開にいたるまでの経緯とその内容について紹介させていただきます。医療関係者の皆様の日常業務にご活用いただければ幸いです。
1 0 0 0 OA 副作用情報資料の重要性
- 著者
- 堀岡 正義
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.127-130, 1970-06-30 (Released:2011-03-18)
- 著者
- 関口 千登世
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.112-115, 2013
城西大学では,地域の社会や文化・教育・環境保護などに貢献する活動を幅広く行い,地域と共にある大学を目指している。その中において図書館も教育・研究成果の情報発信をするとともに,図書館の施設を開放し,専門分野の資料提供や貸出サービスを行ってきた。このたび,これらの活動を図書館総合展ポスターセッションで発表することができた。本稿では,ポスターセッション参加のきっかけから,ポスター制作過程,発表後のポスター活用なども交え報告する。
1 0 0 0 OA 図書館員のためのカウンター英語
- 著者
- 高田 宜美
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.10-20, 1994-01-31 (Released:2011-09-21)
薬学図書館には33巻4号に図書館員のための基礎英語 (1) 英文手紙の書き方と34巻1号に (2) カウンターにおける英会話を2回にわたり執筆した。(1) では図書館において日常目に触れる英文手紙のサンプルをあげ解説した。(2) では大学図書館, 企業の研究所や病院の図書館 (室), 情報センター等のカウンターにおいて留学生, 外国人研究者や訪問者との基本的な会話のサンプルをあげた。今回, 再度前回触れなかった点, 書き加えたい点, 編集者の要望事項を含めて執筆依頼を受けた。今回は約5年を経て図書館を取り巻く環境も大きく変化したので, 特に, カウンター業務を行う初心者が英語で質問された時に対応しなければならないオンライン検索, CD-ROM検索の申込, 料金の説明, Faxによる文献複写の申込, 送付等を中心に出来るだけ簡単で短い会話のサンプルをあげるが, 編集者の希望で前回の内容と一部重複するところもあるのでご了承いただきたい。最後に肯定的, 否定的な応答の仕方, 婉曲的な断わり方, あいつちの仕方等いくつか覚えておけばスムースに話せると思われる短い文章をあげておいたので参考にしてほしいと思う。
1 0 0 0 デジタルアーカイブにおけるDOIなどの永続的識別子の利用(前編)
- 著者
- 時実 象一
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 = Pharmaceutical library bulletin (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.115-120, 2020
1 0 0 0 デジタルアーカイブにおけるDOIなどの永続的識別子の利用(後編)
- 著者
- 時実 象一
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 = Pharmaceutical library bulletin (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.198-204, 2020
1 0 0 0 OA 図書紹介 災害と資料保存/薬社会への処方箋
- 著者
- 瀧本 まのみ 高田 真一
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.76-77, 1998-01-31 (Released:2011-09-21)
1 0 0 0 OA 漢方文献の善本を所蔵する図書館とその利用法その4東北大学附属図書館
- 著者
- 石田 秀実 小曽 戸洋
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2-3, pp.156-161, 1984-11-15 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 23
1 0 0 0 OA 漢方文献の善本を所蔵する図書館とその利用法
- 著者
- 小曽戸 洋 原中 瑠璃子 小林 茂三郎
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.25-32, 1982-06-15 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 漢方文献の善本を所蔵する図書館とその利用法
- 著者
- 小曽戸 洋 真柳 誠
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.31-37, 1983-07-20 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA VDT作業と健康障害
- 著者
- 森本 一成
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.99-106, 1998-04-30 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 特別展「はやり病の文化誌―麻疹・庖瘡・コレラ―」
- 著者
- 伊藤 恭子
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.255-258, 2001-07-31 (Released:2011-09-21)
1 0 0 0 OA 目録カードの複製法
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.120-140, 1974-06-20 (Released:2011-12-05)
1 0 0 0 カウンター中国語3.
- 著者
- 叢 小榕
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.307-315, 1998
1 0 0 0 OA 語義からみた「薬」と「薬学」
- 著者
- 小原 正明 金尾 素健
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.84-91, 1980-07-15 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 IR 「ビブリオバトル首都決戦2011予選会in城西」を開催して
- 著者
- 若生 政江
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.67-69, 2012-01
「1. ビブリオバトルとは」 みなさんはビブリオバトルをご存知でしょうか? ビブリオバトルとは, 1. お気に入りの本を持って集まる. 2. 順番に1人5分でその本の紹介をする. 3. どの本を読みたくなったか? を出場者, 聴衆者で投票をしてチャンプ本を決める. という, 知的書評合戦です. 課題図書などがあるわけでなく, 自分で読んで面白いと思ったものを自分の言葉で, パワーポイントもレジュメもなしで語ります. 5分の発表の後, 2分間で聴衆とのディスカッションを行いますが, どんな質問が出るかもわかりません. 聞き手の多くが一番読んでみたくなったと思う本がチャンプ本になります. 自分の言葉でいかに聞く人の心をつかむか, 5分という限られた時間内で, その本の魅力, 面白さを他人に伝え, 読んでみたいと思わせる, これはプレゼンテーションの勉強にもなります. 考案者の京都大学谷口忠大先生は, ビブリオバトル公式サイト1)の中の「ビブリオバトル誕生」2)で「イイ本に出会える仕組み自体を勉強会の中に取り込めないだろうか?」と考え, 「人の脳は自分が話さないと活性化しない」「『即興性』を大切にして, みんなが探してきた本をレジュメもなく紹介し合って, その中で一番イイ本を勉強すればいいんじゃないか?」と考えられたことを紹介しています.