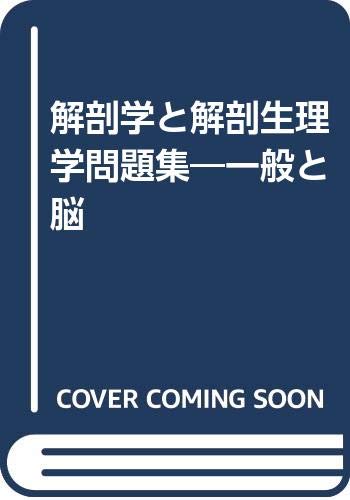8 0 0 0 OA 小胸筋の停止異常と鳥口上腕靱帯との関係について
- 著者
- 肱岡 昭彦 鈴木 勝己 小林 靖幸 北條 暉幸 中島 民治
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.9-12, 1991-09-01 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 10
Abnormal insertions of the pectoralis minor have been reported on by many authors, Most have dealt with its extending beyond the coracoid process and attaching itself to the capsule. We, however, studied the relationship between abnomal insertions of this muscle and the coracohumeral ligament.53 cadavers, i. e.106 shoulders were examined in this study,38 males and 15 females. The age of the cadavers ranged from 43 to 93, with mean age of 67.5 years.Abnomal insertions were found in 26 of the 53 cadavers and 39 of the 106 shoulders. This abnormality presented itself more often in females than in males.The coracohumeral ligament it usualy know as the ligament which occurs from the coracoid and is inserted in the humerus, but in our study this ligament did not clearly exist.In conclusion, we consider the coracohumeral ligament to be a residual l igament of the pectoralis minor or connective tissues in a part of the capsule.
7 0 0 0 OA 日本人肩甲骨形状の時代的変化の研究に基づく徳川将軍集団とアイヌ集団のタイプ分析
- 著者
- 北條 暉幸
- 出版者
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会
- 雑誌
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 (ISSN:13451537)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-5, 2005-10-20
- 被引用文献数
- 1
日本人肩甲骨の計測学的研究結果に基づき徳川将軍集団とアイヌ集団の肩甲骨について主成分分析を行い、おおまかにタイプ分類し、徳川将軍集団と江戸時代などの庶民集団との差を検討した。計測項目は、肩甲骨の形態長(幅)と棘上窩幅(前後幅)で、前者は肩幅、後者は肩の筋肉の盛り上がりを表し、さらに徳川将軍集団と同時代江戸時代庶民の肩甲骨の高さ(背筋が弱いと低い可能性)を比較した。縄文時代集団は最も肩幅が広いが、肩の前後幅は比較的狭く(胸郭が薄い)、筋肉質であり(タイプI)、徳川将軍集団は、肩幅が狭くなで肩、肩甲骨は後代に高くなるが江戸時代庶民より低く、筋肉が最も弱いタイプIV、室町時代集団はがっちりした肩、筋肉も強く、いかり肩のタイプII、江戸時代集団はこの集団に近くタイプIIIである。現代人集団もやや弱い傾向のタイプIIIを示した。室町、江戸両時代集団は特異な徳川将軍集団より頑丈な形状であり、アイヌ集団は比較的がっちりしたタイプIを示し、以上4タイプの大まか分類、肩甲骨のライフスタイルの変化への適応も論じられた。
1 0 0 0 OA 北九州人女子の身長, 座高および比座高
- 著者
- 北條 暉幸 中島 民治 平尾 登美
- 出版者
- The University of Occupational and Environmental Health, Japan
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.355-357, 1984-12-01 (Released:2017-04-11)
- 被引用文献数
- 3 3
北九州市在住の17才の女子高生, 318名の身長,座高および比座高(身長に対する座高の百分率)を対象に研究した, 計測は, Martin-Saller法に基づいて行われた. 計測値は1973年, 1980年および1984年に計測された3群に分けられ, これら3群間に身長, 座高および比座高の各値に統計的に有意な差がなかった. 比座高は約54%で, この値は3群に共通であるばかりでなく, 若干の中国人, エスキモー人, アメリカ・インディアンおよび北海道アイヌ人に共通である.
1 0 0 0 OA ヒト腹直筋鞘弓状線の位置と形状
- 著者
- 北條 暉幸
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.159-162, 1980-06-01 (Released:2017-04-11)
- 被引用文献数
- 1
解剖学用語(PNA)では, 弓状線は腹直筋鞘後葉と腸骨にあるが, 本研究は腹直筋鞘後葉にある弓状線の位置とその形状について, 行われたものである. 研究対象は男性23体, 女性3体, 合計26体である. 弓状線の位置と形状には, かなりの変異が認められた. すなわち, その最も高い位置は臍から下方へ1.7cmで, 後葉が恥骨結合に直接結合する場合が1例観察された. 最も多く出現するのは, 臍から下方へ7cmから12cmまでの距離の間にあり, 88%に出現する. また, 上下2本の弓状線を左右両側にもった重複弓状線が2例認められた.
1 0 0 0 OA 日本人肩甲骨形状の時代的変化の研究に基づく徳川将軍集団とアイヌ集団のタイプ分析
- 著者
- 北條 暉幸
- 出版者
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会
- 雑誌
- バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 (ISSN:13451537)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-5, 2005-10-20 (Released:2017-09-04)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
日本人肩甲骨の計測学的研究結果に基づき徳川将軍集団とアイヌ集団の肩甲骨について主成分分析を行い、おおまかにタイプ分類し、徳川将軍集団と江戸時代などの庶民集団との差を検討した。計測項目は、肩甲骨の形態長(幅)と棘上窩幅(前後幅)で、前者は肩幅、後者は肩の筋肉の盛り上がりを表し、さらに徳川将軍集団と同時代江戸時代庶民の肩甲骨の高さ(背筋が弱いと低い可能性)を比較した。縄文時代集団は最も肩幅が広いが、肩の前後幅は比較的狭く(胸郭が薄い)、筋肉質であり(タイプI)、徳川将軍集団は、肩幅が狭くなで肩、肩甲骨は後代に高くなるが江戸時代庶民より低く、筋肉が最も弱いタイプIV、室町時代集団はがっちりした肩、筋肉も強く、いかり肩のタイプII、江戸時代集団はこの集団に近くタイプIIIである。現代人集団もやや弱い傾向のタイプIIIを示した。室町、江戸両時代集団は特異な徳川将軍集団より頑丈な形状であり、アイヌ集団は比較的がっちりしたタイプIを示し、以上4タイプの大まか分類、肩甲骨のライフスタイルの変化への適応も論じられた。
1 0 0 0 OA 北部九州の女子学生と女性農民の足型
- 著者
- 北條 暉幸 中島 民治
- 出版者
- The University of Occupational and Environmental Health, Japan
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.265-268, 1985-09-01 (Released:2017-04-11)
北九州市とその郊外に住む23人の女子学生の足型の計測学的研究である. 彼等の両親は福岡県人である. 約20年前に計測された北部九州の非都会的環境(農村など)に在住した2つの異なった集団とこれらの女子学生の間に, 足長(足型の長さ)に関して有意の差は存在しなかったが, 女子学生の身長は最も高く, また足指数(足型の長さに対する足型の幅)は小さく足型は細長い形であった. これらの足型の特徴は, 都会的な生活と世代間の相違によるものと考えられる.
1 0 0 0 解剖学と解剖生理学問題集 : 一般と脳
1 0 0 0 アイデア解剖学問題集 : 一般解剖学と脳解剖学、2択から5択へ
1 0 0 0 解剖学教育における用語の検討(1) ―スネ(〓)とネズミ(鼡)―
- 著者
- 北條 暉幸
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- 産業医大誌 (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.433-436, 1984
- 被引用文献数
- 1
筆者は, 解剖学教育の立場から, 若干の日本解剖学用語の検討を行った. 日本解剖学用語は杉田玄白以来200年を超える伝統をもち, 現在では漢字が用いられるだけでなく, カタカナも用いられ, さらに近年は簡略化した漢字も使われるようになっている. 〓骨の〓, 鼡径管の鼡がその例で, 鼡径管はラテン語解剖学名の翻訳ではなく含蓄の深い学名であると考えられる. 解剖学用語の下腿にスネをあてることは誤りで, 下腿前部に脛(〓), スネをあて, ハギも追加するようにし, さらに下腿後部に腓腹, フクラハギをあて, これにコムラを追加することを提唱した. さらに, 日本解剖学用語として, 鼠蹊管の場合, 鼠の代りに鼡, 蹊の代りに径などの新しい字体を採用していることを一般に周知徹底し, さらに辞書類の改訂を求めることを提唱した. なお, 日本解剖学用語としては, 脛に〓, 鼠に鼡の字体を用いることを強制してはいない.<br>(〓=つきへん+又+土)
1 0 0 0 OA 北九州人女子の身長,座高および比座高
- 著者
- 北條 暉幸 中島 民治 平尾 登美
- 出版者
- 産業医科大学学会
- 雑誌
- 産業医科大学雑誌 (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.355-357, 1984-12-01
北九州市在住の17才の女子高生, 318名の身長,座高および比座高(身長に対する座高の百分率)を対象に研究した, 計測は, Martin-Saller法に基づいて行われた. 計測値は1973年, 1980年および1984年に計測された3群に分けられ, これら3群間に身長, 座高および比座高の各値に統計的に有意な差がなかった. 比座高は約54%で, この値は3群に共通であるばかりでなく, 若干の中国人, エスキモー人, アメリカ・インディアンおよび北海道アイヌ人に共通である.