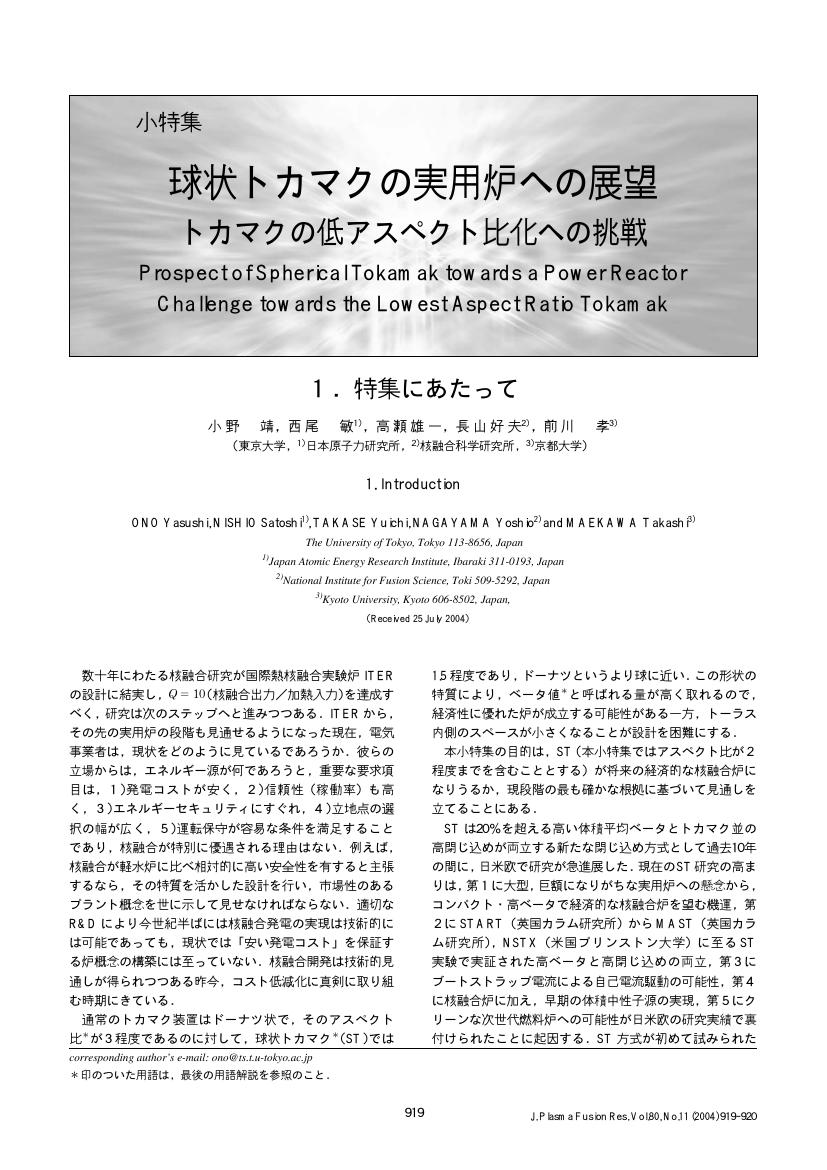2 0 0 0 OA 球状トカマクの実用炉への展望 -トカマクの低アスペクト比化への挑戦- 1.特集にあたって
- 著者
- 小野 靖 西尾 敏 高瀬 雄一 長山 好夫 前川 孝
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.919-920, 2004 (Released:2005-07-14)
2 0 0 0 OA 医療関係者に対するツベルクリン反応およびBCG接種歴調査と二段階ツベルクリン反応の検討
- 著者
- 日野 光紀 小野 靖 小久保 豊 杣 知行 田中 庸介 小俣 雅稔 市野 浩三 上原 隆志 工藤 翔二 葉山 修陽
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS
- 雑誌
- 結核 (ISSN:00229776)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.347-354, 2002-04-15 (Released:2011-05-24)
- 参考文献数
- 17
1998年日本結核病学会予防委員会より院内感染対策についてのガイドラインが指導され, ツベルクリン反応 (以下, ツ反) 二段階法が推奨されている。これにはブースター効果を含めた結核感染診断に際して対照値 (ベースライン値) の記録を必要とする。われわれは612名の医療関係者に対しツ反二段階法を行った。その結果を分析し至適方法を確立すること。さらに, ツ反施行前に質問用紙を用いて過去のBCG接種歴, ツベルクリン反応歴およびその反応値を聴取し, その保存状況を把握することを目的とした。ほとんどの者が過去の測定値管理が不十分であった。二段階法の結果, 発赤径, 硬結径ともにブースター効果を認めた。さらに, 年齢別の硬結径の拡大径で壮年群のほうがより拡大傾向にあった。さらに, 職種別, 勤務部署別の計測値には統計学的有意差は得られなかった。二段階法ツベルクリン検査1回目の発赤径値が30mm以上の計測値でありながら2回目で10mm以上の拡大を認める被検者が多くいることから, 院内感染管理の上でこのような対象者に対しても二段階法を施行することが必須であると考えられた。
1 0 0 0 OA 磁場揺動計測を用いた高ベータ球状トカマクのバルーニングモードの解析
- 著者
- 梅田 耕太郎 小野 靖
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) (ISSN:03854205)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.11, pp.1143-1144, 2003 (Released:2004-02-01)
- 参考文献数
- 4
The Ballooning mode, which occurs at a region where the plasma pressure gradient exceeds a certain limit, needs to be suppressed to achieve high β. Using a magnetic-probe system with a high spatial resolution, we measured magnetic fluctuations in a very local area to get fluctuations due to the Ballooning mode. As its result, we found that the amount of fluctuation decreased with Itfc while Itfc < 40 kA, but that it increased while Itfc > 40 kA, which agreed with the earlier simulation of the ballooning mode. Analyzing the fluctuation of Itfc > 40 kA, we found that the frequency was 0.4 - 0.8 MHz and the mode number was about 10.
- 著者
- 小野 靖
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.921-923, 2004 (Released:2005-07-14)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 1
High-beta ST research is motivated by its high normalized current Ip/aBT0 achievable at a low aspect ratio and its direct access to second stability for ballooning modes. Key issues for the high-beta ST sustainment are profile control for ballooning/ current-driven kink stabilities and positioning of the conductive wall for mode suppression. ST termination by resistive wall modes (RWM) revealed that velocity shear is a useful tool for the better stability.
最終年度である本年度は、レーザー誘起蛍光(LIF)に用いる高速波長掃引(RAFS)色素レーザーの実用可能性の検証を行った。また、高速光強度計測系及びモノクロメーター系を構築し、東京大学球状トカマク装置UTSTにおいてプラズマ流速計測を試みた。レーザーパルス1ショットで流速ベクトル計測を行う場合、波長掃引の時間が必要なこと、プラズマイオンの蛍光の寿命等の理由により、RAFS色素レーザーのパルス幅は長いことが望ましい。そこで、色素レーザーを励起するNd-YAGレーザーの長パルス化を、Qスイッチのオフアライメントにより行った。また、レーザーエネルギーとパルス幅の計測を行い、計算から見積もった、LIFに必要なエネルギーと比較した。その結果、長パルス化は、目標値100nsに対し20-30nsが限界であることがわかった。そのため今回は、レーザーパルス幅は長くせず、色素レーザー内蔵の回折格子の角度制御をレーザーのショットパイショットで行うことによる波長掃引とした。UTSTにおいて、ポロイダル流速計測用高速光計測系及びトロイダル流速計測系を構築し、ワッシャーガン生成プラズモイド、オーミック生成トカマクに対して流速計測を試みた。トロイダル流速計測精度は、音速の1/2~1/3程度であった。結論として、LIFに用いる波長掃引レーザーでは、時間分解能は落ちるが、ショットバイショット計測(現状で〜数十Hz)で行う方がよいこと、色素レーザーの代わりにダイオードレーザーを用いる選択もありうることがいえる。RAFSレーザーで、シングルショットでの波長スキャンも可能だが(PZT駆動エタロンで波長掃引速度は達成可能)、波長モニタ、メンテナンス等に問題が多い空間二次元トロイダル流速分布の導出は本手法で十分可能である。ただし、レーザーの迷光の除去が完了せず、ポロイダル流速の導出に対する評価までには至らなかった。
1 0 0 0 OA ベータ値限界と MHD 4.第二安定化へ向かう高ベータ球状トカマク研究
- 著者
- 小野 靖
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.144-151, 2003 (Released:2005-09-28)
- 参考文献数
- 15
Recently, high-beta operations of Spherical Tokamak (ST) have received increased attention due to the compatibility achieved between high-beta and a long confinement time. In addition to the high normalized current I/aB achievable at a low aspect ratio, an important advantage of high-beta ST is its direct access to second stability for ideal ballooning modes. The mega-ampere class experiments, NSTX and MAST, renewed the record beta values up to βT˜35%, increasing confinement time up to τE˜0.1 sec. Small-scale experiments produced the second-stable STs with diamagnetic toroidal field /absolute minimum-B by transforming oblate FRCs. Major issues for the second stable STs are achieving a stable startup/ profile control for kink and the ballooning stabilities and a concrete approach to high-ratio pressure driven currents .
1 0 0 0 青年期の双極II型障害 : 抑うつ症状を呈する通院患者の再検討
- 著者
- 棟居 俊夫 小野 靖樹 武藤 宏平 下田 和紀 中谷 英夫 越野 好文
- 出版者
- 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1-13, 2008-02-01
- 被引用文献数
- 3