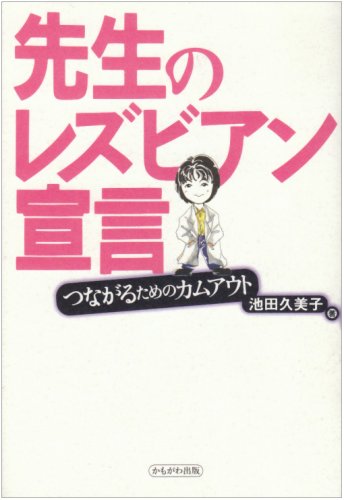19 0 0 0 OA 学生は何が分からないか : 分からなさの型
- 著者
- 池田 久美子
- 出版者
- 信州豊南短期大学
- 雑誌
- 信州豊南短期大学紀要 = Bulletin of Shinshu Honan Junior College (ISSN:1346034X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.105-122, 2001-03-03
本を読ませ、「疑問・分からないことを書きなさい。」と指示する。それに応えて学生は、自分が分からないと感じる事柄を書く。この、学生が分からないと感じる事柄は、多様である。だから、それぞれの分からなさに対してどう指導すべきかも、多様でありうる。どう指導すべきかを考えるためには、学生の分からなさの実態を知らなければならない。分からなさの実態=症状に基づいて、どこでどうつまずいているかを診断しなければ、的確に指導=治療することは出来ない。学生の思考の実態を診断する診断学が必要である。本稿では、学生が分からないと感じる事柄を分類する。分類してみると、そこに複数の型を見出すことが出来る。この型は、指導方法の違いに対応する。型が違えば、指導方法はそれに併せて変わる。型は、的確な指導方法を構想するための手がかりである。
10 0 0 0 OA 「はいまわる経験主義」の再評価 知識生長過程におけるアブダクションの論理
- 著者
- 池田 久美子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1981, no.44, pp.18-33, 1981-11-15 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 18
The experience-oriented learning was heavily criticized as causing learners to 'crawl-about' for trivial facts. But this criticism not only failed to take account of the potential of proliferation of codes formed through experience-oriented learning, but also disturbed the study of their proliferation. A similar mistake was made also by those who defended the experience-oriented learning. Both, the accuser and the defender of the experience-oriented learning, were equally restricted within the frame of the dichotomy of 'experience' and 'knowledge' distorted by a deductive theory of knowledge.Contrary to this dichotomy, it is necessary to construct the theory of learning on the basis of the logic of abduction. The author tries to prove that learning should be regarded as a proliferation of codes; hence the learner first of all must try to transform codes temporarily by abduction. The codes activate the inherent selfproliferating tendency when they fulfil the required conditions to cause abduction.It is through the very 'crawling-about' that these conditions are fulfilled, so it is absurd to maintain that the 'crawling-about' prevents the learner from growing in knowledge. The 'crawling-about' is never fruitless, but should be accepted as the indispensable foundation for subsequent learning.
9 0 0 0 先生のレズビアン宣言 : つながるためのカムアウト
3 0 0 0 OA 外傷性脳損傷後10年以上経過した患者の家族の介護負担感
- 著者
- 渡邉 修 秋元 秀昭 福井 遼太 池田 久美 本田 有正 安保 雅博
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.3-8, 2019 (Released:2020-09-30)
- 参考文献数
- 11
【はじめに】交通事故や転倒転落を主な原因とする外傷性脳損傷(traumatic brain injury;TBI)は、とくに中等度から重度の場合、後遺する身体障害および高次脳機能障害により、介護する家族の負担は深刻である。しかし、外傷後の経過とともに、これらの障害は、改善していくことから、家族の介護負担感も軽減していくと考えられる。本研究は、TBI後、10年以上が経過した事例について、その家族の介護負担感を調査した。【対象および方法】TBI後、10年以上が経過した344例の患者の家族に、質問紙によるアンケート調査を行った。344例(男性289例、女性55例)は、受傷時平均年齢は24.0±13.3歳、現在の平均年齢は、43.6±12.3歳、TBIからの平均経過年数は、19.6±7.5歳であった。【結果】現在、296例(86.0%)が家族と同居していた。このうち、34例(全体の9.9%)が配偶者と同居していた。単身者は48例であった。バーセルインデックス(barthel index;BI)は、平均89.3±19.3で、日常生活が自立しているとされる85点以上は、270例(78.5%)であった。認知行動障害とZarit介護負担尺度は正の相関を認めた。一方、BIとZarit介護負担尺度には相関は認められなかった。就労群の受傷時年齢は非就労群に比し若年であった。そして、現在の年齢も、就労群のほうが若年であった。一方、介護負担感は、有意に就労群のほうが低かった。外出頻度別に介護負担感を比較すると、高頻度外出群のほうが、介護負担感は低かった。【結語および考察】受傷後、10年が経過しても介護する両親(あるいは主に妻)の負担感が大きい。介護負担感と認知行動面の障害には正の相関があり、さらに介護負担感には有意に就労の有無、外出頻度が関連していた。社会性の確立こそがTBIで表れやすい認知行動障害を改善に導く。患者ごとにそれぞれの目標に沿って、地域リハビリテーション、職業リハビリテーションを提供していくことが、家族の介護負担感を軽減することになると考えられる。
2 0 0 0 OA 『夕焼け』の授業における「自我」の欠落 : 文化的同調の要求
- 著者
- 池田 久美子
- 出版者
- 信州豊南女子短期大学
- 雑誌
- 信州豊南女子短期大学紀要 = Bulletin of Shinshu Honan Women's Junior College (ISSN:02897644)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.337-359, 1985-03-10
1 0 0 0 OA 小川博久著『保育援助論』
- 著者
- 池田 久美子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.82, pp.110-111, 2000-11-10 (Released:2010-01-22)
本書は、雑誌連載論文十篇から成る。保育における「指導」「生活」「環境」等の意味、幼稚園教育要領批判・「幼児文化的解釈の必要性」、「援助行為の身体論的考察」等が論じられている。具体的な保育事例に即して語っている所は示唆に富み、面白い。しかし、著者が志した「保育学の理論」 (p.267) の書としては、残念ながら不出来である。主たる原因は二つある。
1 0 0 0 OA 「規則」概念の分析 議論・レトリック思考において
- 著者
- 池田 久美子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1983, no.47, pp.85-89, 1983-05-15 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 動的相対主義の無基準性 特に「確定」「不確定」について
- 著者
- 池田 久美子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.40, pp.50-64, 1979-11-30 (Released:2009-09-04)
Prof. Ueda says, “The dynamic A cannot be identified with an abstract generality, Ao, in the final analysis.” I admit it makes some sense to distinguish an object (A) from an abstract notion of it (Ao).But is he right when he asserts on the basis of this distinction that any actual cognition of an object is entirely uncertain and fluctuant? Is it right to deprive actual cognitions of certainty?I argue against his assertion for the following reasons.i) We should not treat “Certain” and “Uncertain” as an absolute dichotomy. Being certain to some degree necessarily implies being uncertain to some degree at the same time. The real question is to what degree a notion is certain. Many-valued thinking is necessary.ii) It is quite a nonsense to say that our actual cognitions can be uncertain altogether. To regard them uncertain, there must be some unquestionable viewpoint according to which we can measure the degree of uncertainty of the cognitions. Without such a viewpoint, we cannot regard them uncertain at all.iii) It is necessary to measure the degree of certainty of actual cognitions. What matters for this measurement is to analyze the content of individual cognitions. But in his book, Prof. Ueda ignores the content of cognitions in particular cases, so he fails to recognize how indispensable are the criteria to distinguish “Certain” from “Uncertain”.
- 著者
- 川本 和久 池田 久美子
- 出版者
- 日本学生陸上競技連合
- 雑誌
- 陸上競技研究 (ISSN:09199918)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.4, pp.37-43, 2003-12