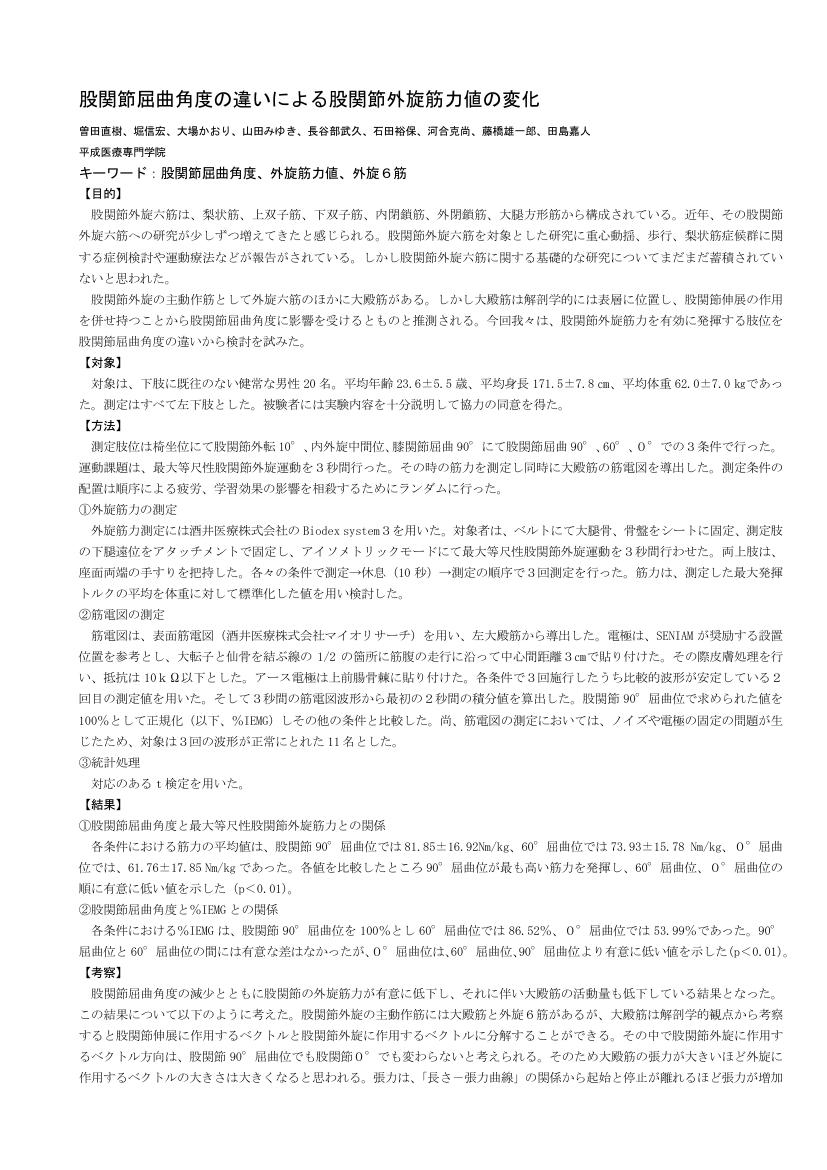7 0 0 0 OA 股関節屈曲角度の違いによる股関節の外旋筋力値の変化
3 0 0 0 OA 筋力と性差の関係から見た腹筋群の特徴
- 著者
- 植木 努 曽田 直樹 山田 勝也 河合 克尚 藤橋 雄一郎
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第26回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.39, 2010 (Released:2010-11-02)
【目的】 これまでに体幹筋の機能に関して多くの報告がされている。腹部表在筋は体幹運動におけるトルクの発揮に関与し、深部筋は腹圧を高め脊柱の安定性に関与しているといわれている。しかし、深部筋の機能に関してはまだ不明な点が多い。そこで本研究の目的は腹筋群の筋厚と体幹筋力及び性差の関係から、腹筋群の特徴を明らかにすることである。 【方法】 対象は健常男性31名、健常女性26名の計57名とした。筋力はバイオデックス及びマイオレットを使用し、各速度30、60°/sでの体幹屈曲最大筋力を測定した。筋厚は超音波画像診断装置を用いて、背臥位にて臍両側の腹直筋と前腋窩線上における腸骨稜近位の外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋を測定し、画像解析はImageJを用いて行った。統計学的分析は、筋力と筋厚の関連性にはPearsonの相関係数、男女間の比較は筋厚及び筋力を対応のないt検定を用いて行った。また被検者には本研究の目的を十分に説明し、参加の同意を得て実施した。 【結果】 体幹屈曲筋力(kg/m)の平均は男性14.80±3.39、女性9.20±2.13、全体11.73±4.64、筋厚(cm)の平均は腹直筋男性1.46±0.30、女性1.10±0.18、全体1.30±0.32、外腹斜筋男性1.00±0.33、女性0.84±0.26、全体0.93±0.31、内腹斜筋男性1.29±0.38、女性1.01±0.30、全体1.16±0.37、腹横筋男性0.66±0.22、女性0.58±0.19、全体0.63±0.20であった。筋力と各筋の筋厚の相関は、腹直筋(r=0.48)、内腹斜筋(r=0.30)、外腹斜筋(r=0.45)は有意な正の相関を示し(p<0.05)、腹横筋は有意な相関は示さなかった。また男女間での比較では、筋力、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋においては、男性が女性に対し有意に高い値を示したが(p<0.05)、腹横筋に有意差は見られなかった。 【考察】 本研究の結果より腹横筋の筋厚は筋力や性差に影響を受けないことが示唆された。その理由として腹横筋は腹圧を高めることで腰椎の安定性に関与し、体幹屈曲作用は少なく表在筋の運動の補助的な役割であるため、筋力に反映されにくいのではないかと考えられる。
1 0 0 0 OA 股関節内・外旋筋出力の優位性についての一考
- 著者
- 曽田 直樹 堀 信宏 大場 かおり 山田 みゆき 長谷部 武久 石田 裕保 河合 克尚 藤橋 雄一郎 田島 嘉人
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第23回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.O007, 2007 (Released:2007-11-02)
【目的】股関節内旋筋及び外旋筋は、股関節を回旋させる以外の機能として歩行時に同時収縮による安定性の役割や遠心性収縮による制御としての役割などがある。そのため両筋群の筋出力の優位性を把握することが必要である。股関節内外旋筋出力の優位性は、一般的に外旋筋出力の方が高いとされている。しかし、股関節伸展位(解剖学的肢位)での報告が多く、関節角度や姿勢変化に応じた筋出力の優位性についての報告はまだない。適切な評価や治療を施行するためには、異なる肢位での筋出力の優位性を把握することは重要であると考える。そこで今回、運動肢位の違いによる股関節内旋筋と外旋筋の筋出力の優位性について若干の考察を加え報告する。 【対象】対象は、下肢に既往のない健常な成人84名とした(平均年齢22.5±4.7歳、平均身長168.3±7.2_cm_、平均体重61.7±9.8_kg_)。全員には、本研究の趣旨を十分説明した上で同意を得た。 【方法】運動課題は最大等尺性股関節内旋・外旋運動とし、股関節屈曲位(椅坐位)と股関節伸展位(背臥位)での条件で筋出力の測定を行った。その際、股関節内外旋中間位・外転10°膝関節90°屈曲位とした。筋出力の測定には、バイオデックス社のシステム3を使用し、各条件でそれぞれ1回測定した。測定は3秒間行い、測定間には10秒間の休息を入れた。代償動作の防止のために、ベルトにて体幹、骨盤、大腿骨をシートに固定した。両上肢は座面両端の手すり、あるいは支柱を把持した。測定順序は、ランダムに行った。統計処理は対応のあるt検定を用い、有意水準は1%未満とした。 【結果】股関節伸展位での内旋筋出力は58.9Nm、外旋筋出力は74.8Nmであった。また股関節屈曲位での内旋筋出力は98.2Nm、外旋筋出力は80.6Nmであった。伸展位では外旋筋出力、屈曲位では内旋筋出力が有意に高い値を示した。 【考察】今回の測定では股関節屈曲位と伸展位では内外旋筋出力の優位性が逆転する結果となった。要因として肢位が異なることにより股関節内外旋に参加する筋が異なることが伺えた。一般的に股関節内旋筋の主な動筋は、小殿筋前部線維・中殿筋前部線維・大腿筋膜張筋であるが、KAPANDJIらによると梨状筋は股関節屈曲60度以下では外旋筋,60度以上では内旋筋として働くと報告している。またDelp SLらは大殿筋上部線維・中殿筋後部線維・小殿筋後部線維・梨状筋は伸展位では外旋筋として働き屈曲位では内旋筋として働くと報告している。つまりこれらの筋作用の逆転が今回の結果に大きく関わったと思われた。
1 0 0 0 OA 人工炭酸泉療法により足部潰瘍の改善が得られた閉塞性動脈硬化症の症例について
- 著者
- 佐伯 宏幸 河合 克尚 溝川 賢史 横家 正樹 皆川 太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.30 Suppl. No.2 (第38回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.443, 2003 (Released:2004-03-19)
【はじめに】人工炭酸泉浴は炭酸ガスの経皮的侵入によって血管拡張と血流増加、組織酸素分圧の上昇、微小組織循環改善などの生理的作用があると報告されている。末梢循環障害による足部潰瘍では切断に至る症例も稀ではない。人工炭酸泉浴はそれら末梢循環障害に対する保存的治療の手段として幅広く使用されている。当院においても人工炭酸泉浴の導入により良好な治療成果が得られた有効例を経験したので報告する。【治療内容】人工炭酸泉は三菱レーヨン・エンジニアリング社製人工炭酸泉製造装置を用いて、濃度約1000ppm、湯温37から38℃とし、浸漬部は下腿局所浴とした。【症例紹介1】48歳、維持透析歴7年の女性。2002年3月より右第1から4趾尖部の潰瘍増悪と疼痛のため歩行困難となり当院入院となる。潰瘍部は黒色壊死にて母趾が約20×22mm、第2から4趾も広範であった。下肢血管造影にて近位から遠位動脈まで高度狭窄病変を呈しており血行再建術不適応、薬物療法も効果不十分の状態であった。人工炭酸泉浴は毎日2回10分間実施した。開始から1ヶ月後、潰瘍の縮小と疼痛の緩和を認め、3ヶ月後には潰瘍と疼痛の消失により独歩にて退院となった。【症例紹介2】67歳、糖尿病、高血圧を有する女性。2002年4月より右踵部に潰瘍が出現し、疼痛の増悪にて歩行困難となり当院入院となる。潰瘍部は25×13×10mmであった。下肢血管造影にて両下腿動脈にびまん性高度狭窄病変を認め、血行再建術は困難と判断された。入院後から人工炭酸泉浴を毎日2回10分間実施したところ、約1ヶ月後には潰瘍の縮小を示し、3ヶ月後には潰瘍および疼痛の消失にて独歩可能となり退院となった。【考察】下肢動脈の慢性閉塞性疾患の根本的治療には血行再建術、薬物療法、理学療法があり、末梢循環障害による潰瘍は循環が改善すれば、潰瘍は軽快すると考えられる。人工炭酸泉浴による理学的治療は、組織循環の30%増加を認め、約4週の局所浴により効果が表れるなど、臨床的にも有効な末梢循環障害の基本的治療であり、長期的に見ても有望なものとされている。今回の症例では、いずれも血行再建術不可、薬物療法も効果不十分であったため、人工炭酸泉療法を行い、足部潰瘍および疼痛が消失し、退院時には独歩可能までになった。潰瘍を合併した虚血肢において人工炭酸泉療法は有用な理学療法の一手段と考えられた。