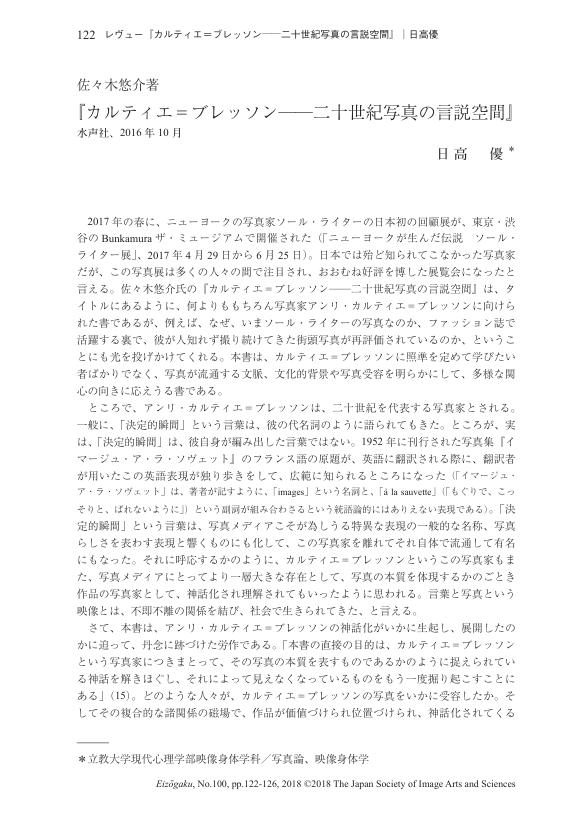2 0 0 0 堀潤之、菅原慶乃編著『越境の映画史』:書評
- 著者
- 応 雄
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, pp.52-55, 2015
- 著者
- 上田 学
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- no.78, pp.5-22, 2007
1 0 0 0 OA 途切れなき物語―ジャン・ユスターシュ『ナンバー・ゼロ』と同時代のテレビ作品
- 著者
- 須藤 健太郎
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, pp.27-40,95-96, 2013-05-25 (Released:2023-03-31)
Le present article se consacre à l’étude sur Numéro zéro (1971) de Jean Eustache (1938-81). En soulignant le contexte dans lequel s’inscrit le film, nous essayons de mettre en lumière un aspect curieusement peu commenté jusqu’a present: Jean Eustache l’a réalisé en marge de la télévision. Malgré son apparence naïve, Numéro zéro représente pour le cinéaste une forme de ≪manifeste≫ et de ≪prototype≫ qui joue un rôle déterminant dans l’orientation de son cinema. Cependant, afin de saisir la potentialité du film, il faudrait également traiter de la télévision, en particulier de la série Les Conteurs (1964-73) d’André Voisin et de l’expérimentation de Jean Frapat. Effectivement, souvent plus fréquente à la télévision qu’au cinéma (les emissions de rencontres, d’interviews et de débats), la tentative eustachienne de filmer la parole est enracinée surtout dans la lignée ouverte par André Voisin depuis les anneés soixante avec la collection Les Conteurs. Cinéaste légendaire des années soixante-dix, ≪auteur≫ par excellence du cinéma, Jean Eustache semble développer et radicaliser de telles pratiques apparues au sein de la télévision. Toutefois, son entreprise de toucher à l’≪automatisme≫ du cinéma est incompatible avec la télévision de l’époque.
- 著者
- 鷲谷 花
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, pp.119-122, 2004-11-25 (Released:2023-03-31)
- 著者
- 鈴木 啓文
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.73-91, 2018-07-25 (Released:2019-03-05)
- 参考文献数
- 21
【要旨】 従来、映画のショック体験がしばしば論じられてきた。対して、本論は触発し変様する映画身体の体験を考える。そのためにまず、ショック体験やイメージの強度的体験を重視するドゥルーズの『シネマ』とドゥルーズ的な映画身体論を確認する。そのうえで本論は、ショックを体験する映画身体とは区別される、触発し変様する映画身体を論じるため、ドゥルーズの身体の映画論からスピノザ的な身体論を掘り起こし検討する。身体の映画論のカサヴェテス作品を論じた箇所などには、触発し変様するスピノザ的な身体を見出せる。だが、思考論が主題である同論では、身体の触発と変様の経験のあり方や可能性が映画身体論的な観点から十分に論じられていない。そこで本論は、身体の映画論に潜在する身体の触発と変様や情動の揺れ動きといったスピノザ的な諸論点を引き出し、ドゥルーズとスピノザの議論と共に吟味する。そして最後に、情動の揺れ動きの観点からカサヴェテス作品の身体の触発と変様を分析する。とりわけ同作品の身体の疲労における情動の揺れ動きに着目し、情動の複数的な触発がもたらす情動の感受の仕方、つまり身体の組成の根本的な変貌を論じることで、触発と変様という映画体験の可能性を示す。
1 0 0 0 OA マニフェストとしての理論――1970年代のフェミニスト映画理論再考
- 著者
- 斉藤 綾子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.5-22,129, 1997-11-25 (Released:2023-03-31)
In this paper I attempt to understand feminist film theory not as the development of an autonomous and absolute theoretical construction, bu t as a manifesto, fraught with contradictions and difficulties which make the whole movement all the more significant, and at the same time historically determinant. Tracing some historically decisive moments in the development of feminist film theory in the 1970s, I introduce some crucial arguments and debates discussed by feminists with different political positions during the period, and in so doing argue that because of the ways in which feminist film theory tried to negotiate the difficult relationship between film theory and film practice it inevitably faced a theoretical impasse which nonetheless opened up other questions and problems latent in the semiotic / linguistic model, a dominant model in the 1960s and 70s film theory. My intention is to show that this is precisely why feminist film theory was and still is important, problematic as it is, today.
- 著者
- 岡村 忠親
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, pp.79-83, 2007-11-25 (Released:2023-03-31)
- 著者
- 渡邉 大輔
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, pp.79-83, 2014-11-25 (Released:2019-07-25)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA ドゥルーズにおける「記号」概念について―『シネマ 2』第2章の精読―
- 著者
- 築地 正明
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.115-136, 2019-07-25 (Released:2019-11-19)
- 参考文献数
- 39
本稿では、ジル・ドゥルーズ著『シネマ 1』、『シネマ 2』における「記号(signe)」概念に焦点を当てた考察を行う。それは、この概念が『シネマ』全二巻における本質的な要素をなしており、ドゥルーズによる「記号」概念の理解と、『シネマ』全体の理論に対する包括的視点を得ることとは、分けて考えることができないと思われるからである。またそれに加えて、ドゥルーズの提起した「記号」の理論は、古典的な映画研究にとどまらず、広く映像理論領域においても、今なお普遍的な価値を有していると考えられる。すでにこれまでにも、『シネマ』の批判的な分析の試みは、多くの理論家によってなされてはいる(1)。しかしながら、特にこの「記号」という点に関しては、必ずしも包括的な論述はなされてこなかったように思われる(2)。それゆえ本稿では、ドゥルーズが、アメリカの論理学者 C.S. パースの記号論、およびフランスの哲学者アンリ・ベルクソンのイマージュ論から引き出し、発展させた自身の新たな記号論と、クリスチャン・メッツの提起した言語学を基礎とする記号学とを対決させている、『シネマ 2』第 2 章の精読を通じて、この概念の重要性とその独特の性質を明らかにすることを試みたい。
- 著者
- 日高 優
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.122-126, 2018-07-25 (Released:2019-03-05)
1 0 0 0 OA 物語映画分析のための物語論の起源
- 著者
- シェアマン スザンネ
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.5-18,118, 1996-05-25 (Released:2023-03-31)
Contrary to the Romantic view of the author and his life as important for the creation of Art, the Russian Formalist Movement in the 1920s centered on the artwork. Besides some theoretical articles who mainly raised the question of the difference between the plot and the story, Vladimir Propp tried to analyze (authorless) fairy tales. These initial studies were reconsidered in the 1960s in France, specially in the Communications review. In this review, Christian Metz, Tzvetan Todorov, and Gérard Genette laid the foundations for the theory of narratology.A clarification of the main terminology of narratology and its origins is given.
- 著者
- 三浦 光彦
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, pp.27-48, 2023-02-25 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 25
本稿では、ロベール・ブレッソンの1951年の作品『田舎司祭の日記』に関して、物語論と演技論の観点から分析を行う。『田舎司祭の日記』において物語がどのように語られているか、物語と演技がいかに結びついているかを精査した上で、テクスト外の現実の作者であるブレッソンとテクスト内の語り手とがどのような関係を結んでいるのかを明らかにすることが本稿の目的である。まず、テクスト外の現実がテクスト内のフィクションに作用する次元を物語論的観点から論じているエドワード・ブラニガンの理論の有用性を示した上で、映画公開当時、ブレッソンがどのような社会的・歴史的状況に置かれていたかを概観し、それが物語理解にいかに作用するかを考究する。次いで、一見、司祭の一人称による語りに見えるこの映画が実際には、司祭とは別のもう一人の語り手を想定する必要があること、そして、司祭による語りと別の語り手による語りが混同していることを、テクスト分析を通じて明らかにする。その上で、こうした語りの構造が映画における役者たちの発声の仕方と結びついていること、さらに、演技指導を通じてブレッソンという現実の作者がテクスト内の語り手に限りなく接近していることを詳らかにする。最終的に、ブレッソンという現実の作者が『田舎司祭の日記』において、「不可視の語り手」としてあたかも映画全体を語っているかのようにテクスト全体を構造化していると結論づける。
1 0 0 0 OA 映像と目とまなざし (特集=写真の原形質)
- 著者
- 近藤 耕人
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.5-17,145, 1994-11-25 (Released:2019-07-25)
- 参考文献数
- 15
The chinese characters for "Eizo" which we Japanese use to mean visual image have a hard and mechanical impression, compared to "image" which means both inner and visual images. Its double meaning enables the word "image" to approach the subject from both the sides of our being, internal and external. J.-D. Nasio witnessed the separation of eyes and manazashi with one of her patients in Les yeux de Laure. Jacque Lacan, following J.P.Sartre, argued that eyes and manazashi do not coexist but hide each other. Lacan saw the embodyment of the invisible power of manazashi in the symbolic object flying in air in the middle space of the tableau, "The Ambassadors" by Hans Holbein the younger. He regards it as the expression of the hidden male desire incarnated in a skull=phallus image. The image as the projection of manazashi reflects the spirit of the viewer as well as his or her figure.
1 0 0 0 OA 他者としてのネイティヴと女性 『満洲グラフ』における植民地表象の様式
- 著者
- 半田 ゆり
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.27-48, 2019-01-25 (Released:2019-06-25)
- 参考文献数
- 31
【要旨】 本稿は、1930年代から40年代にかけて発行されたグラフ雑誌『満洲グラフ』におけるネイティヴと女性の表象が、植民地満洲の政治的背景といかに関わっていたのかを論じたものである。その目的は、時局にふさわしくない芸術性を批判されていた『満洲グラフ』という表象が、むしろ日本の植民地主義との相互依存的な関係にあったことを明らかにすることにある。1930年代に内地で流行した「芸術写真」「新興写真」の実践者たちが制作に関わった『満洲グラフ』は、戦時中の国家による写真家のプロパガンダへの動員を論じるのにふさわしい媒体である。既往研究は『満洲グラフ』の芸術性と政治性を分けて論じてきた。そこで本稿は、『満洲グラフ』の芸術性が植民地満洲のイデオロギーといかなる緊張関係にあったのかを検討した。『満洲グラフ』におけるネイティヴと女性の表象に着目した結果、ロシア人女性と日本人女性を満洲のその他の民族の上に置くという、民族とジェンダーの階層化を見出した。これは、日本人男性を頂点とする満洲の家父長的なヒエラルキーと一致していた。『満洲グラフ』は内地の支配的な「報道写真」に対する「芸術写真」の意図的な対抗として制作されていた。しかし、彼らの抵抗としての芸術性が込められたイメージこそ、満洲を包含する日本のトランスナショナルな帝国のネットワークに下支えされ、その循環的な強化・維持の役割を果たすものだったことが明らかになった。
- 著者
- 門林 岳史
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.73-77, 2018-01-25 (Released:2018-06-11)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- 馬場 伸彦
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.248-251, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
1 0 0 0 OA 山本祐輝著『ロバート・アルトマンを聴く 映画音響の物語学』せりか書房、2021年2月
- 著者
- 北小路 隆志
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.252-255, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
1 0 0 0 OA 溝口健二のリメイク映画を観る――『噂の女』再考
- 著者
- 森 年恵
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.206-225, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 59
本論は、溝口健二作品の中でまだ十分に考察されていない『噂の女』(1954年、大映)を、『ジェニイの家』(マルセル・カルネ監督、1936年)のリメイク作品として検討する。本映画は、舞台をパリのナイトクラブから京都島原の廓、井筒屋に移し、母娘と男性の三角関係などの基本プロットを受け継ぐ。ただし、三角関係に娘も恋人も気づかないまま母の元を去る原作と異なり、『噂の女』はそれに気づいた上での三者の激しい衝突を経て、男性による女性の搾取を認識することで被害者として母娘が連帯するに至る。リメイク過程の詳細な検討から、川口松太郎による小説へのアダプテーションが甘い「母もの」であったことが、製作過程に困難をもたらしたことが見える。女性の搾取という溝口の一貫した主題が導入されたものの、廓の経営者の母娘の和解が搾取への批判を弱くしたことが同時代の低評価となった。しかし、群像を描くカルネの世界を受け継ぎながら、時代を超えた搾取構造の全体を井筒屋の内部に集約したところに本映画の成果を見ることができる。原作の制約の中で新たな表現を生むリメイク映画の創造性の一例と考えられる。
1 0 0 0 OA 菅野優香編著『クィア・シネマ・スタディーズ』晃洋書房、2021年11月
- 著者
- 高 美哿
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.226-230, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 著者
- 佐藤 英裕
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.231-234, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 1