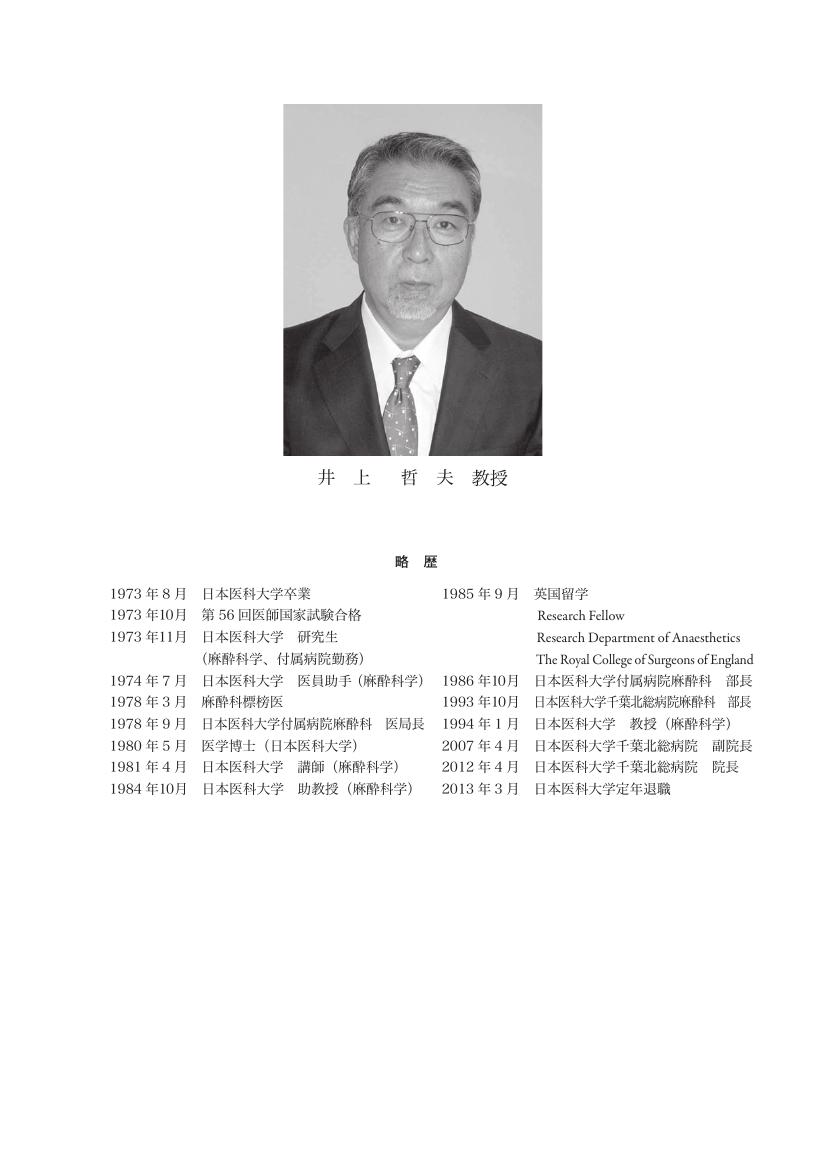1 0 0 0 OA 塩酸メチルフェニデートが生活の質改善に奏効したモルヒネ治療中の末期癌4症例
- 著者
- 益田 律子 井上 哲夫 横山 和子 志賀 麻記子
- 出版者
- Japan Society of Pain Clinicians
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.397-402, 1999-10-25 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 11
モルヒネによる癌性疼痛治療中の眠気に対し, 塩酸メチルフェニデートを用い, 著しい生活の質 (quality of life) 改善が得られた4症例を経験した. いずれもモルヒネによる除痛効果は不十分であるにもかかわらず, 眠気のためにモルヒネ増量が困難な症例であった. 少量の塩酸メチルフェニデート (10~20mg/day) によって得られた効果は, (1)日中の傾眠と夜間覚醒の是正, 睡眠型の正常化, (2)夜間の不安, 恐怖の消失, (3)モルヒネ至適量投与による無痛, (4)摂食・歩行・会話など日常行動型の改善であった. 使用期間は7~50日間で, 明らかな副作用を認めなかった. 少量の塩酸メチルフェニデート投与はモルヒネ治療中の末期癌患者における生活の質 (quality of life) 改善に寄与する.
- 著者
- 吉澤 一巳 益田 律子 井上 哲夫 木本 陶子 福田 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.474-477, 2009-09-25 (Released:2011-09-01)
- 参考文献数
- 7
フェンタニル貼付剤を使用し,内服が困難であったがん性疼痛患者の突出痛の治療に,携帯型ディスポーザブル患者自己調節鎮痛 (patient-controlled analgesia:PCA)用注入ポンプを用いた間歇 PCAを行い,良好な効果を得たので報告する.間歇PCAによる1回ボーラス投与量は,フェンタニル1日量の5%のオピオイド換算量(モルヒネまたはフェンタニル)を,経静脈あるいは経皮下に投与した.ボーラス投与には,ケタミン(1-3 mg)を併用した.至適ボーラスのオピオイド用量は,痛みの強さ,鎮静度ならびに患者満足度により評価し,投与量を適宜増減して決定した.対象患者は16名で,フェンタニル貼付剤2.5-60 mg/72 hrを用いていた.間歇PCAの至適ボーラスのオピオイド換算用量は,フェンタニル貼付剤の1日量の平均5.8±1.9%(平均値±標準偏差)であった.以上の結果より,オピオイド鎮痛薬と少量ケタミンとの併用による間歇PCAは内服困難患者の突出痛の治療として有用であると考えられた.本法は患者満足度の向上,滴定投与による至適投与量決定にも大きく貢献した.
1 0 0 0 OA 気道へのアプローチ
- 著者
- 井上 哲夫
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.69-76, 2013 (Released:2013-05-08)
1 0 0 0 磁場配向させたゲルを利用した種々の結晶材料のゲル成長
平成18年度はPbS(赤外線検出素子)、ZnS(発光材料)、CuCl(シンチレーター)、タンパク質をゲル成長させ、磁場の影響について研究した。ゲル成長を行う場合、そのプロセスは大きく二つに分けられる。一つは成長の場となるゲルの作成段階(プロセス1)、もう一つはゲルの中で実際に結晶を育成する段階(プロセス2)である。そこで磁場の印加時期も、プロセス1においてのみ(Case 1)とプロセス2のみ(Case 2)、およびプロセス1と2の全プロセスに亘って印加する場合(Case 3)の3種類を試みた。また磁場下でゲルを作成したとき磁場がゲル構造に及ぼす効果を計算機シミュレーションにより研究した。得られた結果は以下のようである。1.PbS:無磁場下では正8面体であったのが、磁場印加(Case 1)すると、八方に角の生えた形状(骸晶)になった。またCase2の場合には球晶となった。2.ZnS:磁場の有無にかかわらず、球晶が成長した。しかし球晶のサイズは磁場印加(Case 3)により大きくなった。透過電子顕微鏡(TEM)によると、球晶は5nm位のナノ球晶から構成されていることがわかった。これらの球晶の光吸収スペクトルの短波長端はバルク結晶よりも短波長側へシフトしており、サイズ効果が観察された、3.CuCl:無磁場下では正四面体であったのが、磁場印加(Case3)すると、長い針状結晶へと変化した。4.タンパク質(リゾチーム):リゾチームの配行に磁場が影響することがわかった。無磁場下ではランダムに配向するが、磁場下ではc軸が磁場に平行に配行する傾向があった。しかし、この傾向はリゾチームの濃度が高くなるにつれ弱くなった。また磁場効果として核精製頻度や成長速度を抑制することが分かった。5.計算機シミュレーション:磁場が強くなるにつれ、ゲルネットワークは平行方向に長く伸びる(セルの形状が細長くなる)傾向があった。