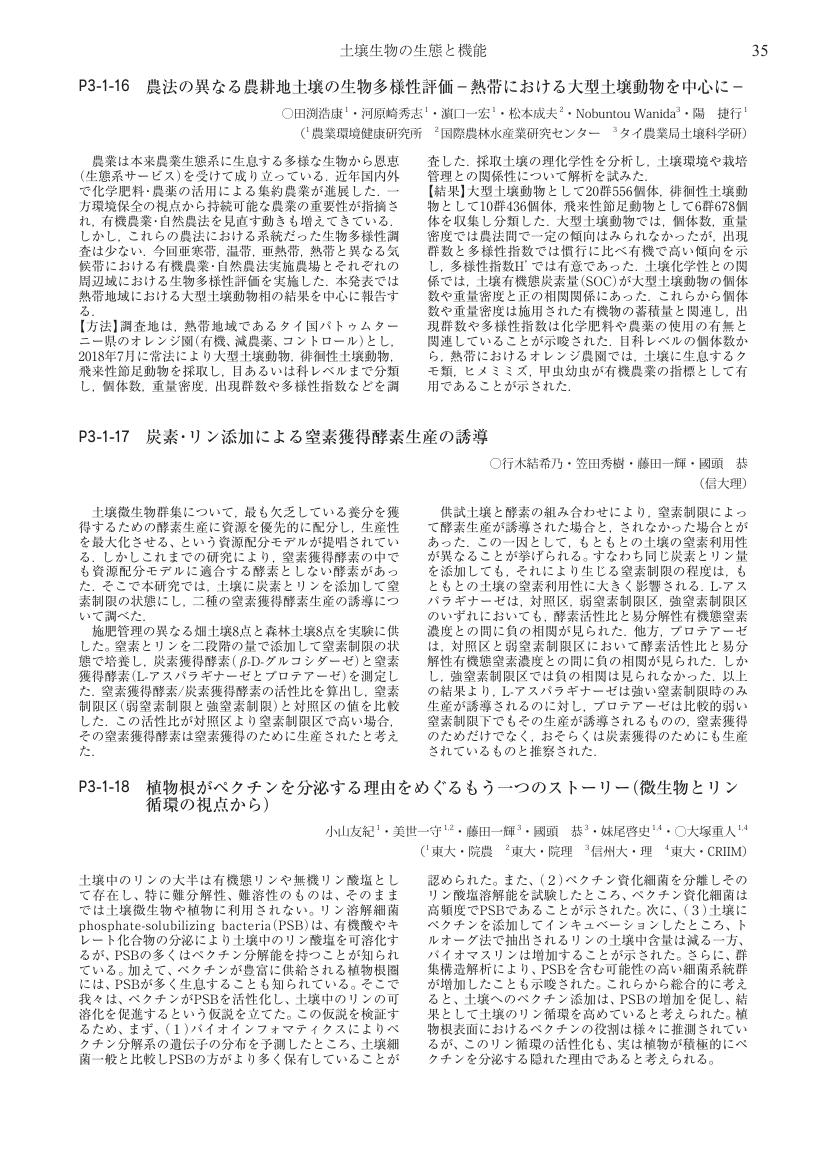2 0 0 0 ベトナム人におけるAS3MT遺伝子多型とヒ素代謝能の関係
- 著者
- 阿草 哲郎 藤原 純子 竹下 治男 田辺 信介 岩田 久人 國頭 恭 MINH Tu Binh TRANG Pham Thi Kim VIET Pham Hung
- 雑誌
- DNA多型 = DNA polymorphism
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.242-245, 2010-05-30
- 参考文献数
- 18
本研究では、野生の高等動物に蓄積している内分泌かく乱物質の汚染と影響を地球的視点で解明し、化学物質の安全な利用と生態系保全のための指針を提示することを目的とした。まず、アジアの先進国および途上国で捕獲した野生の留鳥について有機塩素化合物および有機スズ化合物の汚染実態を調べたところ、PCB等の工業用材料として利用された化学物質は先進国および旧社会主義国で汚染が顕在化しているのに対し、DDTやHCH(ヘキサクロロシクロヘキサン)などの有機塩素系農薬は途上国で著しい汚染が確認された。また、アジア地域を飛翔する渡り鳥は、越冬地や繁殖地で地域固有の汚染暴露を受けることが判明し、南方地域で汚染を受け体内に蓄積した有害物質の影響が、北方地域で営まれる繁殖活動時に現れること、すなわち内分泌かく乱物質の影響は汚染の発生源のみならず遠隔地つまり汚染とは無縁な場所でも発現することが示唆された。さらに、アザラシやカワウを対象に、ダイオキシン類の汚染と影響を検証したところ、毒性の閾値を越えるきわめて高濃度の蓄積がみられ、そのリスクは高いと推察された。CdやHgなどの毒性元素は、陸域に比べ海洋の高等動物で高濃度蓄積がみられ、その細胞内分布や解毒機能の種特異性が示唆された。ところで、鰭脚類や鯨類ではCYP酵素の活性や血中性ホルモン濃度と有機塩素化合物濃度との間に相関関係がみられた。アザラシやカワウの場合、毒性の強いダイオキシン類異性体ほど肝臓に集積しやすい傾向がみられ、AhR関与の毒性に対し本種は敏感であることが示唆された。さらにリンパ球の生育阻害は30-40ng/gの血中ブチルスズ化合物濃度で起こることが明らかとなり、一部の沿岸性鯨類ではこの閾値を超える汚染が認められた。以上の結果を総合すると、生物蓄積性内分泌かく乱物質による野生生物のリスクは水棲哺乳類および魚食性鳥類で高いと推察された。
- 著者
- 小山 友紀 美世 一守 藤田 一輝 國頭 恭 妹尾 啓史 大塚 重人
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学会講演要旨集 65 (ISSN:02885840)
- 巻号頁・発行日
- pp.35, 2019-09-03 (Released:2019-11-24)
鯨類、鰭脚類、海鳥類、海亀類におけるヒ素の体内分布を調べた。鯨類、鰭脚類、海鳥類ではヒ素濃度は肝臓と腎臓で高く、筋肉で低かったのに対し、海亀類、特にタイマイでは筋肉中のヒ素濃度がきわめて高く、低次生物に匹敵するレベルであった。また、これらの種の肝臓中ヒ素の化学形態分析を行なったところ、他の海棲低次動物と同様に、アルセノベタインが主要なヒ素化合物であることが明らかとなった。興味深いことに、ヒ素の蓄積レベルの高い種ほど、アルセノベタインの占める割合が高いことが分かった。ヒトおよび実験動物ではアルセノベタインの排泄は速く、体内に蓄積しないことが報告されているため、海棲高等動物は特異的なアルセノベタイン蓄積機構を有することが予想された。これらの海棲高等動物とは対照的に、イシイルカの肝臓では、ジメチルアルシン酸が主要なヒ素化合物であった。このため、種によりヒ素の代謝あるいは餌生物中のヒ素化合物組成が異なることが予想された。本研究では、毒性の高い無機ヒ素は、大部分の種で検出されなかった。このため、海棲高等動物ではヒ素の蓄積レベルは高いが、その毒性影響は小さいものと予想される。しかしながら、最近の研究により遺伝毒性を示すことが明らかとなったジメチルアルシン酸は、大部分の種で検出された。また海鳥類の羽毛および鰭脚類の毛でヒ素が検出された。毛には、毒性がきわめて強い3価の無機ヒ素と3価の有機ヒ素が蓄積することが知られており、低い濃度ながらこれら毒性の強いヒ素化合物が海棲高等動物の体内に存在することが示唆された。また、無機ヒ素は、非常に低濃度で内分泌撹乱作用を示すことが報告されており、海棲高等動物に対する影響あるいはそれらが進化の過程で獲得した適応能力に興味が持たれる。
1 0 0 0 OA リン可給性をめぐる土壌微生物群集
- 著者
- 國頭 恭 諸 人誌 藤田 一輝 美世 一守 長岡 一成 大塚 重人
- 出版者
- 土壌微生物研究会
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.41-54, 2019 (Released:2020-04-09)
2008年のリン価格の高騰以降,農地に蓄積した「legacy P」の有効化を試みる研究が多くされている。このlegacy Pの有効化は,リン資源枯渇の問題だけでなく,湖沼の富栄養化や植物病害を抑制する上でも重要である。土壌のリンの可給化に寄与する因子としては,アーバスキュラー菌根菌が最もよく研究されているが,ここでは効果が明瞭でない,あるいはあまり研究されていない,リン溶解菌,ホスファターゼ,微生物バイオマスリン,土壌の還元化に関する基礎的情報を提供した。いずれも,いまだ基礎的な知見すら不足しており,すぐに実用的に利用することは困難である。しかし,実際に土壌中で重要な役割を果たしており,農地に蓄積したリンの可給性を規定する仕組みを理解するうえでも,これらに関する理解の深化は不可欠である。またlegacy Pを有効利用するためにリン減肥をする際は,これまでよりもさらに精確なリン可給性の評価が必要となる。その場合,化学的評価法だけではなく,微生物バイオマスリンや土壌酵素の資源配分モデルといった生物指標の利用も有用である可能性があり,今後検証する必要がある。