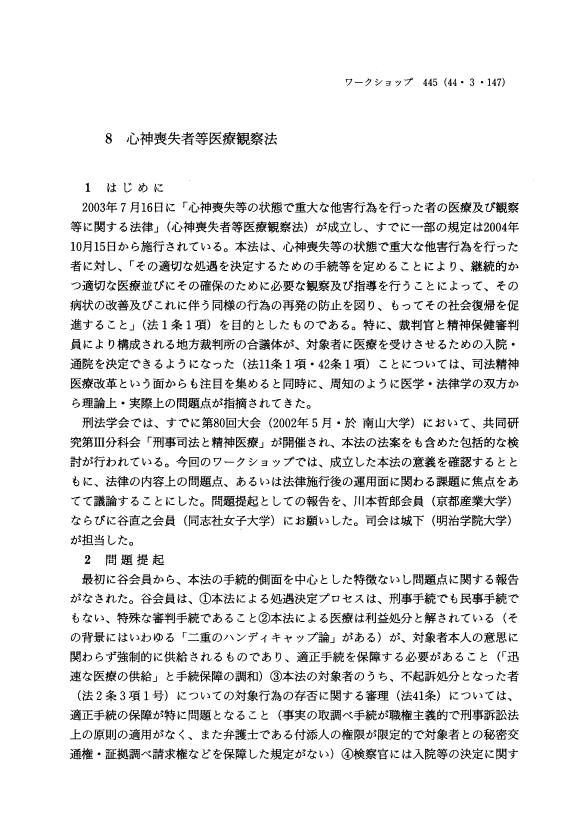3 0 0 0 OA 犯罪被害者と量刑 量刑の本質論・実体刑法の視点から
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.422-434, 2013-05-01 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 OA 犯罪研究動向:触法精神障害者の処遇に関する研究動向
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.131-139, 2020-11-20 (Released:2022-04-26)
2 0 0 0 OA 修復的司法から修復的正義へ-理論と実証のクロスロード-
1 0 0 0 OA 1 生体移植
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.468-473, 2013-05-01 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 8 裁判員裁判における量刑
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.457-462, 2012-03-30 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 2 量刑法
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.274-277, 2007-02-10 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 8 心神喪失者等医療観察法
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.445-448, 2005-04-10 (Released:2020-11-05)
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 現代人文社 ; 1995-
- 雑誌
- 刑事弁護
- 巻号頁・発行日
- no.83, pp.127-134, 2015
1 0 0 0 OA 刑事法学と心理学-刑事裁判心理学の構築に向けて-
- 著者
- 白取 祐司 仲真 紀子 川崎 英明 今井 猛嘉 高倉 新喜 田中 康雄 松村 良之 藤田 政博 森直 久 城下 裕二 内藤 大海
- 出版者
- 北海道大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2007
刑事裁判において法心理学は、法専門家(実務法曹)と司法に関わる市民とりわけ裁判員の間のコミュニケーションの実証分析、刑事司法に対する実務家、市民の意識分析による制度見直しへのデータ提供など、様々なかたちで貢献しうることを、実験や調査等を通して明らかにしてきた。また、子どもに対する心理学的観点からの面接法の研究を進め研修など実践段階までいたったほか、外国調査により、刑事司法における心理鑑定の制度化の可能性と必要性を示すことができた。
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.7-19, 2005-10-18
2004年9月に「凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法の整備に関する要綱(骨子)」が法務大臣に答申され,同年12月に「刑法等の一部を改正する法律」として可決・成立し,2005年1月より施行された.本改正の内容は多岐にわたるが,最も注目されたのは刑法典における凶悪・重大犯罪の(約1世紀ぶりの)法定刑引上げである.今回の改正は「治安回復のための基盤整備」の施策の一環であり,法制審議会における審議状況を概観すると,法定刑引上げを必要とする立法事実としては,(a)国民の正義観念(規範意識)の変化,(b)犯罪認知件数の増加,(c)科刑状況の厳格化の3要因が挙げられ,これらは各種の統計資料によって根拠づけられるということが事務当局から説明されている.本稿は,審議会議事録および配布資料の内容を分析することにより,事務当局が指摘するような立法事実を根拠づけるのは困難であること,また,仮にそうした事実が存在するとしても,法定刑引上げという立法政策が直ちに正当化されるものではないことを明らかにする.そして,わが国の刑事立法政策過程が,EBP(エビデンス・ベイスト・ポリシー)の発想から学ぶべき点は何かを検討する.
1 0 0 0 「回復的司法」モデルの展開とわが国における適用可能性
本研究においては、近年刑事司法におけるパラダイム転換を図る理論として注目されている「回復的司法」(修復的司法)モデルの、わが国での可能性について検討した。もっとも、「応報的司法」モデルが支配的である(と解される)わが国の現況を前提とするならば、「回復的司法」モデル急な導入は、却ってこのモデルを「変質」させるおそれも危惧される。その意味で、現行司法制度の枠組みを維持しつつ、「回復的司法モデル」の段階的に導入する方向が考慮に値するように思われる。「回復的司法」モデルの内容自体、多岐にわたるものであるが、特に注目すべき点は、犯罪への対応の中心に「被害者」を位置づけようとしたことにあるといってよい。そこで、本研究では、被害者との関係修復という要因を、刑事司法過程においていかに捉えていくべきかを検討することとし、その主眼は、「量的段階」におくこととした。同モデルをめぐる議論の焦点の1つは、「刑罰の意義・目的」との関係であり、それが最も先鋭化した形で現れるのが量刑段階であると解されるからである。量刑においてこの問題を検討する際に重要となるのは、刑種・刑量の決定に際して「被害者関係的事情」をどこまで、どのように考慮していくかである。本研究では、すでに実体刑法理論との関係で、従来の量刑基準に「被害感情の充足」を代置し、あるいは付加することには多くの疑問があることが明らかにされた。また、処断形成過程における減免事由、特に中止未遂規定の本質に「被害者関係的」な要因を見出そうとする(わが国およびドイツで主張されている)見解にも問題があることが判明した。もとより、現行の刑法体系と「訣別」して、量刑においても「被害者関係的事情」を全面的に考慮することが、将にわたって否定されるものではない。しかし、同モデルの実証研究が十分ではなく、内容自体も論者による多様性が認められる現時点においては、慎重な対応が求められよう。