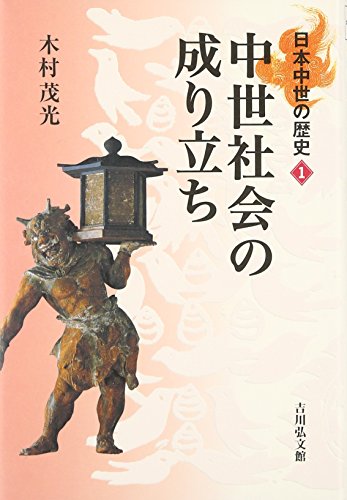31 0 0 0 OA 国文研ニューズ No.39 SPRING 2015
- 著者
- 木村 茂光 小山 順子 野網 摩利子 丸島 和洋 青山 英正 寺島 恒世 恋田 知子 畑中 千晶 山下 則子
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文研ニューズ = NIJL News (ISSN:18831931)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.1-16, 2015-05-08
●メッセージ「唐物」研究の豊かな進展のために●研究ノート後土御門天皇禁裏文芸と女性日中の古文辞学と漱石高野山子院の東国への教線拡大と檀那場争い「リンボウ先生の書誌学講座」受業記●トピックス平成26年度日本古典籍講習会平成27年度アーカイブズカレッジ(史料管理学研修会通算第61回)の開催「山鹿文庫」受贈に関わる表彰式について通常展示「書物で見る日本古典文学史」国際連携研究「日本文学のフォルム」第2回国際シンポジウム「男たちの性愛―春本と春画と―」総合研究大学院大学日本文学研究専攻の近況
7 0 0 0 OA サイエンスアゴラシンポジウム 「科学・技術でわかること, わからないこと」
- 著者
- 室伏 きみ子 毛利 衛 柴田 徳思 本田 孔士 北原 和夫 木村 茂光
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.9, pp.9_54-9_86, 2012-09-01 (Released:2013-01-09)
- 著者
- 木村 茂光
- 出版者
- 歴史科学協議会
- 雑誌
- 歴史評論 = Historical journal (ISSN:03868907)
- 巻号頁・発行日
- no.845, pp.5-18, 2020-09
1 0 0 0 OA 古代日本における度量衡制の成立・整備・展開の研究
1 0 0 0 OA 『伊勢物語』を考え直す
1 0 0 0 IR 河越重頼の妻と妹 : 鎌倉初期の河越氏をめぐる一齣
- 著者
- 木村 茂光
- 出版者
- 帝京大学文学部史学科
- 雑誌
- 帝京史学 (ISSN:09114645)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.83-100, 2015-02
1 0 0 0 『日韓交流の歴史』 (明石書店) 編纂から学んだこと
- 著者
- 木村 茂光
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.73-75, 2009