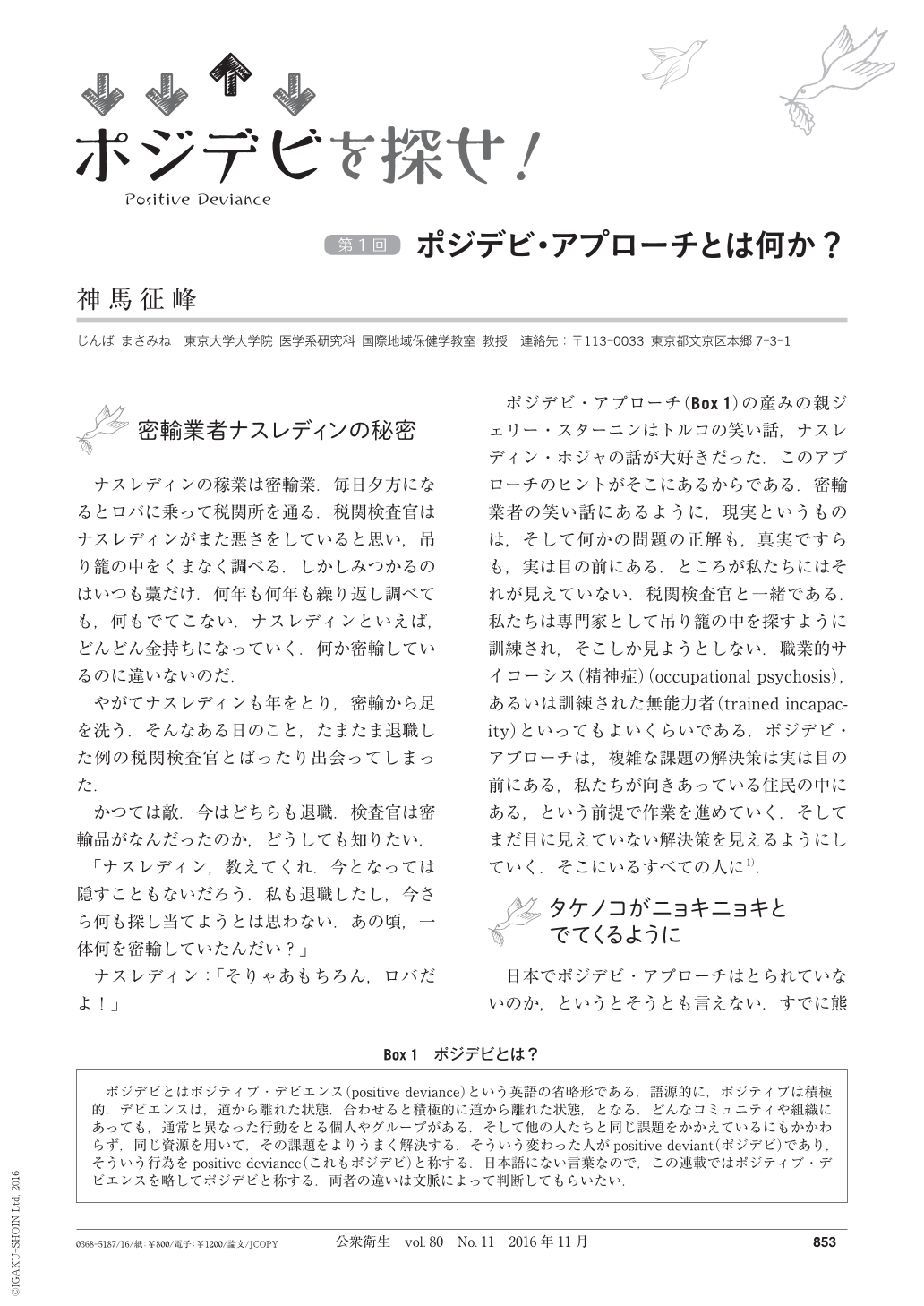原子力災害後、被災者はどのような心理社会的健康影響を受けるのか。日本でも世界でも学術的研究は少なく、その影響要因はほとんど明らかになっていない。本研究では、2011年3月に発生した福島第一原発事故の現場で、質的・量的調査の両手法を用いて、その要因を特定する。「放射線による健康不安」に着目し、一人ひとりの被災者や避難者が抱える不安を具体的かつ系統的に把握できる尺度(質問票)の開発を行うのが最初の目的である。次に、開発された尺度によって、精神健康指標をはじめとする健康状態と健康不安との関連を探索する。今後、原子力事故を含む同様の複合災害が発生した場合にも起こりうる心理社会的影響の予防や長期化した時のあり方について具体的に提言することを目指す。本研究は、三段階で構成される。1) 「放射線による健康不安」を把握するための尺度開発にあたり、質的手法を用いて被災者のインタビュー調査を行い、情報収集を行う。2) インタビュー調査で得られた内容に基づき、福島版「放射線による健康不安」尺度の開発を行う。3) 更に、開発された尺度を用いて、精神健康指標をはじめとする健康状態との関連を探索する。研究初年の26年度においては、避難生活を続ける高齢者を主な対象として、インタビュー調査を実施した。27年度においては、別の対象(母親、子供等)にインタビューを実施しながら、入手した情報の整理を行い、尺度開発を進めている。28年度においては、インタビューで得られた内容を、チェルノブイリ原発事故被災地のウクライナで開発され、使用されている「放射線被ばくによるPTSD尺度」及び、その他関連のある尺度等を参考に福島避難者用の尺度の作成を行った。29年度においては、国内での調査の一部を実施。また、尺度が長期的に使用可能かを調査するため、チェルノブイリ原発事故被災地における聞き取り調査を実施した。
5 0 0 0 OA 健康教育・ヘルスプロモーション領域における健康行動理論・モデルの系統と変遷
- 著者
- 戸ヶ里 泰典 福田 吉治 助友 裕子 神馬 征峰
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.329-341, 2018-11-30 (Released:2018-11-30)
- 参考文献数
- 60
目的:健康教育学・ヘルスプロモーション領域において,介入プログラムを開発するうえで健康行動理論・モデルに基づくことが重要とされている.しかし数ある理論・モデルについて意図的にその整理を試みた報告は十分にない.そこで当該領域における理論・モデルを系統的,歴史的に整理することを本報告の目的とした.方法:健康教育・ヘルスプロモーション領域において,国内外6つの健康行動理論・モデルを扱っている定評のある文献を参考に,著者間での議論を通じて理論・モデルを抽出した.これらは,Glanzらの整理に沿って,個人,個人間,集団・マルチレベルの3つの枠組みで分類し,歴史的な変遷を図示化した.結果:個人の理論・モデルは期待価値理論を基礎とした連続性モデルと時間軸を含み行動へのプロセスをモデル化したステージモデルとに区分して分類した.個人間レベルの理論・モデルについては,社会的認知理論,ストレスと健康生成論,社会関係,健康・医療とコミュニケーションの4つの系譜に分けて整理を行った.集団・マルチレベルの理論についてはコミュニティエンゲージメント,問題解決型アプローチ,戦略立案型アプローチの3つの系譜に分けて整理した.結論:個人,個人間,集団・マルチレベルの3つの枠組みで主要行動理論・モデルについて整理し下位水準の分類まで明らかにした.また理論の系統的発展を体系的に記述することができた.本研究を通じて理論・モデル各々の特徴の理解をより深めることが可能となった.
5 0 0 0 OA 行動変容のためのポジティブ・デビエンス・アプローチ
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.253-261, 2013 (Released:2014-09-05)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2
背景:健康教育やヘルスプロモーションによる行動変容は最重要課題の一つである.しかしながら,これらの戦略をもってしても,行動変容が難しい場合がある.本稿では行動変容の一つの手段として,Positive Deviance Approachを紹介することを目的とする.内容:他の人たちと同じ課題を抱えているにもかかわらず,その課題をよりうまく解決する人を positive deviant,その行為をpositive devianceという(本稿では以下いずれもポジデビと称する).1990年,米国のNGO,Save the Childrenがベトナムの4つの村で栄養調査を行った結果,3歳未満児の64%が栄養不良であった.ということは,36%は栄養不良ではない,ということでもある.この36%の中でポジデビを探した結果,見えてきた特徴は以下のようであった.「田んぼや畑からお金のかからない食品を入手している」,「汚れたら子供の手を随時洗わせている」,「子供が1日に食べる回数を2回から4,5回に増やしている」.これに基づいたポジデビ・アプローチをとることによって,7年間で 50,000人以上の子供たちの栄養状態が改善した.その後さらにこのアプローチは,院内感染対策,乳幼児死亡改善策,肥満対策,妊婦の栄養対策などに用いられ,困難な行動変容課題を克服してきた.結論:ポジデビ・アプローチは行動変容が困難な健康課題を克服するための手段として有効に使える.日本でも今後これが広がっていくことを期待したい.老人対策,震災後の地域保健対策,学校のいじめ対策などに,このアプローチは使える可能性がある.
2 0 0 0 OA 途上国における栄養不良克服のためのポジティブデビエンス・アプローチ
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業研究 (ISSN:18828434)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.49-53, 2014 (Released:2016-03-03)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 ポジデビ・アプローチとは何か?
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.853-858, 2016-11-15
密輸業者ナスレディンの秘密 ナスレディンの稼業は密輸業.毎日夕方になるとロバに乗って税関所を通る.税関検査官はナスレディンがまた悪さをしていると思い,吊り籠の中をくまなく調べる.しかしみつかるのはいつも藁だけ.何年も何年も繰り返し調べても,何もでてこない.ナスレディンといえば,どんどん金持ちになっていく.何か密輸しているのに違いないのだ. やがてナスレディンも年をとり,密輸から足を洗う.そんなある日のこと,たまたま退職した例の税関検査官とばったり出会ってしまった.
2 0 0 0 OA ヘルスプロモーション再考:その潜在力強化のために
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.245-252, 2013 (Released:2014-09-05)
- 参考文献数
- 20
背景:1994年以降ポピュレーション・ヘルスの波が高まるにつれ,とりわけカナダではヘルスプロモーションが下火となり,ヘルスプロモーションの価値見直しの検討がなされてきた.注目すべき事項として,本稿では3つの課題をとりあげる.第1に「ヘルスのプロモーション」と「ヘルスプロモーション」の違い,第2にヘルスプロモーションにとって望ましいエビデンス,第3にヘルスプロモーションの発展過程についてである.内容:第1に,「ヘルスのプロモーション」とは,健康を増進しようと思っている人すべてにあてはまる共通な言説である.一方「ヘルスプロモーション」は「健康に影響を及ぼすライフスタイルや生活状態を計画的に変容させていく」ための専門分野ととらえるべきである.第2にエビデンスに関しては,プロミスィング・プラクティス(有望実践例)がより適切であるとの動きがある.有望実践例とは,「ベスト・プラクティスと称するほどには十分(科学的に)評価されていないかもしれないけれども,輝きに満ち(illuminating)かつ心をゆさぶる(inspiring)実践例」である.最後に,ヘルスプロモーションの発展プロセスとして,ツリー型(樹木型)に対して,ヘルスプロモーション活動があちこちから生じるリゾーム型(地下茎型)の発展がみられている.結論:公衆衛生分野においてヘルスプロモーションの定義をより専門的なものと捉え,有望実践例が,リゾーム型に発展していくプロセスに今後注目すべきである.
1 0 0 0 OA 若井晋:次世代へのメッセージ
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 日本国際保健医療学会
- 雑誌
- 国際保健医療 (ISSN:09176543)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.25-34, 2021 (Released:2021-07-22)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA アドボカシー実践に必要な2つの成長
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.107-111, 2017 (Released:2017-05-31)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.9, pp.690-693, 2009-09
1 0 0 0 OA 査読をめぐるやりとりのポイント
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.171-176, 2013 (Released:2014-06-11)
- 参考文献数
- 2
背景:論文査読は論文の質を上げるために有効な手段である.査読をめぐるやり取りのポイントをあらかじめ知ることによって,投稿者は投稿原稿の小さなミスを避けることができる.本稿では本誌への投稿者のために,査読をめぐる主要な疑問や指摘を示すことを目的とする.内容:タイトルとキーワードは,自分の論文を他の研究者に読んでもらうための入り口である.投稿者は読者の目をひきつけるような魅力的なタイトルをつけ,自分の論文が共通のキーワード検索によって見つかりやすくなるように出来る限りMeSHキーワードを使用すべきである.和文抄録に関しては執筆要領にある小見出しをつけ,方法には研究デザインを示すこと,結果にはできるだけ主要データを示すこと,そして最後に結論ではその内容が引用されることを意識して記載することが重要である.また英文抄録は文法の修正だけでなく読みやすさにも気をつけて仕上げるべきである.最後に本文に関しては,諸言では総論から各論へ,考察では各論から総論へというストーリー展開をするとよい.また方法は専門家に読まれることを意識すること,結果に関しては図表の数を増やしすぎないようにし,結論につながるデータを明快に示すべきである.結論:基本的なミスを事前に防ぐことによって,論文の本質に関わる査読が可能になる.そのような査読をしてもらえるように,ぜひ基本的なルールをマスターし,明快で説得力のある論文作成にとりかかっていただきたい.
1 0 0 0 行動変容のためのポジティブ・デビエンス・アプローチ
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF HEALTH EDUCATION AND PROMOTION
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.253-261, 2013
背景:健康教育やヘルスプロモーションによる行動変容は最重要課題の一つである.しかしながら,これらの戦略をもってしても,行動変容が難しい場合がある.本稿では行動変容の一つの手段として,Positive Deviance Approachを紹介することを目的とする.<br>内容:他の人たちと同じ課題を抱えているにもかかわらず,その課題をよりうまく解決する人を positive deviant,その行為をpositive devianceという(本稿では以下いずれもポジデビと称する).1990年,米国のNGO,Save the Childrenがベトナムの4つの村で栄養調査を行った結果,3歳未満児の64%が栄養不良であった.ということは,36%は栄養不良ではない,ということでもある.この36%の中でポジデビを探した結果,見えてきた特徴は以下のようであった.「田んぼや畑からお金のかからない食品を入手している」,「汚れたら子供の手を随時洗わせている」,「子供が1日に食べる回数を2回から4,5回に増やしている」.これに基づいたポジデビ・アプローチをとることによって,7年間で 50,000人以上の子供たちの栄養状態が改善した.その後さらにこのアプローチは,院内感染対策,乳幼児死亡改善策,肥満対策,妊婦の栄養対策などに用いられ,困難な行動変容課題を克服してきた.<br>結論:ポジデビ・アプローチは行動変容が困難な健康課題を克服するための手段として有効に使える.日本でも今後これが広がっていくことを期待したい.老人対策,震災後の地域保健対策,学校のいじめ対策などに,このアプローチは使える可能性がある.
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.7, pp.530-533, 2009-07
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.466-469, 2009-06
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.374-377, 2009-05
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.221-223, 2009-03
- 著者
- 神馬 征峰
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.306-309, 2009-04