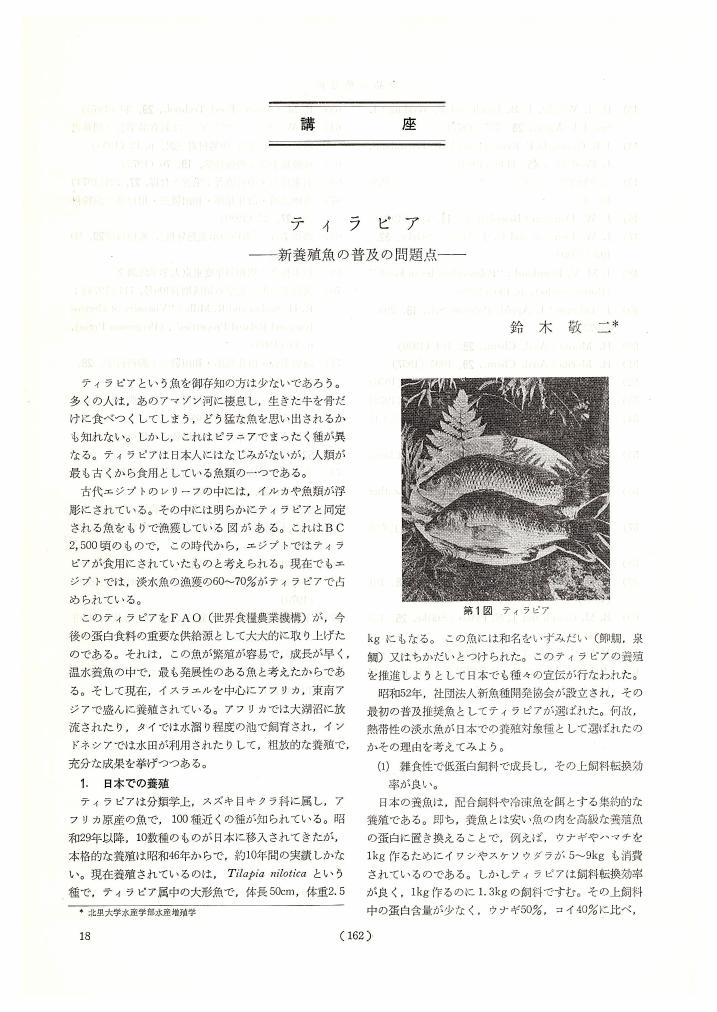1 0 0 0 OA ティラピア 新養殖魚の普及の問題点
- 著者
- 鈴木 敬二
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.162-165, 1981-10-20 (Released:2013-04-26)
- 著者
- 中橋 史衡 田中 周 武藤 友和 吉田 真一 佐藤 貴子 鈴木 敬二 森豊 浩代子 鈴川 活水
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.E-171_1-E-171_1, 2019
<p>【はじめに・目的】</p><p>乾,山口,實はChungらによる被殼出血症例の出血部位を血管支配領域別に分けた6分類を用いて,それぞれ回復期病棟,急性期病棟の独歩獲得率を調査している.しかし,同分類と被殻出血症例に対する装具処方の関連を調査した報告はみられない.今回被殼出血症例における当院退院時の独歩獲得率及び装具処方との関連を各部位間で調査し先行研究との比較検討を行った.</p><p>【方法】</p><p>2011年~2018年の間に入院した被殻出血患者87名を対象とした.男性56名,女性31名,年齢平均58.52(±12.59)歳,損傷側は左側36名,右側51名であった.既往歴に脳血管疾患や整形外科疾患を有する症例は除外した.急性期頭部CT画像と回復期入院 時頭部CT画像(撮影日:発症後平均25±11日)を用いて出血位置を確認しChungらが報告している6タイプ(前方タイプ,中間タイプ,後内側タイプ,後外側タイプ,外側タイプ,大出血タイプ)に分類した.退院時Functional Independent Measure(以下;FIM)移動項目1-5点を独歩不可能群,6-7点を独歩可能群とし,独歩獲得率を求めた.各タイプの割合,年齢平均,独歩獲得率,退院時FIM移動項目およびFIM認知項目の点数,BRS,内包後脚への進展の有無を比較した.統計学的解析はJ-STATを用い,独立した多群の差の検定としてKruskal Wallis検定を行い,多群比較としてscheffe法を行った.有意水準はいずれも p<0.05とした.</p><p>【結果】</p><p>分類別の症例数は前方タイプ3名(3.4%),中間タイプ7名(8.0%),後内側タイプ2名(2.0%),後外側タイプ30名(34.4%),外側タイプ21名(26.4%),大出血タイプ22名(25.2%).各タイプでの年齢・性別の有意差なし.独歩獲得率(装具処方)は前方タイプ100%(処方なし),中間タイプ100%(処方なし),後内側タイプ100%(処方なし),後外側タイプ93.3%(AFO43.3%,KAFO23.3%),外側タイプ90.4%(KAFO9.5%),大出血タイプ54.5%(AFO13.6%,KAFO86.3%,その他9.0%).大出血タイプにて有意に独歩獲得率およびBRSの低下が認められた.内包後脚への進展は後外側タイプ,大出血タイプにおいて有意にみられ,この両タイプ間の比較では大出血タイプに有意な進展を認めた.</p><p>【考察】</p><p>山口によると独歩獲得率は後外側タイプにて50%,大出血タイプにて13.4%と有意に低下しているとされるが当院では大出血タイプのみに有意な低下が認められた.また,当院での独歩獲得率は後外側タイプ93.3%・大出血タイプ54.5%と先行研究に比べ良好であった.当院では発症から回リハ病棟入棟までの入棟期間が短く(平均25±11日),また当院入院後比較的早期の装具処方(平均11.3±18.5日)と起立訓練の実施により積極的な立位・歩行訓練を実施している.実際に大出血タイプ症例の86.3%に早期にKAFOが処方されておりこれらが良好な独歩獲得率に寄与した可能性が示唆される.タイプ別の装具処方数については内包後脚および放線冠への進展がみられやすい後外側タイプ,大出血タイプにおいて多くの装具が処方されたことが考えられる.</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>本研究はヘルシンキ宣言の基準に従い、データは研究以外の目的には使用せず、個人が特定されないよう匿名化した。また当院の規定に基づき個人情報の取り扱いには十分配慮して行った。</p>
1 0 0 0 OA 胃癌術後化学療法中に発症したビタミンB1欠乏による乳酸アシドーシスの1例
- 著者
- 森谷 雅人 高木 融 鈴木 敬二 佐々木 啓成 伊藤 一成 片柳 創 土田 明彦 青木 達哉 小柳 〓久
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.9, pp.2114-2117, 2002-09-25 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 13
症例は61歳,女性.胃癌にて1997年12月9日,胃全摘術,膵脾合併切除施行. 1998年1月9日より化学療法施行. 18日より経口摂取不良となり,高カロリー輸液(以下, TPN)を開始したが, 2月10日より記銘力低下, 14日より意識レベル低下し, 15日に急性循環不全を呈した.血液ガス分析では, pH 7.136, PaO2 157.0mmHg, PaCO2 9.8mmHg, HCO3-3.3mEq/l, Base Excess -23.4mEq/lと代謝性アシドーシスを呈していた.炭酸水素ナトリウム500ml投与するも効なく,乳酸値を測定したところ144.0mg/dlと高値を示したためビタミンB1欠乏による乳酸アシドーシスを疑い塩酸チアミンを投与したところ,投与後6時間でpH 7.598, Base Excess 8.9mEq/lとなり,意識レベル,循環動態も改善した. 自験例を含めたTPN施行時のビタミン欠乏による乳酸アシドーシスの報告例について文献的考察を加えて報告する.
1 0 0 0 OA オランダの大学図書館事情
- 著者
- 鈴木 敬二
- 出版者
- 京都大学附属図書館
- 雑誌
- 静脩 (ISSN:05824478)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.17-20, 2000-03