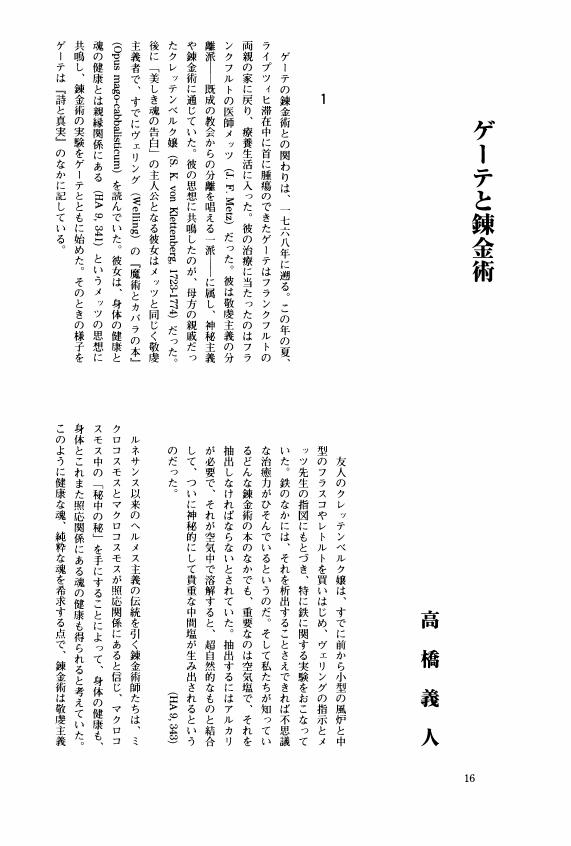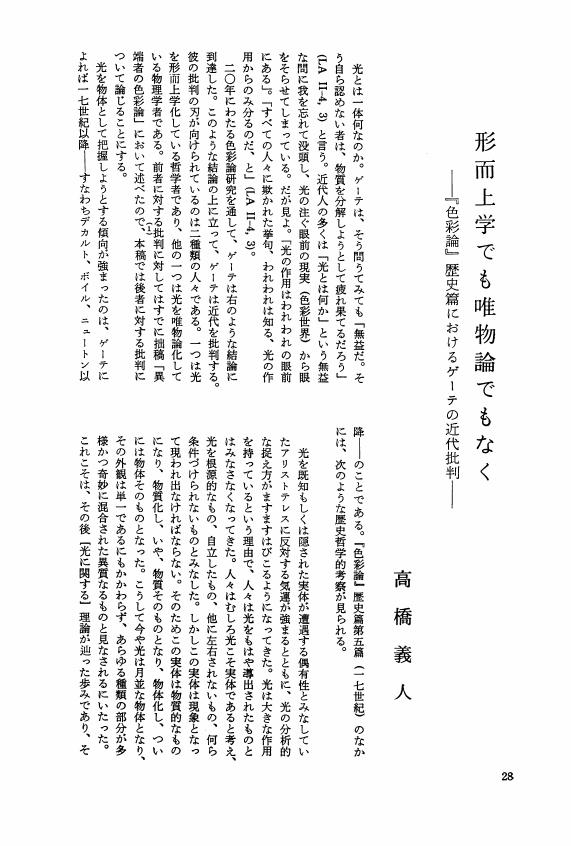17 0 0 0 グリム童話と古代ゲルマン信仰
一般民衆のあいだで語り継がれてきたメルヘンのなかには、キリスト教が導入される以前の古代ゲルマンの古い神話や信仰の痕跡が残っている。『子どもと家庭のためのメルヘン集』を収集しながら、グリム兄弟はそのような考えに想到した。本研究は、グリム兄弟のそうした意図がどの程度まで正しかったかを確証し、キリスト教導入以前のヨーロッパ文化を復元することにある。本研究の結果、「灰かぶり」のようなメルヘンには、おそらくは太古にさかのぼるヨーロッパの民衆の農耕儀礼が反映していることが判明した。それを知る上で重要だったのは、ヨーロッパの辺境の地に残る古い祭りだった。祭りにおいて村人たちが動物や植物に変身して冬を追い払おうとするように、「灰かぶり」やその類話において女主人公は動物の毛皮や植物でできたマントを身にまとい、危機から脱出する。本研究は、両者の類似性を緻密に跡付けた。「いばら姫」に登場する塔の上の老婆を、グリム兄弟は古代ゲルマン神話の女神ホルダとして描いた。ホルダは古代ゲルマンの地母神であり、地上の生死、吉凶、豊作と不作を司っていた。その地母1神を誕生パーティに招待しなかった以上、いばら姫が長い眠りにつくのは当然のことだった。ホルダは「ホレおばさん」にも登場する。ホルダ(ホレ)は働き者にはほうびを、怠け者には罰を与えるという古代ゲルマンの信仰を、メルヘン「ホレおばさん」に明瞭に見て取ることができる。また「蛙の王さま」と日本民話の「鶴の恩返し」を比較検討することによって、大昔の人類は、人間から動物、動物から人間への変身は比較的普通に起きると考えていたことが判明した。そして前者のタイプが、魔女ののろいによって人間から動物に変身させられるというグリム童話のメルヘンに、そして後者のタイプが、自分を助けてくれた人間に恩返しをするために、人間(多くは若い女性)に変身し、人間の妻となって甲斐甲斐しく働くという日本民話になったと考えられる。本研究を通して、西欧文化と日本文化の根底に流れる共通のルーツを明らかにすることができた。
8 0 0 0 OA ゲーテと錬金術
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.24, pp.16-27, 2002-10-30 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 7
4 0 0 0 戦後の日本におけるゲーテ受容
戦後の日本におけるゲーテ受容について語るとき、最も重要なのは、『ファウスト』である。ゲーテの『ファウスト』の中核には悪魔との契約譚がある。したがって日本の作家が『ファウスト』文学を受容するときには、「悪魔との契約」という主題を日本の風土に馴染ませなければならない。ところがこれは決して容易なことではない。というのも日本人の多くは、「悪魔との契約」はもとより、悪魔の存在そのものを信じてはいないからだ。遠藤周作は小説『真昼の悪魔』(1980年)のなかで、日本人にとっての悪魔の間題に真正面から挑んだが、その試みは成功したとはいえない。これに対して三島由紀夫は「悪魔」ではなく「通り魔」のような「魔」を間題にし、より日本の現実に即した考察を行なった。しかもその「魔」の考察を三島はゲーテの『ファウスト』と結びつけ、三島の「わがファウスト」を書いた。それが彼の『禁色』と『卒塔婆小町』である。この2作品の中核をなすのは、美と醜の対立であり、メフィストには「醜」の役が与えられている。石川達三は『四十八歳の抵抗』において、ゲーテの『ファウスト』を下敷きにしながら、現代日本のサラリーマンの悲哀に満ちた生活をパロディ風に描き出した。ファウストのように人生をやり直そうと試みた主人公の試みは挫折せざるをえない。ファウストのように生きることは、現代の日本においては不可能だということを石川達三は示した。手塚治虫は生涯に3度、ゲーテの『ファウスト』を漫画化している。彼の諸作品の中心にあるテーマは、科学技術による地球環境の汚染であるが、このテーマは遺作の『ネオファウスト』に明瞭に表れる。ゲーテの『ファウスト』に出てくる人造人間ホムンクルスを手塚はクローン人間に置き換え、大量生産されたクローン人間による軍隊によって地球が壊滅する。『ネオファウスト』によって手塚は、漫画がどれほど強い時代批判力を持っているかを示すことに成功した。
3 0 0 0 OA ホムンクルス ―錬金術から神話的自然讃歌へ―
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1985, no.7, pp.25-44, 1985-11-03 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 16
2 0 0 0 OA ハイトラーとゲーテ
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.26, pp.2-14, 2004-10-30 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 13
2 0 0 0 OA 形而上学でも唯物論でもなく ―『色彩論』歴史篇におけるゲーテの近代批判―
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.12, pp.28-39, 1990-10-30 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA ホムンクルス―パラケルズスから手塚治虫まで
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.28, pp.24-34, 2006-10-31 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA ファウストと冥府への旅 ―「母たち」の場をめぐって―
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.20, pp.51-59, 1998-10-24 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 形と力 ―形態学とは何か―
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.1, pp.43-64, 1979-11-03 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 16
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- 平安女学院大学
- 雑誌
- 平安女学院大学研究年報 = Heian Jogakuin University Journal (ISSN:1346227X)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.1-10, 2019-03
建国以来の歴史が浅く「新しい国」であったアメリカには、20 世紀に入ってからも「アメリカ音楽文化」と呼べるようなものがまだわずかしか存在していなかった。アメリカを政治的にのみならず文化的にも「大国」にするために、アメリカ独自の音楽文化を育てることは喫緊の課題だった。その契機のひとつをなしたのが、レハールのオペレッタ『メリー・ウィドウ』のアメリカ上演(1906 年)だった。その爆発的人気をもとに、1934 年、『メリー・ウィドウ』はエルンスト・ルビッチ監督によって映画化され、オペレッタのアメリカ化が行われた。本稿は、18 世紀前半のイタリアにおけるオペラ・ブッファから、19 世紀後半~20 世紀初頭のヴィーンにおけるオペレッタを経て、20 世紀半ばに与えられたアメリカでミュージカルが誕生するまでの喜歌劇の歴史をたどりつつ、アメリカン・ミュージカルに与えられた課題を探る。
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- 平安女学院大学
- 雑誌
- 平安女学院大学研究年報 = Heian Jogakuin University Journal (ISSN:1346227X)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.1-10, 2019-03
建国以来の歴史が浅く「新しい国」であったアメリカには、20 世紀に入ってからも「アメリカ音楽文化」と呼べるようなものがまだわずかしか存在していなかった。アメリカを政治的にのみならず文化的にも「大国」にするために、アメリカ独自の音楽文化を育てることは喫緊の課題だった。その契機のひとつをなしたのが、レハールのオペレッタ『メリー・ウィドウ』のアメリカ上演(1906 年)だった。その爆発的人気をもとに、1934 年、『メリー・ウィドウ』はエルンスト・ルビッチ監督によって映画化され、オペレッタのアメリカ化が行われた。本稿は、18 世紀前半のイタリアにおけるオペラ・ブッファから、19 世紀後半~20 世紀初頭のヴィーンにおけるオペレッタを経て、20 世紀半ばに与えられたアメリカでミュージカルが誕生するまでの喜歌劇の歴史をたどりつつ、アメリカン・ミュージカルに与えられた課題を探る。
- 著者
- 高橋 義人
- 雑誌
- 白鴎法學 = Hakuoh hougaku : Hakuoh review of law and politics (ISSN:13488473)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.199-221, 2014-12-01
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア : ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.13-27, 2010
1 0 0 0 ホムンクルス
- 著者
- 高橋 義人
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1985, no.7, pp.25-44, 1985
1 0 0 0 グノーシス主義と近代ヨーロッパ文学
ヨーロッパの精神史ではキリスト教と並んでグノーシス思想が大きな役割を果たしてきていること、グノーシス思想を知らなければ、ヨーロッパの哲学や文学も真に理解することはできない、と近年しばしば言われるようになってきた。本報告書の目的は、グノーシス思想をもとに、ヨーロッパの哲学や文学を読み直すことにある。しかしグノーシス思想の全体像について知らなければ、グノーシス主義と近代ヨーロッパの哲学や文学との関係を知ることはできない。そこで本報告書の前半では、グノーシス主義の概要について記した。第1章(失楽園)、第2章(二元論)、第3章(ソフィアと「男・女」)、第4章(救済された救済者)、第5章(黙示録と終末思想)、第6章(アウグスティヌスとマニ教)、第7章(スコラ学派とカタリ派)、第8章(聖杯伝説とグノーシス)、第9章(マイスター・エックハルトとグノーシス)、第10章(ヤーコプ・ベーメとグノーシス)である。本報告書の後半は、全11章からなる。ファウスト伝説がグノーシス主義者シモン・マグスに関する逸話に由来するのではないかと推測した第11章、ウィリアム・ブレイクがベーメの影響の下にグノーシス思想に親しんでいったことを跡付けた第12章、ピエティスムスの指導者エーティンガーの有するグノーシス主義的思想がドイツ観念論にいかに大きな影響を与えたかを論じた第13章、フィヒテの『浄福なる生への導き』のなかにグノーシス思想を探った第14章、シェリングの『人間的自由の本質』における善悪の問題の追究がグノーシス主義的であると論じた第15章、ヘーゲルの「キリスト教の精神とその運命」に見られるグノーシス思想が彼の「弁証法」を生み出し、さらに彼のグノーシス的思想はヘーゲル左派を通してマルクス主義へとつながり、またヘーゲル右派を通してナチズムにつながっていった経緯を明らかにした第16章、さらには自分ではグノーシス主義者とは述べていないものの、『罪と罰』などの見られる思想は明らかにグノーシス的と認められるドストエフスキーについて論じた第17章、同じく自分ではグノーシス主義者とは洩らしていないものの、『パルジファル』には明白なグノーシス思想が認められると論じた第18章、ユング派の医師によって精神病の治療を受け、グノーシス思想に接近したH・ヘッセの記念碑的小説『デミアン』について論じた第19章、タルコフスキー監督の映画『ノスタルジア』や「」サクリファイス』のなかにグノーシス思想を認めた第20章、20世紀後半のSF作家フィリップ・ディックがいかにグノーシス思想に近づいたかを論じた第21章である。
1 0 0 0 OA ゲーテの象徴形式と魔術的・錬金術的伝統
ルネサンス以降、人間の感性と理性が分離するとともに、二つの知的系譜(文系と理系)に世界は分裂していった。この分裂はF・ベーコンによって決定的になった。他方、感性と理性の統合を目指す動きもまた存在した。その第一はレオナルドであり、第二は魔術的・錬金術的運動である。レオナルドが、自然は完全には探究しがたいと信じていたのに対して、錬金術師たちは、太陽の生命力(プリマ・マテリア)を抽出しようと無駄な努力を重ねた。ニュートンもじつは錬金術的な伝統の継承者である。本研究は、若い頃、錬金術の研究に傾倒していたゲーテが、やがてレオナルド的な立場に立ち、ニュートン的・ベーコン的な近代科学の批判こそ自らの使命だと考えるようになった経緯を明らかにしている。