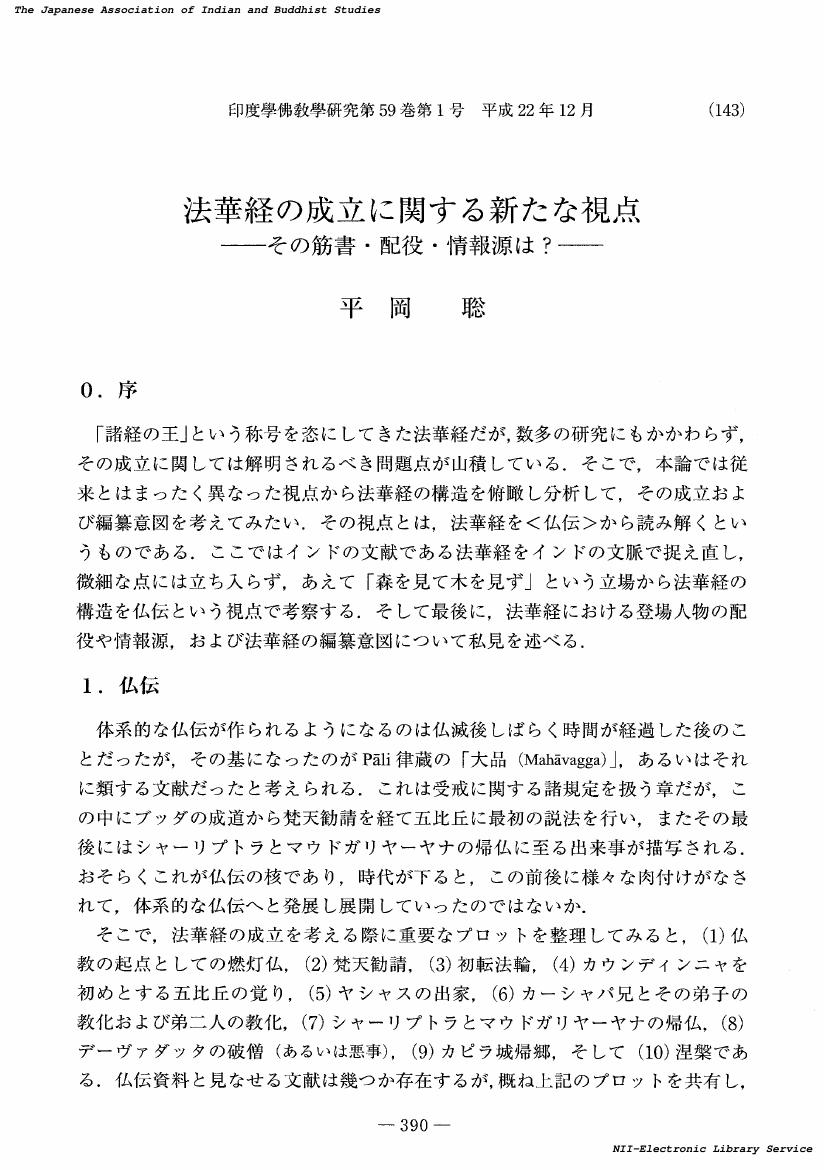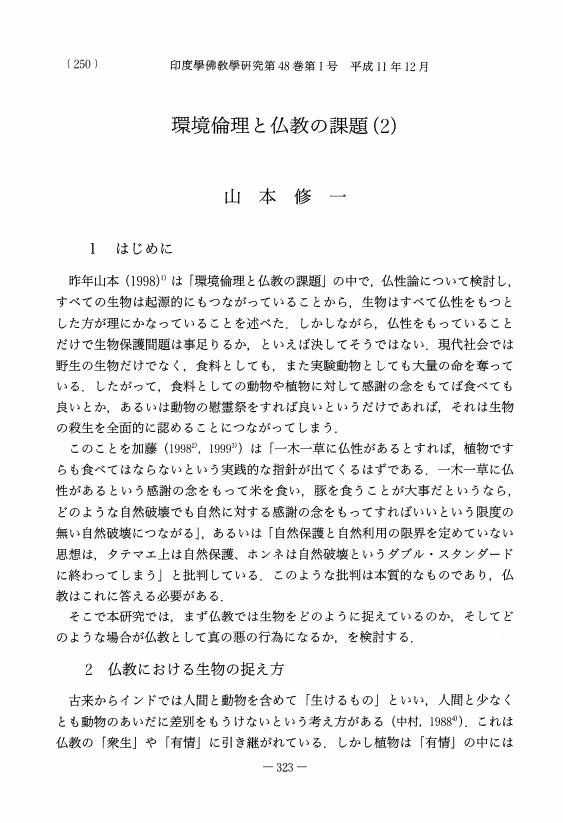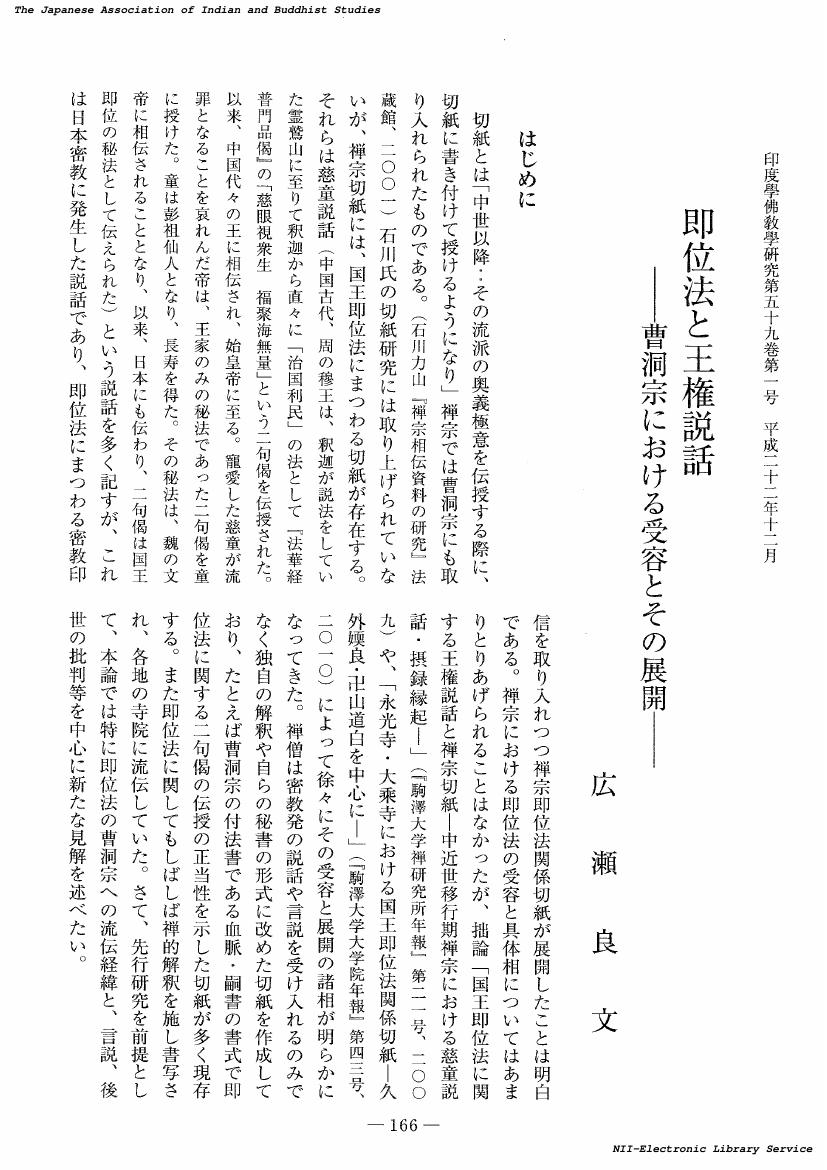4 0 0 0 OA 曹洞宗における世襲制と僧侶の婚姻
- 著者
- 中野 優子
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.644-647, 1995-03-25 (Released:2010-03-09)
4 0 0 0 OA 道教における瞑想について
- 著者
- 宮澤 正順
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.190-197, 2004-12-20 (Released:2010-03-09)
4 0 0 0 康僧会と建初寺:――寺号の由来について――
- 著者
- 伊藤 千賀子
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.1036-1031, 2015
4 0 0 0 OA 写経で用いる書体について
- 著者
- 高井 恭子
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.237-241, 2003-12-20
4 0 0 0 親鸞の女性観
- 著者
- 源 淳子
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.146-147, 1976
4 0 0 0 OA インドネシアにおける最近の仏教
- 著者
- 前田 惠學
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.1-9, 1976-12-25 (Released:2010-03-09)
4 0 0 0 OA 法華経の成立に関する新たな視点 ――その筋書・配役・情報源は? ――
- 著者
- 平岡 聡
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.390-382, 2010-12-20 (Released:2017-09-01)
- 著者
- 柳 幹康
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.516-510, 2016-12
4 0 0 0 OA 環境倫理と仏教の課題 (2)
- 著者
- 山本 修一
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.323-317, 1999-12-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 10
4 0 0 0 OA 『二入四行論』の成立について
- 著者
- 伊吹 敦
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.127-134,1195, 2006-12-20 (Released:2010-03-09)
- 被引用文献数
- 1 1
Though the Treatise on the Two Entrances and Four Practices has been handed down as the record of Bodhidharma's teaching, the reliability of this tradition has not been adequately verified. Surely scholars such as YANAGIDA Seizan and ISHII Kosei have contributed toward the analysis of the sutras on which it was based, and also have pointed out the influence of Chinese classics on it. But the origin of the structure of ‘The Two Entrances and Four Practices’ has not been explained. In my opinion, it should be regarded as the highly original evolution of the method of interpreting the Dharma which had widely prevailed in the South-North Dynasty, especially among Dilun scholars. Therefore, there is no reason to consider that the Treatise on the Two Entrances and Four Practices originates from the teaching of an Indian monk Bodhidharma.
4 0 0 0 OA マイトリパの僧院追放とアティシャ
- 著者
- 静 春樹
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.1315-1321, 2015-03-25
本稿はマイトリパのヴィクラマシーラ僧院追放とアティシャの関与の問題を検討し,僧院における声聞乗の律と金剛乗の三昧耶の対立を述べる.マイトリパ(別名アドヴァヤヴァジラ)は有名な学匠でありタントラの実践者でもあった.マイトリパの生涯とその事績について論じた羽田野伯猷は,アティシャに十九年間師事したナクツォ訳経師からの口承に基づくとされる『アティシャ伝』に大きな信頼を置いてマイトリパの追放事件に言及している.Mark Tatzはこの問題を再検討しチベット人歴史家の方法論自体に疑問を挟み,羽田野論文に批判的な見解を提出している.本稿では最初にチベット人の歴史書を引用する.つぎにTatz論文の要点を紹介する.そこで筆者は,僧院規律に違犯して追放された出家者が,僧院の外部に何らかの活動拠点をつくり,それが金剛乗の信解者たちの交流の場となる可能性を指摘する.玄奘を始めとする中国人巡礼僧の報告によれば,インドの仏教僧院は「大小共住」であった.こうした状況下で,タントラ行の目的で酒を備えもち瑜伽女と目される女性と飲むことが僧院追放となるのであれば,ガナチャクラや「行の誓戒」「明の誓戒」などの金剛乗の信解者に義務づけられている行の実践はおよそ不可能となる.それらのタントラ的実践は単なる創作だったのであろうか.もし実際になされていたとすれば,問題はどこで実行されていたかである.ひとつ明確なことは,誰が僧院から追放されたとしても,その金剛乗の比丘は「ヴァーギーシュヴァラ準則」(bhiksum vajradharam kuryat)によって持金剛者のアイデンティティをもっていることである.僧院に属する金剛乗の比丘と僧院外部の在俗瑜伽行者が金剛乗の仲間内にだけ開かれた何らかの宗教施設でタントラ的行を実践することは可能だったはずである.金剛乗の世界が僧院以外の施設を建立し運営していたことは典籍に窺える.金剛乗の比丘たちはそのような施設を訪れタントラ的実践を行っていたと筆者は問題提起する.
4 0 0 0 OA ツォンカパにおける中観帰謬派の時間論
- 著者
- 根本 裕史
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.1168-1172, 2008-03-25
本稿は,ツォンカパ・ロサンタクパが中観帰謬派の時間論をどのように再解釈し,そこにいかなる独自性を見出そうとしたかを考察するものである.彼によると,帰謬派は未来,現在,過去の三つの時間をいずれも実在と見なしている.つまり,彼の理解する帰謬派説では,現在のみならず未来(事物の未生起状態)と過去(事物の消滅状態)もまた,原因によって生み出され,かつ,自身の結果を生み出しつつ消滅するというのである.こうした考えは毘婆沙師の三世実有説を連想させるものであるが,ツォンカパによると帰謬派の時間論は三世実有説とは相容れないものである.なぜなら,毘婆沙師は事物が三つの時間を通じて同一性を保ちつつ存続することを主張するのに対し,帰謬派は経量部等と同じ過未無体の立場を取っており,事物は現在にのみ存在すると主張するからである.さらにまた,未来と過去を実在と見なす帰謬派説は,それらを非実在と見なす経量部,唯識派,自立派の説と対照をなすものである.ツォンカパによれば後者の三学派は,事物が未だ生起していない時と既に消滅した時にいかなる実在も見出されないことを根拠に,未来と過去は非実在であると結論する.一方,「自性によって成立した物」を全く認めない帰謬派の立場においては,未来や過去として特徴づけられる実在が探し求められなくとも,それらを実在であると見なすことができる.すなわち,事物の未生起状態と消滅状態はいずれも原因によってもたらされるものであるゆえに,それらは実在に他ならないと結論されるのである.こうしたツォンカパの説明が如実に示すのは,一切法無自性の立場に立つ帰謬派だからこそ,未来と過去を実在と捉えることができるのだという事柄である.
4 0 0 0 『発心集』、『沙石集』、『徒然草』と天台本覚思想
- 著者
- 辻本 臣哉
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.92-95, 2019
<p>This paper studies the <i>Hosshinshū</i>, <i>Shasekishū</i> and <i>Tsurezuregusa</i> in relation to Tendai <i>hongaku</i> philosophy. The following results are obtained. Firstly, the <i>Hosshinshū</i> is not affected by Tendai <i>hongaku</i> philosophy. Its stance detests this impure world and encourages seeking rebirth in the Pure Land. The <i>Shasekishū</i> has the idea that everyone can reborn in the Pure Land. However, it does not contain the idea that this real world is a manifestation of Buddha. Finally, the <i>Tsurezuregusa</i> accepts the real world. It finds the truth in the real world and might be affected by Tendai <i>hongaku</i> philosophy.</p>
4 0 0 0 OA 震災と仏教(仏教学は何をめざすのか,第63回学術大会パネル発表報告)
- 著者
- 師 茂樹
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.795-794, 2013-03-20 (Released:2017-09-05)
4 0 0 0 OA インド密教における肉の売却――『ブータダーマラ・タントラ』の記述を中心にして――
- 著者
- 藤井 明
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.1183-1188, 2019-03-25 (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 13
本論文では仏教版とヒンドゥー教版とで近似する内容を備える『ブータダーマラ・タントラ』(Bhūtaḍāmaratantra)内の「下男,下女の成就法」に見ることの出来るśmaśānaに於ける「肉を売る」修法を挙げ,仏教版BTの特色を明らかにすることを目的としている.BT内では修法者は規定の量(8パラ)の黒山羊の肉を持ってśmaśāna(尸林/火葬場)に赴き,四方を見る.その後,śmaśānaに住むマハーブーティニーがバラモンの姿で現れ,肉と同量の黄金でその肉を受け取るとされる.これと類似の修法は『蘇婆呼童子請問經』の蔵訳にのみ見られる「人肉による成就法」が挙げられ,人肉(mi yi sha)を売りたいと思う者がdur khrod(śmaśāna)に赴くことが説かれている.ここでは夜に死人の肉を切り取り,左手で肉を持ち,右手に刀(ral gri)を持って修法を行い,肉を売ることを大声で呼びかけ,それを繰り返し言いながら東西南北を歩き回る行者の姿が描かれる.また,『妙吉祥最勝根本大教經』内に説かれる修法にも強い親縁関係が認められる.これら修法に関連する修法が,7世紀末から8世紀中葉に活躍したと考えられるバヴァブーティによる戯曲Mālatīmādhavaにも認められ,これらの修法は人口に膾炙した物語を基礎とした,仏教・ヒンドゥー教双方に共有された修法であったと言い得る.この様な共通の修法を扱う題材としては起屍鬼法が挙げられるが,「śmaśānaで物を売る修法」も同様の題材の一つであったと言えよう.
4 0 0 0 OA 親鸞における肉食の意味
- 著者
- 吉田 宗男
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.213-215, 1998-12-20 (Released:2010-03-09)
4 0 0 0 OA 即位法と王権説話
- 著者
- 広瀬 良文
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.166-169, 2010-12-20 (Released:2017-09-01)
4 0 0 0 OA 地方陰陽師の性格と活動
- 著者
- 木場 明志
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.164-165, 1972-12-31 (Released:2010-03-09)
4 0 0 0 OA 「五趣生死輪図」版木について
- 著者
- 興津 香織
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.213-218, 2013-12-20 (Released:2017-09-01)
4 0 0 0 OA 雲英晃耀の因明学
- 著者
- 師 茂樹
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.1126-1132, 2015-03-25
雲英晃耀(きら・こうよう,1831-1910)は,幕末から明治時代にかけて活躍した浄土真宗大谷派の僧侶で,キリスト教を批判した『護法総論』(1869)の著者として,また因明の研究者・教育者として知られる.特にその因明学については,『因明入正理論疏方隅録』のような註釈書だけでなく,『因明初歩』『因明大意』などの入門書が知られているが,その内容についてはこれまでほとんど研究されてこなかった.雲英晃耀の因明学については,いくつかの特徴が見られる.一つは実践的,応用的な面である.雲英は国会開設の詔(1881)以来,因明の入門書等を多数出版しているが,そのなかで共和制(反天皇制)批判などの例をあげながら因明を解説している.また,議会や裁判所などで因明が活用できるという信念から因明学協会を設立し,政治家や法曹関係者への普及活動を積極的に行った.もう一つは,西洋の論理学(当時はJ. S. ミルの『論理学体系』)をふまえた因明の再解釈である.雲英は,演繹法・帰納法と因明とを比較しながら,西洋論理学には悟他がないこと,演繹法・帰納法は因明の一部にすぎないことなどを論じ,西洋論理学に比して因明がいかに勝れているかを繰り返し主張していた.そして,三段論法に合わせる形で三支作法の順序を変えるなどの提案(新々因明)を行った.この提案は西洋論理学の研究者である大西祝や,弟子の村上専精から批判されることになる.雲英による因明の普及は失敗したものの,因明を仏教から独立させようとした点,演繹法・帰納法との比較など,後の因明学・仏教論理学研究に大きな影響を与える部分もあったと考えられる.