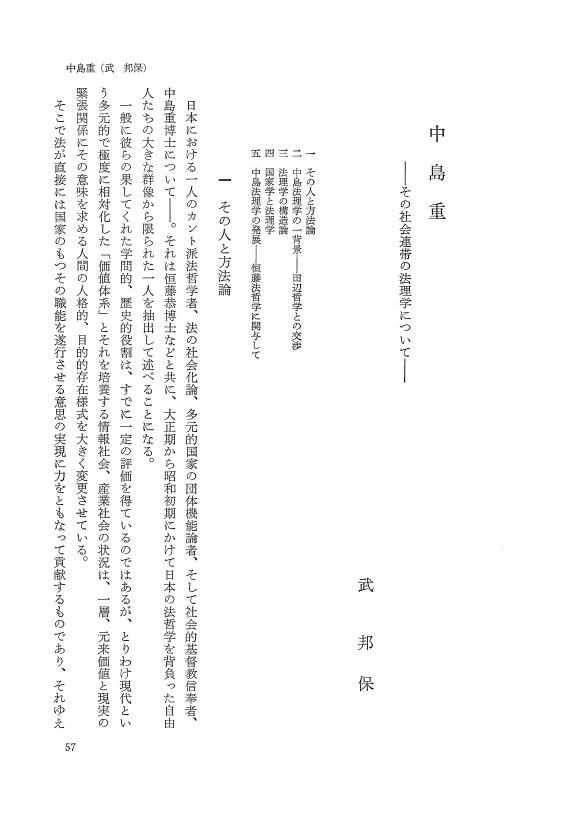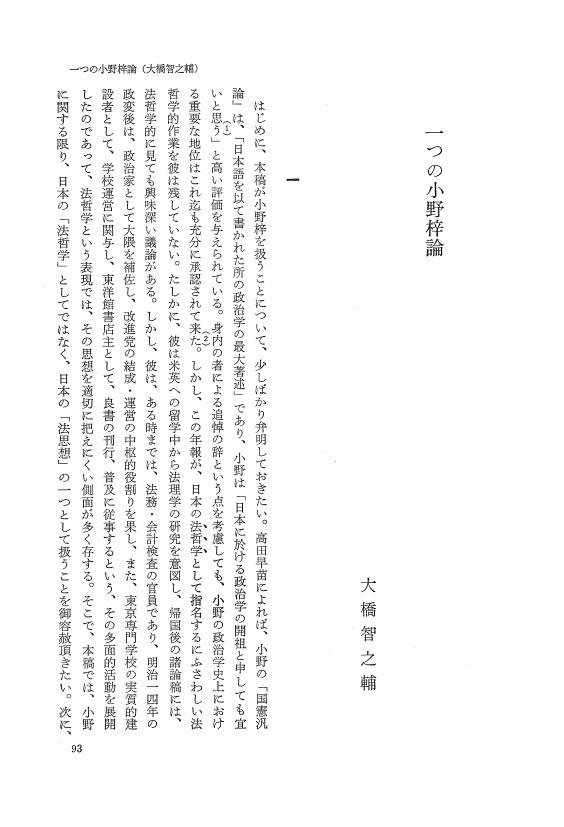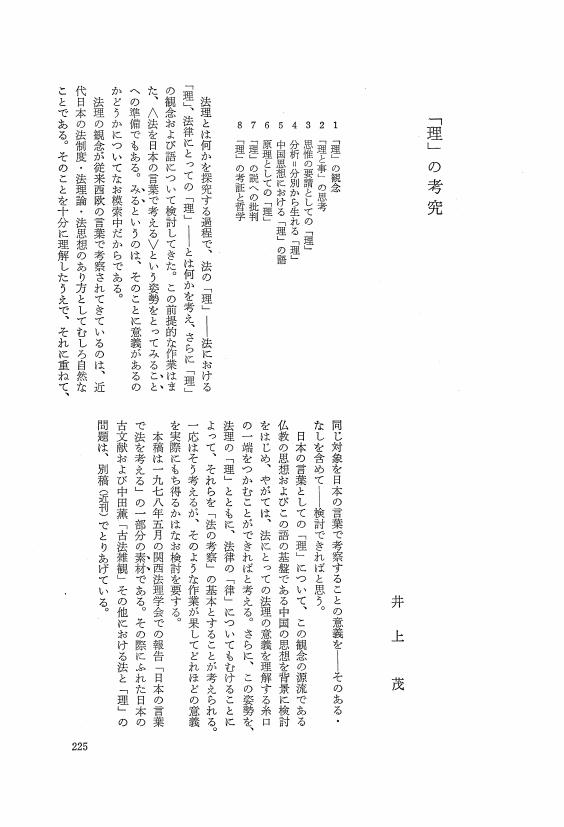1 0 0 0 OA エーミル・ラスク法哲学の哲学的基礎 所謂「客観主義」への転換を中心に
- 著者
- 陶久 利彦
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.204-213, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 53
1 0 0 0 OA 田中成明著『裁判をめぐる法と政治』
- 著者
- 深田 三徳
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.223-231, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
1 0 0 0 OA 駒城鎮一著『理論法学の方法』
- 著者
- 竹下 賢
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.232-241, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
1 0 0 0 OA 笹倉秀夫著『近代ドイッの国家と法学』
- 著者
- 西村 稔
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.242-252, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
まず第一章「イェーリングにおける『個人』と『国家』」の第一節では、「国家観法観上の前期イェーリング」(一八七四~七五年以前)が、絶対主義的官僚国家の伝統に対決して個人の自由と自立(私的自治)の確立を第一課題とし、その拠点を自治規範たるsitteに求めつつ、同時にその保障を成文法・抽象的一般規定(方法論上は論理的体系的方法とその中核であるWillensdogma)に見出していたということを、『ローマ法の精神』第一巻第二巻及び『権利のための闘争』に即して跡づけている。第二節では、これに対して後期イェーリング(『法における目的』第一巻)が、前期の「自由の体系」を自から批判して「社会の目的」を強調するに至り、その結果国家的監督(強制法)を理論の前面に押し出し、それを通じて国家社会主義者A・ヴァーグナーと同じく「アメとムチ」のビスマルク・レジームに同化していったと把捉される。そしてこの転換(「転向」)の理由は、ドイツ資本主義の高度化に伴う内部矛盾の激化、自由放任主義の破綻、伝統的社会秩序がもつていたsittlichな力の弱化、ビスマルクのレアル・ポリティークへの心酔に求められている。尤も、こうした転換にも拘らず、前-後期を通じて個人と国家との有機体的一体性を志向した点でイェーリングの思想には一貫性があり、ただ前期の重点が個人に、後期では国家(社会)にあったこと、後期では一体性の枠組が理想に留まつたことに相違があるとされている。次いで第二章「イェーリングとドイツ自由主義」は、前期イェーリングの国制像に焦点をあて、彼が個人と国家との媒介として伝統的身分的基盤に立つ団体的(コルポラツィオン的)国制の保持を求めたこと、かかる国制像並びに法観国家観がロマニストとゲルマニストの区別なく、プフタやゲルバー、更にドイツ自由主義一般(ハンゼマン、べーゼラー、ライヒェンスペルガー、ヘーゲル)にも共通して見出せることを詳述している。ここでの重要な論点は、彼らが一様に自由な自立的人格(近代市民社会)の確立を希求し乍ら、同時に強力な主権国家による個人の統合をも追求したので、両者の媒介として団体的国制を要求し、しかもそれを近代化の論理に合わせるために、抽象的法、非特権的な「開かれた身分制」を理想としたということ、政治的には多元論的な立場からする反絶対主義、反民主主義の態度を採ったこと(穏健自由主義乃至保守的自由主義)、彼らの社会的基盤が、Bourgeoisと対置されるBurger=「旧中間身分」=「財産と教養の階層」にあったこと(この点は、経済史学との関連も踏まえて「全体のむすび」で論じられている)である。なお、ここで「ドイツ自由主義」として一括された思想は、著者によればF・v・シュタインに始まり、ヘーゲル・イェーリング等を経てM・ヴェーバーにまで一貫して保持されていたとされており、近代ドイツ思想全体(法思想だけでなく)を一望の下に収めようとする著者の並々ならぬ意欲が窺われる(ヴェーバーについては、本書の補完ともいうべき著者の「いわゆる『ヴェーバー問題』について-マックス・ヴェーバーにおける「自立人」・「小集団」・「国家」の関連構造-」大阪市大法学雑誌第二五巻三・四号所収参照)。第三章では、一八五九年を境としてイェーリングの方法論上の思想が前後期に分たれており、更に前期のうち一八四〇年代、五〇年代前半、五〇年代後半についてそれぞれ詳細な論証が試みられている。第一節では、プフタ、サヴィニー、ヴィントシャイトのhereditas jacens論及び法学論と対比しつつ、イェーリングにおける「法と事実」「理論と実践」の関係に対する考えの変化が追求され、イェーリングは、四〇年代及び五〇年代前半では、サヴィニーに連なる実践的な法的構成とプフタ的た「法学の論理的構成」(前期概念法学)を共存させ、あるいはその間を動揺していたが、五〇年代後半では論理主義的側面の重視という後退が見られることが明らかにされる。しかし第二節では、一転して方法論的後期に入ったイェーリングが実践性を優位に置き、概念法学批判へ向うこと(とはいえ法的技術にもなお高い評価を与えていたが故に後期概念法学乃至構成法学と呼ばれること)、この方法論的「転向」は、内容上も目的論乃至利益衡量的傾向(社会目的の重視=個人主義批判)となって現われ、従って国学観法観上の「転向」と密接不可分の関係にあること、・最後に前期及び後期のイェーリングの立場と自由法論者エールリッヒの多元的民主主義との相違を論じている。
1 0 0 0 OA ホセ・ヨンパルト著『法の歴史性-現行法の法哲学的試論』
- 著者
- 三島 淑臣
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.245-256, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 木村亀二の法哲学 (一) その法の本質論と刑法学
- 著者
- 大野 平吉
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.24-42, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 40
1 0 0 0 OA 和田小次郎の法哲学
- 著者
- 佐藤 篤士
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.87-110, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 33
1 0 0 0 OA 穂積法理学ノート
- 著者
- 長尾 龍一
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.111-133, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 79
- 著者
- 蓮沼 啓介
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.134-154, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 中島重 その社会連帯の法理学について
- 著者
- 武 邦保
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.57-91, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 78
1 0 0 0 OA 一つの小野梓論
- 著者
- 大橋 智之輔
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.93-116, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 40
1 0 0 0 OA 西周における人間と社会
- 著者
- 長尾 龍一
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.117-141, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 OA 法学における「科学」イメージの機能
- 著者
- 松浦 好治
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.142-164, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 68
1 0 0 0 OA 孔子の礼思想
- 著者
- 石川 英昭
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.165-180, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
1 0 0 0 OA 自然法と民事訴訟
- 著者
- 栗田 陸雄
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.181-189, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 54
本書は八つの章からなる。第一章「始まり」では、Grotius (2)及びPufendorf (3)の思想を中心に、社会契約による国家の裁判権の基礎づけ(4)が説明される。(1)Grotiusによれば、自然状態においては自力救済(5)が支配する。もっとも、自力救済は最後の手段であるから、これを用いる前に可能なあらゆる手段、たとえば友好的説得、仲裁人による仲裁、占いなどが試みられなければならない。その中では、仲裁人にょる仲裁手続が国家的裁判と対比されるが、この仲裁手続においては、仲裁人は理性に従って手続を進めるので、手続の規定を考える必要がないことになる(S. 3-4)。(2)この手続規定の軽視は、自然法思想のひとつの特徴である(6)(S. 4-この傾向は、後にフリードリッヒ訴訟法典において、裁判官を手続の形式性から解放することになる)。(3)またこの時期に、みぎのような自然法とは全く系統を異にする自然法思想が見出される。中世後期の伝統(7)を承けて、現行の簡易訴訟(8)(Processus summarius)における本質的要素を、古典的意味における自然法の要求と看做すところの流れが、それである。この思想は後の時代まで残り続ける。同時代の代表者として、Althusius (9)とCarpzov (10)をあげることができる(S. 6-7)。 第二章「BoehmerからWolffまで」では、具体的国家性へ接近した自然法説の視野における訴訟観が説明される。ひとつの社会秩序及び法秩序の偉大な理想的草案は、現実にも利用できるものでなければならない。そこで、かかる草案を描くところの自然法は、いまやその視野をひとつの国家の全体の法秩序に、つまりそのあらゆる部分、したがって訴訟にも及ぼさなければならない。その代表者としては、まずJustas Henning Boehmer (11)が取り上げられる。Boehmerは二つの性質の異なった自然法的主張を行う。(1)まず、彼は近世自然法の流れにおいて、彼の絶対主義的、国家法的問題提起の枠内で裁判を論じ(12)(S. 8)、(2)次に、訴訟法が存在しない場合に裁判官が従うべきところの、その自然法的訴訟秩序の輪郭を描く。この秩序は、普通法の伝統において簡易訴訟の本質的内容から構成される。また、この自然の秩序は、継受以前のドイツの古い手続法と同一視され、現行のドイツの訴訟手続と対立させられる(13)(S. 9)。(3)この古い手続法を現行の手続法と対比する自然法的思惟は、継受とともにドイツに浸透してきたカノン法に対する一般的な敵意の反映である。かかるカノン法に対する一般的敵意は、Christian Thomasius (14)に見出される。カノン法の拒絶と古い手続法に対する愛着は、一八世紀に広く用意されたものであるが、これはまた自然法とゲルマニスティークの同盟の先ぶれを示している(S. 13)。(4)Boehmerは普通ローマ法を個々的に自然法として採用したが、Samuel Cocceji (15)はこれを明確な原則の形式において自然法と同視する。両者は現行の訴訟法を自然法と看做す点で共通している。但し、前者の自然法は簡易訴訟、後者のそれは正規訴訟である点で異なる(S. 15)。(5)Christian Wolff(16)の自然法的訴訟観はGrotius及びPufendorfが拓いた道に戻るもので、前進していない(S. 16-17)。 第三章「Nettelbladtと訴訟行為の概念」では、(1)「弁論主義(Verhandlungsmaxime)」の他に近世自然法が訴訟理論にもちこんだもうひとつの概念、つまり、Nettelbladt (17)が体系整備のために自然法的概念形成の方法によって獲得した「訴訟行為(Prozeβhandlung)」の概念が取り上げられる(S. 19)。(2)Nettelbladtは実体的な法的行為と訴訟行為を区別し(18)、彼の訴訟理論の中で、訴訟行為をなす技術の理論となされた訴訟行為に関する技術の理論を区別する。この点に眼を奪われて、Degenkolb (19)以来、彼が訴訟を行為に関する技術と看做している、と非難することが行われているが、この非難は、第一に彼の全体像を、第二に彼の「行為」の意味を理解しないことに基づく不当なものである(20)(S. 20-21)。(3)Nettelblabtは、訴訟の実施にさいして現われる個々の行為を訴訟それ自体、つまり訴訟の経過から区別することで、我々のテーマにとって決定的な一歩を踏みだしている。つまり、彼の発見した「訴訟行為」は、彼自身によっては理論化されなかったが、一九世紀の普通訴訟法学において、民事訴訟法の説明を秩序づけるという重要な役割を果たすことになる(S. 21-23)。 第四章「フリードリッヒ訴訟法」では、実際に自然法思想によって立法化されたところの、フリードリッヒ訴訟法が取リ上げられる(21)。(1)この立法の特徴は、理性に対する信仰だけでは訴訟秩序を明示することが難しいという認識(22)の下に、まず全体訴訟を導くための具体的な指導理念が展開されたことである。
1 0 0 0 OA 現代韓国・台湾における法学哲学の潮流
- 著者
- 鈴木 敬夫
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.190-199, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 OA Realism か Idealism か
- 著者
- 出水 忠勝
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.213-224, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 「理」の考究
- 著者
- 井上 茂
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.225-244, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 著者
- 兼子 義人
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, pp.134-145, 1978-11-20 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 23
1 0 0 0 OA 純粋法学の「構造」問題
- 著者
- 大塚 滋
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, pp.146-154, 1978-11-20 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 29