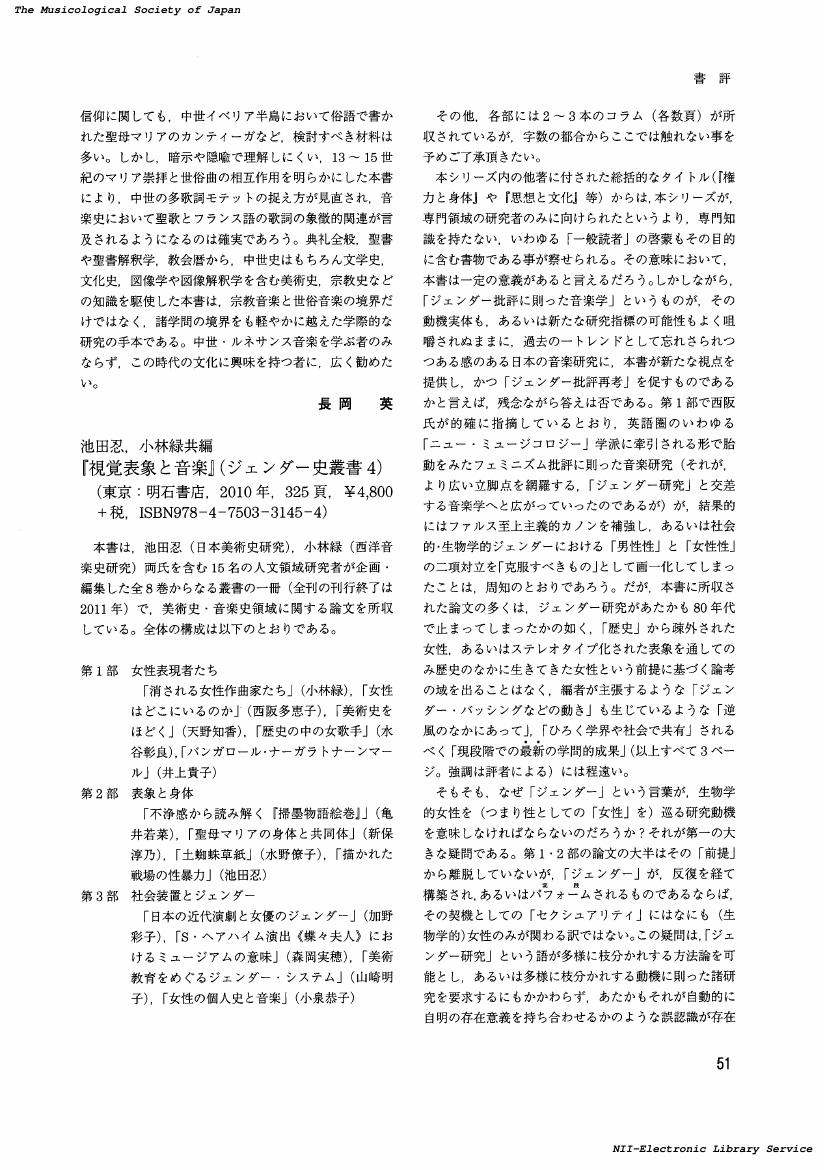1 0 0 0 『催馬楽略譜』における律と呂の特徴
- 著者
- 李 知宣
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1-17, 2003-10
- 著者
- 野原 泰子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.15-27, 2011-10-05 (Released:2017-04-03)
This paper examines the relationship between Alexander Scriabin's musical language and his philosophy by focusing on his late piano sonatas (Nos.6-10). In his Memoirs of Scriabin, Leonid Sabaneev quotes Scriabin, showing that this composer wrote sonatas of contrasting character: sacred or satanic. In light of this source and the theosophical creed to which Scriabin was devoted, the sonatas were analyzed by taking into account similarities found in them and his orchestral work Prometheus. As a result of the analysis, these sonatas can be divided into two groups according to their philosophical content. Nos.7, 8 and 10 form one group, and Nos.6 and 9 form the other. Sonatas Nos.7 (the "White Mass"), 8 and 10 share common techniques also seen in the Prometheus. In them, Scriabin imbues themes, motifs and harmonies with symbolic meaning, and, using suitable musical materials for the content of each scene, he expresses his theosophical cosmic view that "everything comes from, and returns to, the one being." In Nos. 6 and 9, however, harmonic progressions contrast sharply with those heard in Nos.7 and 8, and they reflect different content from the other three sonatas. Particularly in No.9 (the "Black Mass"), the analysis shows the content to be blasphemous: the sacred (the second theme) is desecrated by an evil spell (the first theme). While composing these sonatas, Scriabin was also mulling over his unfinished Mysterium. The writings of his brother-in-law, Boris de Schloezer, indicate that this ultimate work was to concern itself with the theosophical evolution of the universe. This is also the theme of sonatas Nos.7, 8 and 10, and the other two sonatas also have much in common with one scene of the work. Thus the significance of all five sonatas in the preparation for the Mysterium comes to light.
- 著者
- 福中 冬子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.51-53, 2012-10-15 (Released:2017-04-03)
- 著者
- 高瀬 澄子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.105-106, 2014
1 0 0 0 書評:榧木亨著 『日本近世期における楽律研究──『律 呂新書』を中心として』 (東京:東方書店,2017年3月31日,xiv+296頁,¥4,200+税,ISBN978-4-497-21703-5)
- 著者
- 高瀬 澄子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.72-74, 2018
- 著者
- 村田 千尋
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.54-56, 2016 (Released:2017-10-15)
- 著者
- 山口 真季子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.78-93, 2018 (Released:2019-03-15)
指揮者ヘルマン・シェルヘンは、シェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》の初演ツアーでデビューを果たし、新ウィーン楽派の音楽をはじめとする多くの同時代作品を積極的に演奏したことで知られている。彼に関する研究においては、彼の「現代音楽」に対する理解や、ラジオや音響実験に対する取り組みが着目されてきたが、彼の古典作品に対する態度を検討したものはほとんど無い。 しかし、シェルヘンが未完、未出版のまま残した原稿の中には、シューベルトの交響曲ロ短調D759「未完成」及びハ長調D944について論じた一連の原稿(「シューベルト・ブック」)が存在する。本論は、このベルリン芸術アカデミー・ヘルマン・シェルヘン・アルヒーフに残された「シューベルト・ブック」を基に、シェルヘンのシューベルトの音楽に対する解釈を明らかにしようとするものである。 シェルヘンはシューベルトの交響曲を、来るべきものへと突き進むベートーヴェンの交響曲とは対照的なものとして、すなわち一瞬の中にすべてを内包しようとするような音楽として捉える。彼の考えによれば、それは多様なシンメトリー、音楽構造の意味を明らかにしていくような表現記号の役割、そして動機操作ではなく和声や音色の変化による主題の変容によって実現される。 興味深いのは、シンメトリー構造や形式における平面構成、音空間の音色における開拓など、シェルヘンが指摘する音楽的特徴が、彼と同時代の作曲における問題意識に通じている点である。シェルヘンは、シューベルトの音楽が20世紀の作曲に対してアクチュアリティを持つものとして示そうとしたのである。そしてそのことが、シェルヘンをしてシューベルトの音楽を新たな側面から照らし出すことを可能にしたといえる。
- 著者
- 赤塚 健太郎
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.1-13, 2016 (Released:2017-10-15)
ドイツの作曲家ゲオルク・ムッファトが1698年に出版した組曲集《フロリレギウム》第2集の序文は、舞曲演奏で用いられるフランス流儀のヴァイオリンの運弓法について詳細に述べた重要な資料である。彼の運弓法の特徴として、各小節の最初の音符を下げ弓で弾くことを原則とし、この原則を守るためにしばしば下げ弓を二度連続で行うことを求めている点が挙げられる。下げ弓の連続という運弓では、最初の下げ弓の後に、二度目の下げ弓を準備するための弓の返しが必要となる。この弓の返しという動作が沈黙や響きの減衰をもたらし、結果としてフレーズの区切りを明瞭化することが先行研究で指摘されてきた。 本論文では、当時最も人気を集めていた舞踏・舞曲であるメヌエットに注目し、ムッファトの述べる運弓法を《フロリレギウム》第2集のメヌエット楽章に適用することで、連続する下げ弓がもたらす上述の効果がどのように働くか検証した。その結果、2つの注目すべき傾向が確認された。第一の傾向は、奇数小節の冒頭音符の直前に弓の返しが頻繁に現れる一方、偶数小節の冒頭音符の直前にはあまり現れないことである。第二の傾向は、奇数小節の直前に現れる弓の返しは腕の大きな動きを要するものであり、フレーズを区切る効果が強い一方、偶数小節の直前に現れる場合は小さな運動にとどまるということである。 以上の傾向の結果として、ムッファトの運弓法には、2小節単位のフレーズ構造を強める働きがあることが明らかとなった。当時のメヌエットの基本ステップは2小節を要するものであり、踊り手は奇数小節の開始時点を聴き分けてステップを踏むのが通例であった。よってムッファトの運弓法には、2小節フレーズを明瞭にすることで踊りのリズムを強める働きがあると考えられる。
1 0 0 0 エリック・リーヴィー著, 高橋宣也訳, 『モーツァルトとナチス-第三帝国による芸術の歪曲』, 東京:白水社, 2012年, 410頁, \4,000+税, ISBN978-4-560-08260-7
- 著者
- 大津 聡
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.35-36, 2013
- 著者
- 輪島 裕介
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.110-112, 2017
- 著者
- 稲田 隆之
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.116-119, 2017 (Released:2018-03-15)
- 著者
- 中村 美亜
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.94-110, 2006-02
1 0 0 0 多田純一著, 『日本人とショパン-洋楽導入期のピアノ音楽』, 東京:アルテスパブリッシング, 2014年3月31日, 427頁, \3,900+税, ISBN978-4-903951-82-9
- 著者
- 小岩 信治
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.41-43, 2015
1 0 0 0 戦前日本における学生オーケストラの曲目選択に関する実証研究
- 著者
- 井上 登喜子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.53-67, 2010-06
- 著者
- 和田 ちはる
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.30-44, 2012
Das Chorwerk Deutsches Miserere (1943-47) von Paul Dessau (1894-1979) und Bertolt Brecht (1898-1956) ist unter den im 20. Jahrhundert entstandenen antifaschistischen Musikwerken eines der bekanntesten. Allerdings wurde das Werk bis heute selten aufgefuhrt und es erfuhr auch in der Musikwissenschaft bislang wenig Beachtung. Dabei besitzt dieses Werk insofern auch eine grosse Bedeutung, weil es fur Brecht und Dessau die erste gemeinsame Arbeit war. Die Zusammenarbeit erfolgte zwar auf einen Vorschlag von Dessau, aber bei der Zusammenarbeit hat Brecht mehr Einfluss ausgeubt, als es ein Komponist einem Dichter normalerweise zugestehen wurde. Nach seinen Autographen, die sowohl uber einige umfangreiche und grundsatzliche Anderungen, als auch uber die Gesprache der Beiden informieren, kann man zusammenfassend urteilen, dass Dessau sich wahrend des Schaffensverlauf kompromissbereit zeigte. In der bisherigen Forschung wurde das Werk oft gemass der Asthetik von Brecht interpretiert. Sicherlich wurde die gesamte Textstruktur in diesem Werk logisch und verstandlich durch die Musik aufgegriffen und die Haltung der Musik in Bezug auf den Textinhalt tragt zu der vielschichtigen Verkettung der Verfremdungseffekte bei, die Brechts Theorie entspricht. Allerdings enthalt die musikalische Struktur weitaus grossere Dimensionen als vermutet. Musikalisch gibt es darin sowohl einige leicht als missverstandlich zu interpretierende Botschaften, die, von Brecht so sicher nicht beabsichtigt, seiner Theorie widersprechen, als auch einige Stellen, die von der Anhanglichkeit des Komponisten fur das rein musikalische Entwicklungsprinzip zeugen. Auf diese Widerspruchlichkeiten konzentriert dieser Aufsatz seine Aufmerksamkeit. Bei unserer Uberprufung des Musikwerkes werden wir den Schwerpunkt auf die Art und Weise der Beziehungen zwischen dem Gesamtkonzept und den einzelnen musikalischen Darstellungen legen. Bei unserer Forschung werden wir naturlich auch den Entstehungsanlass sowie den Schaffensverlauf in Betracht ziehen, die zum Verstandnis des Werkes notwendig sind. Die musikalische Vielseitigkeit des Werkes und dessen Bedeutung konnen erst durch diese Vorgehensweise bewertet werden.
- 著者
- 井口 淳子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.186-188, 2015
- 著者
- 仲 万美子
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.p109-125, 1980
1 0 0 0 地歌筝曲の<打ち合わせ>の考察
- 著者
- 福田 千絵
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.113-127, 1998
- 著者
- 井手口 彰典
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.101-103, 2014-03-15