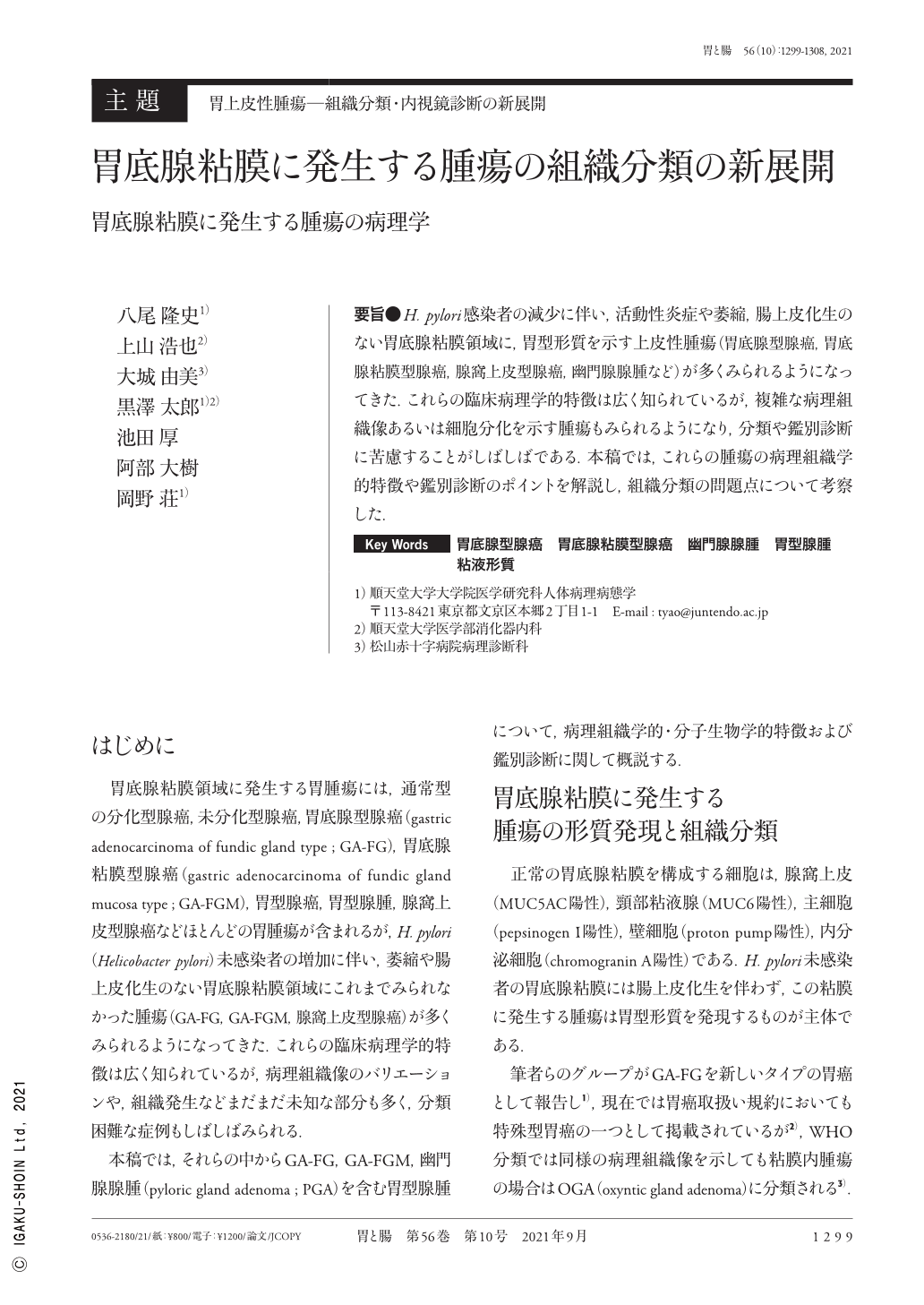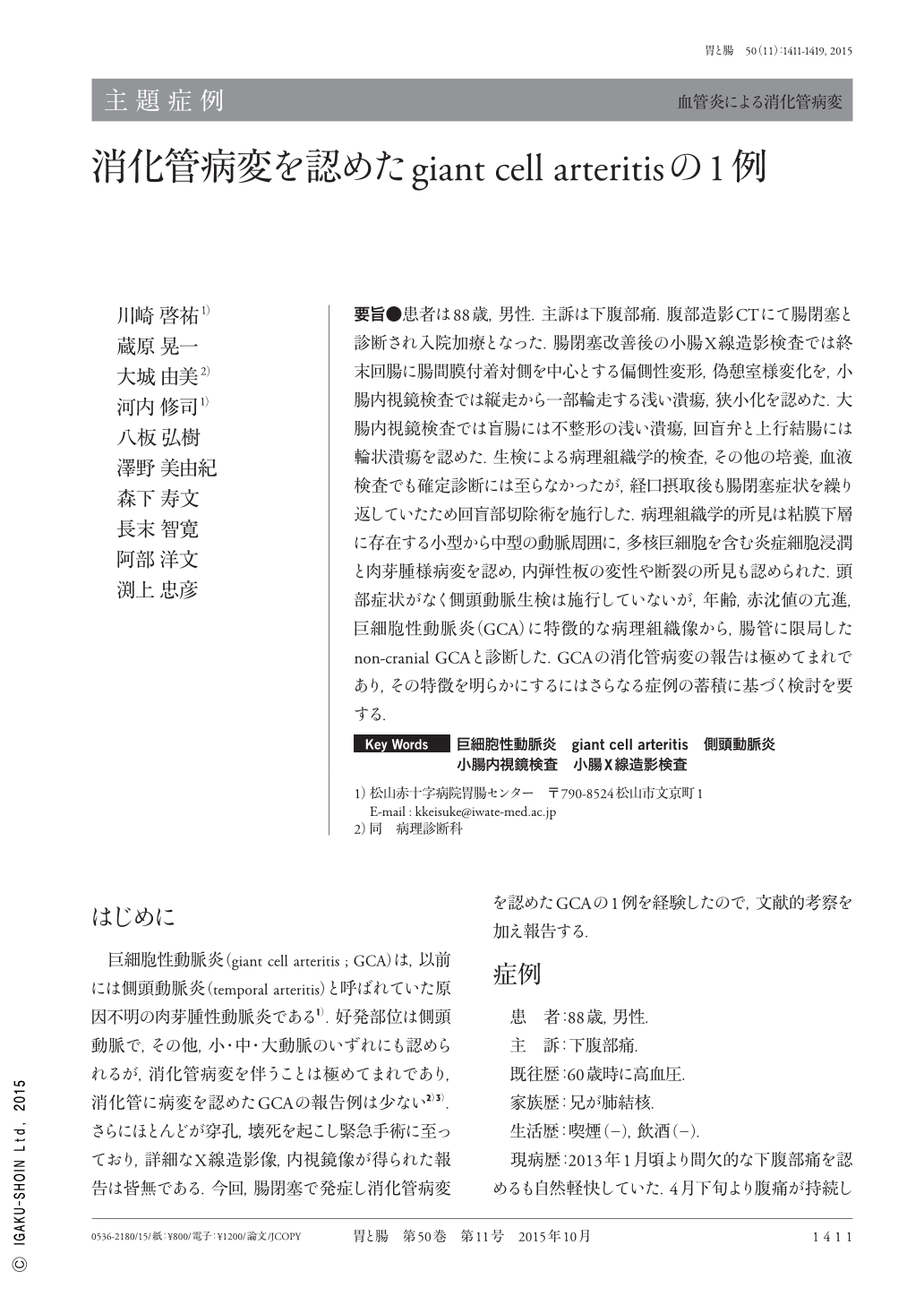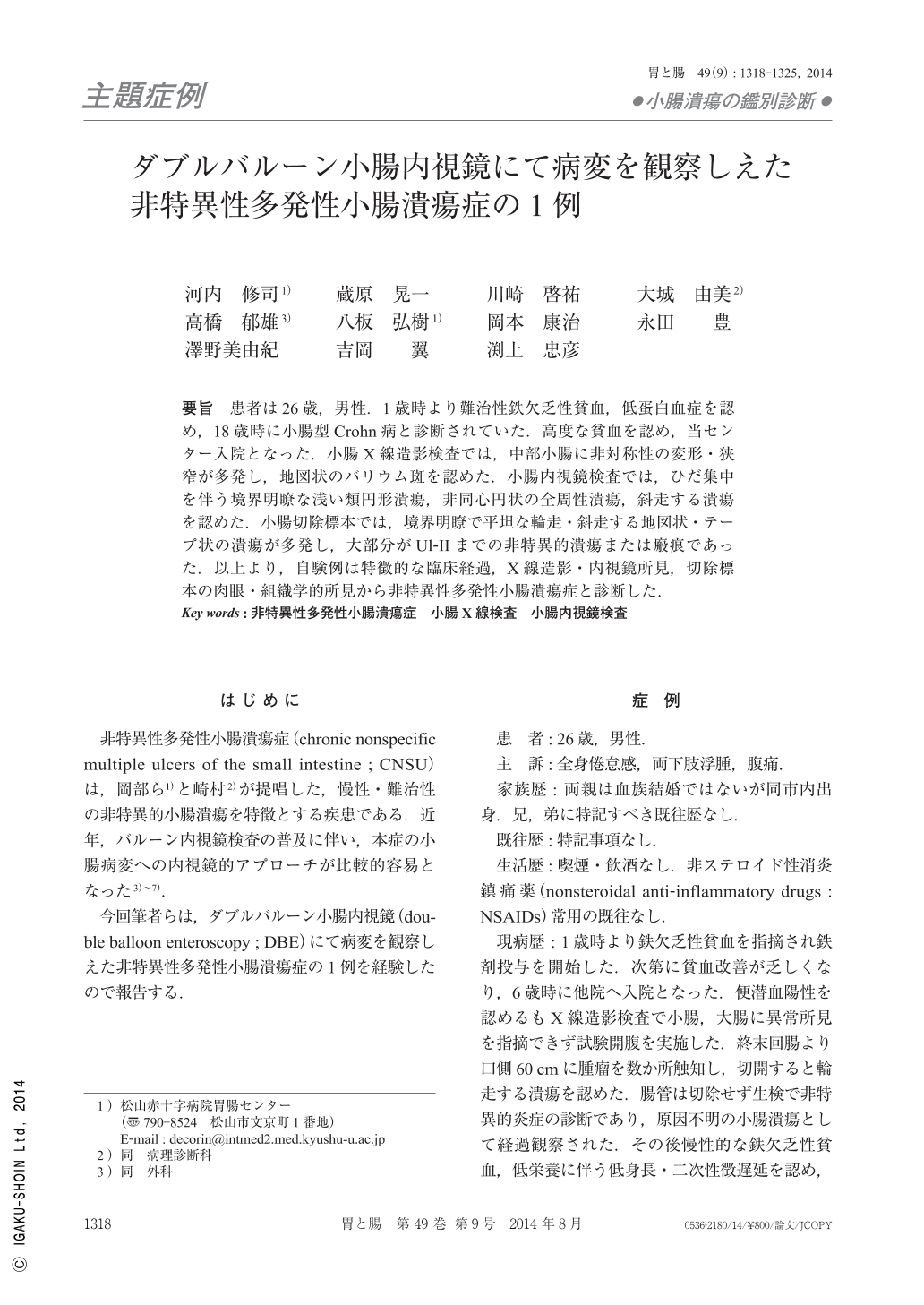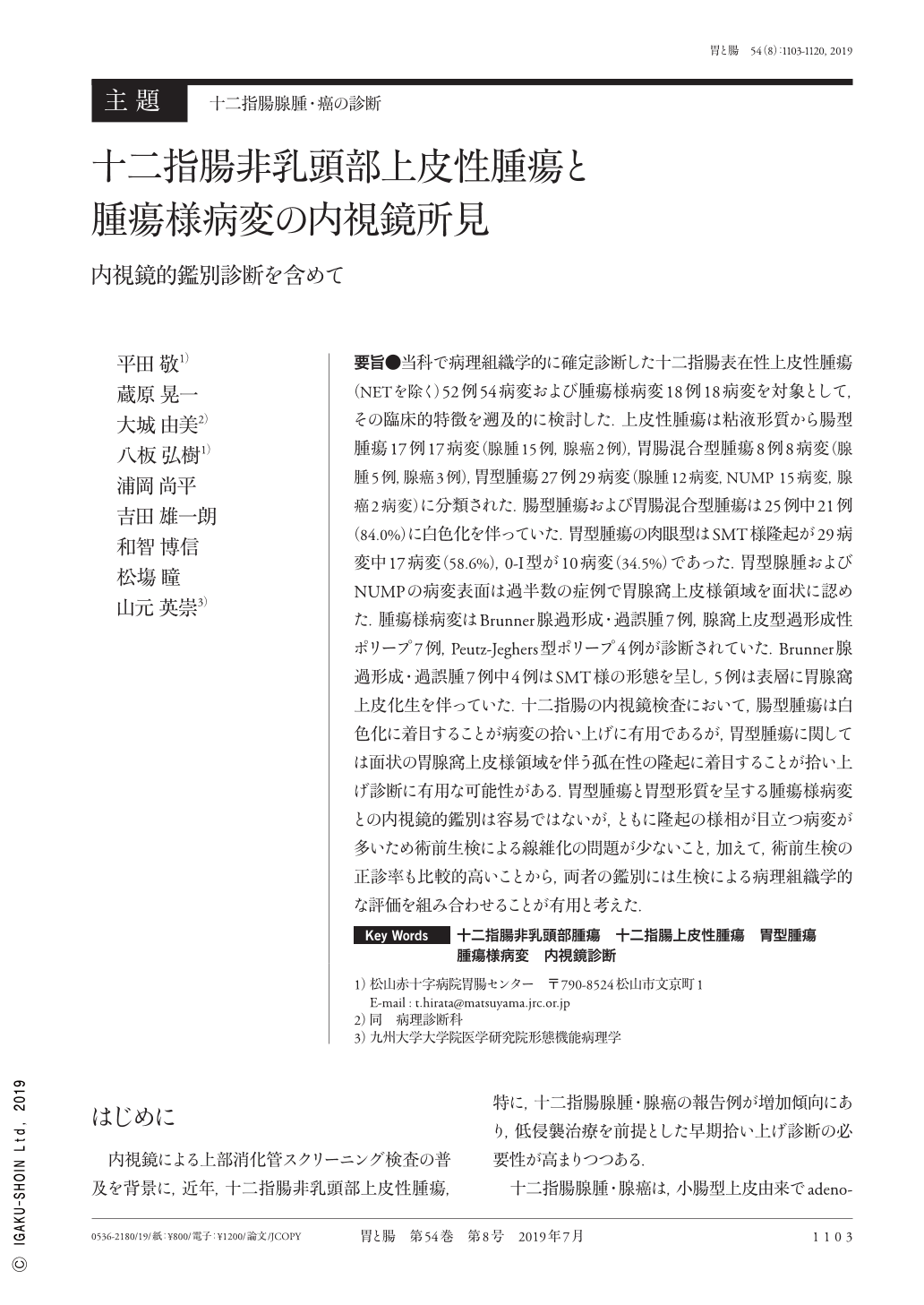要旨●H. pylori感染者の減少に伴い,活動性炎症や萎縮,腸上皮化生のない胃底腺粘膜領域に,胃型形質を示す上皮性腫瘍(胃底腺型腺癌,胃底腺粘膜型腺癌,腺窩上皮型腺癌,幽門腺腺腫など)が多くみられるようになってきた.これらの臨床病理学的特徴は広く知られているが,複雑な病理組織像あるいは細胞分化を示す腫瘍もみられるようになり,分類や鑑別診断に苦慮することがしばしばである.本稿では,これらの腫瘍の病理組織学的特徴や鑑別診断のポイントを解説し,組織分類の問題点について考察した.
2 0 0 0 消化管病変を認めたgiant cell arteritisの1例
- 著者
- 川崎 啓祐 蔵原 晃一 大城 由美 河内 修司 八板 弘樹 澤野 美由紀 森下 寿文 長末 智寛 阿部 洋文 渕上 忠彦
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.1411-1419, 2015-10-25
要旨●患者は88歳,男性.主訴は下腹部痛.腹部造影CTにて腸閉塞と診断され入院加療となった.腸閉塞改善後の小腸X線造影検査では終末回腸に腸間膜付着対側を中心とする偏側性変形,偽憩室様変化を,小腸内視鏡検査では縦走から一部輪走する浅い潰瘍,狭小化を認めた.大腸内視鏡検査では盲腸には不整形の浅い潰瘍,回盲弁と上行結腸には輪状潰瘍を認めた.生検による病理組織学的検査,その他の培養,血液検査でも確定診断には至らなかったが,経口摂取後も腸閉塞症状を繰り返していたため回盲部切除術を施行した.病理組織学的所見は粘膜下層に存在する小型から中型の動脈周囲に,多核巨細胞を含む炎症細胞浸潤と肉芽腫様病変を認め,内弾性板の変性や断裂の所見も認められた.頭部症状がなく側頭動脈生検は施行していないが,年齢,赤沈値の亢進,巨細胞性動脈炎(GCA)に特徴的な病理組織像から,腸管に限局したnon-cranial GCAと診断した.GCAの消化管病変の報告は極めてまれであり,その特徴を明らかにするにはさらなる症例の蓄積に基づく検討を要する.
- 著者
- 河内 修司 蔵原 晃一 川崎 啓祐 大城 由美 高橋 郁雄 八板 弘樹 岡本 康治 永田 豊 澤野 美由紀 吉岡 翼 渕上 忠彦
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.1318-1325, 2014-08-25
要旨 患者は26歳,男性.1歳時より難治性鉄欠乏性貧血,低蛋白血症を認め,18歳時に小腸型Crohn病と診断されていた.高度な貧血を認め,当センター入院となった.小腸X線造影検査では,中部小腸に非対称性の変形・狭窄が多発し,地図状のバリウム斑を認めた.小腸内視鏡検査では,ひだ集中を伴う境界明瞭な浅い類円形潰瘍,非同心円状の全周性潰瘍,斜走する潰瘍を認めた.小腸切除標本では,境界明瞭で平坦な輪走・斜走する地図状・テープ状の潰瘍が多発し,大部分がUl-IIまでの非特異的潰瘍または瘢痕であった.以上より,自験例は特徴的な臨床経過,X線造影・内視鏡所見,切除標本の肉眼・組織学的所見から非特異性多発性小腸潰瘍症と診断した.
要旨●当科で病理組織学的に確定診断した十二指腸表在性上皮性腫瘍(NETを除く)52例54病変および腫瘍様病変18例18病変を対象として,その臨床的特徴を遡及的に検討した.上皮性腫瘍は粘液形質から腸型腫瘍17例17病変(腺腫15例,腺癌2例),胃腸混合型腫瘍8例8病変(腺腫5例,腺癌3例),胃型腫瘍27例29病変(腺腫12病変,NUMP 15病変,腺癌2病変)に分類された.腸型腫瘍および胃腸混合型腫瘍は25例中21例(84.0%)に白色化を伴っていた.胃型腫瘍の肉眼型はSMT様隆起が29病変中17病変(58.6%),0-I型が10病変(34.5%)であった.胃型腺腫およびNUMPの病変表面は過半数の症例で胃腺窩上皮様領域を面状に認めた.腫瘍様病変はBrunner腺過形成・過誤腫7例,腺窩上皮型過形成性ポリープ7例,Peutz-Jeghers型ポリープ4例が診断されていた.Brunner腺過形成・過誤腫7例中4例はSMT様の形態を呈し,5例は表層に胃腺窩上皮化生を伴っていた.十二指腸の内視鏡検査において,腸型腫瘍は白色化に着目することが病変の拾い上げに有用であるが,胃型腫瘍に関しては面状の胃腺窩上皮様領域を伴う孤在性の隆起に着目することが拾い上げ診断に有用な可能性がある.胃型腫瘍と胃型形質を呈する腫瘍様病変との内視鏡的鑑別は容易ではないが,ともに隆起の様相が目立つ病変が多いため術前生検による線維化の問題が少ないこと,加えて,術前生検の正診率も比較的高いことから,両者の鑑別には生検による病理組織学的な評価を組み合わせることが有用と考えた.
1 0 0 0 脳性麻痺に対する機能的脊髄後根切断術について
- 著者
- 比屋根 直美 赤嶺 大志 宮城 淳 溝田 弘美 又吉 清子 運天 智子 仲地 正人 渡慶次 賀寿 新里 真由実 大城 由美子
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.76, 2003
2000年11月から2002年11月までに10名の脳性麻痺児に対して機能的脊髄後根切断術を実施した。タイプは痙直型両麻痺9名、混合型四肢麻痺1名。股関節亜脱臼は3名4股、術前運動機能は臥位1名、這い這い3名、バニーホッピング2名、四つ這い3名、独歩1名、術後期間は平均14.6ヶ月であった。術前後で痙性の程度(Ashworth scale)・関節可動域・粗大運動能力尺度・Migration Percentage(MP)を評価し、独歩例は観察による歩行分析を行った。<BR>下肢の痙性は、Ashworth scaleの平均でみると全症例で軽減しており、術後1年以上経過している5名も維持されている。関節可動域は、股関節外転8名、伸展5名、膝窩角5名に改善がみられ、足関節背屈はfast stretchでは全例改善しているが、最大可動域では3名で改善し、過背屈はなかった。粗大運動能力尺度は術後1_から_3ヶ月は低下することもあるが、多くは3_から_6ヶ月で術前の状況に回復、もしくは若干の伸びがみられた。MP50%以上の股関節亜脱臼は術後2名2股になった。独歩可能な1名の術前後の歩行を比較すると、尖足歩行は残っているものの膝・足関節の動的関節可動域は改善し、歩幅が大きくなった。
1 0 0 0 OA 抗菌化学療法が奏功したWhipple病の1例
- 著者
- 大久保 智恵 藤崎 智明 横田 英介 川崎 啓祐 大城 由美
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.10, pp.2598-2600, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3
Whipple病は放線菌近縁のグラム陽性桿菌Tropheryma whipplei(T. whipplei)感染により多彩な臨床症状を生じる全身感染症である.1907年の1例目の報告以来,世界各地から1,000例程度の報告があるが,中年以降の白人例が多く,本邦からの報告はまれである.当科に原因不明の遷延性下痢・低蛋白血症のため入院し,十二指腸生検の病理所見からWhipple病と診断し,抗菌化学療法で劇的な改善を認めた1例を経験した.Whipple病は抗菌薬がない時代は致死的疾患であったが,現在は抗菌療法で治療可能である.しかし,現在でも診断,治療が遅れると予後不良となるため,本邦においても留意すべきと考え報告する.