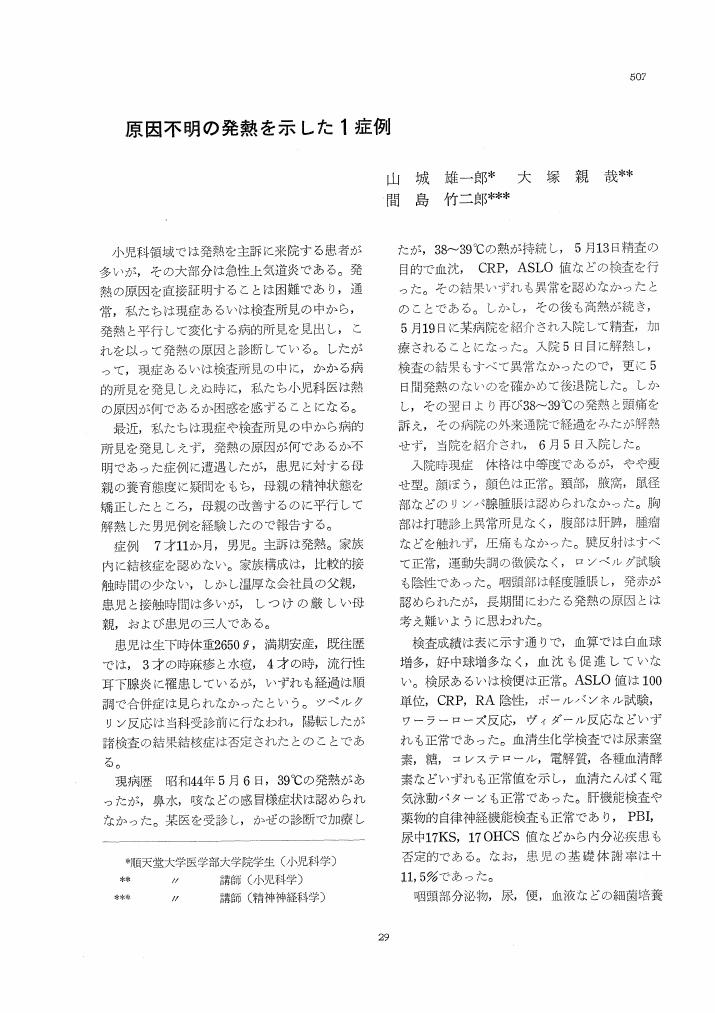4 0 0 0 腸内細菌:宿主の健康と疾病への密接な関係
- 著者
- 山城 雄一郎
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂醫事雑誌 (ISSN:21879737)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.25-34, 2014
- 被引用文献数
- 1
近年,細菌の検索に導入された菌の遺伝子DNAやリボゾーム16SrRNAをターゲットにした分子生物学的手法の普及により,ヒトの腸内細菌の動態が,培養不可でそれまで知りえなかった菌も含め,より詳細に明らかになってきた.ヒト成人の腸内細菌には,約500~1,000種,100兆個の菌が生着し,その構成の割合は食事(栄養)の影響を受けて生涯を通して変化し,また内的,外的な両方の環境の変動にも修飾されて敏感に反応する.腸内細菌構成菌の変動は,分子シグナルを介して宿主の代謝と免疫など,生理,生化学的機能に影響し,宿主の健康と病的状態に密接に関係する.胎児期に無菌の腸管は,出産時に産道を通過する際に母親から菌を獲得し腸管内へ生着が開始する.母乳栄養児では生後3ヵ月頃までにBifidobacteria優位の菌叢になり,生後6ヵ月頃には全体の90%以上を占めるようになる.しかし離乳食の導入に伴い,人工栄養児のそれと次第に差異は縮小する.他方未熟児は帝王切開(帝切)で出産する例が多く,母親から出産時に菌を獲得する機会を逸し,NICU等の環境から得る菌が最初に腸管へ生着する結果,腸内細菌構成の異常(dysbiosis)を生じ,新生児期の感染や壊死性腸炎(NEC)等の病的潜在リスクとなる.いわゆる善玉菌の腸内細菌,特にBifidobacteriaは,消化吸収,免疫を含む腸管防御等の腸管機能や解剖学的発達,成長に重要な役割を果たす.腸内細菌と食事(栄養)は,相互に密接な関係を有する.食習慣は腸内細菌構成に影響を与え,蛋白質や動物性脂肪(高飽和脂肪酸)の食事摂取が多いとEnterobacteriaceae(Preteobacteria)の割合が多く,高炭水化物食はPrevotellaが増加する.腸内細菌は,食事中の難消化性炭水化物(食物繊維)を代謝,発酵し短鎖脂肪酸(SCFs)の酢酸,プロピオン酸,酪酸を主として産生する.酢酸とプロピオン酸は宿主の,酪酸は直腸上皮細胞それぞれのエネルギー源となる.また,腸内細菌は胆汁酸代謝,食事由来のcholine代謝に関与し,前者は脂質代謝や糖代謝,後者は動脈硬化の進展に関係する.世界的な流行の様相を呈する肥満の元凶は,近代の社会環境の変化に基因したエネルギー摂取と消費のアンバランス,すなわち "西洋食" と称される高カロリー,高(飽和)脂肪食の摂取にある.高カロリー,高脂肪食はFirmicutes, Proteobacteriaの増加,Bacteroidetesの減少など,腸内細菌構成の異常dysbiosisを招く.これらの増加した菌はエネルギー産生や抽出能が高く,宿主の脂肪組織を増加させる.さらに細胞毒性かつ炎症惹起作用のあるリポポリサッカライドを産生し血中に吸収され(endotoxemia),軽度でしかし慢性の炎症を生じる.そのため,炎症性サイトカインが分泌され,インスリン抵抗性の原因となる.インスリン抵抗性が長期化すると2型糖尿病(T2DM)やその他のメタボリック症候群の高リスク因子となる.共同研究者の佐藤淳子ら(順天堂大学代謝内分泌科)は,T2DM患者の腸内細菌が健常者のそれと異なり,その20数%で菌血症を伴うことを世界で初めて発表した.腸内細菌の異常は毒性のある二次胆汁酸産生を増加し,肝に運ばれ肝細胞癌の発症の原因になることをがん研究会の大谷らは報告している.大腸癌の一部も二次胆汁酸がその発症に関与していることが示唆される.腸内細菌と宿主の免疫,代謝等の密接な関係から,腸内細菌のdysbiosisが宿主の健康と疾病に影響を及ぼす学術的エビデンスが近年急速に蓄積されてきている.これに伴いProbioticsによる健康管理,疾病の予防や治療をも見据えた研究も活発になり,近い未来の医療に大きなインパクトを与えるものと期待される.
1 0 0 0 OA 原因不明の発熱を示した1症例
1 0 0 0 OA 1.新生児高ビリルビン血症の光線療法
- 著者
- 山城 雄一郎
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.441-446, 1973-12-10 (Released:2014-11-22)
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 川崎病患児小腸粘膜細菌叢の病態発症への関与についての検討
インフォームド・コンセントの得られた川崎病患児14例中9例の小腸粘膜から,患児末梢血単核球を有意に刺激する4種のグラム陰性桿菌,3種のグラム陽性球菌,3種のグラム陰性球菌を検出した.このうち患児2例からはスーパー抗原活性を有するS.aureusが検出された.また検出された細菌のうち1種は偏性嫌気性菌で通常の咽頭/後鼻腔,便培養では得られない細菌群であった.これらの培養上清を同一患児血清と反応させ,Western blottingにより反応した蛋白成分をIgG抗体を用いて検出した.その結果,9例全例からγグロブリン投与前の血清で検出されなかった各細菌の産生物に対するIgG抗体が投与後の血清にて検出されていた.以上より,小腸粘膜から検出された細菌の産生物が,患児単核球を増殖させ,何らかの免疫学的活性をもたらしていること,しかもその細菌産生物の産生時期は川崎病急性期であること,γグロブリンによりその中和抗体が供給されたことより,川崎病が治癒を迎えた可能性が大きいことが推測され,これら細菌産生物が川崎痛の原因物質であることを強く示唆する結果と考えられた.これらのうち2例から得られた56kDa,47kDa,37kDaの3種のバンドについてのみアミノ酸分析が行い得たが,これらはいずれも細菌の内因性蛋白であった.以上のことから,川崎病の病原菌は単一なものではなく極めてheterogeneousなものであることが推察された.
1 0 0 0 小児におけるHelicobactor pyloriの感染
平成7年12月から平成8年3月の間に、1.5歳児検診を受診した95人と3歳児検診を受診した113人の唾液中Helicobactor pylori抗体を測定した。また、平成7年度に小学校1年生であった310人と中学2年生であった300人から、平成7年6月と平成8年6月の2回唾液を採取し、唾液中H.pylori抗体を測定した。同意に保護者に、既往症、家族歴、ペットなどに関する質問票の記入を依頼した。さらに、平成8年に小児科受診者85人の血清Helicobactor pylori抗体と唾液中H.pylori抗体を測定した。唾液の測定は、英国Cortecs社製のキット、Helisalによって、血清の測定は米国Biomerica社製のキット、Pilika Plate G Helicobactorによって行った。小児科受診者85人の血清Helicobactor pylori抗体と唾液中H.pylori抗体を測定したところ血清陽性者は4人で、その唾液中抗体価は1.5以上が3人、0.5未満が1人であった。こうしたデータに基づき、1.5歳児では唾液中抗体価1.0以上を陽性、1.0未満を陰性とし、3歳児では1.5以上を陽性、1.0未満を陰性とし、1.0-1.49の児は分析から除いた。小学生と中学生については、平成7年8年とも唾液中抗体価1.0以上を陽性、2回とも1.0未満を陽性とし、2回の結果が1.0にまたがる例は分析から除いた。同胞がいる小児は1.5歳と3歳で唾液中抗体陽性率はそれぞれ8.6%、24.1%で、同胞のいない小児の0.6%、7.7%より大きく、3歳児では有意であったが、小中学生では唾液中抗体と関連を認めなかった。1.5歳児では、同室で同胞と寝ていた期間が唾液中抗体陽性者で有意に長かった。3歳児では、親が添い寝していた期間が唾液中抗体陽性者で有意に短かった。小中学生では、唾液中抗体陽性者で、小学校入学以前の共同生活の期間が有意に長かった。乳幼児の栄養や、親が噛んだ食べ物を与えたか否か、出生児や健康受診時の体格、両親の胃疾患の既往、ペットの有無は、いずれの年齢でも唾液中抗体と関連を認めなかった。