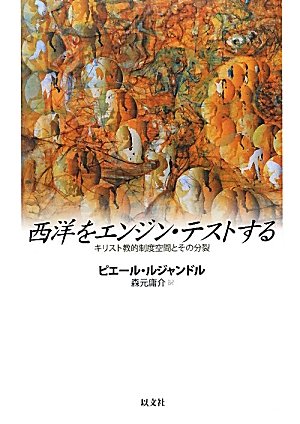5 0 0 0 OA 17世紀演劇論争を再考するために : 決疑論をプリズムとして(研究論文)
- 著者
- 森元 庸介
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- no.99, pp.131-147, 2011-08-26
La litterature consacree a la <<querelle du theatre>> au XVII^e siecle francais, malgre son abondance, laisse une question sans reponse: qui defendit le theatre dans ce proces litteraire? Notre etude tente de combler cette lacune en analysant tour a tour les textes d'auteurs hostiles au theatre-notamment le Traite du theatre (1667) de Pierre Nicole-et ceux d'auteurs du camp adverse. Le Traite commence par condamner, en y trouvant une marque de la <<corruption>> de son siecle, le <<soin>> pris par les contemporains pour allier hypocritement l'amour du theatre et la devotion. Une lecture detaillee conduit a supposer que l'auteur, en rejoignant le Prince de Conti (Traite du theatre et des spectacles, 1666), fait allusion aux casuistes dits <<relaches>>, dont il devait examiner attentivement les textes au cours de sa collaboration pour la redaction des Provinciates de Blaise Pascal, ouvrage connu pour sa critique de la casuistique. De fait, Antonio Escobar y Mendoza, la victime la plus celebre de la plume pascalienne, soutient dans son Liber theologiae moralis (1644) qu'il n'est pas peccamineux de voir un spectacle meme scandaleux si ce n'est qu'<<ob aliquem bonem finem>>. L'argument correspond exactement a la description de Nicole, en ceci qu'il recourt a la methode couramment appelee <<direction d'intention>>, qui cristalliserait toute l'hypocrisie casuistique. A cela s'ajoute une autre coincidence. Nicole ecarte une <<idee metaphysique>> selon laquelle le theatre ne serait qu'une <<representation d'actions et de paroles>>. Une illustration parfaite de cette idee se trouve dans les Resolutiones morales (1628-1655) d'un laxiste par excellence, Antonino Diana. Ce theologien theatin avance en effet que l'interet pour le theatre est moralement neutre tant qu'il se concentre sur la <<repraesentatio ipsa>>, et non sur la <<res repraesentata>>. Ces correspondances textuelles conduisent a repenser la querelle du theatre a travers le debat autour de la morale laxiste, qui caracterise, au-dela du seul jansenisme, les courants principaux de la pensee catholique dans la France classique.
2 0 0 0 OA 生命統治時代の〈オイコス〉再考とポスト・グローバル世界像の研究
折からの東日本大震災と福島第一原発事故は研究課題を先鋭化するかたちで起こり、これを受けて、グローバル化した世界における〈オイコス〉再検討という課題を、 現代の文明的ともいうべき災害や核技術の諸問題、さらに近年注目されている「脱成長」のヴィジョンに結び付け、主としてフランスの論者たちとの交流を通じて〈技術・産業・経済〉システムの飽和の問題として明らかにした。その内容や、そこから引き出される展望については、下に列記した雑誌諸論文や以下の刊行物に示した。『〈経済〉を審問する』(せりか書房)、報告書『核のある世界』(A5、100p.)『自発的隷従を撃つ』(A5、121p.)
1 0 0 0 西洋をエンジン・テストする : キリスト教的制度空間とその分裂
- 著者
- ピエール・ルジャンドル著 森元庸介訳
- 出版者
- 以文社
- 巻号頁・発行日
- 2012
- 著者
- 渡名喜庸哲 森元庸介編著
- 出版者
- 以文社
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 OA <書評>『啓蒙の運命』[富永茂樹編, 名古屋大学出版会, 2011年]
- 著者
- 森元 庸介
- 出版者
- 京都大學人文科學研究所
- 雑誌
- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.89-91, 2012-03
1 0 0 0 藝術とその正当性:決疑論と萌芽期美学の思想連関を検討主題として
史料整理に注力した前2年度の成果に立脚し、今年度は、近世決疑論における藝術の位置づけについて、総括的な考察をおこなうことを主眼とした。その内容と意義は以下のごとくまとめられる。(1)藝術に対する寛解主義と厳格主義の対立は、一義的には道徳上の対立である。だが、この対立は、美学的な見地からするならば、作品を非実効的であるがゆえに安全とみなす「弱い」藝術観と、実効的であるがゆえに危険とみなす「強い」藝術観の対立として翻案される。(2)とりわけ前者、換言するなら藝術を形式主義的な相のもとで理解する態度について、思想史の通念は、それをもっぱら18世紀以降に成立したものとみなしてきたが、16-17世紀に全盛期を仰えた決疑論について精査することで、西洋における藝術観の変遷をめぐる時間的な見取りを再検討する必要を明らかにした。また、一般的には、上記の対立は、理念的には作品の間然することなき理解を前提する検閲という営為の逆説について再考をうながすと同時に、翻っては、表現の自由、さらには思想の自由が抱える消極性について一定の光を投げかけることにもなった。(3)また、本研究は、決疑論が依拠した法学的コーパス(主として教会法の領域)をつうじて、藝術の問題を法制史の文脈に位置づける道筋を実証的に示すとともに、中世に成立した法文書群の近世における持続的な効果を裏づけた点でも意義を有している。前2年の成果と併せ、以上の内容を、学会発表2点をつうじて公表した。