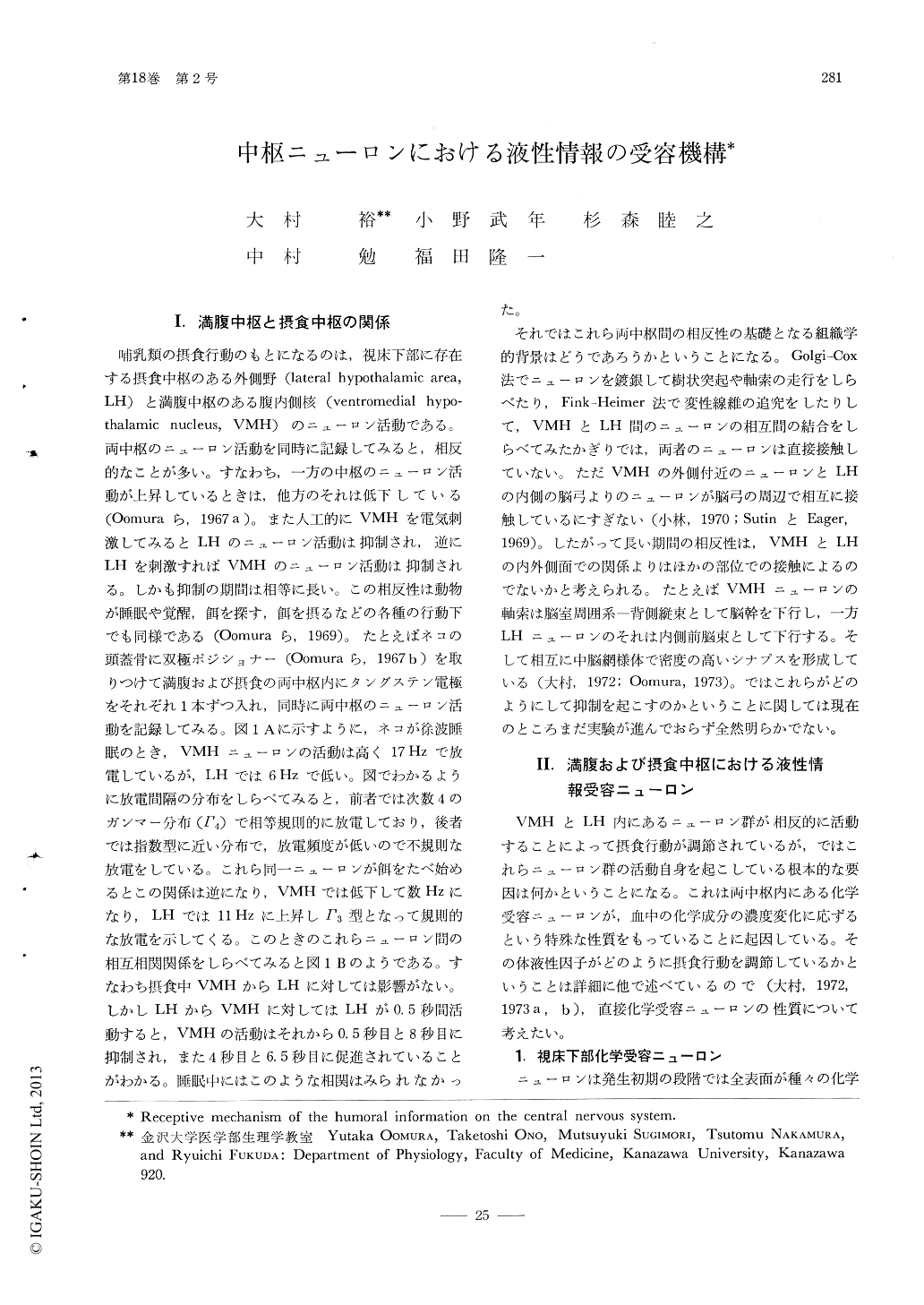3 0 0 0 中枢ニューロンにおける液性情報の受容機構
- 著者
- 大村 裕 小野 武年 杉森 睦之 中村 勉 福田 隆一
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 神経研究の進歩 (ISSN:00018724)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.281-294, 1974-04-10
Ⅰ.満腹中枢と摂食中枢の関係 哺乳類の摂食行動のもとになるのは,視床下部に存在する摂食中枢のある外側野(lateral hypothalamic area,LH)と満腹中枢のある腹内側核(ventromedial hypothalamic nucleus,VMH)のニューロン活動である。両中枢のニューロン活動を同時に記録してみると,相反的なことが多い。すなわち,一方の中枢のニューロン活動が上昇しているときは,他方のそれは低下している(Oomuraら,1967 a)。また人工的にVMHを電気刺激してみるとLHのニューロン活動は抑制され,逆にLHを刺激すればVMHのニューロン活動は抑制される。しかも抑制の期間は相等に長い。この相反性は動物が睡眠や覚醒,餌を探す,餌を摂るなどの各種の行動下でも同様である(Oomuraら,1969)。たとえばネコの頭蓋骨に双極ポジショナー(Oomuraら,1967 b)を取りつけて満腹および摂食の両中枢内にタングステン電極をそれぞれ1本ずつ入れ,同時に両中枢のニューロン活動を記録してみる。図1Aに示すように,ネコが徐波睡眠のとき,VMHニューロンの活動は高く17Hzで放電しているが,LHでは6Hzで低い。
2 0 0 0 OA 四つ這い位からみた胸椎部の可動性と腰痛との関連性について
- 著者
- 前田 廣恵 福田 隆一 宮本 良美
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 第27回九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- pp.50, 2005 (Released:2006-08-01)
【目的】四つ這い位での胸椎部可動性と腰痛との関連性について調査する。【対象と方法】神経症状のない慢性腰痛患者(以下腰痛群)10名、健常者(以下非腰痛群)10名を対象に四つ這いにて肩峰・坐骨結節・胸骨剣状突起の高さの棘突起(以下A点)にランドマークしキャットカールを行い、それぞれの肢位にて写真撮影を行う。肩峰・坐骨結節を結ぶ線を基準線にA点とのなす角を胸椎部可動性とし腰痛群・非腰痛群で比較、また、下肢のタイトネス・股関節の可動域との関連性について検討した。【結果】1、胸椎部伸展位への角度変化において腰痛群で有意に可動性低下を認めた。2、胸椎部屈曲位から伸展位への角度変化において腰痛群で有意に可動性低下を認めた。3、股関節可動域において腰痛群の屈曲・内旋に有意な制限を認めた。4、タイトネステストにおいて腰痛群の大腿四頭筋に有意なタイトネスを認めた。【考察】今回の結果より、腰痛群において胸椎部伸展方向への可動性低下があり、上半身重心が後方に位置している傾向にあると推測された。胸椎制御は体幹に柔軟性を要求し、支持性を筋活動から非収縮組織に移行でき筋疲労しにくいという利点があるが、腰痛群においては胸椎部可動性の低下により周囲筋への負担が大きいことが予測される。また、下部体幹制御は上半身重心の前後移動に関与するという報告より、腰痛群において、上半身重心が後方へ偏移した姿勢が固定化された代償として下半身にも影響を及ぼしていると考えられる。腰痛群の股関節屈曲に有意な制限を認めた要因として、股関節伸筋群のタイトネスによる骨盤後傾位が挙げられ、同様に大腿四頭筋のタイトネスも生じたものと考えられる。また、股関節内旋制限においては、骨盤の運動のみを考えると、胸椎部伸展位への運動制限により骨盤においては寛骨のうなずき運動が不十分(骨盤後傾位)となり、股関節は外旋位優位となるためであると考えられる。以上のことから、上半身重心の存在する胸椎レベルの可動性獲得は重要であり、胸椎部の可動性低下が腰痛を引き起こす一要因であると捉えるべきである。しかし、今回の研究では純粋な胸椎可動性の評価には到らなかったため、今後は下肢・骨盤の影響を除去した肢位での純粋な胸椎可動性の評価法を考案し、腰痛との関連性について更に調査していきたい。【まとめ】1、四つ這い位での胸椎部可動性と腰痛との関連について調査した。2、腰痛群において胸椎伸展方向への可動性低下を認めた。3、腰痛群の股関節屈曲・内旋制限、大腿四頭筋のタイトネスを認めた。4、胸椎可動性低下が腰痛の1要因として考えられた。5、下肢・骨盤の影響を除去した肢位での純粋な胸椎可動性の評価法が重要である。
1 0 0 0 女子高校野球選手の肩関節可動域の特徴(スポーツ)
- 著者
- 永濱 良太 福田 秀文 福田 隆一 藤井 康成
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, 2002
1 0 0 0 OA 下腿浮腫に対するアプローチに関しての一考察
- 著者
- 瀬戸山 雄介 福田 隆一 山下 真司 中畑 敏秀 宮崎 麻理子 福田 秀文 了徳寺 孝文 工藤 貴裕 永濱 智美
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 第29回九州理学療法士・作業療法士合同学会 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- pp.166, 2007 (Released:2008-02-01)
【はじめに】 大腿骨頚部骨折術後において、浮腫が関節拘縮、感覚障害など二次的に機能障害を起こす要因となり、理学療法を進める上で問題となることが多い。そのアプローチとしてパンピングを用いる事は多いが、良好な結果を得られないことも経験する。そこで今回大腿静脈に通過障害があることを仮定し、その阻害因子と成りうる筋に対してアプローチを行い、若干の知見を得たのでここに報告する。【対象】 大腿骨頸部骨折術後3週以上経過しており明らかな心疾患、腎疾患がなく下腿に浮腫がみられるとした。大腿静脈通過障害にアプローチを行った群(以下アプローチ群)に関しては6名10脚、内訳は男性1名、女性5名、平均年齢85.6±7.8歳。 コントロール群は4名7脚、内訳は女性4名、平均年齢89.5±4.4歳であった。【方法】 アプローチ内容に関して、アプローチ群は、腸腰筋、恥骨筋、内転筋を中心に内転筋管周囲筋及び鼠径部周囲筋に対してストレッチ、マッサージ、ストレッチ、筋収縮の順に行った後、足趾及び足部パンピングを実施した。コントロール群は足趾及び足部パンピングのみ実施した。浮腫の評価は下腿周径(最大、最小)、足部周径(第一中足骨骨底と舟状骨を結ぶ周径)を測定。測定時間はアプローチ前の午前9時とアプローチ後の翌日午前9時とし、アプローチ実施時間に関しては午後2時とした。データ処理に関しては、両群における改善脚数の割合及び周径の改善率を算出した。改善率に関しては、対応のないt検定を用いてデータ処理を行った。【結果】 前日と比較して改善がみられた脚数の割合は、下腿最大周径においてアプローチ群では70%(0.5センチ~1.5センチ改善)であり、コントロール群では14%(0.5センチ~0.8センチ改善)であった。下腿最小周径において、0.5センチ以上改善した脚数の割合はアプローチ群で50%、コントロール群で0%であった。足部周径において、0.5センチ以上改善した脚数の割合は、アプローチ群で30%、コントロール群で14%であった。また下腿最大部周径におけるアプローチ群とコントロール群の改善率の比較において、有意差が認められた。(P<0.05)【考察】 アプローチを行った方が下腿浮腫は改善する傾向にあった。これは大腿静脈が内転筋管、大腿三角、血管裂孔を通過しており、周囲の筋(内転筋管周囲筋、鼠径部周囲筋)から圧迫を受け、循環障害を起こす可能性が示唆された。また内転筋管・鼠径部周囲筋に関しては、術後の外転筋不全による内転筋の代償や、長時間の臥床・座位による適応性短縮などにより機能不全を生じやすい。これに対して内転筋管・鼠径部周囲筋にアプローチを行うことで大腿静脈通過障害が改善したことが、下腿浮腫の改善につながったと考えられる。