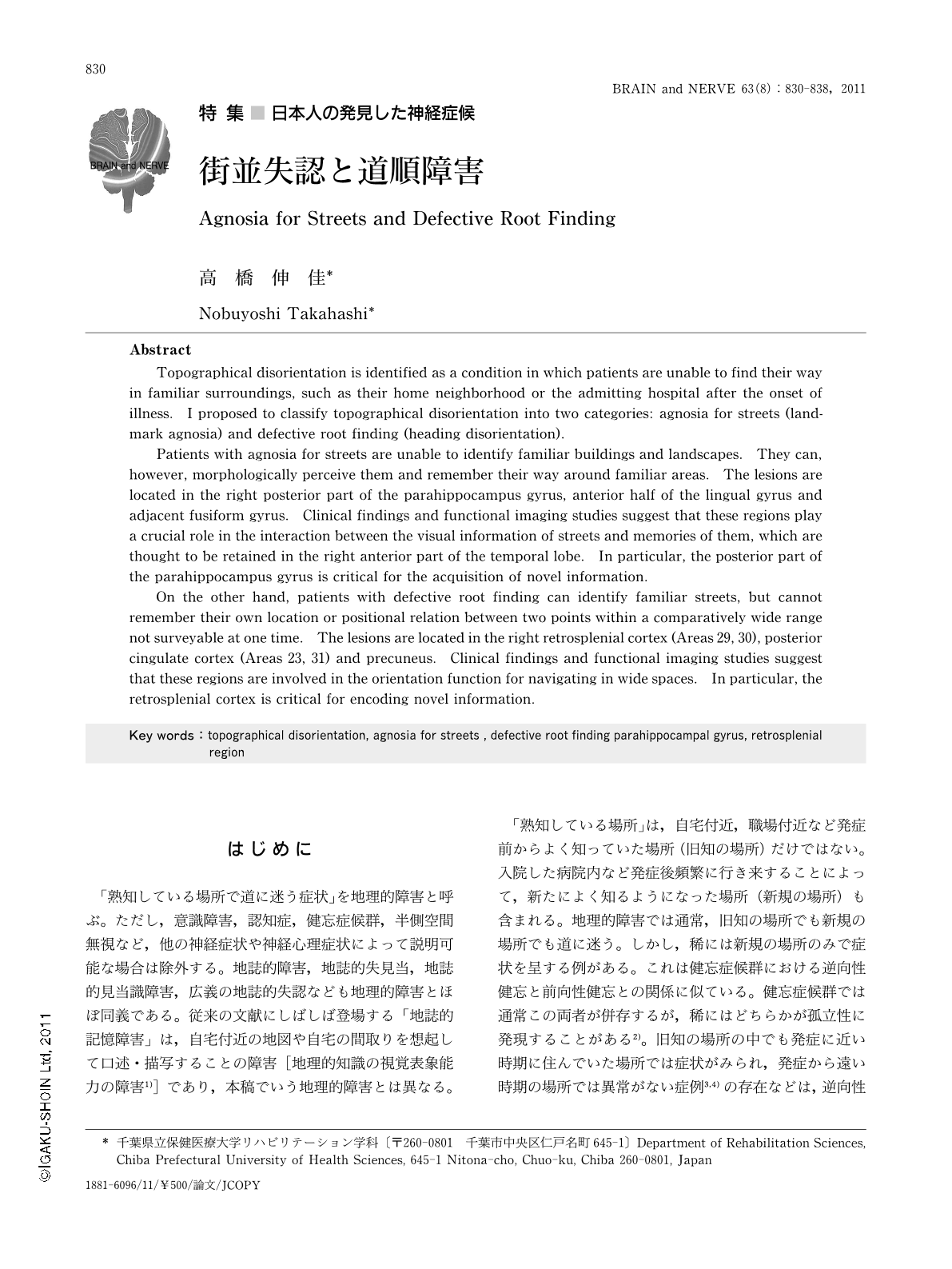4 0 0 0 OA Marchiafava-Bignami病の臨床的検討
- 著者
- 石川 直将 高橋 伸佳 河村 満 塩田 純一 荒木 重夫
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.232-237, 2008-08-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 15
Marchiafava-Bignami病 (以下, MBD) 自験8症例において, 急性期および慢性期の症候と病巣について検討した.8例中6例は意識障害にて発症し, 慢性期に構音障害と半球離断症候を呈し, 画像検査にて脳梁に限局した病変を認めた.これらは従来報告されているMBDの臨床像と一致していた.一方, 発症時に意識障害を呈さない例が2例みられた.これは, 発症時の意識障害の存在が必ずしもMBDの診断に必須ではないことを示している.また, 2例では肢位の異常, 固縮などの錐体外路症状がみられ, そのうちの1例ではMRIで両側の被殻に病変が認められた.同様の症例の報告は過去に4例のみであるが, この症候もMBDの症候の1つとして注目される.慢性期には意識障害, 前頭葉症状は消失するが, 錐体路症状が構音障害, 半球間離断症候とともに長期にわたり持続することが示された.以上から, MBDの臨床像は急性期, 慢性期ともに従来考えられていたよりも多彩である可能性がある.従って, アルコール多飲者が急性の構音障害, 歩行障害, 痙攣などを呈し, 局所徴候が明らかでない場合には, MBDの可能性も考え, 画像検査で脳梁病変の有無を確認する必要があると思われた.
1 0 0 0 OA 小児認知機能の発達的変化 —小児における高次脳機能評価法の予備的検討—
- 著者
- 荏原 実千代 高橋 伸佳 山崎 正子 赤城 建夫
- 出版者
- 社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.249-258, 2006 (Released:2006-05-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 6 1
小児の高次脳機能障害を評価するために必要なコントロール値作成のため,成人用検査を6~18歳の健常児133名に行った.行ったのはウエクスラー記憶検査(WMS-R),Trail making testなどの注意機能検査,Wisconsin card sorting test—慶応—F-S version(WCST)および標準失語症検査(SLTA)である.WMS-Rで記銘力は12歳で16~17歳レベルの90%以上に達していた.注意機能も14歳まで急速に発達し以後ほぼ一定になった.SLTAでは6~7歳で90~100%の正答率を示す項目が多いが,8~12歳で90~100%の正答率に達する項目もあった.一方,WCSTの処理能力は10歳まで向上後思春期に停滞し,16歳以降再び向上する2段階の発達を示した.これらの検査を小児に用いる場合にはWISC-III知能検査と組み合わせて,総合的に評価する必要がある.
1 0 0 0 OA 重度認知症患者における視線と表情による簡易心理評価スケールの開発
- 著者
- 矢野 啓明 高橋 伸佳 斯波 純子 旭 俊臣
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.312-319, 2012-06-30 (Released:2013-07-01)
- 参考文献数
- 9
FAST (Functional Assessment Staging) 6 および 7 に相当する重度認知症患者を対象とした, 新たな簡易心理評価スケール (Psychological Assessment Scale by Facial Expression for DementedPeople-Interview version : PAFED-I) を作成し, その信頼性と妥当性について検討した。PAFED─I は, 視線の変化に関する 18 項目 (視線得点) と表情の変化に関する 12 項目 (表情得点) から成り, 検者が個別に面接を行い, 各項目を評価した。FAST 6 の患者群では, 視線得点, 表情得点ともに高い内的整合性と評定者間一致率を示し, 信頼性は十分と考えられた。また, 標準意欲評価法 (CAS) との有意な相関がみられた。FAST 7 の患者群では, 視線得点で十分な信頼性と CAS との有意な相関がみられた。PAFED-I は, 重度認知症患者の意欲・自発性を評価する簡易スケールとして有用と考えられた。
1 0 0 0 街並失認と道順障害
- 著者
- 高橋 伸佳
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- BRAIN and NERVE-神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.830-838, 2011-08-01
はじめに 「熟知している場所で道に迷う症状」を地理的障害と呼ぶ。ただし,意識障害,認知症,健忘症候群,半側空間無視など,他の神経症状や神経心理症状によって説明可能な場合は除外する。地誌的障害,地誌的失見当,地誌的見当識障害,広義の地誌的失認なども地理的障害とほぼ同義である。従来の文献にしばしば登場する「地誌的記憶障害」は,自宅付近の地図や自宅の間取りを想起して口述・描写することの障害[地理的知識の視覚表象能力の障害1)]であり,本稿でいう地理的障害とは異なる。 「熟知している場所」は,自宅付近,職場付近など発症前からよく知っていた場所(旧知の場所)だけではない。入院した病院内など発症後頻繁に行き来することによって,新たによく知るようになった場所(新規の場所)も含まれる。地理的障害では通常,旧知の場所でも新規の場所でも道に迷う。しかし,稀には新規の場所のみで症状を呈する例がある。これは健忘症候群における逆向性健忘と前向性健忘との関係に似ている。健忘症候群では通常この両者が併存するが,稀にはどちらかが孤立性に発現することがある2)。旧知の場所の中でも発症に近い時期に住んでいた場所では症状がみられ,発症から遠い時期の場所では異常がない症例3,4)の存在などは,逆向性健忘の「時間勾配」を思わせる。地理的障害では,現在まで旧知の場所のみの症例は報告されていない。しかし,理論的にはその存在が推定される。 筆者らは地理的障害を症候と病巣の違いから街並失認(agnosia for streetsまたはlandmark agnosia)と道順障害(defective root findingまたはheading disorientation)の2つに分類した5)。一言でいえば,前者は街並(建物・風景)の同定障害に基づくものであり,視覚性失認の一型と考えられる。後者は広い地域内における自己や,離れた他の地点の空間的定位障害であり,視空間失認に含まれる。 街並失認は相貌失認と合併して生ずることが多く,その存在自体は古くから知られていた6,7)。環境失認(environmental agnosia)8),場所失認(agnosia for place)などと呼ばれたこともある。筆者は多数例の検討から,その症候や病巣を整理し,地理的障害全体の中での位置づけを示したにすぎない。この症候を街並失認と呼ぶことにしたのは,物体失認,画像失認,相貌失認などと同様,「街並(建物・風景)」という視覚対象に対する失認であることを明確にするためである。最近まで,神経心理学の中で地理的障害に関する研究が後れをとっていたとすれば,孤立性の症状を呈する症例が少ない,検査方法が確立されていない,などの点とともに用語の混乱にその一因があったのではないかと思われる。 一方,道順障害は従来ほとんど注目されていなかった症候である。筆者らは街並失認の症候,病巣の分析を進める過程で,これとは異なる地理的障害の1例に出会った。街並失認での患者の訴えが「(よく知っているはずの)回りの景色が初めてみるように感じる」であるのに対し,その症例の訴えは「(よく知っている)目の前の交叉点をどの方角へ曲がればよいかわからない」というものであった。これは,私たちが道をたどる際に,現在いる地点の周囲にある建物・風景を確認するだけではなく,目的地の方角を意識していることとよく対応する。この方角定位能力が選択的に障害されている症例と考えられた。その後,さらに同様の症例を経験し,1990年9)と1993年5)に日本神経心理学会総会で発表するとともに,3例をまとめて原著論文10)とした。 本稿は街並失認と道順障害について,原著10,11)およびその後の総説12-15)や著書16)に記載した内容を総括し,さらに最近の知見を加えたものである。
1 0 0 0 OA 道順障害のリハビリテーション
- 著者
- 揚戸 薫 高橋 伸佳 高杉 潤 村山 尊司
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.62-66, 2010-03-31 (Released:2011-05-11)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2 2
遷延性の道順障害を呈した 1 例における移動手段獲得のためのアプローチについて検討した。通常の地図を見ながらの移動訓練は有効ではなく,これは移動中の各地点で自分の向いている方角が地図上でどの方角にあたるかを判断できないことが一因と考えられた。そこで視覚的手段は用いず,目的地まで道順に沿って目印となる指標や分岐点での進むべき方角を言語的に記述したメモを用いたところ非常に有効であり,さらにそれを言語的に記憶することでメモなしでの移動が可能となった。道順障害は,症状の持続が短期間のことが多いが,病院内の移動などには大きな支障をきたす。本例で用いたような言語メモを活用したリハビリテーションは,道順障害での方角定位障害を代償する手段として有効であり,早期から積極的に取り入れるべきと考えられる。