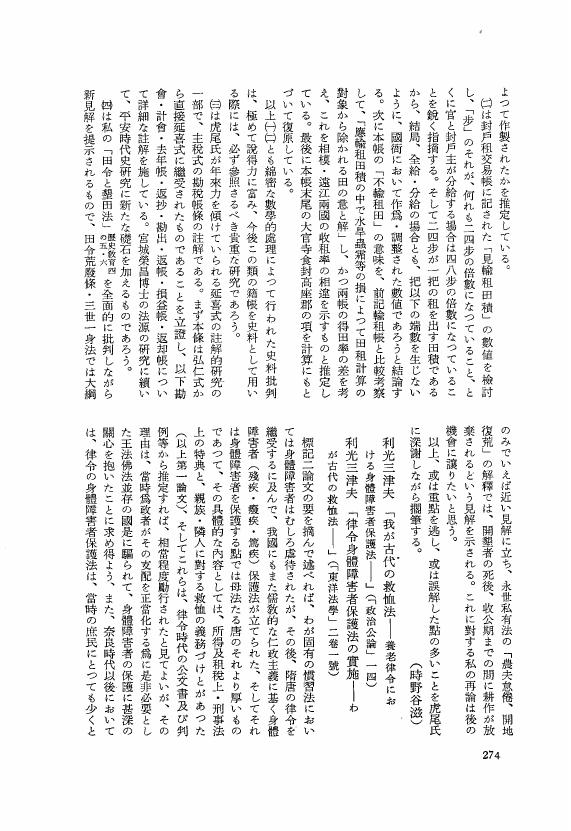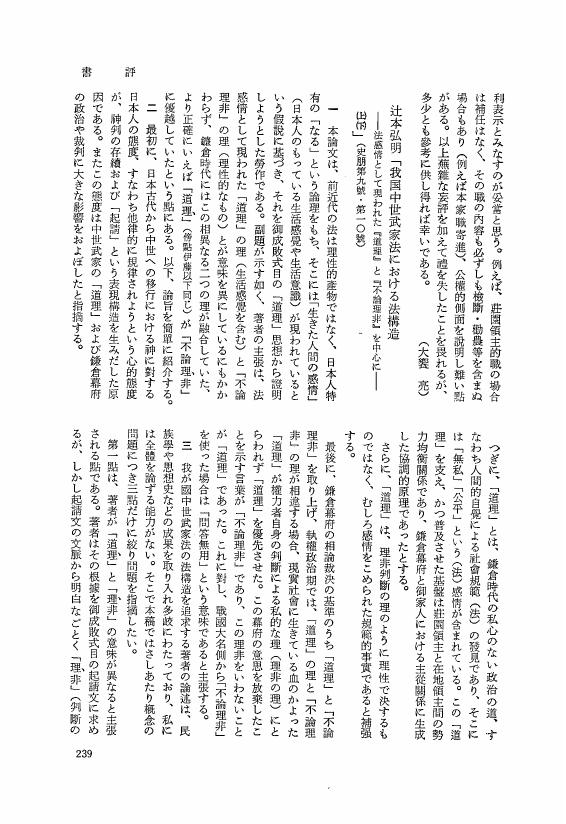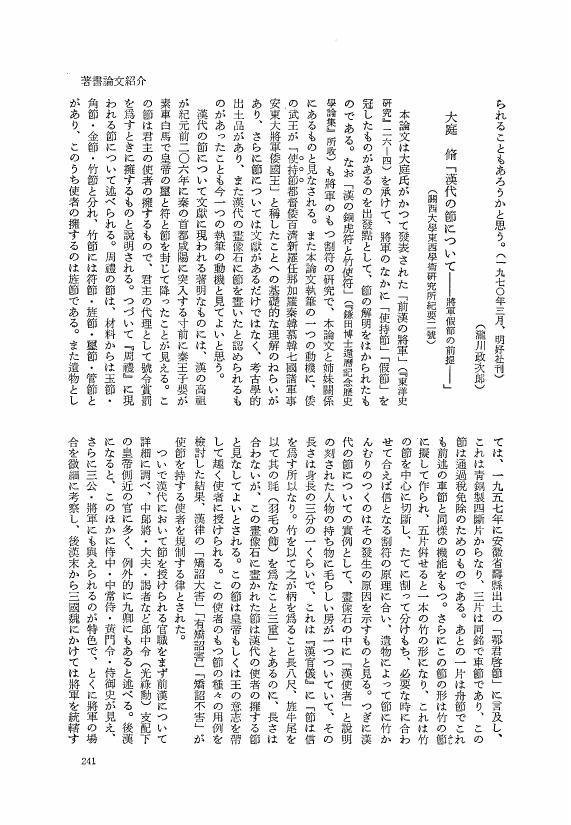2 0 0 0 OA (書評)町田實秀著「多數決原理の研究」
- 著者
- 三戸 寿
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1959, no.9, pp.309-310, 1959-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA (書評)中村修也著「「京職論―平安京行政機構研究の試み―」(「延喜式研究」一〇号)」
- 著者
- 井上 満郎
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.46, pp.210-212, 1997-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA (書評)毛利利彦著「江藤新平――急進的改革者の悲劇――」
- 著者
- 三阪 佳弘
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1988, no.38, pp.231-236, 1989-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 前澤 伸行
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.318-320, 1987
- 著者
- 虎尾 俊哉
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.10, pp.274-275, 1960-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 高 友希子
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.376-380, 2000
2 0 0 0 OA シャイバーニー『アスル』の編纂過程
- 著者
- 柳橋 博之
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.1-46,en3, 2009-03-30 (Released:2014-03-31)
カルダーによれば、九世紀の法学テキストが一般にそうであったように、現在我々が目にするような『アスル』のテキストは、最初に弟子が師の言葉を書き取り、それにたいしてその弟子自身またはそれ以後の編纂者が次々と加筆、修正、並べ替えなどの編集を積み重ねる過程を経て確定され、シャイバーニーの著作とされた。ハッラークも、法源学の著作を資料として用いて、九世紀末までの法学者は、「導出」によって学祖の説から二次的に導き出した説を、学祖の説と識別不能な形でテキスト中に取り込んだとしている。しかし両者とも、用いている資料に由来する制約から、そのような著述の方法がいつどのようにして始まったのかについては述べていない。本稿は、その過程を、カイロ写本、シャイバーニー(八〇五年没)『アスル』「賃約の書」を分析することによって推察する試みである。この写本の一部は、これまでに刊本になっている最終版『アスル』が成立する前の編纂段階を反映している点で、その編纂過程を知る上で有益な情報をもたらしてくれる。その分析の結果、つぎのような結論を得た。1.原『アスル』は、シャイバーニーの口述である。2.そのつぎの段階―編纂の前期―では、原『アスル』を補足・敷衍する形で設例が付け加えられるが、テキストとしては原『アスル』とは切り離された形で作成された3.最終段階―編纂の後期―では、テキストの混交が行われ、シャイバーニー以降に作成されたテキストが原『アスル』に埋め込まれている。このように、『アスル』の前期の編纂段階においては新しいテキストは古いテキストとは別個に作成され、また異なる文体が用いられたが、それ以降の編纂段階においてテキストの統一ないし混交が行われ、校訂本の多くの書に見られるようなテキストが確立したのである。このことは、前期の編纂者が学祖の説とそれ以降の学説を区別しようとしていたのにたいして、後期の編纂者には、学祖の説とそこから「導出」によって導かれる学説を全体として一つの体系―つまりはハナフィー派学説―とみなす傾向が見られると解することができよう。
- 著者
- 伊藤 一義
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1976, no.26, pp.239-240, 1977-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 森 洋
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1985, no.35, pp.383-391, 1986-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA (書評)桑原朝子著「平安朝の漢詩と「法」―文人貴族の貴族制構想の成立と挫折」
- 著者
- 所 功
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.57, pp.245-247, 2007 (Released:2013-04-01)
- 著者
- 神寶 秀夫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.47, pp.404-407, 1998-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA 近世中後期幕府の上方支配
- 著者
- 小倉 宗
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.57, pp.85-122,en6, 2007 (Released:2013-04-01)
本稿では、近世中後期の江戸幕府において、公事方御定書とともに最重要の法源であった御仕置例類集を主にとりあげ、仕置に関することがらを中心に、関東とならぶ幕府の拠点地域である上方の支配を検討した。その際、上方の内部や江戸との間において、幕府役人が行政・裁判を処理する過程や権限に注目した。(1)幕府の上方役人は、伺とそれに対する指示という同じ過程のなかで、行政と裁判を一体的・連続的に処理し、すでに発生している問題を個別的に解決するとともに、今後発生する問題について一般的に対処するための規則や制度を設定・変更していた。(2)上方役人の伺には、上方の奉行より京都の所司代や大坂城代への伺(上方奉行伺)、所司代や大坂城代より江戸の老中への伺(所司代伺・大坂城代伺)、上方奉行より老中への伺(江戸上り伺)、の三通りがあった。また、上方奉行と老中のやりとりは、伺とそれに対する指示との両面において、所司代や大坂城代による監督・仲介のもとになされた。(3)所司代や大坂城代は、老中と同じ形式の文書を用いながら、上方奉行の伺に対して自ら決定・指示し、仕置をはじめとするさまざまな問題が上方の内部で処理されていた。延享元年(一七四四)に、仕置をめぐる所司代・大坂城代と上方奉行との関係が確立され、天明八年(一七八八)には、所司代や大坂城代が自ら指示しうる仕置の範囲は大幅に拡大された。(4)京都・大坂町奉行は、所司代や大坂城代のもと、それらの監督・担当する業務の全般にわたって調査・答申するという特別な役割を果たしていた。そうしたあり方は、老中のもとにある評定所のあり方と同様であり、上方における、所司代・大坂城代と京都・大坂町奉行の関係は、江戸における老中と評定所の関係と相似であった。
2 0 0 0 OA 榎村寛之氏の「書評」に応える
- 著者
- 水林 彪
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.431-448, 2009-03-30 (Released:2014-03-31)
- 著者
- 布目 潮〓
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1971, no.21, pp.241-242, 1972-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA (書評)杉山晴康著「日本法史概論」
- 著者
- 大竹 秀男
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1981, no.31, pp.202-203, 1982-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA (書評)石井良助著「「刑罰の歴史」(日本)」
- 著者
- 平松 義郎
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1954, no.4, pp.249-252, 1954-07-31 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA (書評)池田雄一著「「李〓の法経について」(中央大学文学部紀要(史学科)第二九号)」
- 著者
- 工藤 元男
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1985, no.35, pp.321-323, 1986-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA (書評)「法史料の性格と史料操作の「批判手続」」
- 著者
- 石川 武
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.54, pp.259-266, 2005-03-30 (Released:2010-05-10)
- 著者
- 千葉 治男
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.44, pp.313-316, 1995-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA ポルトガル領事裁判権の回収について
- 著者
- 中網 栄美子
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.55, pp.81-119,8, 2006-03-30 (Released:2011-04-13)
本稿は最初の改正条約といわれる明治二七年に締結された日英通商航海条約に先立ち、日本がポルトガルの領事裁判権を回収した事件を取り上げ、その背景を紹介するとともに、条約改正における意義を問うものである。一九世紀後半に入るとポルトガルにはかつての繁栄はなく、イギリス、フランス、ドイツなどに比べれば、その存在は日本にとって決して重いものではなかった。他方、司法統計に表れた日葡間の民事事件数をみると、無視しうるほど小さい存在ともいいきれなかった。このような中間的位置にあって、ポルトガルが領事裁判を行うにあたって商人領事を用いたことが日葡間の紛議を生むこととなった。日本の度重なる抗議にもかかわらず、明治二五年にポルトガルが総領事館を廃止し、専任領事を本国に帰還させたことにより、日本は勅令六四号発布に踏み切る。これにより、万延元年以来の日葡修好通商条約中の領事裁判に関する条項を無効にせしめ、事後在留ポルトガル人に対する裁判管轄権を日本が有すると宣言したのであった。条約改正交渉途中に起こったこの事件が、列強諸国をいたずらに刺激することのないよう、日本は各国の動向に細心の注意を払った。当時最大勢力を誇っていたイギリスは介入してこず、むしろポルトガルに冷淡な姿勢をとった。しかし、ポルトガルが代理領事に仏公使プランシーを任命してきたことにより、フランスが日葡事件の前面に出てくることになり、その成り行きは緊張をはらんだものとなった。いつ領事裁判復活への揺り戻しがくるとも知れぬ状況にあって、日本は勅令後ほどなくしてポルトガル人に対する裁判権を行使したが、西欧諸国からの介入を極力回避するため、近代的な法と法制度に基づく裁判を行うべく努めた。この事件はまた、相手国に領事裁判権を実効的に行使できない事由があった場合、国内法をもって、領事裁判を回収することができるということを証明した事件でもあった。