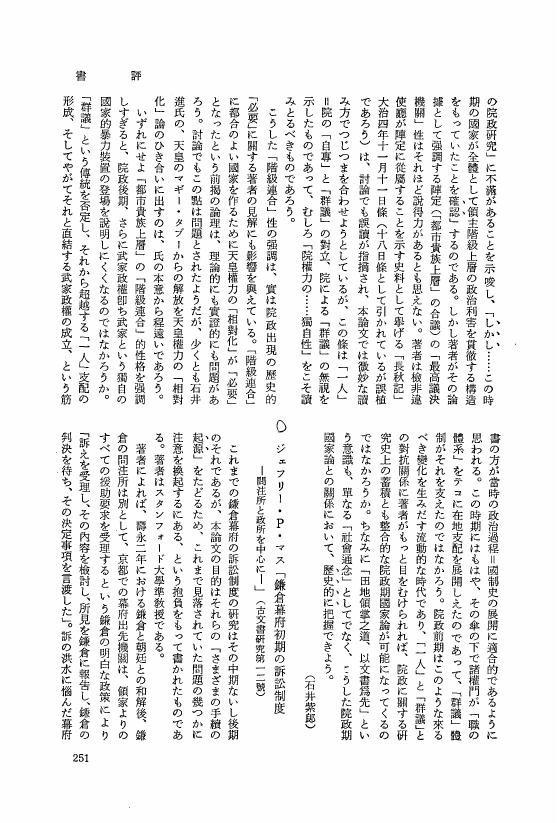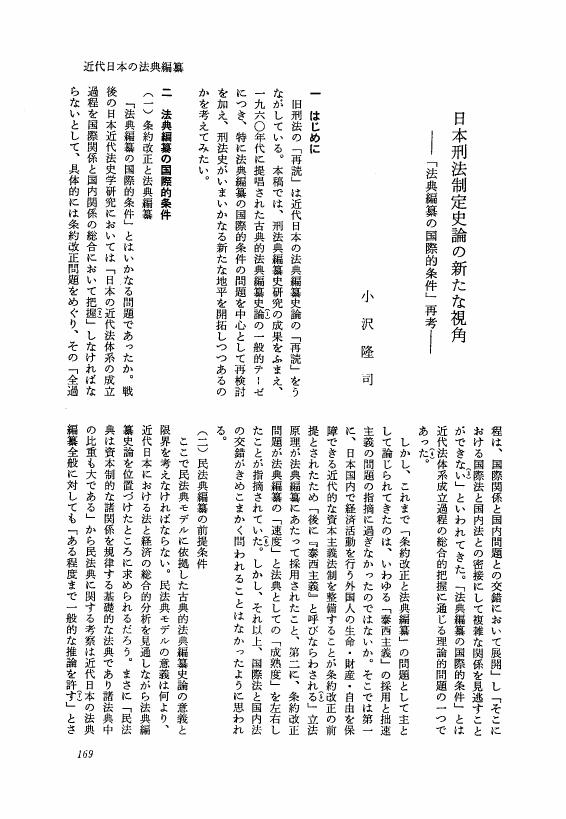- 著者
- 若曽根 健治
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.360-364, 1996
1 0 0 0 OA (書評)森公章著「「「天皇」号の成立をめぐって」(日本歴史第四一八号)」
- 著者
- 平野 邦雄
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1984, no.34, pp.228-230, 1985-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- ゲールハルト シュック 和仁 陽訳
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.46, pp.106-126, 1997-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 石井 良助
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.30, pp.251-253, 1981-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA 共通課題 土地所有をめぐる諸問題――権力と土地所有 討論
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1964, no.14, pp.161-205, 1964-11-15 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA 中世後期イングランド刑事司法の構造 重罪犯有罪事例を軸として
- 著者
- 北野 かほる
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.1-51,en3, 2016-03-30 (Released:2022-03-05)
中世後期イングランドの刑事司法について、さきに解明した刑事侵害(軽罪)の手続過程を補完する位置づけで、重罪の手続過程をあきらかにした。イギリスでは現在も軽罪と重罪で刑事司法手続が分かれているが、近代初期まで、重罪にかかわる裁判開始手続は陪審起訴と重罪私訴が形式上併存していた。陪審起訴は中世以降の主要な刑事裁判開始手続で、従来の刑事司法過程分析は基本的にこれを焦点としてきた。他方重罪私訴は中世以降実質的な消失の過程をたどったといわれ、そのせいもあってこれまでほとんど専門的な調査分析が加えられてこなかった。しかしこれまで、陪審起訴による刑事司法過程についても中世段階の状況の専門的な分析研究はなく、かならずしも手続過程細部があきらかになっているわけではない。 本稿は、重罪犯有罪事例を主たる素材としながら、陪審起訴による司法過程と重罪私訴による司法過程を、典型的な形態にかぎらず、多岐にわたる例外措置をふくめて解明したものである。さきの軽罪の手続過程とあわせて、中世後期段階の刑事司法過程の全容をほぼあきらかにできたと考えている。とりわけ陪審起訴による手続過程について、多岐にわたる例外措置をあきらかにした結果、起訴―審理―審理陪審評決―有罪判決―死刑という理論的に典型的な過程をたどる事例が実態的にはかならずしも多くない状況を説明する手がかりが得られたと考える。また重罪私訴についても、王の制度としての陪審起訴による刑事司法過程(これ自体は重罪だけでなく軽罪にも妥当する)とは異なる、私人による訴としての一般の民事裁判とりわけ民事侵害訴訟(損害賠償請求訴訟)手続との親近性をあきらかにする手がかりが得られた。これら司法過程の全体像は、中世後期イングランド社会の法文化・法慣行とその所以の理解にも役立つと考えている。
1 0 0 0 OA 苑田亜矢著「一二世紀イングランドにおける教会裁判手続と起訴陪審制の成立」
- 著者
- 松本 和洋
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.334-336, 2016-03-30 (Released:2022-03-05)
1 0 0 0 OA (書評)佐藤次高著「Sato Tsugitaka, State & Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqta's & Fallahun」
- 著者
- 三浦 徹
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.48, pp.269-274, 1999-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA (書評)福井重雅著「漢代官史登用制度の研究」
- 著者
- 若江 賢三
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.40, pp.320-326, 1991-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA (書評)高橋秀樹著「日本中世の家と親族」
- 著者
- 西谷 正浩
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.47, pp.188-193, 1998-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA (書評)利光三津夫・長谷山彰著「新・裁判の歴史」
- 著者
- 梅田 康夫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.48, pp.195-201, 1999-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 小沢 隆司
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.47, pp.169-174, 1998-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 ハルミスカラとカロリング時代の俗人エリート
- 著者
- 木下 憲治
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.97-141,en7, 2015
<p> 近年初期・中期中世国制史研究において、儀礼や象徴的コミュニケーションに関連した研究が多数なされている。その第一人者はG・アルトホフである。しかし、彼らのグループは、カロリング期のハルミスカラにはほとんど関心を示してこなかった。本論文は、カロリング期のハルミスカラの意義を解明するためにカロリング期のハルミスカラに関連するカピトゥラリアと先行研究が扱わなかった史料を分析したものである。J・M・メグランは、ハルミスカラと公的贖罪には関連性があると示唆していた。また、彼は公的贖罪とは神の復讐であるという仮説を提起しており、ハルミスカラにおいても公的贖罪においても被害者の復讐の側面を強調していた。最近のM・デヨングとC・M・ブッカーのルイ敬虔帝の贖罪と国王官職概念についての研究を参照することによって、八二九年のハルミスカラに対してはメグランの仮説の正当性を裏付けることができた。しかし、八五三年以降のハルミスカラは、その意味の重点を変えていった。すなわち、ハルミスカラは、「神の復讐」という側面を希薄にし、鞍運びという儀礼的な行為と引き替えに、非行を犯した者を国王支配へと再統合する側面があった。また、カロリング期のハルミスカラにおいては、国王支配へと再統合される人物は、貧しい自由人ではなく、政治指導層から従軍義務が「免除されない」階層にまで及んでいた。後期カロリング朝の国王は、ハルミスカラによって中間層までをも再統合によって再び王国の秩序に組み込む必要に迫られていたのである。本稿の結論は、M・イネスが明らかにしたような局地的エリートとの連携及び彼らとの互酬性によって王国を支配する必要に迫られたカロリング王権の姿と密接に関連している。</p>
1 0 0 0 OA (書評)碧海純一・伊藤正己・村上淳一編著「法学史」
- 著者
- 上山 安敏
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, no.27, pp.309-312, 1978-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 小室 輝久
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.426-431, 2015
- 著者
- 深尾 裕造
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.365-369, 1988
- 著者
- 近藤 治
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.36, pp.383-384, 1987-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 大平 祐一
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.336-339, 2015-03-30 (Released:2021-03-20)
1 0 0 0 中国国民政府初期における反省院の設置と人事
<p>本稿は、党国体制下の司法制度の底流になる「司法の党化」に着目し、その現れの一つである党系統の情報機関が関与した反省院―政治犯を矯正する特殊な教育施設―の設置の経緯と人事を検討することで、中国国民政府初期における中国国民党と司法機関の連繋を明らかにするものである。<br>党国体制下の司法当局は、国家の富強が個人の自由に優先するという考えの下、敵対する勢力(中国共産党)を取締まる特別法を設けて中国国民党政権の維持に資する司法制度の構築をはかりつつ、憲政に備えた「近代化」を模索していた。前者に比重を置いた「司法の党化」を推進する勢力は、立憲主義の確立を目指す勢力と鬩ぎ合いながら、「司法は党の決定する政治の下にあるべきである」とする方策を引継いで司法機関を運営していった。<br>一九三二年に司法院から行政院に司法行政部の所管が変更されると、司法院は全国に赴任する司法官の人事権と司法経費などの権限を失った。そして、司法行政部部長の羅文幹によって人権と自由権が重視されると、これまでの「司法の党化」の路線は抑えられた。司法院の要職をほぼ独占し、党と政府の要職を一定数占めた旧西山会議派と、党系統の情報機関を任された陳立夫を中心としたCC系は、それを不満として司法行政部を司法院に回帰させ、部次長人事に介入して、司法官の党員化を積極的に進めた。<br>一九二七年四月の清党後、旧西山会議派の沈玄蘆を院長に、浙江省に浙江反省院が設置された。司法行政部は、浙江反省院の修正草案を参考に「反省院条例」(一九二九年一一月二五日)を制定し、反革命犯を感化するための反省院を設置した。院内は総務、管理、訓育の三科に分かれていたが、一般の監獄とは異なり、訓育科が中心となる特殊な教育施設であった。反省院には数多くの中国共産党員が収容された。<br>当初、反省院院長には、高等法院院長が兼任し、司法機関側が実権を掌握していた。一九三三年に「各反省院を中央の直轄に改める案」が出されると、党系統の情報機関が反省院の実権を掌握し、徐々に勢力を伸ばしていった。<br>党国体制下の司法機関と党系統の情報機関の連繋の裏には、中国国民党中央執行委員会における、旧西山会議派とCC系による有形無形の支持があったことを提示する。</p>
1 0 0 0 OA フランスにおける近代行政史研究 その若干の動向について
- 著者
- 大久保 泰甫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1982, no.32, pp.193-225, 1983-03-30 (Released:2009-11-16)