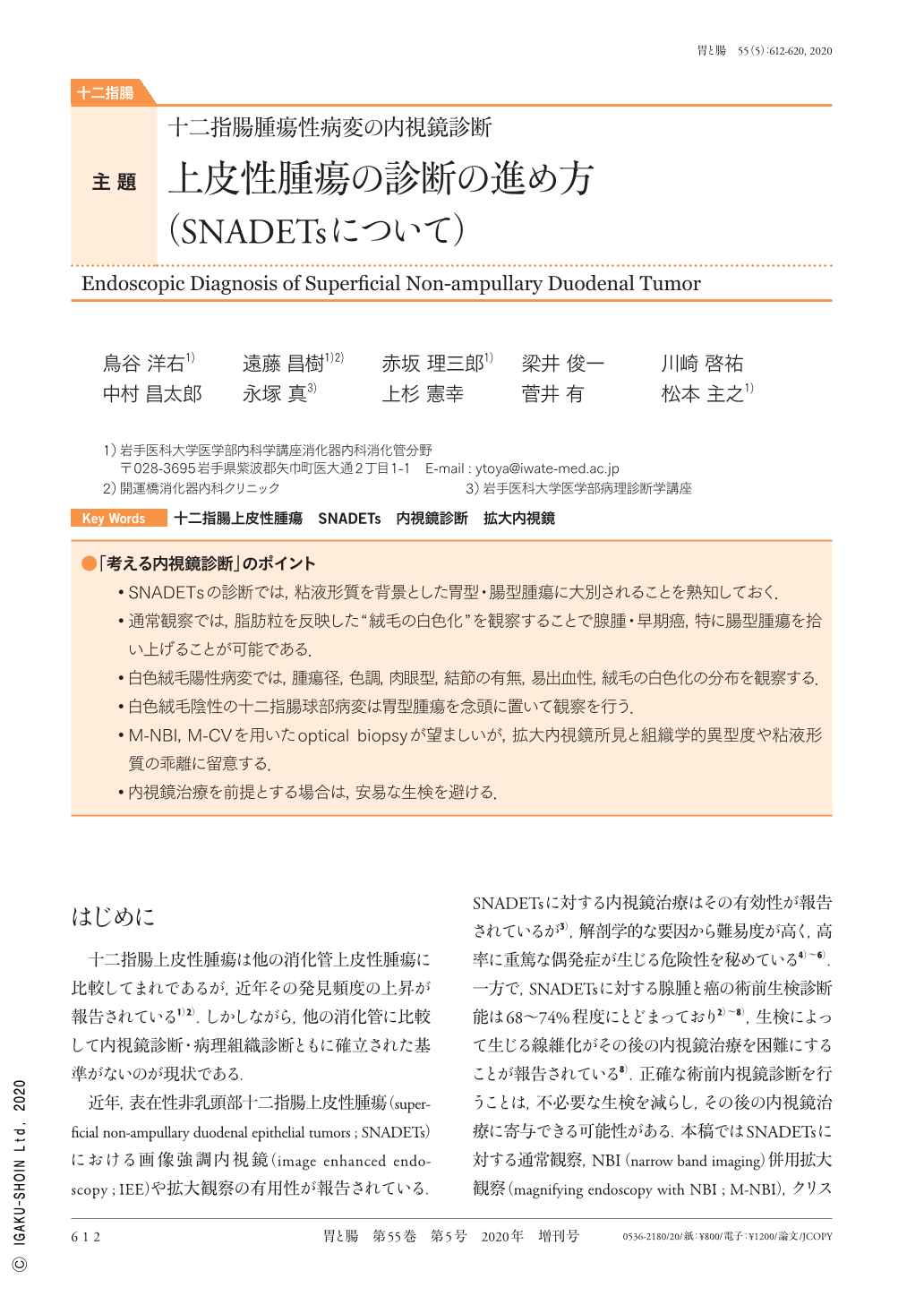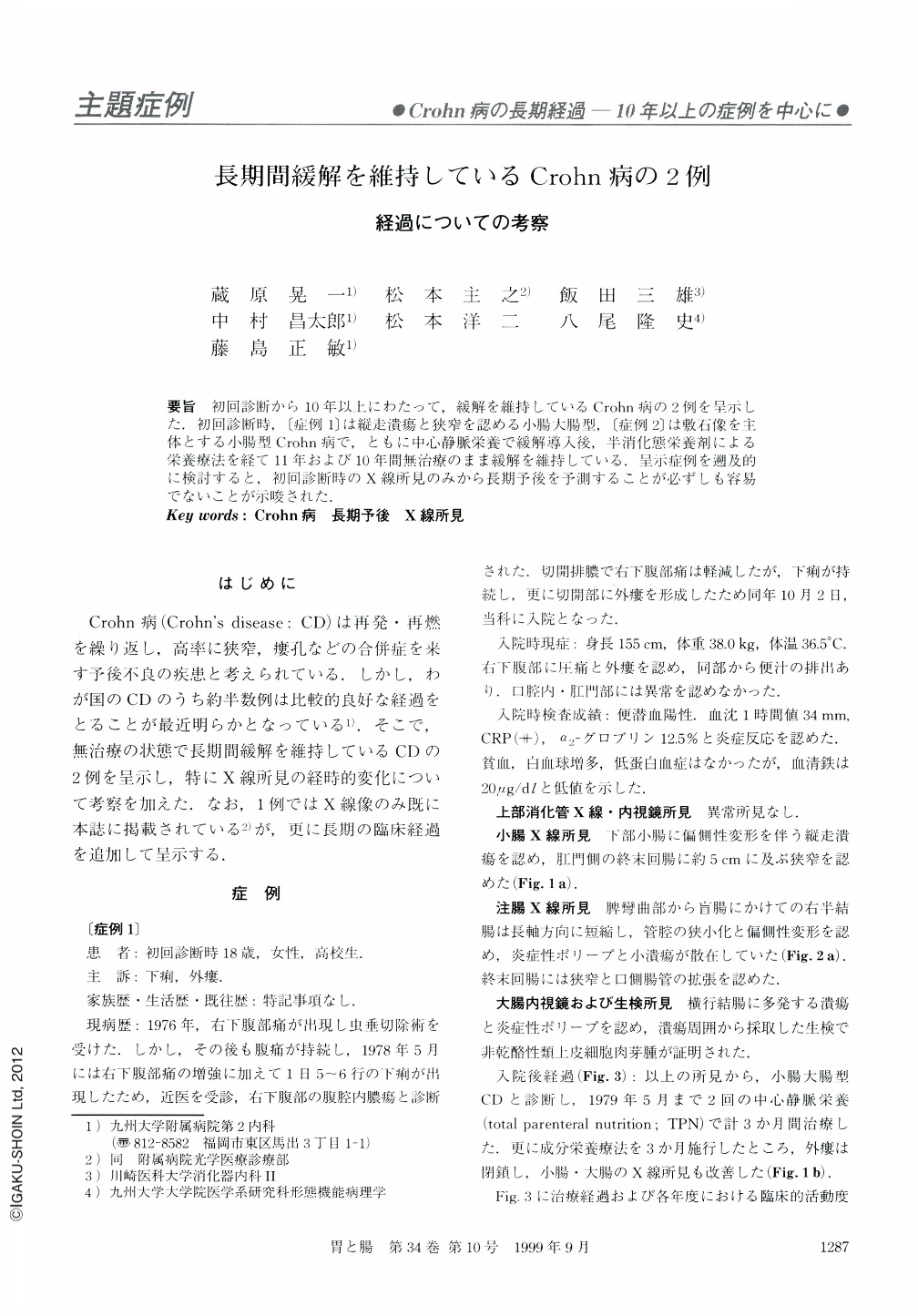8 0 0 0 OA Collagenous colitisの診断と治療
- 著者
- 梅野 淳嗣 松本 主之 中村 昌太郎 飯田 三雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.1233-1242, 2010 (Released:2011-11-07)
- 参考文献数
- 74
- 被引用文献数
- 6
Collagenous colitisの診断と治療について概説した.本症は慢性の水様性下痢と大腸粘膜直下の膠原線維帯の肥厚を特徴とし,中年以降の女性に好発する.原因として遺伝的要因,薬剤(プロトンポンプ阻害薬,非ステロイド性消炎鎮痛薬,アスピリン,チクロピジンなど),自己免疫疾患,腸管感染症,一酸化窒素などが示唆されている.本症の内視鏡所見は,正常あるいは毛細血管の増生などの非特異的所見にとどまることが多いが,mucosal tearsと呼ばれる幅の狭い縦走潰瘍がみられることもある.本症の診断基準は臨床症状および病理組織学的所見よりなり,薬剤が関与する場合にはその薬剤の中止のみで改善することもある.治療薬として,アミノサリチル酸製剤,ステロイド,免疫抑制剤などの有効性が報告されている.
3 0 0 0 中毒性巨大結腸(toxic megacolon)
中毒性巨大結腸は,重症の腸炎により腸管が弛緩性に拡張した状態で,通常,横行結腸に認められる.多くは重症の潰瘍性大腸炎に合併したもので,頻脈,発熱,低蛋白血症,電解質異常を伴っている.しばしば穿孔を来し,その場合,死亡率が高率で約50%に及ぶとも言われている.当初,Bockusら1)が“toxic aganglionic megacolon”という名称で記載したが,本症の発生機序として腸筋神経叢の障害以外にも,筋層の広範な破壊や抗コリン薬の使用などが関与する2)ことから,現在では“toxic megacolon”と呼んでいる.なお,原疾患は潰瘍性大腸炎に限定されず,Crohn病,偽膜性腸炎,感染性腸炎(サルモネラ,キャンピロバクター,Clostridium dtfficile,サイトメガロウイルス)でも起こりうる. X線学的には,背臥位での腹部単純写真が診断に有用であり,横行結腸の拡張(直径7~10cm以上)2)3)が特徴的である(Fig.1).拡張した腸管はhaustraが消失し,また潰瘍と炎症性ポリープのため,辺縁のぼけ像を伴う結節状の凹凸像として認められる.
- 著者
- 鳥谷 洋右 遠藤 昌樹 赤坂 理三郎 梁井 俊一 川崎 啓祐 中村 昌太郎 永塚 真 上杉 憲幸 菅井 有 松本 主之
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.612-620, 2020-05-24
●「考える内視鏡診断」のポイント・SNADETsの診断では,粘液形質を背景とした胃型・腸型腫瘍に大別されることを熟知しておく.・通常観察では,脂肪粒を反映した“絨毛の白色化”を観察することで腺腫・早期癌,特に腸型腫瘍を拾い上げることが可能である.・白色絨毛陽性病変では,腫瘍径,色調,肉眼型,結節の有無,易出血性,絨毛の白色化の分布を観察する.・白色絨毛陰性の十二指腸球部病変は胃型腫瘍を念頭に置いて観察を行う.・M-NBI,M-CVを用いたoptical biopsyが望ましいが,拡大内視鏡所見と組織学的異型度や粘液形質の乖離に留意する.・内視鏡治療を前提とする場合は,安易な生検を避ける.
2 0 0 0 長期間緩解を維持しているCrohn病の2例―経過についての考察
要旨 初回診断から10年以上にわたって,緩解を維持しているCrohn病の2例を呈示した.初回診断時,〔症例1〕は縦走潰瘍と狭窄を認める小腸大腸型,〔症例2〕は敷石像を主体とする小腸型Crohn病で,ともに中心静脈栄養で緩解導入後,半消化態栄養剤による栄養療法を経て11年および10年間無治療のまま緩解を維持している.呈示症例をさかのぼ及的に検討すると,初回診断時のX線所見のみから長期予後を予測することが必ずしも容易でないことが示唆された.
1 0 0 0 OA 胃MALTリンパ腫除菌治療後の長期予後
- 著者
- 中村 昌太郎 松本 主之
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.1, pp.47-53, 2012 (Released:2012-01-06)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
胃MALTリンパ腫の診療に関する最近の知見について,Helicobacter pylori除菌後の長期予後を中心に解説した.本邦における多施設大規模追跡試験により,H. pylori除菌後の胃MALTリンパ腫の長期予後がきわめて良好であることが明らかとなった.対象420例の除菌による完全寛解率は77%であり,3~14.6年(平均6.5年)の追跡の結果,除菌10年後の治療失敗回避率は90%,全生存率95%,無イベント生存率86%であった.多変量解析の結果,H. pylori陰性,粘膜下層深部浸潤およびt(11;18)/API2-MALT1転座が除菌抵抗因子として抽出された.本症に対する除菌治療の保険収載により,H. pylori依存性胃MALTリンパ腫症例が減少し,将来は除菌抵抗例やH. pylori陰性例の診療が問題となることが予想される.
1 0 0 0 OA 小腸原発腸管症関連CD8陽性T細胞リンパ腫の細胞組織学的特徴と増殖機序
日本のEATL(腸管症関連T細胞リンパ腫)では大部分がII型であり、その多くはCD56+, CD8+T細胞リンパ腫であった。その非腫瘍部位の粘膜には、腫瘍性のIEL(上皮内リンパ球)が約70%にみられ、また反応性IELが多くみられる腸管症病変が約50%に認められた。腫瘍細胞はC-METの反応が約80%に、またリン酸化MAPKが90%、C-MYCが約40%、BCL2が70%強に認められた。また、FISH によるC-METの増幅は65%、C-MYCの増幅が71%に認められた。EATLでは、C-MET/MAPK系やC-MYC/BCL2系を介する細胞の増殖維持が腫瘍化に関与していると推測した。