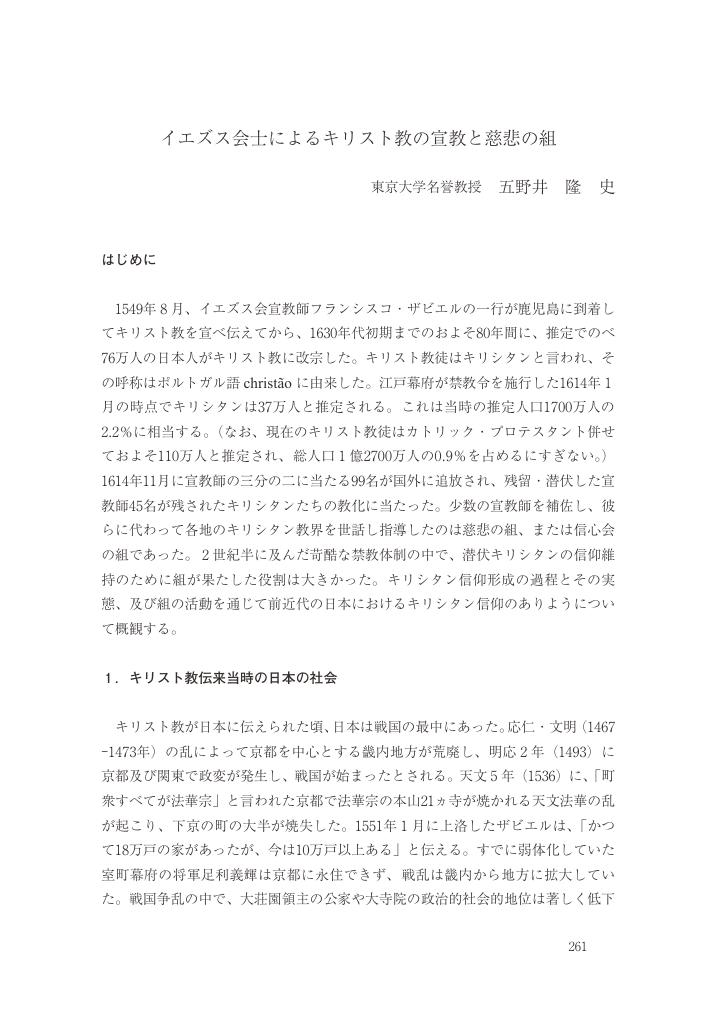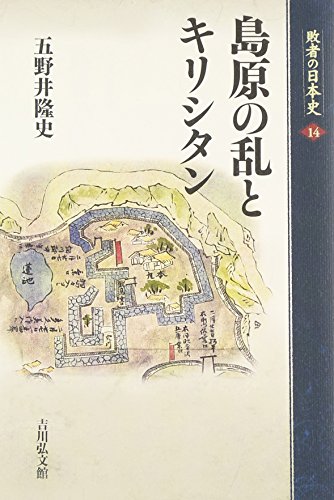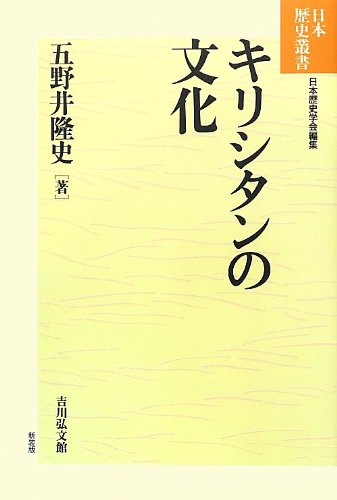9 0 0 0 16・7世紀、蝦夷情報とキリシタン
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 聖トマス大学
- 雑誌
- サピエンチア 聖トマス大学論叢 (ISSN:02862204)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.1-21, 2014-02
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 聖トマス大学
- 雑誌
- サピエンチア : 英知大学論叢 (ISSN:02862204)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.A1-A19, 2006-02-28
これは、日本イエズス会副管区長ジェロニモ・ロドリゲスが一六一八年一月一〇日付をもってマカオにおいて作成した、日本のキリスト教界の組ないしコンフラリア(信心会)に関するポルトガル語文文書からの日本語翻訳文である。同文書は、縦二二・四糎、横一七・〇糎の和紙一〇丁からなる。同文書の作成日は、表題の書かれた上書には上記の一六一八年一月一〇日となっているが、本文の末尾に一六一七年一二月二〇日とあるように、すでにこの時点で本文が完成していたことが知れる。本文書の作成者ジェロニモ・ロドリゲスは、江戸幕府が発令したキリスト教禁教令の施行によって、日本管区長ヴァレンチン・カルヴァリョが一六一四年一一月に日本からマカオに去ったのち、同管区副管区長として日本に残留潜伏した。彼は、大坂の陣で敗れて徳川方から追求されていた豊臣方の武将明石掃部全登の子内記パウロを匿うことを同会宣教師達に指図したが、これが発覚し、一六一六年宣教師の捜索が行なわれた。このため、同年一二月、突如長崎で捜索が行なわれ、イルマンの木村レオナルドが捕らえられ、ロドリゲスは翌年マカオに退去せざるをえなかった。従って、この文書は、禁制下におけるキリスト教界の活動に密接に関わっていたロドリゲス神父が、キリスト教徒達の最新の信仰活動について言及したものとして貴重な情報を提供してくれる。本文書は、三部から構成される。一部では、被昇天の聖母の組ないしコンフラリアの規則の要項であって、組の目的、組の構成と組織、組維持の方法、組の会員(組衆)達が守るべき義務(掟)と、それによってもたらされる霊的利益、役務者(役人)の名称と役務、組において許されない過失(科)などが、六章五六箇条にわたって言及されている。二部は、被昇天の聖母の組(コンフラリア)に関する戒めについて述べたもので、キリスト教徒達が日常行なっている信心に関する所作(業(ぎょう))、すなわち、慈悲の所作や、教皇に請願する贖宥(免償)に関する覚書、及び宥が許可されることによって可能となる有効な所作など一八箇条からなる。ここでは特に、ドミニコ会設立のロザリオのコンフラリアがすでに贖宥を獲得していたことに対し、イエズス会が設立した被昇天の聖母のコンフラリアの由緒とその自立性について言及して、同会指導によるコンフラリアの正当性と固有性が主張されている。三部では、教皇に請願される贖宥獲得のための条件である諸々の所作が二四項にわたって述べられている。本文書のコンフラリアに関する規則は、シュッテ師Joseph Schutte S.J.が指摘されているように、包括的なものであり、これを通じてイエズス会が設立し指導していた組(コンフラリア)の組織とその活動の全体像を容易に把握できる点で、極めて貴重な情報である。なお、ロドリゲスの同文書(一〜三部)の日本語訳文については、シュッテ稿、柳谷武夫訳「二つの古文書に現はれたる日本初期キリシタン時代に於ける「さんたまりやの御組」の組織に就いて」(『キリシタン研究』第二輯、九一〜一四八頁、東京堂、一九四四年)がある。訳文はドイツ語からの重訳と思われ、しかも日本語訳文はキリシタン時代に合わせて擬古文の体裁をとっているため、ポルトガル語原文と対照する時、意訳にかたよりがちで文意を損ねている箇所が少なくないことである。同文書の第一部については、ポルトガル語原文からの翻訳が、川村信三『キリシタン信徒組織の誕生と変容』(『キリシタン研究』第四〇輯、教文館、二〇〇三年)の第七章(「被昇天の聖母のこんふらりや」の規則抜粋、三五八〜三八三頁)において、丁寧な解説付きで紹介されている。著者は「抄訳を基本とし、必要なかぎり解説を加え」たとされる。しかし、その労は多とするものの、同翻訳が厳密性を要求される歴史史料としてその利用に供し得るものかと問えば、遺憾ながらと言わざるをえない。原文翻字の若干の誤りは利用者が少数であり原文と対照すれば解決できることであるが、翻訳文の場合には利用者が多く、その多数は訳文のみしか利用できないところから、翻訳史料の提供者はできる限り最善を尽した翻訳文を提供することが求められる。同訳文は必ずしも原文に忠実であると言い難く、また誤訳が多いように私には思われる。翻訳が困難と思われるならば、その箇所を空白にしておくほうが、利用者にとってはよほど良心的である。そのような次第で、私はここに敢えて拙訳を試みた次第である。(二〇〇五年二月八日)
3 0 0 0 OA イエズス会士によるキリスト教の宣教と慈悲の組
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.Special_Issue, pp.261-272, 2018-04-11 (Released:2018-05-23)
2 0 0 0 横瀬浦の開港と焼亡について (聖トマス大学創立50周年記念号)
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 聖トマス大学
- 雑誌
- サピエンチア : 英知大学論叢 (ISSN:02862204)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.1-29, 2013-03
1 0 0 0 島原の乱とキリシタン
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 青山学院女子短期大学総合文化研究所
- 雑誌
- 青山学院女子短期大学総合文化研究所年報 (ISSN:09195939)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.41-55, 2008-12
- 著者
- 五野井 隆史 Takashi Gonoi
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-15, 2008-07-01
1 0 0 0 OA イエズス会日本管区によるトンキン布教の始まり(<特集>対外交渉史)
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.495-517, 1991
論文特集対外交渉史はじめに一 トンキン初期布教に関する史料二 使節派遣の経緯三 使節のマカオ・トンキン往還四 トンキンにおける使節 (一) 国王鄭氏との接触 (二) 情報の蒐集 (三) 教化活動おわりに
1 0 0 0 OA キリシタン墓碑の調査研究-その源流と型式分類のための再調査-
片岡弥吉の論文「長崎県下キリシタン墓碑総覧」(1942年)と「キリシタン墓碑の源流と墓碑型式分類」(1976年)を基礎として国内及び海外の調査を行った。国内115か所の墓地・墓碑調査、海外では18か所の博物館及び墓地での調査を行うことが出来た。その結果、国内の墓碑について、キリシタン墓碑の概念、その特徴と定義、意義、型式をまとめることができた。海外調査では、ローマ、スペイン、ポルトガルでの調査から、エトルスキの墓地や墓碑を源流とするローマ式墓碑がポルトガルに伝えられ、キリスト教宣教師の世界布教の過程で日本を含む世界の各地に広がったことを確認できた。
- 著者
- 五野井 隆史
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 東京大学史料編纂所研究紀要 (ISSN:09172416)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.154-167, 2001-03