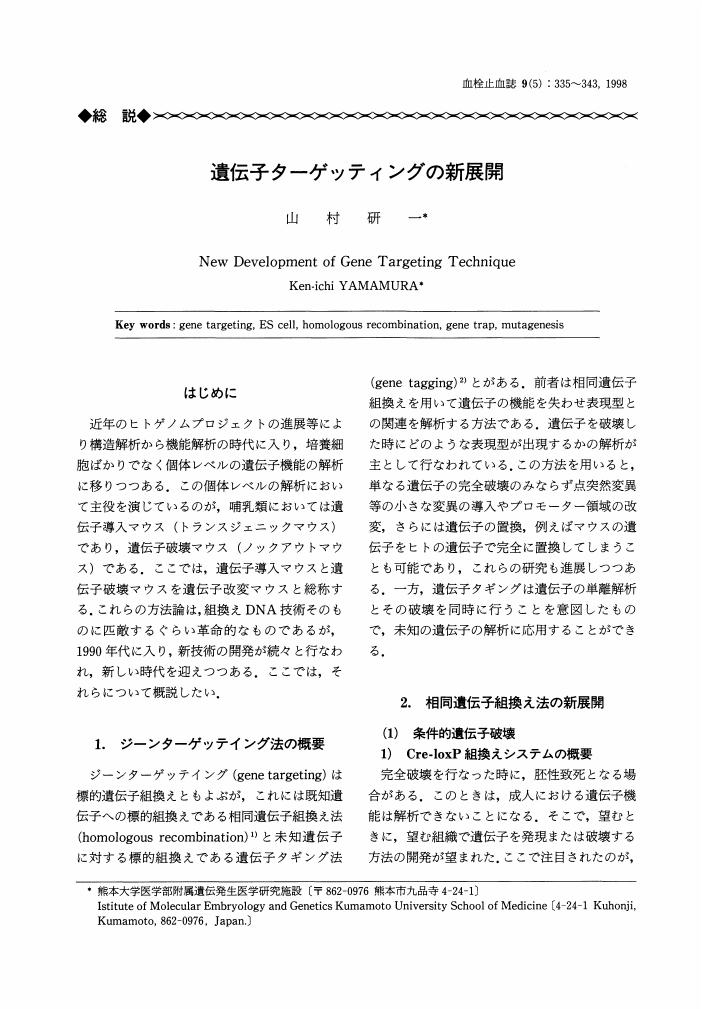2 0 0 0 生殖細胞系列の制御機構と発生工学
当研究領域においては、研究項目A01「生殖細胞系列の制御機構と発生工学」を設定し、計画研究課題7件によって研究を進め、領域代表者中辻憲夫と計画研究代表者西宗義武に外部から7名を加えた総括班を設置し、研究者間の協力と交流を推進した。平成12年11月には公開シンポジウムと班会議を開催した。平成13年11月には国外から主要な研究者7名を招聰して、生殖系列・クローン動物・エピジェネティックス・再プログラム化をテーマとする国際シンポジウム"を開催した。平成14年度には、班会議と公開シンポジウム「生殖細胞の発生プロセス・再プログラム化とエピジェネティクス」を開催した。松居靖久(大阪府母子センタ)「生殖細胞の発生運命の制御機構」、阿部訓也(理研)「哺乳類全能性細胞・生殖細胞における遺伝子発現の研究」、仲野徹(阪大)「始原生殖細胞成立のシグナル」、野瀬俊明(三菱生命研)「培養系における生殖細胞分化」、中馬新一郎・中辻憲夫(京大)「雌雄生殖細胞の分化プログラム」、尾畑やよい(群馬大)「in vitroにおける卵子分化プログラムの再生」、蓬田健太郎(阪大)「生殖幹細胞の維持と分化の制御機構」、篠原隆司(京大)「凍結精巣バンクの開発」、岡部勝(阪大)「生殖細胞における性の決定」、角田幸雄(近畿大)「化学的染色体除去法を用いた体細胞クローン動物の作出」、若山照彦(理研)「クローンマウスにおける核移植技術の問題点と応用」、小倉淳郎(理研)「体細胞クローンマウスの正常と異常-表現型を中心として」、石野史敏(東工大)「体細胞・生殖細胞クローンにおける遺伝子発現」、塩田邦郎(東大)「DNAメチル化コード:個体発生・細胞分化のエピジェネティックス」、岡野正樹(理研)「DNAメチル化パターン制御機構と再プログラム化における役割」、佐々木裕之(遺伝研)「生殖系列における一次インプリントとメチル化の獲得機構」
1 0 0 0 OA 遺伝子ターゲッティングの新展開
- 著者
- 山村 研一
- 出版者
- The Japanese Society on Thrombosis and Hemostasis
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.5, pp.335-343, 1998-10-01 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 遺伝子トラップ法による遺伝子破壊マウス作製技術
- 著者
- 山村 研一
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 : FOLIA PHARMACOLOGICA JAPONICA (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.5, pp.337-342, 2007-05-01
- 参考文献数
- 14
ヒトゲノムプロジェクトの進展により種々の生物のゲノムの塩基配列は明らかとなったが,塩基配列のみでは,遺伝子およびコード領域以外の部分がどのような機能を持っているのか推定すらできないし,また遺伝子自身の機能に関する情報も不十分である.このため全長cDNA配列の決定,DNAチップによる発現パターンの解析,タンパクの構造解析,タンパクに対する抗体作製等の機能解析系が必要であるといわれている.しかし,これらは重要ではあるが,あくまで機能を同定するための状況証拠を提供するにすぎないとみるべきである.具体例を一つあげれば,Cbfa1は,リンパ球で発現する遺伝子の転写因子として発見されたが,その破壊マウスでは骨形成がみられず,骨形成のマスター遺伝子であることが分かった.このことは,構造や発現パターンからだけでは,必ずしも機能は推測できないことを示唆している.そこで,遺伝子改変マウスを用いたin vivoの解析の重要性が再認識され,欧米でノックアウトマウスプロジェクトが始まり,合計すれば年間約40億円に達する金額が投じられることとなった.その内容は,遺伝子トラップ法や相同組換え法を用いてほぼ網羅的にノックアウトESクローンを取るプロジェクトであるが,当面は129系統由来のES細胞を用い,やがて確立されればC57BL/6由来のES細胞を用いて行うというものである.筆者らは網羅的遺伝子破壊を目指して,可変型遺伝子トラップ法を開発した.この方法により,第1段階で完全破壊が,第2段階でトラップベクター内のマーカー遺伝子を,別の遺伝子で置換,第3段階で条件的遺伝子破壊が可能となった.やがて,遺伝子破壊されたES細胞が全世界に配られ,遺伝子破壊マウスが多量に作製され,保存される時が来る.熊本大学生命資源研究支援センターでは,世界の主要なリソースセンターが参加し,保存と供給の支援を行うFIMRe(Federation of International Mouse Resources)にも創立メンバーとして参加し,また,アジアにおけるミュータジェネシスとリソースセンターの連合体であるAMMRA(Asian Mouse Mutagenesis and Resource Association)も立ち上げ,今後の対応も視野にいれた活動を行っている.<br>
個体レベルで生体の機能との関連において遺伝子の発現機構を研究する手段として外来遺伝子を受精卵に導入する技術が開発されている。この技術を家畜家禽の受精卵に利用し、育種的改良技術への応用をも期待されるようになった。本研究では、外来遺伝子導入の為の発生学的手法の開発、遺伝子のクローニングとマッピング及び導入遺伝子による発現機構の解析を哺乳動物と家禽を用いて行なう。材料としての卵子の供給を円滑にする為に豚卵母細胞の冷却保存法を試みたが、20℃への感作でも発生能は著しく阻害された。牛や鶏の体外受精法によって、牛卵子では産仔まで発育することが、鶏卵子では精子の進入過程が詳細に明らかにされた。遺伝子導入実験の際の標識となる遺伝子の探索とクローニングが行なわれた。鳥類の性分化を司る遺伝子に焦点をあて、雌から雄への性転換を引き起こす因子の同定と発現を試みる為初期胚に精巣を移植した。その結果性腺は精巣に特有の構造を呈し、未分化性腺に作用して精巣化する未知の物質の存在が知られた。さらにラット肝臓のOTC遺伝子DNAをプローブとして鶏ヒナ肝臓DNAから2種のmRNAを得た。将来このOTC遺伝子を使って遺伝子導入制御機構の変異を解析する予定である。又、ラットを使ってアンギオテンシノーゲン遺伝子の多型の分析から3型の変化が第19染色体上にあることが同定されたので、今後の系統同定やモニタリングへの利用が期待される。ヒト成長ホルモン遺伝子DNAをプローブとしてヤギ下垂体よりcDNAを取り出し、MTプロモーターが置換された構造遺伝子を作り、マウス受精卵へ注入した。マウス卵子への遺伝子導入法を用いた発現機構の解析が、ヒトA-γ鎖とβ鎖の連結遺伝子とヒトプレアルブミン遺伝子で行なわれた。初期発生と成体ではγ遺伝子とβ遺伝子の発現時期が異なり、アルブミン構造遺伝子は肝臓や脳で特異的に発現した。