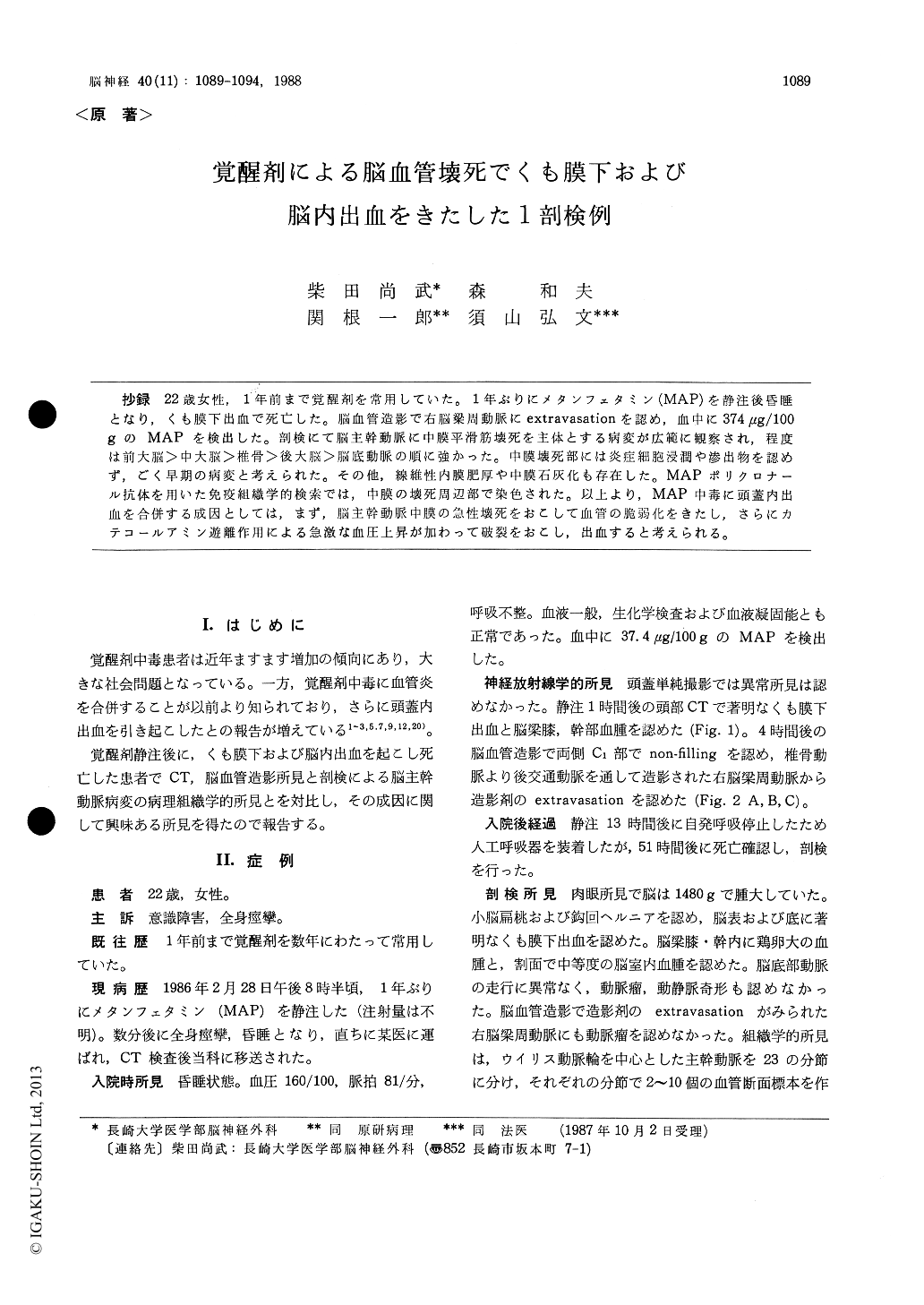2 0 0 0 覚醒剤による脳血管壊死でくも膜下および脳内出血をきたした1剖検例
抄録 22歳女性,1年前まで覚醒剤を常用していた。1年ぶりにメタンフェタミン(MAP)を静注後昏睡となり,くも膜下出血で死亡した。脳血管造影で右脳梁周動脈にextravasationを認め,血中に374μg/100gのMAPを検出した。剖検にて脳主幹動脈に中膜平滑筋壊死を主体とする病変が広範に観察され,程度は前大脳>中大脳>椎骨>後大脳>脳底動脈の順に強かった。中膜壊死部には炎症細胞浸潤や滲出物を認めず,ごく早期の病変と考えられた。その他,線維性内膜肥厚や中膜石灰化も存在した。MAPポリクロナール抗体を用いた免疫組織学的検索では,中膜の壊死周辺部で染色された。以上より,MAP中毒に頭蓋内出血を合併する成因としては,まず,脳主幹動脈中膜の急性壊死をおこして血管の脆弱化をきたし,さらにカテコールアミン遊離作用による急激な血圧上昇が加わって破裂をおこし,出血すると考えられる。
1 0 0 0 OA 感覚運動系技能の習熟過程に関する研究
- 著者
- 森 和夫 菊池 安行
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.Supplement, pp.72-73, 1991-06-01 (Released:2010-03-11)
- 著者
- 寺嶋 吉保 森 和夫 川野 卓二 永廣 信治 佐野 壽昭 玉置 俊晃
- 出版者
- 徳島大学
- 雑誌
- 大学教育研究ジャーナル (ISSN:18811256)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.26-35, 2005-03
- 被引用文献数
- 1
チュートリアル教育は、少人数グループにチューターが付いて学生の自主的な学習を指導・促進する学習方法である。徳島大学医学部医学科では2001 年から導入して、3 年生の9 月から4 年生12 月までの47 週間行なっている。2004 年度で4 年目を迎えるが、学生が教員に学習課題を少なめに出して早く終了する傾向もみられ始めた。われわれは、こうした傾向を憂い、グループ学習の楽しさを体験させてからチュートリアル学習を開始する方が、好ましい学習態度を形成できるのではないかと考え、3 年生の7 月に従来の2 時間程度の説明会以外に4 時間かけて「沖縄旅行計画」を作る学生ワークショップを行なった。この結果、前年度の学生よりも、このチュートリアル学習に対する好感度・有用感などが高くなり、グループ学習時間も増加して、この導入プログラムの有効性を示唆した。New curriculum of the school of medicine, the University of Tokushima included 47-week PBL-tutorial hybridprogram started in 2001.To improve their learning skill and attitude, and to introduce a new learning style ofPBL-tutorial to students smoothly, we held a half day student workshop. The content of workshop is of makingtour plans for a family who had relationship problems among family members. Twelve groups with eightstudents respectively competed and evaluated each other, and all students enjoyed working as groups. Theefficacy of this introductory program was evaluated with questionnaire and their study time of grouplearning between this year and last year students. Impression and feeling of usefulness toward PBL-tutorialwas improved, and time of group study increased this year. Results suggested usefulness of this introductoryprogram. We will continue the evaluation of this program.
1 0 0 0 OA 2C2-3 人に依存する作業の品質向上手法の構築
- 著者
- 森 和夫 比佐 静枝 鈴木 宗三 菅井 浩二 酒井 秀章 樋渡 信夫 菊地 孝夫 宍戸 洋 後藤 由夫 高橋 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.256-262, 1983 (Released:2009-01-26)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
The patient is a 14 year old boy, who admitted to our Department because of severe hemorrhagic diathesis and oliguria following a bite by Rhabdophis tigrinus. He had a snake bite on the 5th finger of right hand on September, 28, 1980. After 9 hrs, he noticed the bleeding at the sites of snake bite and gingiva. On the next day, he developed nasal, gastrointestinal, petechial and subcutaneous bleeding and hematoma 2 days later, and macroscopic hematuria 3 days later.Hemostatic examinations revealed complete incoagulability of whole blood clotting time, partial thromboplastin time, prothrombin time, serial thrombin time, and decreased amount of fibrinogen and elevated level of FDP. However, platelet count increased up to 50×104/mm3 at about 30 hrs after the snake bite. About 34 hrs after the first examination, platelet count decreased to 2.3×104/mm3, and at this time a diagnosis of disseminated intravascular coagulation (DIC) syndrome was made. As antiserum against this snake venom was not available, exchange blood transfusion was performed. His clinical feature and the hemostatic function were recovered well on the following days, while chronic renal failure has been persisted for several months.From above results, the exchange blood transfusion is favorable therapy in order to exclude the snake venom from the blood circulation.