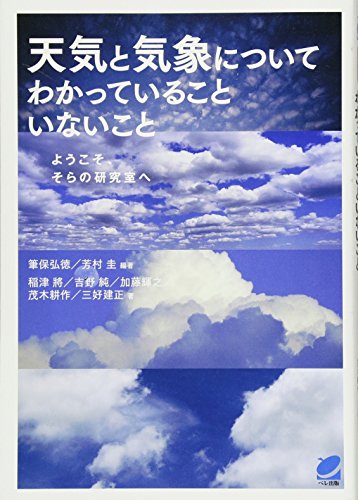4 0 0 0 OA 原発事故由来の放射性セシウム大気濃度の長期解析:土壌、植物からの再飛散
- 著者
- 梶野 瑞王 石塚 正秀 五十嵐 康人 北 和之 吉川 知里 稲津 將
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2016年大会
- 巻号頁・発行日
- 2016-03-10
はじめに2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い大気中に放出された放射性Csは、東北・関東地方において広範囲に沈着した。事故約1年半後の2012年12月以来、避難指示区域内に位置する福島県浪江町・浪江高校津島分校の校庭において、放射性Csの大気濃度の長期間変動と、陸面に沈着した放射性Csの再飛散を評価するために、連続観測が行われて来た。本研究では、約30年と半減期の長い137Csを対象として、再飛散モジュールを実装した3次元物質輸送モデルと、避難指示区域内(浪江高校)と区域外(茨城県つくば市)の2地点の長期間大気濃度観測結果を用いて、東北・関東地方における再飛散を伴う137Csの収支解析を行った。期間は2012年12月から2013年12月までの約1年間を対象とした。手法モデル:ラグランジュ型移流拡散モデル(梶野ら, 2014)を用いた。気象庁メソ解析データ(GPV-MSM)を用いて、放射性物質の放出、輸送、沈着、反応、放射性壊変を解く。土壌からの再飛散は、浪江高校校庭におけるダストフラックス観測に基づいて開発された再飛散モジュール(Ishizuka et al., 2016)を用いた。植生からの再飛散については、メカニズムが明らかになっていないため、放出率は一定として137Csの航空機モニタリング結果による地表面沈着量(減衰率は放射性壊変のみ考慮)と森林面積および植物活性の指標としてGreen Fraction(Chen and Dudhia, 2001)を掛け合わせたものを用いた。観測:大気濃度は、浪江高校校庭および茨城県つくば市の気象研観測露場(Igarashi et al., 2015)でハイボリウムエアサンプラーを用いて捕集されたエアロゾル中の137Cs濃度の測定値を用いた。サンプリングの時間間隔はそれぞれ、浪江高校は1日間、気象研は1週間である。結果浪江における137Cs濃度は、冬に低く(0.1 – 1 mBq/m3)夏に高い(~1 mBq/m3)傾向が見られ、つくばにおける濃度(0.01-0.1 mBq/m3)に比べて1桁程度高かった。モデルにより計算された2地点間の濃度比は、観測の濃度比と整合的であった。土壌からの再飛散は、逆に冬に高く夏に低くなる傾向があり、絶対値は冬季の浪江の観測値を説明できるレベルであるが、夏季の濃度ピークを1-2桁程度過小評価した。解析期間中の原子炉建屋からの放出量は約106 Bq/hr程度(TEPCO, 2013など)であり、浪江の観測値を説明できるレベルではなかった(2-3桁程度過小評価)。植生からの再飛散計算結果は、浪江の季節変動をよく再現し、10-7 /hrの放出率を仮定すると、観測濃度の絶対値と同レベルとなった。依然、事故から5年が経過した現在でも再飛散のメカニズムは明らかにされておらず、観測・実験に基づいたメカニズムの解明研究の発展が望まれる。参考文献Chen and Dudhia, Monthly Weather Review, 129, 569-585, 2001.Igarashi et al., Progress in Earth and Planetary Science, 2:44, 2015.Ishizuka et al. Journal of Environmental Radioactivity, 2016, in press.梶野ら, 天気, 61, 79-86, 2014.TEPCO, 2014 原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(平成26年3月)
- 著者
- 筆保弘徳 芳村圭編著 稲津將 [ほか] 著
- 出版者
- べレ出版
- 巻号頁・発行日
- 2013
3 0 0 0 OA 流線トポロジー解析(TFDA)による大気ブロッキング現象の抽出とその型同定
- 著者
- 宇田 智紀 坂上 貴之 稲津 將 古賀 一基
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.5, pp.1169-1183, 2021 (Released:2021-10-27)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3
本論文では500hPaの等高線が作るトポロジー構造を抽出して大気ブロッキング現象の同定を実現するアルゴリズムを提案する。このアルゴリズムは,構造安定な2次元のハミルトンベクトル場の作る流線パターンのトポロジーによる分類理論に基づいて、この流線構造に部分順序根付き木(partially cyclically ordered rooted tree=COT)表現とそれに付随するレーブグラフ(Reeb graph)という木構造を一意に割り当て、それを用いてブロッキング同定を可能にする。この方法は,従来手法に比べて気象学的なパラメータをほとんど利用せずに簡便かつ効果的に大気ブロッキング現象を抽出できる。加えて、従来手法では困難であったオメガ(Ω)型や双極子型といった大気ブロッキングのタイプ(型)を区別することもできる。このアルゴリズムで同定された大気ブロッキングイベントの期間やそのタイプは現業予報で行われている主観的な判断とよく一致する。
1 0 0 0 OA Evaluation of microphysical schemes in a meteorological model for winter snowfall events in Hokkaido
- 著者
- 近藤 誠 佐藤 陽祐 稲津 將 勝山 祐太
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
This study evaluated microphysical schemes implemented in a meteorological model SCALE (Nishizawa et al. 2015; Sato et al. 2015) targeting midwinter snowfall events in Hokkaido. Cloud microphysical schemes of a 2-moment bulk scheme (Seiki and Nakajima 2014: SN14), a 1-moment bulk scheme of Roh and Satoh (2014: RS14), and that of Tomita (2008: T08) were evaluated with the simulation for events, based on ground-based measurement by disdrometer. Our analysis elucidated that SN14 successfully simulated the measured relationship between the particle size and terminal velocity distribution (PVSD). On the other hand, T08 overestimated the frequency of graupel with fast fall velocity, and underestimated particle diameters. RS14 also overestimated the frequency of the graupel, but reproduced the fall velocity of graupel particles. Sensitivity experiments indicated that RS14 scheme can be improved by the modification for the slope parameter, mass-diameter(m-D) relationship, and PVSD relationship of graupel.ReferencesNishizawa, S., H. Yashiro, Y. Sato, Y. Miyamoto, and H. Tomita, 2015: Influence of grid aspect ratio on planetary boundary layer turbulence in large-eddy simulations. Geosci. Model Dev., 8, 3393–3419, https://doi.org/10.5194/gmd-8-3393-2015.Roh, W., and M. Satoh, 2014: Evaluation of precipitating hydrometeor parameterizations in a single-moment bulk microphysics scheme for deep convective systems over the tropical central pacific. J. Atmos. Sci., 71, 2654–2673, https://doi.org/10.1175/JAS-D-13-0252.1.Sato, Y., S. Nishizawa, H. Yashiro, Y. Miyamoto, Y. Kajikawa, and H. Tomita, 2015: Impacts of cloud microphysics on trade wind cumulus: which cloud microphysics processes contribute to the diversity in a large eddy simulation? Prog. Earth Planet. Sci., 2, https://doi.org/10.1186/s40645-015-0053-6.Seiki, T., and T. Nakajima, 2014: Aerosol effects of the condensation process on a convective cloud simulation. J. Atmos. Sci., 71, 833–853, https://doi.org/10.1175/JAS-D-12-0195.1.Tomita, H., 2008: New microphysical schemes with five and six categories by diagnostic generation of cloud ice. J. Meteorol. Soc. Japan, 86A, 121–142, https://doi.org/10.2151/jmsj.86A.121.