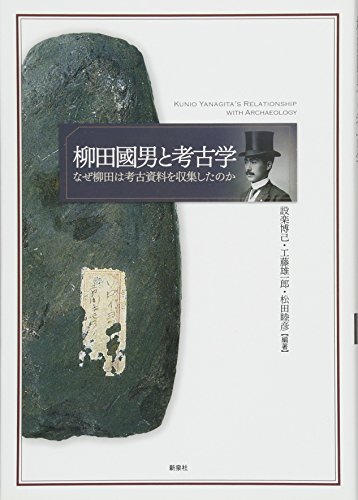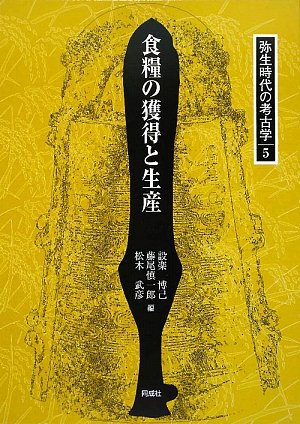4 0 0 0 柳田國男と考古学 : なぜ柳田は考古資料を収集したのか
- 著者
- 設楽博己 工藤雄一郎 松田睦彦編著
- 出版者
- 新泉社
- 巻号頁・発行日
- 2016
2 0 0 0 OA 続縄文文化と弥生文化の相互交流
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.17-44, 2003-10-31
東日本の弥生文化は西日本からの影響のもとに形成されるという観点が,これまでの研究の主流を占めてきた。しかし,東日本における弥生文化の形成は,西日本からの一方的な影響だけで説明できず,地域相互の絡み合いの中から固有の地域文化が成立してきたという視点が重視されつつある。本稿は弥生文化圏外の北海道を中心として展開した続縄文文化である恵山文化ならびにそれに先立つ時期の文化と中部日本の弥生文化との地域を越えた相互交流を,墓制を構成する文化要素を中心に経済的側面をまじえて考察した。東日本の縄文時代から弥生時代に至る経済的,文化的な画期は,①縄文晩期後葉の大洞A式期に稲作を含む西日本の新たな文化の情報を獲得し,②縄文晩期終末の大洞A´式に続く砂沢式期,すなわち弥生Ⅰ期に水田稲作を導入し,試行錯誤を経て③弥生Ⅲ期に大規模な水田の経営を達成する,というように概括できるが,そうした諸段階と連動するかのように,北海道と中部日本の弥生文化には遠隔地間の相互交流が認められる。①,②の画期には,恵山文化およびそれに先立つ時期の墓に中部日本の再葬墓に付随する要素が認められる一方,恵山文化で発達した剥片や小型土器の副葬が中部日本に認められ,そうした交流を経て③の画期には再葬墓に特有の顔面付土器の要素が恵山文化に受容された。弥生Ⅲ期は東日本で本格的な農業集落が成立した大画期であり,弥生Ⅳ期にかけての太平洋沿岸では北海道から駿河湾に及ぶ交流を,土器の動きや回転式銛頭の南下・北上から跡づけることができる。北方系文化が南関東の農業集団の漁撈活動に影響を与えていたことと,農耕集落の組織編成が漁撈集団との関わりのなかで進行した可能性が指摘できるのも重要である。こうした稲作以外の面での相互交流が道南地方と中部日本の間に築かれていたことは,恵山文化の性格のみならず,東日本の弥生文化の性格を理解する上でも看過できない点である。
1 0 0 0 OA 関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, pp.109-153, 2006-12-20
神奈川県小田原市中里遺跡は弥生中期中葉における,西日本的様相を強くもつ関東地方最初期の大型農耕集落である。近畿地方系の土器や,独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物などが西日本的要素を代表する。一方,伝統的な要素も諸所に認められる。中里遺跡の住居跡はいくつかの群に分かれ,そのなかには環状をなすものがある。また再葬の蔵骨器である土偶形容器を有している。それ以前に台地縁辺に散在していた集落が消滅した後,平野に忽然と出現したのも,この遺跡の特徴である。中里集落出現以前,すなわち弥生前期から中期前葉の関東地方における初期農耕集落は,小規模ながらも縄文集落の伝統を引いた環状集落が認められる。これらは,縄文晩期に気候寒冷化などの影響から集落が小規模分散化していった延長線上にある。土偶形容器を伴う場合のある再葬墓は,この地域の初期農耕集落に特徴的な墓であった。中里集落に初期農耕集落に特有の文化要素が引き継がれていることからすると,中里集落は初期農耕集落のいくつかが,灌漑農耕という大規模な共同作業をおこなうために結集した集落である可能性がきわめて高い。環状をなす住居群は,その一つ一つが周辺に散在していた小集落だったのだろう。結集の原点である大型建物に再葬墓に通じる祖先祭祀の役割を推測する説があるが,その蓋然性も高い。水田稲作という技術的な関与はもちろんのこと,それを遂行するための集団編成のありかたや,それに伴う集落設計などに近畿系集団の関与がうかがえるが,在来小集団の共生が円滑に進んだ背景には,中里集落出現以前,あるいは縄文時代にさかのぼる血縁関係を基軸とした居住原理の継承が想定できる。関東地方の本格的な農耕集落の形成は,このように西日本からの技術の関与と同時に,在来の同族小集団-単位集団-が結集した結果達成された。同族小集団の集合によって規模の大きな農耕集落が編成されているが,それは大阪湾岸の弥生集落あるいは東北地方北部の初期農耕集落など,各地で捉えることができる現象である。
1 0 0 0 OA 擦文文化期における環オホーツク海地域の交流と社会変動
- 著者
- 熊木 俊朗 大貫 静夫 佐藤 宏之 設楽 博己 國木田 大 夏木 大吾 福田 正宏 笹田 朋孝 佐野 雄三 守屋 豊人 山田 哲 中村 雄紀 守屋 亮
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-01
擦文文化期における地域間交流や社会変化の様相を解明するため、北見市大島2遺跡にて擦文文化の竪穴住居跡の発掘調査を実施した。大島2遺跡は標高の高い尾根上というやや特異な環境下にあり、低地や砂丘上にある他の集落とは異なる性格を有することが予想されたが、発掘調査の結果、海獣狩猟や動物儀礼、住居の廃絶儀礼、建築木材の選択、木製品の様相などに、オホーツク文化やトビニタイ文化との関連を思わせるような特徴が認められることが明らかになった。
1 0 0 0 食糧の獲得と生産
- 著者
- 設楽博己 藤尾慎一郎 松木武彦編
- 出版者
- 同成社
- 巻号頁・発行日
- 2009
1 0 0 0 OA 副葬される土偶(日本の死者儀札と死の観念(1))
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.9-29, 1996-03-29
縄文時代の代表的な呪具である土偶は,基本的に女性の産む能力とそれにからむ役割といった,成熟した女性原理にもとつく象徴性をほぼ一貫して保持していた。多くの土偶は割れた状態で,何ら施設を伴わずに出土する。これらは故意に割って捨てたものだという説があるが,賛否両論ある。縄文時代後・晩期に発達した呪具である石棒や土版,岩版,岩偶などには火にかけたり叩いたりして故意に破壊したものがみられる。したがって,これらの呪具と関連する儀礼の際に用いたと考えられる土偶にも,故意に壊したものがあった蓋然性は高い。壊したり壊れた呪具を再利用することも,しばしばおこなわれた。土偶のもうひとつの大きな特徴は,ヒトの埋葬に伴わないことである。しかし,他界観の明確化にともなって副葬行為が発達した北海道において,縄文後期後葉に土偶の副葬が始まる。この死者儀礼は晩期終末に南東北地方から東海地方にかけての中部日本に広まった。縄文晩期終末から弥生時代前半のこの地方では,遺骨を再埋葬した再葬が発達するが,再葬墓に土偶が副葬されるようになったり,土偶自体が再葬用の蔵骨器へと変化した。中部日本の弥生時代の再葬には,縄文晩期の葬法を受け継いだ,多数の人骨を焼いて埋納したり処理する焼人骨葬がみられる。こうした集団的な葬送儀礼としての再葬の目的の一つは,呪具の取り扱いと同様,遺体を解体したり遺骨を焼いたり破壊して再生を願うものと考えられる。つまり,ヒトの多産を含む自然の豊饒に対する思いが背後にあり,それが土偶の本来的意味と結びついて土偶を副葬するようになったのだろう。そもそも土偶が埋葬に伴わないのは,男性の象徴である石棒が埋葬に伴うことと対照的なありかたを示すが,それは縄文時代の生業活動などに根ざした,社会における性別の原理によって規定されたものであった。土偶の副葬,すなわち埋葬への関与はこうした縄文社会の原理に弛緩をもたらすもので,縄文時代から弥生時代へと移り変わる社会状況を反映した現象だといえる。
1 0 0 0 IR 関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, pp.109-153, 2006-12
神奈川県小田原市中里遺跡は弥生中期中葉における,西日本的様相を強くもつ関東地方最初期の大型農耕集落である。近畿地方系の土器や,独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物などが西日本的要素を代表する。一方,伝統的な要素も諸所に認められる。中里遺跡の住居跡はいくつかの群に分かれ,そのなかには環状をなすものがある。また再葬の蔵骨器である土偶形容器を有している。それ以前に台地縁辺に散在していた集落が消滅した後,平野に忽然と出現したのも,この遺跡の特徴である。中里集落出現以前,すなわち弥生前期から中期前葉の関東地方における初期農耕集落は,小規模ながらも縄文集落の伝統を引いた環状集落が認められる。これらは,縄文晩期に気候寒冷化などの影響から集落が小規模分散化していった延長線上にある。土偶形容器を伴う場合のある再葬墓は,この地域の初期農耕集落に特徴的な墓であった。中里集落に初期農耕集落に特有の文化要素が引き継がれていることからすると,中里集落は初期農耕集落のいくつかが,灌漑農耕という大規模な共同作業をおこなうために結集した集落である可能性がきわめて高い。環状をなす住居群は,その一つ一つが周辺に散在していた小集落だったのだろう。結集の原点である大型建物に再葬墓に通じる祖先祭祀の役割を推測する説があるが,その蓋然性も高い。水田稲作という技術的な関与はもちろんのこと,それを遂行するための集団編成のありかたや,それに伴う集落設計などに近畿系集団の関与がうかがえるが,在来小集団の共生が円滑に進んだ背景には,中里集落出現以前,あるいは縄文時代にさかのぼる血縁関係を基軸とした居住原理の継承が想定できる。関東地方の本格的な農耕集落の形成は,このように西日本からの技術の関与と同時に,在来の同族小集団-単位集団-が結集した結果達成された。同族小集団の集合によって規模の大きな農耕集落が編成されているが,それは大阪湾岸の弥生集落あるいは東北地方北部の初期農耕集落など,各地で捉えることができる現象である。
1 0 0 0 IR 独立棟持柱建物と祖霊祭祀 (縄文・弥生集落遺跡の集成的研究) -- (弥生時代の集落論)
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.149, pp.55-90, 2009-03
独立棟持柱建物は,Ⅰ類)居住域に伴う場合と,Ⅱ類)墓域に伴う場合がある。Ⅰ類にはA類)竪穴住居と混在する,B類)特定の場所を占める,C類)区画に伴う,という三つのパターンがある。A類からC類への流れは,共同体的施設から首長居館の施設への変貌を示すもので,古墳時代へと溝や塀で囲まれ秘儀的性格を強めて首長に独占されていった。弥生土器などの絵画に描かれた独立棟持柱建物の特殊な装飾,柱穴などから出土した遺物からすると,この種の建物に祭殿としての役割があったことは間違いない。問題は祭儀の内容だが,Ⅱ類にそれを解く手がかりがある。北部九州地方では,弥生中期初頭から宗廟的性格をもつ大型建物が墓域に伴う。中期後半になると,楽浪郡を通じた漢文化の影響により,大型建物は王権形成に不可欠な祖霊祭祀の役割を強めた。福岡県平原遺跡1号墓は,墓坑上に祖霊祭祀のための独立棟持柱建物がある。建物は本州・四国型であるので,近畿地方から導入されたと考えられる。したがって,近畿地方の独立棟持柱建物には,祖霊祭祀の施設としての役割があったとみなせる。ところが,近畿地方でこの種の建物は墓に伴わない。近畿地方では祖霊を居住域の独立棟持柱建物に招いて祭ったのであり,王権の形成が未熟な弥生中期の近畿地方では,墳墓で祖霊を祭ることはなかった。しかし,弥生後期終末の奈良県ホケノ山墳丘墓の墓坑上には独立棟持柱建物が建っている。畿内地方の王権形成期に,北部九州からいわば逆輸入されたのである。南関東地方のこの種の建物も祖霊祭祀の役割をもつが,それは在地の伝統を引いていた。独立棟持柱建物の役割の一つは祖霊祭祀であるという点で共通している一方,その系譜や展開は縄文文化の伝統,漢文化との関係,王権の位相などに応じて三地域で三様だった。
1 0 0 0 IR 黥面土偶から黥面絵画へ
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.80, pp.185-202, 1999-03
弥生時代には,イレズミと考えられる線刻のある顔を表現した黥面絵画が知られている。いくつかの様式があるが,目を取り巻く線を描いた黥面絵画A,目の下の線が頰を斜めに横切るように下がった黥面絵画B,額から頰に弧状の線の束を描いた黥面絵画Cがおもなものである。それぞれの年代は弥生中期,中~後期,後期~古墳前期であり,型式学的な連続性から,A→B→Cという変遷が考えられる。Aは弥生前期の土偶にも表現されており,それは縄文時代の東日本の土偶の表現にさかのぼる。つまり,弥生時代の黥面絵画は縄文時代の土偶に起源をもつことが推測される。黥面絵画には鳥装の戦士を表現したものがある。民族学的知見を参考にすると,イレズミには戦士の仲間入りをするための通過儀礼としての役割りがあったり,種族の認識票としての意味をもつ場合もある。弥生時代のイレズミには祖先への仲間入りの印という意味が考えられ,戦士が鳥に扮するのは祖先との交信をはかるための変身ではなかろうか。畿内地方では,弥生中期末~後期にイレズミの習俗を捨てるが,そこには漢文化の影響が考えられる。その後,イレズミはこの習俗本来の持ち主である非農耕民に収斂する。社会の中にイレズミの習俗をもつものともたないものという二重構造が生まれたのであり,そうした視点でイレズミの消長を分析することは,権力による異民支配のあり方を探る手掛かりをも提示するであろう。
1 0 0 0 OA 縄文時代の再葬
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.7-46, 1993-03-25
いったん遺体を骨にしてから再び埋葬する葬法を、複葬と呼ぶ。考古学的な事象からは、死の確認や一次葬など、複葬制全体を明らかにすることは困難で、最終的な埋葬遺跡で複葬制の存在を確認する場合が多い。そうした墓を再葬墓、その複葬の過程を再葬と呼んでいる。東日本の初期弥生時代に、大形壺を蔵骨器に用いた壺棺再葬墓が発達する。その起源の追究は、縄文時代の再葬にさかのぼって検討する必要がある。縄文後・晩期の再葬は、普遍的葬法といえるものはまれであるものの、南東北地方から近畿地方にいたる比較的広い地域に広がっていた。再葬法には遺骨を集積した集骨葬や、土器に納めた土器棺再葬、人骨を破壊して四角く組んだ盤状集骨葬や、人骨を焼いて埋葬した焼人骨葬などがあり、けっして縄文後・晩期の再葬も一様ではない。縄文時代には、生前の血縁関係や年齢に応じたつながりを死後も維持するためと思われる合葬がしばしばおこなわれるが、再葬のひとつの要因として合葬が考えられる。そうした再葬を伴う合葬のなかには、祖先や集落の始祖に対する意識の萌芽的な側面が指摘できるものもある。しかし、同様な形態の再葬でもその内容が同じとはいえず、さらに長い年月の間、その性格も不変のものではありえないと思われる。地域間の相互交流、再葬の際の骨の扱い方の変化など再葬法の時代的な変化を整理することにより、そうした多様性の内実に近づくことが可能だろう。中部高地の縄文晩期の再葬の特色は、多人数の遺骸を処理する焼人骨葬であり、それは北陸に広がり、伊勢湾、近畿地方に伝播した。一方、中部高地には伊勢湾地方の集骨葬が影響を与えた可能性がある。再葬の際の骨の取り扱い方という点では、縄文後期に顕著であった全身骨再葬と、頭骨重視の傾向が晩期初頭~前葉にも引きつがれる一方、それ以降部分骨再葬や中期にさかのぼる遺骨破壊の行為も比較的広範囲に広まるように、晩期前葉を過渡期として遺骨の取り扱いにも変化がみられるようになる。晩期中葉の近畿地方では部分骨再葬と結びついた土器棺再葬をおこなっていた。土器棺再葬を部分骨再葬とみなせば、焼人骨はその残余骨の処理であったと考えられ、遺骨破壊の必要性が高まった反面、遺骨保存の措置が採られた二重構造を想定することができる。多様な再葬の形態と相互の影響関係が認められる近畿地方から中部高地の内陸地帯で、晩期中葉には集骨葬が衰退するなか、類例は少ないが土器棺再葬と焼人骨葬が晩期終末まで継続するのは、弥生時代の壺棺再葬墓の成立を考えるうえで重要な現象である。
1 0 0 0 OA 壷棺再葬墓の基礎的研究
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.3-48, 1993-02-26
民族・民俗学で複葬と呼ぶ葬法は遺体を何度も故意に取り扱うため,葬儀が複数回におよぶもので,考古学ではこれを一般的に再葬と呼んでいる。日本列島では縄文晩期終末から弥生Ⅲ期までの東日本の一部で、主に壺形土器を蔵骨器にした再葬墓が発達した。この再葬墓に特徴的なものは,一つの土坑の中に複数の土器を納めた複棺再葬墓であるが,複数の土器棺に納めた人骨が複数体の場合は,一括埋納の契機や合葬された人々の社会的関係が問題になってくる。複棺再葬墓の土器には摩滅状態の著しいものや補修痕のあるものが日常集落以上に含まれる。また,一土坑の複数の土器には型式差のあるものが共存し,埋納までに要した長い集積の期間を推測させるものもあるが,それはまれである。一土坑の遺体数は2~4体で7体という例もみられる。これら合葬人骨は男女ともにあり,また成人と小児など世代を超えたものが組み合わさる場合もある。したがって一土坑における複数の納骨土器は,ある期間の集積を経て一括埋納されたものであり,集積の期間はまれに長期にわたる場合もあるが,多くは土器型式の存続期間を超えるほど長くなかったとみられる。ならば,この一土坑に合葬された者の紐帯は累世的なものは考えにくく,血縁的紐帯か世帯のまとまりか世代によるまとまりかということになる。出土人骨におもきを置けば年齢階梯的つながりは想定しがたく,血縁か世帯であろうが,これを解くてがかりは墓域の構成にある。初期の再葬墓群は弧状を呈するものがある。福島県根古屋遺跡の分析からすると,弧状の墓域がいくつかの群に分かれており,各群に新古の墓坑がみられる。これはあらかじめ墓域を区画して埋葬していったものであり,これら各群は縄文時代の埋葬小群と同様なものだといえる。縄文時代の埋葬小群は血縁のつながりがある身内のグループと,非血縁の婚入者のグループからなる一つの世帯の累積的墓群とされる。縄文時代後・晩期には夫婦など血縁関係にないものどうしの合葬はおこなわなかったとされる。複棺再葬を合葬の一形態とみなし,そこに縄文時代の合葬原理が生きているとすれば,こうした縄文時代の墓域構成を踏襲した初期の複棺再葬墓は,なんらかの血縁的な関係にある者どうしを合葬した土坑と考えるのが妥当だろう。そしてそれらが集合した埋葬小群が,一つの世帯の歴史的な墓群であり,墓域全体が一つの集落の墓地だと考える。
1 0 0 0 OA 農耕文化複合と弥生文化
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.185, pp.449-469, 2014-02-28
弥生時代の定義に関しては,水田稲作など本格的な農耕のはじまった時代とする経済的側面を重視する立場と,イデオロギーの質的転換などの社会的側面を重視する立場がある。時代区分の指標は時代性を反映していると同時に単純でわかりやすいことが求められるから,弥生文化の指標として,水田稲作という同じ現象に「目的」や「目指すもの」の違いという思惟的な分野での価値判断を要求する後者の立場は,客観的でだれにでもわかる基準とはいいがたい。本稿は前者の立場に立ち,その場合に問題とされてきた「本格的な」という判断の基準を,縄文農耕との違いである「農耕文化複合」の形成に求める。これまでの東日本の弥生文化研究の歴史に,近年のレプリカ法による初期農耕の様態解明の研究成果を踏まえたうえで,東日本の初期弥生文化を農耕文化複合ととらえ,関東地方の中期中葉以前あるいは東北地方北部などの農耕文化を弥生文化と認めない後者の立場との異同を論じる。弥生文化は,大陸で長い期間をかけて形成された多様な農耕の形態を受容して,土地条件などの自然環境や集団編成の違いに応じて地域ごとに多様に展開した農耕文化複合ととらえたうえで,真の農耕社会や政治的社会の形成はその後半期に,限られた地域で進行したものとみなした。
1 0 0 0 柳田國男の山人論と考古学 (柳田國男収集考古資料の研究)
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.202, pp.157-180, 2017-03
1 0 0 0 OA スス・コゲからみた縄文・弥生土器と土師器による調理方法
- 著者
- 小林 正史 北野 博司 設楽 博巳 若林 邦彦 徳澤 啓一 鐘ケ江 賢二 北野 博司 鐘ヶ江 賢二 徳澤 啓一 若林 邦彦 設楽 博己 久世 建二 田畑 直彦 菊池 誠一
- 出版者
- 北陸学院大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2007
縄文から古代までの調理方法を復元し、土鍋の形・作りの機能的意味を明らかにする、という目的に沿って、ワークショップ形式による土器観察会、伝統的蒸し調理の民族調査(タイと雲南)、調理実験、を組み合わせた研究を行った。成果として、各時代の調理方法が解明されてきたこと、および、ワークショップを通じて土器使用痕分析を行う研究者が増え始めたことがあげられる。前者については、(1)縄文晩期の小型精製深鍋と中・大型素文深鍋の機能の違いの解明、(2)炊飯専用深鍋の確立程度から弥生時代の米食程度の高さを推定、(3)弥生・古墳時代の炊飯方法の復元、(4)古墳前期後半における深鍋の大型化に対応した「球胴鍋の高い浮き置き」から「長胴鍋の低い浮き置き」への変化の解明、(4)古代の竈掛けした長胴鍋と甑による蒸し調理の復元、などがあげられる。