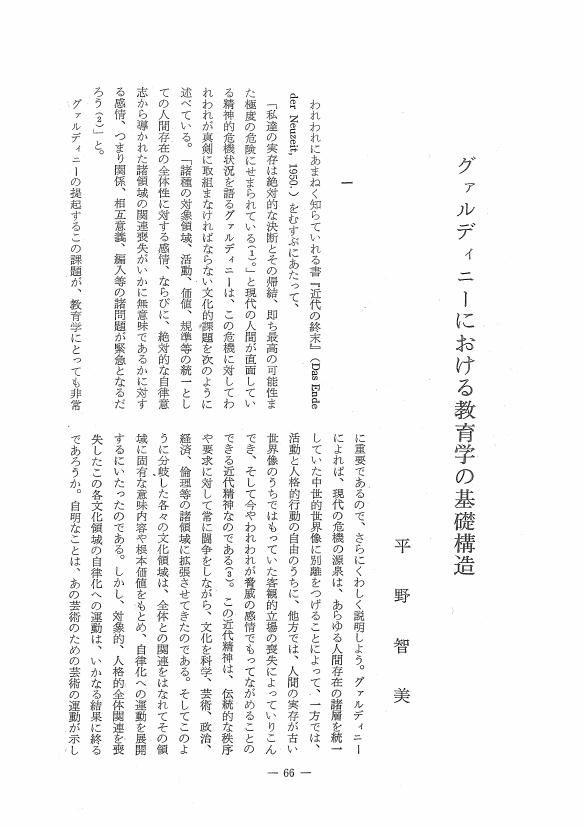1 0 0 0 OA シュプランガーにおける教育理想と教育者の位置 戦後の作品について
- 著者
- 安谷屋 良子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1962, no.6, pp.63-77, 1962-06-25 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 39
人間は、その人独自の内面的な世界をもっており、その内面性の深みにおいて人は全く孤独に神と対決するのであり、彼の神との対決において人は人生の意義を理解し、高次の人間性への要求と義務とを見出すのであるということは、宗教性を人間の精神構造の最も深い中核においているシュラプンガーの理想主義的思想を貫いている根本的信念である。従ってこの個人個人に特有の内面性に刺戟を与えて自ずから目醒めるに到るまでその影響を及ぼすことは彼にとって当然の教育の狙いである。彼にとっては、いかなる心身の育成も、有用な知識の修得も (もちろん欠くべからざる重要な教育の部分ではあるけれども) それだけでは充分に教育であるとはいえないのである。個々の人間が、その魂の底から揺ぶられて、真の人間性にめざめることこそ個人を最高度に発展させることであり、同時にまた社会および文化の発達向上の要因ともなるのである。このような思想は彼の数々の作品を通して読み取ることのできるものである。望ましい環境と指導者が与えられれば、若い者の魂に清らかな火がともされて燃え上る可能性のあることを彼の宗教的信念は語っている。然しながら、神にまで通う清浄な火を一人一人の魂の内に燃え上がらせようという彼の思想はあまりにも理想主義的であり、且個人主義的にすぎる感があり、我々の現実の厳しさにも縁遠いもののようにも思われる。私共の歴史的現実は個々人の清らかな魂のめざめを期待するにはあまりにも混濁しており、複雑な社会の機構は個人の意志の介入を許さないほどに我々を縛り上げてしまっているからである。だが一方おいて、社会そのものが個人を要素として成立し、個人の創意や発明が巨大な社会の力となって動いているという単純な事実を改めて思い起す時、シュプランガーの思想は我々の歴史的現実における歩みに対して何か示唆を与えるものではないかとも考えられる。いな、むしろ個人の介入の余地の少なくなっている現代ほど個人の存在の重要性を改めて高く掲げなければならない時代はないかも知れない。ここは彼の戦後の作品だけを取り上げたのは、それらが第二次大戦に引きつづくきびしい条件のもとで書かれたものであるからである。彼はしばしばヨーロッパの危機ということを問題にしているが、それはまた一般に現代の危機に対して書かれたものであると見ることもできよう。彼が警告を与えているところの、イデオロギーに縛られて一つの型にはまった考えしか出来ないような人間、マスコミの宣伝に影響されて自ら考えることをしないようなMassenmensch, あるいは科学技術の発達に伴って尨大な機械の附属品の如くになってしまっている人間、社会工学に基づく社会組織の中で位置づけられ、動機づけられて動く人間-こういった人間の状態は我々にとって決して縁遠いものではない。このような現代文化社会に共通の現象に対してシュプランガーが如何なる型で警告を与えているかは甚だ興味あることである。ここでは特に教育理想と教育者を主題としつつ現実の課題との結びつきをとらえたいと思った。
1 0 0 0 OA 近世における人間観の展開 室鳩巣の思想にあらわれた人間観の論理
- 著者
- 石川 謙
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.4, pp.1-11, 1961-04-20 (Released:2009-09-04)
Muro Kyuso's theory of man was a theory that organized in a philosophical manner various aspects of the social problems that began to raise their head toward the middle of the eighteenth century. Kyuso worked out his theory of man in liking his general views of the universe with his views on human society. In his general view of the universe he attached first importance to this world (as opposed to a future world), and in his theory of man he insisted on the absolute autonomy of human value. His theory of man developed into a concrete image of man throuth a thought process peculiar to himself, a process which, based on a feeling for modernity, grasped something of the meaning of the new social organizations and structures then emerging. In this easy I have considered Kyuso's thought in connection with the social problems of the first half of the eighteenth century.
1 0 0 0 OA ジョン・デューイとアメリカ進歩主義教育運動
- 著者
- 杉浦 宏
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.4, pp.12-30, 1961-04-20 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 64
In this eassy my chief interest lies in discussing some of the personal characteristics connected with the progressive Education Movement in a United States. For such a discussion I think it is necessary to make a rough sketch of the historical development of the progressive Education Movement (1918-1956) and this I do in the first part of the essay. My reason for giving the essay the title it has is that its main point comes down to an investigation of the relation between Dewey and the educational theories of the movement. My conclusion is that the progressive Education Movement, in which the educational theories of Romantic Naturalism were prominent, failed to carry faithfully into practice Dewey's Empirical Naturalism.
1 0 0 0 OA デューイ思想における普遍的性格
- 著者
- 佐藤 三郎
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.4, pp.31-45, 1961-04-20 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 36
環境の諸相が絶えず変っていくということ、我々が二度と同じ川の流れの中に立つことが出来ないという事実は、否定され得ない。従ってまた、我々の実践的態度も、この変貌していく条件に即して変ってこなければならないということが出来る。けれどもこのような、変化にはある変化をもって応えていく我々の日常行動には、既に、ある不変なものが変化の規準として内在することを前提にしている。さもなければ、変転する条件に我々が即応することの何らの正当性もなくなるであろう。たとえ如何なる姿で存在するにせよ、我々は常に、この暗黙裡の前提に立脚することによって、流転する現実に何らかの是非の態度をもって取り組んでいる、と考えられる。我々の行動の規準であるこの暗黙裡の前提は、様々な形で表現されて来たが、表現され概念化されたものと、それの拠って立つ実相との間には、常にある距離が存在している。この距離は、人間の存在の仕方である実存の本質が絶えざる自己更新であり自己超越であるところから、或いは永遠の距離であるとも考えられる。思想の歴史に見られる具体的な思想の消長変化の事実は、かかる関係の明白な証左であると思う。従って、もしも思想の永遠性というものがあるとするならば、それは、この暗黙裡の前提の実相にどれ程忠実に立脚して、そこから絶えず生命を補給していくかに依存するものである、という見方が成り立つようにも思われる。私は今このような観点から、デューイの思想を考察して見たいと思う。彼の試みた過去の思想的伝統への挑戦とその革新への努力が、やがては彼の思想そのものが挑戦され革新される契機をはらみながらも、なお且つ生きていく永遠なものをそこに探って見ること、これが本稿の論点である。
1 0 0 0 OA シュプランガーにおける生活と教育との関連について
- 著者
- 伊東 亮三
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.4, pp.46-61, 1961-04-20 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 49
The educational views of E. Spranger, a foremost scholar in Pestalozzi studies in contemporary Germany, are originally based in many respects on the latter's thought. In 1959 he published successively two studies under the same title as Pestalozzi's famous theme, “Life is education.” His major concern at the present, in my opinion, is to lay a foundation for, and to subject to critical examination, two movements of modern education, the “theory of life-education” and the “fundamentals of life.” This work he is carrying on through his interpretation of Pestalozzi's “Life is education.” In this essay I have based myself principally on these two studies of Spranger, though at the same time I have consulted the works of other writers. In order to clarify his concept of “life” and the relation in his thought between “education” and “life” I discuss the matter under four headings : 1) the educatiue power of life; 2) life in the pupil's world; 3) cultured life as the objective world; 4) the educationalizing of life.
1 0 0 0 OA コメニウスの教授学とその哲学的基礎
- 著者
- ホルンシュタイン H
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.4, pp.62-79, 1961-04-20 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 52
The twofold aspect of the educational theory of Comenius is a testimony to the change of times in the West. Its metaphysical foundation reflects a former age, its educational concern the new age. So, the educational program of the pampaideia, which aimed to teach everything to everybody, is not thoroughly understandable apart from the assumptions of medieval metaphysics. The school, which for Comenius was excluively an institution in the service of education, teaches universal knowledge but not as an end in itself. It is, rather, merely the condition for man too to reach his goal as a creature, (namely) through the right use of things and through correct belief in God, for the time being withholds from him the attainment of his final goal. This “pansophical” approach to teaching would be a futile undertaking on the basis of the new scientific approach, for this latter dose not simply find its object as something given as does the “knowledge of thing” of Comenius with its orientation toward the qualitative essential element of things. Rather, it constructs its own object in accordance with the hypothetical method it employs. So, the only question to be answered is : within the framework of the modern approach to teaching what place can be given to the material aspect of the educational theory of Comenius, that aspect being considered as an integral part of his theory? The directon of a possible answer to this question is merely pointed out in this essay.
1 0 0 0 OA オットー・F・ボルノウ「ディルタイ哲学入門」
- 著者
- 西村 晧
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.4, pp.80-83, 1961-04-20 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 機械の概念と哲学の諸問題
- 著者
- 沢田 允茂
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.5, pp.1-12, 1961-09-30 (Released:2009-09-04)
The concept of “machine” has been generally taken to stand in opposition to that of “man.” However, when the remarkable progress of machines in recent times is considered, the very notion of “machine” fitted to recent models of the machine is seen to be in desperate need of reform.At the heart of the new theories on machines are notions, such as that of “feedback”, which can formally and structurally be applied to the actions of reflection, consciousness, and the like in man. Consequently, it has become possible again to work out an explanation, based on machine theory, of various problems relating to man and philosophy.One of the characterisitics of machines containing “feedback” systems is that of “presentation”, a concept which was used idealistically and dialectically by Hegel and Marx and can serve as an aid in explaining the laws of hitorical and social movements. The problem of “subjectivity, ” which was the target of much criticism in older machine theories, is, thanks to the new theory, no longer a problem.
1 0 0 0 OA 学習の機械化とその理論
- 著者
- 沼野 一男
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.5, pp.13-31, 1961-09-30 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 17
A teaching machine is an educational tool designed to provide a program enabling a student to approach a desired educational activity by gradual steps and, by multiple reinforcements of the student's responses immediately after he has given them, to increase learning efficiency. Teaching machines deffer from audio-visual devices in that they envisage individual direction and provide an immediate feedback to the student's responses.The teaching machines which are now being used are divided into two types, according to their response mechanism : the Pressey model (Recognition system) and the Skinner model (construction system). The effective use of either or these models depends on appropriate programming of the teaching materials used. A “program” is so devised that the student is led to follow cues and prompts which gradually reduce the successive steps necessary for the learning of the apportioned material, which must be so arranged that the student can have his correct responses reinforced at each step and thus reach his learning goal.Teaching machines not only increase learning efficiency and reduce the teacher's burden but also make possible an empirical analysis of the learning process. As a consequence of this union of educational science and practice a shift in educational emphasis-from teacher-centered to student-centered learning-can be expected.
1 0 0 0 OA 科学と教育 マルクス主義教育論における科学の位置
- 著者
- 永冶 日出雄
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.5, pp.32-42, 1961-09-30 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 28
「人間の安息を憎む神が、科学の発明者であった。エジプトからギリシァに伝えられた古い伝説はこう語っている。天文学は迷信から、雄弁術は野心、憎悪、追従、虚言から、幾何学は貪欲、物理学は空虚な好奇心から、すべてのものが、道徳そのもがすらが、人間の傲慢から生まれた。科学と芸術とはしたがってその誕生をわれわれの悪徳に負っている。もしもわれわれの美徳が生みだしたものならば、われわれはそれらの利益をこれほど疑問にはしないであろう。」 (1) いまからおよそ二百年前、ジャン・ジャックルソーはその有名な懸賞論文のなかで、科学と芸術をこう痛烈に弾劾した。このような科学の全面的否定は今日ではほとんどみられない。けれども、科学の発展と浸透にたいして不安と恐怖を感じ、科学と人間の矛盾を指摘する人は、けっしてすくなくないように思われる。たとえば、務台理作氏は科学と技術の進歩によって生活上の便宜が増大したことを認めつつ、「科学とその技術化の進歩に伴って、人間の物化・量化・平均化がいちじるしくなり、それに加えて失業と貧困への不安、人類とその文化の大半を絶滅させるかもしれない世界戦争への恐怖も生まれつついるではないか。要するに人間の非人間化が進められつついるではないか。」 (2) と述べておられる。原子戦争の危険やいわゆる「大衆社会」的現象を考えるならば、科学はルソーの時代にもまして疑惑の眼をもってみられ、弁明を迫られているといってよいであろう。しかし、科学への懐疑を消しきれぬままに、人々は日々の生活のなかにそれの成果を吸収せねばならない。人々は好むと好まざるにかかわらず、科学と技術の発展に相応した方策をとらざるをえない。教育の分野においても「各層の科学者と技術者の数を大巾にふやし、その教育の質を高めようという計画が、第二次大戦以後、とくに最近における、世界各国の科学技術政策ならびに教育政策の中心的な課題になってきている。」 (3) オートメーションの採用や原子力の利用による技術革新の波は、教育の領域にも押し寄せ、科学技術教育はいまや教育学の主要な論題の一つとなったのである。科学技術教育についての論義は科学と人間、科学と教育をどう考えるかにつながっている。科学にたいし不信の念をいだく人はこれについてもまた批判的な態度をとるであろう。この論文は科学技術教育の現状について具体的に論ずるのではないが、科学と教育についての思想をマルクス主義の古典のなかに追求し、それを整理することによって、この問題にたいする一つの基礎的な資料を提供しようとしている。われわれはまず科学の意義を人間の生活の全体との関係で理解し、つぎにマルクス主義の教育論のなかで科学がどのように位置づけられているかを検討することとしよう。
1 0 0 0 OA ナトルプにおける労作人の構造について
- 著者
- 西頭 三雄児
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.3, pp.33-46, 1960 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 44
In this essay I consider Natorp's writings on the formation of homo faber, considered as part of the process of human formation. By “human formation” I mean the process of unlimited awareness, the essential ', starting point of which I wish to consider as labor. In Natorp's mind, labor is that genuinely human activity by which man establishes relations with the natural world. This activity, considered in its early and later stages, is not entirely the same, but in both stages it may be said to be the limiless exertion of a person as he aims at a spiritual idea. If Natorp's “awareness” is taken in the sense of laying hold of an idea, an essential relation between “awareness” and “labor” is indicated. We must remember that “awareness” in Natorp necessarily means social awareness. Consequently, a relation between it and socially cooperative labor is established. When labor is considered in its later stage and is grasped at a more profound level, it is seen in its dialectical character as a basic human activity rooted in intelligent volition. With his notion of “latent harmony” Natorp differs from Hegel in his dialectical theory and (unlike Hegel) was unable to conceive of the active meaning of contradiction. Natorp's special characteristic may be considered to lie in his concept of “the religion of labor” and of “leisure.”
1 0 0 0 OA シュプランガーにおける教育の本質概念について
- 著者
- 村田 昇
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.3, pp.47-59, 1960 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 17
「教育とは何か?」この問題に関しては、古来、多くの思想家や教育学者によって、さまざまな定義がくだされてきた。しかしそれらは十入十色であって、決して一様でない。それは、究極的には、その人それぞれの世界観に依存するものだからである。そうだといって、教育の定義や概念を各人各様の考えのままの無政府的な規定や使用に委ねるならば、教育活動における混乱は避けられ得ないであろう。ここに、それらの全体を通じて流れる何ものか、それらに共通の、教育固有の (pädagogisch・eigentlich) 本質といったものを見出すことの必要な所以がある。このことに関して、エドウァルト・シュプランガーが、その著『教育学的展望』 (Eduard Spranger : Pädagogische Perspektiven. Beiträgezu Erziehungsfragen der Gegenwart 1950.) において展開した見解は、示唆するところすこぶる多いものと思われる。これを、他の諸著作にあらわれた彼の見解によって拡大・深化しながら、教育の本質概念ともいうべきものを探り出そうとするのが、この小論のねらいである。
1 0 0 0 OA シュプランガーの内面的学校改革について 戦後シュプランガー教育思想の一考察
- 著者
- 天野 正治
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.3, pp.60-77, 1960 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 49
This essay pressents some considerations on the post-war educational thinking of the renowned German scholar, Eduard Spranger. It is his theory of culture wich forms the background and the foundation of his post-war thinking. For the sake of convenience, this theory is divided into three parts : a general theory of culture ; criticism of modern culture ; criticism of the culture of west Germany. Modern culture, as Spranger sees it, is in a diseased state. He argues that it can be restored to a state of health through an improvement in its moral, legal, and political functioning, and to this end education for consientious living and for political activity based on a moral foundation must be carried on. If we look at school education from this point of view, we see that it must be thoroughly reformed ; and this is Spranger's contention. The concrete development of his theory is precisely his “theory of the inner renovation of the school.” Consequently, I have taken this expression of Spranger as the leit-motif of his post-war educational thought and traced its concrete development from the point of view of the objectives, the content, and the social aspects of education.
1 0 0 0 OA ルネ・ユベール「一般教育学」
- 著者
- 周郷 博
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.3, pp.78-79, 1960 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA ロバート・M・ハッチンズ「教育における葛藤」
- 著者
- 市村 尚久
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.3, pp.79-82, 1960 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 道徳的思考における言語記号の喚情的機能
- 著者
- 宇佐美 寛
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.2, pp.47-65, 1960-03-01 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 29
1 0 0 0 OA グァルディニーにおける教育学の基礎構造
- 著者
- 平野 智美
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.2, pp.66-76, 1960-03-01 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 29
1 0 0 0 OA アメリカ教育とジョン・デューイ
- 著者
- ブルーエット S・J
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.2, pp.77-80, 1960-03-01 (Released:2010-05-07)
1 0 0 0 OA ジョージ・F・ネラー「実存主義と教育」
- 著者
- 中嶋 博
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.2, pp.81-82, 1960-03-01 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA アメリカ教育哲学の現状
- 著者
- 新堀 通也
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.2, pp.83-85, 1960-03-01 (Released:2009-09-04)