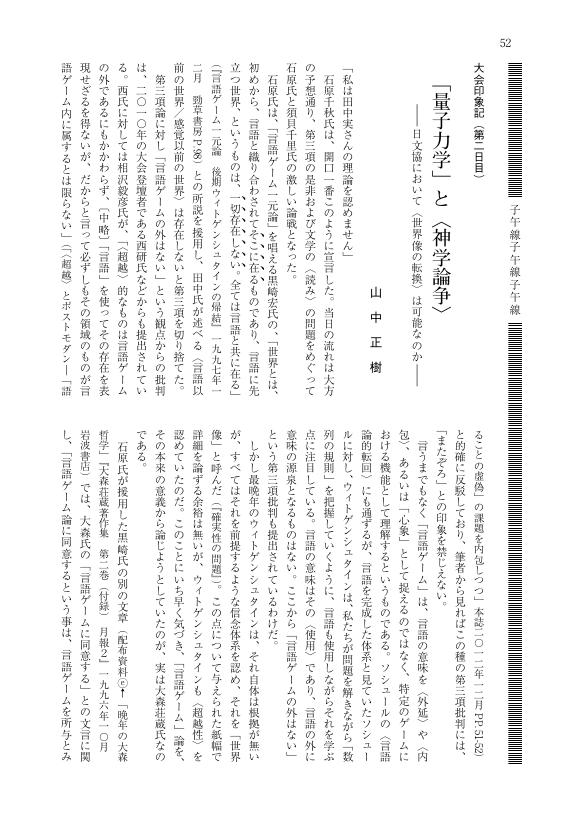2 0 0 0 OA 「地獄変」私論 : <語り>の詐術/<語り手>の裏切り
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 桜花学園大学
- 雑誌
- 桜花学園大学人文学部研究紀要 (ISSN:13495607)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.240-233, 2006-03-31
「地獄変は」、芥川龍之介の最高傑作のひとつとして、発表直後から高く評価されてきた。それは、所謂<主人公>良秀の「芸術の完成のためにはいかなる犠牲も厭わない」という姿勢が、芸術至上主義の徹底的追求という芥川自身の姿勢と絡めて論じられてきたからである。しかし「地獄変」の<語り手>の語りを詳細に分析してみると、それは決して良秀の芸術至上主義的姿勢だけを宣揚しょうというものでないことが判明する。むしろ<語り手>は、良秀を描くというよりは、「地獄変」屏風完成の逸話を語りながら、「堀川の大殿」の実態を暴こうとしていたと考えられる。すなわち「堀川の大殿」に「二十年来御奉公」してきた、「大殿」に臣従し、従順であるはずの<語り手>が、実は「大殿」を裏切り、表面的な言説とは裏腹にその悪辣さを糾弾していたのである。そのことにより、良秀の芸術至上主義的姿勢が極まったのである。本稿は<語り手>に注目する事で、新しいテクストの読みを提示した。
2 0 0 0 OA 「量子力学」と〈神学論争〉 ―― 日文協において〈世界像の転換〉は可能なのか ――
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.52-54, 2015-04-10 (Released:2020-05-26)
2 0 0 0 OA 文芸時代と川端康成
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 桜花学園大学
- 雑誌
- 桜花学園大学人文学部研究紀要 (ISSN:13495607)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.右十一-右二十二, 2009-03-31
2 0 0 0 OA 「文芸時代」と川端康成 : 川端康成の言語観〈二〉 : (承前)
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 桜花学園大学
- 雑誌
- 桜花学園大学人文学部研究紀要 (ISSN:13495607)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.154-144, 2011-03-31
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.8, pp.84-97, 2013-08-10 (Released:2018-08-06)
日文協第67回大会(第一日目)において加藤典洋氏は、テクスト論の立場から生ずる「ナンデモアリ」の読みに対する違和感を唱え、「〈第三項〉の理論とは、同じ出発点に立って」いるとしながらも、「読者と作品の関係性の一回性に基礎を置く文学理論」、「読者と作品のなかに浮上する」「作者の像」が、読者一人ひとりの「コレシカナイ性を作り上げる」という氏の「読書行為論」を提唱した。それは、第66回大会に登壇した竹田青嗣氏の唱える「一般言語表象」に触発されたものであるという。また加藤氏は、田中実氏の提唱する「第三項」を超越的なものであるとし、カントの「物自体」との類縁性を訴え、前年の竹田氏の講演内容にも示されたヘーゲルの説いた「事自体」との違いに関する議論に興味を示している(本誌二〇一三年三月号)。本稿ではまず、加藤氏の理論の背景となった竹田氏の「一般言語表象」について検討したい。その上で、〈第三項〉理論との違いを考えながら我々の読書行為を再検討し、〈第三項〉理論が拓く新たな「読み」の可能性を探っていきたいと思う。
1 0 0 0 IR 第三項論の意義に関する私論 ─その序説─
- 著者
- 山中 正樹 Masaki YAMANAKA
- 出版者
- 創価大学日本語日本文学会
- 雑誌
- 日本語日本文学 (ISSN:09171762)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.1-12, 2015-03-20
近代の日本文学研究においては、伝記研究の成果をもと\nに作家の思想信条を明らかにし、作品はその表現だと位置\nづける〈作家論〉が主流であった。その後、三好行雄の〈作\n品論〉が登場し、近代文学研究の中心的位置を占める。\n この三好〈作品論〉を打ち砕いたのが、R・バルトの理\n論であり、そこから生まれた〈テクスト論〉である。しか\nし日本における〈テクスト論〉は、バルトの理論の中核で\nあった〈還元不可能な複数性〉の意味を正しく理解せず、\nバルトが退けた〈容認可能な複数性〉の範疇に留まるもの\nであった。そのため、多数の〈読み(解釈)〉がすべて容\n認されるという、アナーキーな状況が生まれた。\n それに加え、21世紀を迎える前後に巻き起こった「国文\n学者の自己点検/反省」は、日本の近代文学研究の息の根\nを止めることとなる。ここにいたって「〈文学〉を研究す\nることも教えることも不毛/不可能である」という考えが\n蔓延し、研究の主流は〈文化研究〉に移行した。\n こうした状況の中で、〈文学(研究)〉の復権を目指すと\nともに、〈「読むこと」自体を問い直す〉原理論の構築を標\n榜して提出されたのが、田中実氏の第三項論である。第三\n項論とは〈主体〉と〈客体〉の二項に加え、〈客体そのもの〉\nという第三項を立てる「世界観認識」である。〈客体その\nもの〉とは私たちの認識の源泉ではあるが、決して私たち\nの感覚や言語では直接的には捉えられないものである。し\nかしその第三項を措定することで〈還元不可能な複数性〉\nを潜り抜け、世界を私たちの手に取り戻すことが可能になる。それは私たちの世界〈認識〉の在り様を根本から問い\n直すものであり、新たなる文学研究の領域を切り拓いたも\nのであるといえよう。
1 0 0 0 OA 川端康成の戦後・序説 : 川端康成と敗戦
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 桜花学園大学
- 雑誌
- 桜花学園大学研究紀要 (ISSN:13447459)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.A41-A51, 1999-03-31
敗戦と相次ぐ知己の死去は、川端康成に大きな衝撃を与えた。それは川端文学に一貫して描き続けられたテーマをより根源的なものへと深化させることになる。そのため戦後の川端文学は、表面的には戦前のそれと大きく相貌を異にすることとなった。しかし<呪縛>と<解放>という観点から作品を眺めたとき、川端文学を通底する基本的な構造が浮かび上がってくる。本稿ではまず「古典回帰」といわれた戦後の川端の出発をふまえた上で、戦後作品にもつながっていく初期作品の特徴について考察した。
1 0 0 0 銀平の変容 : 「みづうみ」における<時間>と<空間>
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 桜花学園大学
- 雑誌
- 桜花学園大学人文学部研究紀要 (ISSN:13495607)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.A29-A37, 2004-03-31
川端康成の「みづうみ」の独自性は、他の川端作品にはない「追跡者」(=<行為者>)としての主人公が描かれているという点にあると言われる。それゆえ「みづうみ」には、後期の川端の思想が如実に表れているのだと評価されて来た。しかし、「みづうみ」の意義はそこに留まるものではない。主人公銀平の意識の在り様とその変容こそが重要なのであり、それは作中の<時間>と<空間>の問題として考えることができる。本稿は、この<時間>と<空間>という観点から、銀平の意識の変容をとらえ、そこから「みづうみ」を再評価しようとするものである。
1 0 0 0 OA 「千羽鶴」論 : 「美」と「醜」との相克
- 著者
- 山中 正樹
- 出版者
- 桜花学園大学
- 雑誌
- 桜花学園大学研究紀要 (ISSN:13447459)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.A23-A37, 2001-03-31
「千羽鶴」は、戦後川端文学の中でも特に高い評価を得た作品である。発表直後から、川端のいわゆる「古典回帰宣言」の文脈の中で、日本の古典や伝統美を描いた作品であると論じられて来た。確かに「千羽鶴」には「美しい」ものが描かれている。しかし同時に「醜い」ものも「美」と同様、あるいはそれ以上に描き出されている。いままでの<読み>では、「醜」は「美」をきわだたせるための相対的要素であるという視点からの論及が多かった。しかしそれは「醜い」ものを「美しいもの」に転化する、あるいはそう見せてしまう川端の戦略によるものである。「千羽鶴」の基底部には「ちか子のあざ」という「醜い」ものが厳然としてあり、それが菊治の意識を<呪縛>すると同時に、読者の<読み>すらも支配しているのである。本稿は、そうした「醜」というコードから「千羽鶴」を読み直す試みである。