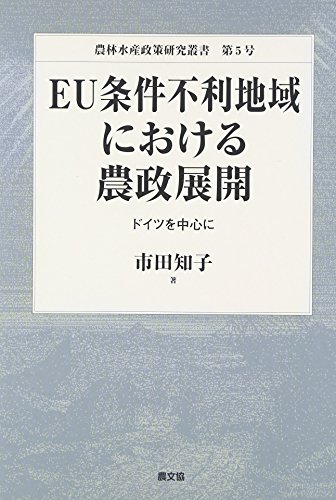5 0 0 0 OA 村落研究を問う 村研ジャーナルのこれまでの蓄積から
- 著者
- 芦田 裕介 市田 知子 松村 和則 望月 美希
- 出版者
- 日本村落研究学会
- 雑誌
- 村落社会研究ジャーナル (ISSN:18824560)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.13-44, 2021-10-25 (Released:2022-10-03)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1 1
2020 年度の日本村落研究学会大会では、「ジャーナルセッション」を企画した。これまで『村落社会研究ジャーナル』(以下『村研ジャーナル』)が担ってきた意義と役割を検討しながら、今後のジャーナルのあり方、ひいては村落研究のあり方を考えようというのがこのセッションの目的である。 いうまでもないことだが、本学会においては、農林漁業、農村、地域社会といった対象をめぐり学際的に研究が展開されてきた。つまり、研究対象に対する関心そのものは大きなところで共有されながらも、分析手法や問いの設定の仕方には多様性を有してきたということになる。イエ・ムラ論は本学会にとっては大きな意味を持つ理論設定ではあるのだが、必ずしもそれぞれの研究がその枠づけのなかにあったわけではない。そして『村研ジャーナル』では媒体の性質上、既存の議論の方法を超えて、先進的な研究の試みを展開されてきた。 ただ、学会を取り巻く事情は大きく変化している。投稿論文数の減少の要因にもなる大学院生数の減少、類似の研究を展開できる場となるような大小さまざまな学会の存在、大学等の研究機関における独自のプロジェクトや研究枠組みの創出といった動きのなかで、村研とはどのような問題関心や議論を共有する場なのかということを問われるべき時期にさしかかっている。もちろん、これは本学会に限ったことではなく、さまざまな学会や学問分野においても同様の事態に直面しており、少なくとも人文科学の諸領域においてそれぞれが問うていかねばならない問題でもある。 この「ジャーナルセッション」では、「村落研究」が、自明な領域であるかのようにみえながらも、それぞれの時代の要請や、広く学界の動向を背景に、問いの立て方の幅が転位/変容してきたことのたどり直しを試みた。この「問い」の転位/変容は、学がどうあるべきなのか、という問いとつながっている。いくつかの切り口から、これまでの『村研ジャーナル』の掲載論文を検証し、今後、どのような研究の展開があるべきで、そしてどのような関心を共有していくべきなのかを考える礎にしたい。 *日本村落研究学会では、1994 年から『村落社会研究』の刊行を開始し、第14 巻から『村落社会研究ジャーナル』と改題した。 この特集では、叙述が繁雑になることを避けるため、適宜『村研ジャーナル』の略称を用いることとする。
1 0 0 0 IR 原発事故避難者による営農再開と展望 : 福島県相馬郡飯舘村の事例分析
- 著者
- 福田 恭礼 市田 知子
- 出版者
- 明治大学農学部
- 雑誌
- 明治大学農学部研究報告 (ISSN:04656083)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1-21, 2017-02
2011年3月11日東日本大震災に伴う福島第一原発事故により福島県相馬郡飯舘村は,現在なお全村避難を強いられている。本稿では,飯舘村から避難し,その避難先で営農を再開している4つの事例に焦点を当てる。その上で,避難から営農再開までの経緯,および営農再開を可能にした要因を明らかにし,将来,帰村した際の地域の復興,営農再開の可能性を考察する。本稿の第一義的な意義は震災から5年余を経た現在,営農再開者の実態を記録することにある。環境社会学の被害構造概念を援用すると,原発被災者の置かれた状況は「個人化」であるとされる。飯舘村では,原発事故前には農家が約960世帯あったが,避難後の営農再開状況が把握できたのは約20世帯である。筆者らはそのうちの4つの事例の分析を行った。分析の結果,営農再開を可能にした要因として,個々の置かれた状況に合った営農タイプの選択,避難先での農地の確保,再開に当たって必要となる資金の確保,さらに損害賠償の4つが挙げられる。営農タイプの選択に際しては,非経済的要因も関わっている。帰村後,営農再開の可能性が高い部門は施設園芸(野菜,花卉),畜産(繁殖牛)であると推察される。飯舘村が今後,地域復興を実現するためには,長期的に農業を支援し,再建するための仕組みを作ることが重要である。それぞれの営農再開タイプに沿って,農地や資金面の支援,損害賠償を継続的に行う必要がある。研究の側としては,被災者が現在なお「個人化」した状況にあることを認識しつつ,継続的に注視していくことが重要である。
1 0 0 0 EU条件不利地域における農政展開 : ドイツを中心に
- 著者
- 市田知子著 農林水産省農林水産政策研究所編集
- 出版者
- 農山漁村文化協会
- 巻号頁・発行日
- 2004
1 0 0 0 OA 農村多角化経済活動の発展とその社会的成立基盤に関する地域間比較研究
農村経済多角化に資する経済活動の運営方式と、地域レベルの経済活動を下支えする社会的成立基盤との関係性を分析し、以下の諸点を明らかにした。(1)農産物直売所が開設されている農村社会では、高齢出荷者の社会活動レベルの低下および出荷活動の停滞がみられる一方、後発参入者が広域的な社会ネットワークを広げ、出荷活動にも積極的である。(2)多角化活動の実践は地域社会における経済循環を形成している。(3)政府による農商工等連携事業において、農業部門の自主的な参画・連携がみられない。(4)アイルランドで活発な地域支援組織LAGはプロジェクト方式で自主的に運営され、地域の利害関係者間に新たな協働をもたらしている。(5)アメリカの消費者直売型農業にかつてみられたオールタナティブ性が変化し、対面型コミュニケーションが希薄化している。