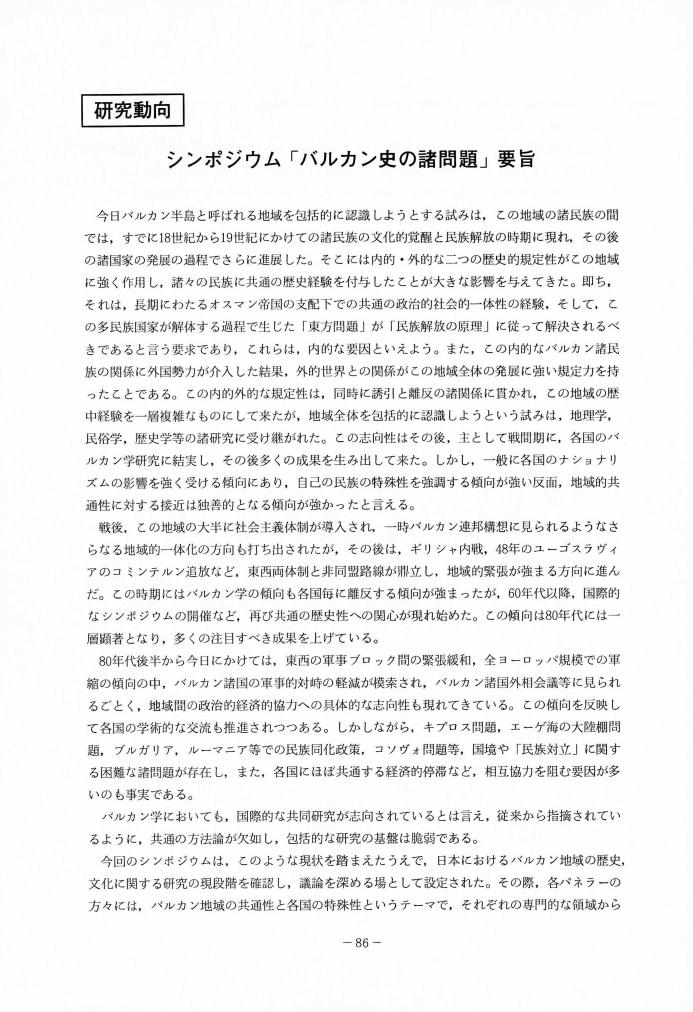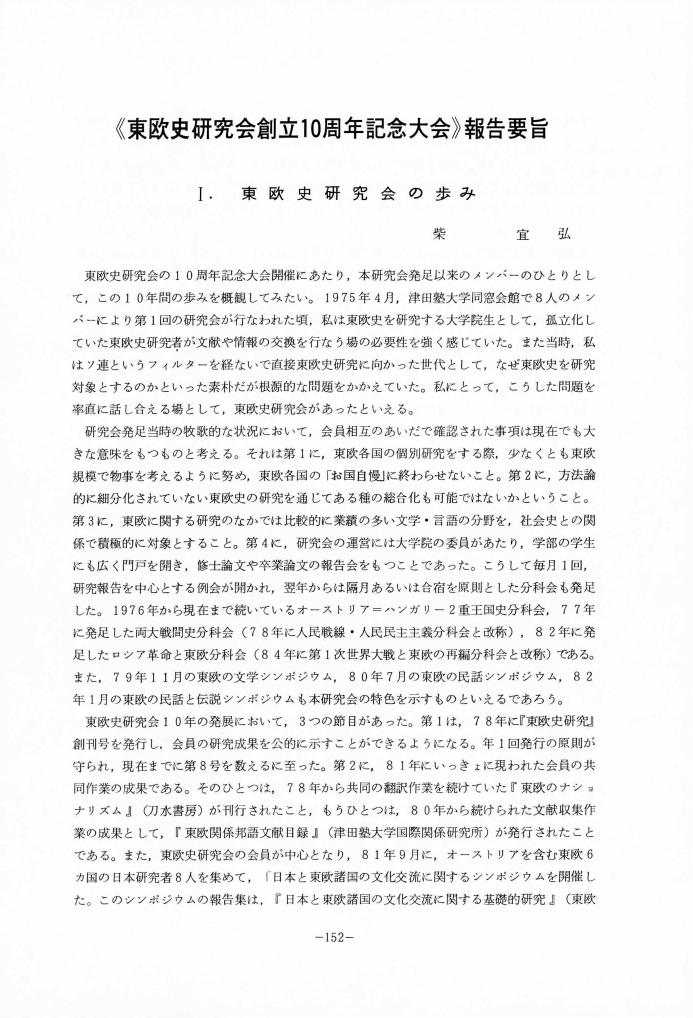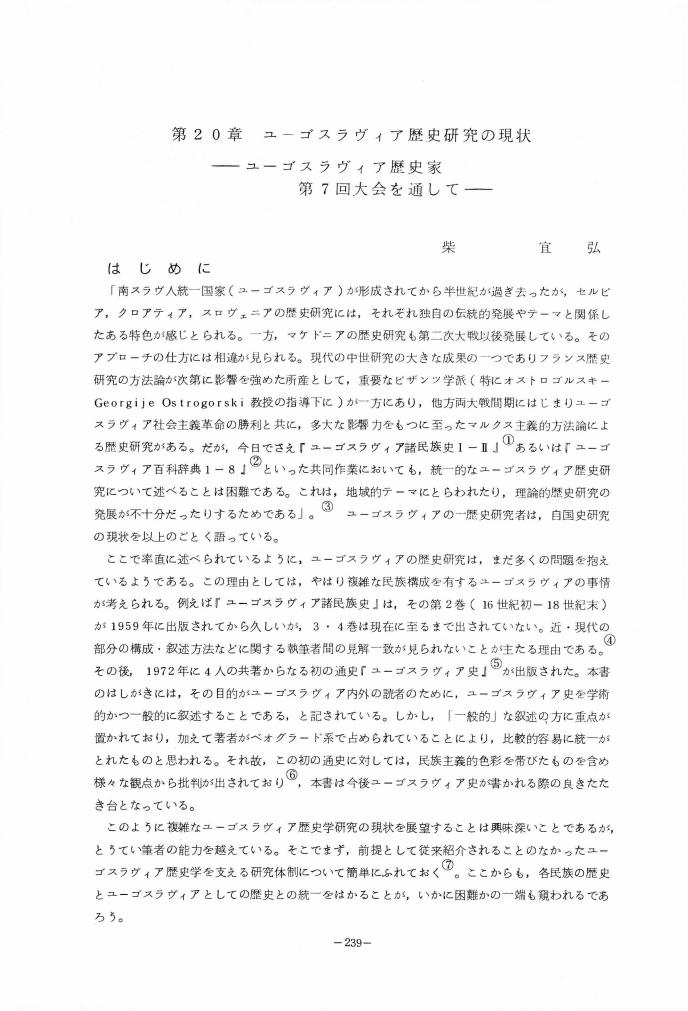3 0 0 0 OA 〈パネルディスカッション〉 歴史の中の体制転換
- 著者
- 塩川 伸明 柴 宜弘 田口 雅弘 望月 哲男
- 出版者
- The Japanese Association for Russian and East European Studies
- 雑誌
- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.39, pp.26-56, 2010 (Released:2012-06-20)
1 0 0 0 OA 近況報告──二足の草鞋
- 著者
- 柴 宜弘
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.37-40, 2012 (Released:2019-06-15)
1 0 0 0 OA 2001年度シンポジウム 歴史教育の中の「東欧」
1 0 0 0 OA シンポジウム「バルカン史の諸問題」要旨
1 0 0 0 OA 《東欧史研究会創立10周年記念大会》報告要旨
- 著者
- 柴 宜弘、ほか
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.152-172, 1986 (Released:2017-09-28)
1 0 0 0 OA ヴォイヴォディナの1848年革命に関する戦後の研究動向
- 著者
- 柴 宜弘
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.76-85, 1980 (Released:2017-09-28)
1 0 0 0 OA 第20章 ユーゴスラヴィア歴史研究の現状―ユーゴスラヴィア歴史家第七回大会を通して―
- 著者
- 柴 宜弘
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.239-248, 1978 (Released:2017-09-28)
1 0 0 0 OA 『ユーゴスラヴィア史』をめぐる諸問題―エクメチッチ、グロス論争とその背景
- 著者
- 柴 宜弘
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.43-57, 1979 (Released:2017-09-28)
1 0 0 0 1918-19年像の再構築―継続と変容―
- 著者
- 大津留 厚 柴 理子 桐生 裕子 野村 真理 家田 修 篠原 琢 佐藤 雪野 馬場 優 柴 宜弘 辻河 典子 森下 嘉之 飯尾 唯紀 村上 亮 ボシティアン ベルタラニチュ 米岡 大輔
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2017-04-01
1939年9月4日、アメリカ合衆国の週刊誌『タイム』はその前の週の9月1日にドイツ軍がポーランドに侵攻したのを受けて、「第二次世界大戦が始まった」と報じた。この時、「その前の戦争」が第一次世界大戦の名を与えられることになったと言える。その意味での第一次世界大戦が始まるきっかけになったのは、ハプスブルク家を君主とする諸領邦が最終的に名乗ったオーストリア=ハンガリーが、隣国セルビアに対して、ハプスブルク君主の継承者の暗殺の責を問うて宣戦を布告したことにあった。そしてその戦争を終えるための講和会議が開かれた時、すでにこの国は講和会議に代表される存在であることを止めていた。したがってこの戦争はこの国にとっては「最後の戦争」に他ならなかった。1914年からあるいはその前から始まった、ヨーロッパを主な戦場とする戦争を何と呼ぶのか、これがそれから100年経ったときに問われている。そして呼び方の問題はその戦争の継続した期間の捉え方と関係し、またその後の世界の把握の方法とも関係している。本科研ではセルビア共和国の代表的な現代史研究者ミラン・リストヴィッチ教授を招き、また研究代表者がウィーンで開催された1918年の持つ意味を再考するシンポジウムに参加して国際的な研究動向を踏まえながら、分担者がそれぞれ研究を進めてきた。その成果は2019年5月に静岡大学で開催される西洋史学会の小シンポジウムで発表されることになる。そこでは研究代表者が趣旨説明を行い、「国境の画定」、「制度的連続性と断絶」、「アイデンティティの変容」それぞれの班から報告が行われる。
20世紀末に近代の産物である「国民国家」を否定する方向でヨーロッパ統合という試みがなされる一方、旧ソ連・東欧諸国においては、ソ連の解体し、「東欧革命」のあと、逆に「国民国家」として新たな国家統合を試みる動きがはじまり、各地で紛争が生じている。本研究はこうした状況を踏まえ、それ自体多様な歴史的内実を有するドイツ理念とヨーロッパ理念の相関関係という問題を、特に20世紀における展開を中心に、今日的視点で整理することを目的とした。そして、ドイツを中心としつつも、歴史的にはギリシア、ラテン文化・思想の伝統を踏まえ、地域的には周辺諸地域、とりわけ旧東欧、ソ連諸国との関わりのなかで、ヨーロッパ統合の時代における新たなドイツ理念の展開を研究していった。その結果、19世紀のドイツ・ロマン主義や20世紀初頭のドイツにおける民族主義がその周辺諸地域に大きな影響を与えたこと、こうした地域、とりわけバルカン諸国においては、この影響下で作り上げられた民族的な神話と、それに基づく人々の集団的な記憶と強力なナショナリズムが今日に至るまでなお力を持ち続けていることが確認できた。さらに、国法学者カール・シュミットに中心を当てた共同研究も行ない、この思想家が汎カトリックの思想基盤に立つヨーロッパ有数の思想家であると同時に、その活躍した時代がナチズムの時代に当たり、ヒトラーの桂冠法学者としての20世紀におけるドイツとヨーロッパの理念の相関関係を体現する思想家であることが浮かび上がってきた。また、ミュンヒェン・シュヴァービングを震源地とする母権思想はシュミット自信も自覚していたように、彼の男性的父権的政治思想の対極をなしていること、ベルリンを本拠とする男性同盟的ドイツという思想とミュンヒェンの母権思想の対比が20世紀初頭のドイツにおけるヨーロッパ理念の対極であることなども明確になった。