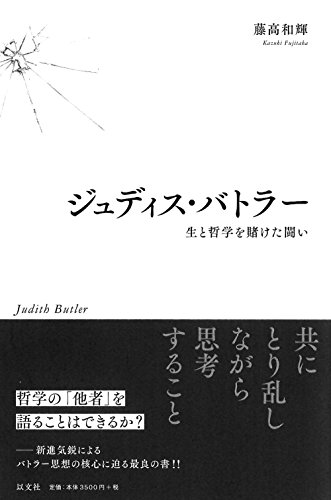41 0 0 0 OA アイデンティティを引き受ける : バトラーとクィア/ アイデンティティ・ポリティックス
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学 (ISSN:13499904)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.23-41, 2015-03-31
27 0 0 0 IR ポストフェミニズムとしてのトランス?――千田有紀「「女」の境界線を引きなおす」を読み解く
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- お茶の水女子大学ジェンダー研究所
- 雑誌
- ジェンダー研究 : お茶の水女子大学ジェンダー研究所年報
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.171-187, 2021-07-31
本論文は、千田有紀の論考「 女の境界線を引きなおす」 を批判的に読み解くことを通して、現代の日本社会におけるトランス排除的言説の構造を明らかにすることを試みるものである。千田の論考は 2020年3月に出版された『現代思想』臨時増刊号「フェミニズムの現在」に掲載されるや否や、トランス当事者を含めた多くの人たちからトランス排除的な論考であると批判され、物議を醸したものである。本稿では、千田の論考を読解することを通して、その背後にあるトランスフォビックな認識論的枠組みを明らかにする。その枠組みとは「ポストフェミニズムとしてのトランス」という図式である。そして、その図式が千田個人だけではなく「トランス排除的ラディカル・フェミニズム」に広く共有されている可能性を提起する。以上を通して、現在のフェミニズムが抱える問題点を浮き彫りにし、インターセクショナルな視点をもったトランス・インクルーシブなフェミニズムの必要性を主張する。
7 0 0 0 OA 感じられた身体―トランスジェンダーと『知覚の現象学』
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 立命館大学人文科学研究所
- 雑誌
- 立命館大学人文科学研究所紀要 = Memoirs of the Research Institute of the Cultural Sciences of Ritsumeikan University (ISSN:02873303)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, pp.217-232, 2019-12
6 0 0 0 IR 現象学からフーコーへ : 初期ジュディス・バトラーにおける身体論の変遷
- 著者
- 藤高 和輝 フジタカ カズキ Fujitaka Kazuki
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.103-117, 2015-03-31
本稿は、J・バトラーの一九八〇年代における身体論を考察する。バトラーの代名詞といえる『ジェンダー・トラブル』における理論的観点は一挙に形成されたわけではない。それは八〇年代における思索を通じて、ゆっくりと形成されたのである。八〇年代のバトラーにとって、第一義的な問題は身体であり、ジェンダーもそのような思索の延長にある。身体とは何か、身体の問題にいかにアプローチすべきかという問題は、八〇年代のバトラーを悩ませた大きな問題であった。この問題へのアプローチは八〇年代を通じて、「現象学からフーコーへ」の移行として描くことができる。逆にいえば、現象学との対決は『ジェンダー・トラブル』におけるバトラーの理論を生み出すうえでひじょうに重要な契機だった。本稿では、私たちはバトラーの思索において現象学が果たした役割を明らかにし、それがいかにフーコーの系譜学へと移行するかを示したい。This paper examines Judith Butler's thought regarding the body in the 1980s. Her theoretical perspective in Gender Trouble (1990) which has become a synonym for Butler, was not created at once. It was gradually formed thorough her speculations during the 1980s. In this paper, we show how her theory in Gender Trouble had been created through her thought in the 1980s. For Butler in the 1980s, the primary problem is the body, where gender is a facet of the problem. What is the body? How should we approach the body? These questions are the problems Butler engages in the 1980s. We can trace her approach to the body in the 1980s as the turn "from phenomenology to genealogy." In turn, her confrontation with phenomenology played a very important part in the establishment of her theory in Gender Trouble. Butler fi rst found phenomenology a method for approaching the body, redefining genealogy as theorized by Foucault, thorough her later critique of phenomenology, at least in 1989. In this paper, we illustrate the role played by phenomenology in Butler's thought in the 1980s, and how she shifts from phenomenology to genealogy.
5 0 0 0 IR ジュディス・バトラーにおけるスピノザの行方(上)「社会存在論」への道
- 著者
- 藤高 和輝 フジタカ カズキ Fujitaka Kazuki
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.163-180, 2013
ジュディス・バトラーがスピノザの熱心な読者であるということはあまり知られていない。しかし、スピノザは彼女にとってきわめて重要な思想家である。実際、彼女は『ジェンダーをほどく』(2004)で「スピノザのコナトゥス概念は私の作品の核心でありつづけている(198 頁)」と述べている。本論はこの言葉の意味を明らかにしようとするものである。バトラーがスピノザの『エチカ』に最初に出会ったのは思春期に遡る。その後、彼女はイェール大学の博士課程でヘーゲルを通して間接的にスピノザと再会する。この二番目の出会いは、彼女の学位論文『欲望の主体』(1987)を生み出すことになる。最後に、このスピノザからヘーゲルへの移行によって、彼女は「社会存在論」を確立することができた。バトラーの著作におけるスピノザのコナトゥス概念に着目することで、私はこれらの運動を明らかにするだろう。そして、このような考察を通して、バトラーの思想においてコナトゥス概念が持つ意味も明らかになるだろう。It is not well known that Judith Butler is an avid reader of Spinoza. However, Spinoza is a very important philosopher for her. Indeed, she said in Undoing Gender (2004) "the Spinozan conatus remains at the core of my own work (p.198)." This paper tries to elucidate the meaning of this sentence. Butler rst encountered Spinoza's Ethics during her adolescence. Afterwards, she indirectly met Spinoza again through Hegel during her doctoral studies at Yale University. This second encounter led to the production of her dissertation, Subjects of Desire (1987). Finally, by this journey from Spinoza to Hegel, she could establish "social ontology." I will make these movements clear by paying attention to the Spinozan conatus in Butler's works and we can understand what is meant by conatus in Butler's thought.
4 0 0 0 OA ジュディス・バトラーにおけるスピノザの行方(上) : 「社会存在論」への道
- 著者
- 藤高 和輝 Fujitaka Kazuki フジタカ カズキ
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.163-180, 2013-03-31 (Released:2013-03-31)
ジュディス・バトラーがスピノザの熱心な読者であるということはあまり知られていない。しかし、スピノザは彼女にとってきわめて重要な思想家である。実際、彼女は『ジェンダーをほどく』(2004)で「スピノザのコナトゥス概念は私の作品の核心でありつづけている(198 頁)」と述べている。本論はこの言葉の意味を明らかにしようとするものである。バトラーがスピノザの『エチカ』に最初に出会ったのは思春期に遡る。その後、彼女はイェール大学の博士課程でヘーゲルを通して間接的にスピノザと再会する。この二番目の出会いは、彼女の学位論文『欲望の主体』(1987)を生み出すことになる。最後に、このスピノザからヘーゲルへの移行によって、彼女は「社会存在論」を確立することができた。バトラーの著作におけるスピノザのコナトゥス概念に着目することで、私はこれらの運動を明らかにするだろう。そして、このような考察を通して、バトラーの思想においてコナトゥス概念が持つ意味も明らかになるだろう。 It is not well known that Judith Butler is an avid reader of Spinoza. However, Spinoza is a very important philosopher for her. Indeed, she said in Undoing Gender (2004) “the Spinozan conatus remains at the core of my own work (p.198).” This paper tries to elucidate the meaning of this sentence. Butler rst encountered Spinoza’s Ethics during her adolescence. Afterwards, she indirectly met Spinoza again through Hegel during her doctoral studies at Yale University. This second encounter led to the production of her dissertation, Subjects of Desire (1987). Finally, by this journey from Spinoza to Hegel, she could establish “social ontology.” I will make these movements clear by paying attention to the Spinozan conatus in Butler’s works and we can understand what is meant by conatus in Butler’s thought.
4 0 0 0 OA 普遍の主張 : J・バトラーにおける「共生」のポリティックス
- 著者
- 藤高 和輝 フジタカ カズキ Fujitaka Kazuki
- 出版者
- 大阪大学未来戦略機構第五部門未来共生イノベーター博士課程プログラム
- 雑誌
- 未来共生学
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.205-227, 2015-03-20
3 0 0 0 OA J・バトラーのジェンダー・パフォーマティヴィティとそのもうひとつの系譜
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 国際基督教大学ジェンダー研究センター
- 雑誌
- Gender and Sexuality (ISSN:18804764)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.183-204, 2017-03-31
Gender performativity is the most famous and influential theory in Judith Butler. It questioned the sex/ gender distinction which some feminists took for granted at that time when Gender Trouble (1990) was published. This distinction regarded sex as the natural category on the one hand, gender as the cultural expression of sex on the other hand. It means naturalizing the dualistic representation of gender. On the contrary, Butler's performative theory suggested that sex is not a natural category, but is a fiction which is constructed by repeating gender performances. Through denaturalizing gender, her theory criticizes the representation of gender/ sexual minorities as "unnatural" and "abnormal," and seeks to theorize the way to make their survival possible. This paper examines how gender performativity was theorized from the 1980s to Gender Trouble. Interestingly, her performative theory cannot be reduced to speech act theory, but it was also formed in relation to other theories; feminist/ queer theory and performance theory. Indeed, in her article "Performative Act and Gender Constitution" (1988) in which she referred to "performative" at first, Butler started from Simone de Beauvoir's text, The Second Sex, and then reread Beauvoir's idea of "gender as act" as "social performance" in performance theory. Moreover, she extended Beauvoir's argument of denaturalizing sex, referring to Gayle Rubin's study of kinship, Monique Wittig's theory of sex, and Esther Newton's analysis of Drag Queen. Thus, her performative theory is found not only in the context of speech act theory, but also in contexts of feminist/ queer theory and performance theory. From this genealogical perspective, this article seeks to rethink gender performativity.
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 国際基督教大学ジェンダー研究センター
- 雑誌
- Gender and sexuality : journal of Center for Gender Studies, ICU = ジェンダー&セクシュアリティ : 国際基督教大学ジェンダー研究センタージャーナル (ISSN:18804764)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.183-204, 2017
- 著者
- エーデルマン リー 藤高 和輝
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 思想 (ISSN:03862755)
- 巻号頁・発行日
- no.1141, pp.107-126, 2019-05
2 0 0 0 IR 普遍の主張 : J・バトラーにおける「共生」のポリティックス
- 著者
- 藤高 和輝 Fujitaka Kazuki フジタカ カズキ
- 出版者
- 大阪大学未来戦略機構第五部門未来共生イノベーター博士課程プログラム
- 雑誌
- 未来共生学
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.205-227, 2015-03-20
2 0 0 0 IR へーゲル的主体のメランコリー : 『欲望の主体』におけるバトラーのヘーゲル解釈とその展開
- 著者
- 藤高 和輝 Fujitaka Kazuki フジタカ カズキ
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.71-86, 2016-03-31
Judith Butler is well known as a feminist and queer theorist. Also, her thought is understood to have been infl uenced by poststructuralism. However, her philosophical background also includes Hegelian philosophy. Indeed, her academic career started from a study of Hegel, which was published as Subjects of Desire: Hegelian Refl ections in 20th Century France (1987). In this sense, it can be said that Hegelianism is an indispensable to comprehending her thought. Thus, we must elucidate how Butler interprets Hegel, and how her Hegelian background is linked to her own theory from Gender Trouble (1990) on. Therefore, this article examines Butler's Hegelianism, focusing on a reading of Subjects of Desire. From the fi rst to third sections, I clarify the "Hegelian subject" Butler describes in Subjects of Desire. In the fourth section, I prove that the Hegelian subject is structuralized by melancholy. Through these discussions, I would like to suggest a connection between Butler's early work on Hegel and her theory of melancholy after Gender Trouble.ジュディス・バトラーは『ジェンダー・トラブル―フェミニズムとアイデンティティの転覆』(1990年)の出版によってフェミニスト/クィア理論家として知られ、またその思想はポスト構造主義に連なるものとして理解されている。しかし、バトラーの思想的バックグラウンドはヘーゲル哲学にある。バトラーのキャリアはヘーゲル哲学研究に始まり、へーゲル哲学を扱った彼女の博士論文は一九八七年に『欲望の主体―二〇世紀フランスにおけるヘーゲル哲学の影響』として出版されることになる。この意味で、「バトラーのへーゲル主義」は彼女の思想を理解する上で欠くことのできない視角である。したがって、『欲望の主体』におけるバトラーのヘーゲル解釈がどのようなものであり、それが『ジェンダー・トラブル』以後のバトラー自身の思想にどのような影響を与えたのかが考察されなければならない。そこで本稿では、バトラーの『欲望の主体』を中心に「バトラーのへーゲル主義」を考察する。第一節から第三節では、バトラーが描く「へーゲル的主体」とは何かを明らかにする。第四節では、バトラーが提示した「ヘーゲル的主体」がメランコリーの構造をもつものであることを論証する。それによって、初期のへーゲル論と『ジェンダー・トラブル』以後のメランコリー論の架橋を図りたい。
2 0 0 0 OA へーゲル的主体のメランコリー : 『欲望の主体』におけるバトラーのヘーゲル解釈とその展開
- 著者
- 藤高 和輝 フジタカ カズキ Fujitaka Kazuki
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.71-86, 2016-03-31
ジュディス・バトラーは『ジェンダー・トラブル―フェミニズムとアイデンティティの転覆』(1990年)の出版によってフェミニスト/クィア理論家として知られ、またその思想はポスト構造主義に連なるものとして理解されている。しかし、バトラーの思想的バックグラウンドはヘーゲル哲学にある。バトラーのキャリアはヘーゲル哲学研究に始まり、へーゲル哲学を扱った彼女の博士論文は一九八七年に『欲望の主体―二〇世紀フランスにおけるヘーゲル哲学の影響』として出版されることになる。この意味で、「バトラーのへーゲル主義」は彼女の思想を理解する上で欠くことのできない視角である。したがって、『欲望の主体』におけるバトラーのヘーゲル解釈がどのようなものであり、それが『ジェンダー・トラブル』以後のバトラー自身の思想にどのような影響を与えたのかが考察されなければならない。そこで本稿では、バトラーの『欲望の主体』を中心に「バトラーのへーゲル主義」を考察する。第一節から第三節では、バトラーが描く「へーゲル的主体」とは何かを明らかにする。第四節では、バトラーが提示した「ヘーゲル的主体」がメランコリーの構造をもつものであることを論証する。それによって、初期のへーゲル論と『ジェンダー・トラブル』以後のメランコリー論の架橋を図りたい。
2 0 0 0 OA 現象学からフーコーへ : 初期ジュディス・バトラーにおける身体論の変遷
- 著者
- 藤高 和輝 フジタカ カズキ Fujitaka Kazuki
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.103-117, 2015-03-31
本稿は、J・バトラーの一九八〇年代における身体論を考察する。バトラーの代名詞といえる『ジェンダー・トラブル』における理論的観点は一挙に形成されたわけではない。それは八〇年代における思索を通じて、ゆっくりと形成されたのである。八〇年代のバトラーにとって、第一義的な問題は身体であり、ジェンダーもそのような思索の延長にある。身体とは何か、身体の問題にいかにアプローチすべきかという問題は、八〇年代のバトラーを悩ませた大きな問題であった。この問題へのアプローチは八〇年代を通じて、「現象学からフーコーへ」の移行として描くことができる。逆にいえば、現象学との対決は『ジェンダー・トラブル』におけるバトラーの理論を生み出すうえでひじょうに重要な契機だった。本稿では、私たちはバトラーの思索において現象学が果たした役割を明らかにし、それがいかにフーコーの系譜学へと移行するかを示したい。
2 0 0 0 OA ジュディス・バトラーにおけるスピノザの行方(上) : 「社会存在論」への道
- 著者
- 藤高 和輝 フジタカ カズキ Fujitaka Kazuki
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.163-180, 2013-03-31
ジュディス・バトラーがスピノザの熱心な読者であるということはあまり知られていない。しかし、スピノザは彼女にとってきわめて重要な思想家である。実際、彼女は『ジェンダーをほどく』(2004)で「スピノザのコナトゥス概念は私の作品の核心でありつづけている(198 頁)」と述べている。本論はこの言葉の意味を明らかにしようとするものである。バトラーがスピノザの『エチカ』に最初に出会ったのは思春期に遡る。その後、彼女はイェール大学の博士課程でヘーゲルを通して間接的にスピノザと再会する。この二番目の出会いは、彼女の学位論文『欲望の主体』(1987)を生み出すことになる。最後に、このスピノザからヘーゲルへの移行によって、彼女は「社会存在論」を確立することができた。バトラーの著作におけるスピノザのコナトゥス概念に着目することで、私はこれらの運動を明らかにするだろう。そして、このような考察を通して、バトラーの思想においてコナトゥス概念が持つ意味も明らかになるだろう。
もともとの研究計画をほとんど達成し、且つこれまでの研究成果をほぼ公表することができた。とりわけ、ゲイル・サラモン『身体を引き受ける――トランスジェンダーと物質性のレトリック』(以文社)の翻訳出版を達成できたことが大きな成果である。他には、「感じられた身体--トランスジェンダーと『知覚の現象学』」(立命館大学人文科学研究所紀要)、「「曖昧なジェンダー」の承認に向けて――ボーヴォワール『第二の性』における「両義性=曖昧性」」(『女性空間』)、「インターセクショナル・フェミニズムから/へ」(『現代思想』)など、多くの論文を公表する機会を得た。以上を通して、トランスジェンダーの「生きられた経験」を哲学的に研究する「トランスジェンダー現象学」の導入・深化を行った。トランスジェンダーの経験をよりリアルに捉える分析枠組みを提示することで、「哲学・倫理学」の学問分野のみならず、社会学や心理学、ジェンダー・スタディーズ、クィア理論などより広い分野に貢献することができたと自負している。今後は、特別研究員のあいだに行った研究を一冊の書籍にまとめ、研究成果をさらに社会に発信・公表していきたい。
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 日仏女性資料センター
- 雑誌
- 女性空間 = Espace des femmes (ISSN:13436732)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.81-92, 2019
1 0 0 0 ジュディス・バトラー : 生と哲学を賭けた闘い
1 0 0 0 IR J・バトラーのジェンダー・パフォーマティヴィティとそのもうひとつの系譜
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 国際基督教大学ジェンダー研究センター
- 雑誌
- Gender and sexuality : journal of Center for Gender Studies, ICU = ジェンダー&セクシュアリティ : 国際基督教大学ジェンダー研究センタージャーナル (ISSN:18804764)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.183-204, 2017
Gender performativity is the most famous and influential theory in Judith Butler. It questioned the sex/ gender distinction which some feminists took for granted at that time when Gender Trouble (1990) was published. This distinction regarded sex as the natural category on the one hand, gender as the cultural expression of sex on the other hand. It means naturalizing the dualistic representation of gender. On the contrary, Butler's performative theory suggested that sex is not a natural category, but is a fiction which is constructed by repeating gender performances. Through denaturalizing gender, her theory criticizes the representation of gender/ sexual minorities as "unnatural" and "abnormal," and seeks to theorize the way to make their survival possible. This paper examines how gender performativity was theorized from the 1980s to Gender Trouble. Interestingly, her performative theory cannot be reduced to speech act theory, but it was also formed in relation to other theories; feminist/ queer theory and performance theory. Indeed, in her article "Performative Act and Gender Constitution" (1988) in which she referred to "performative" at first, Butler started from Simone de Beauvoir's text, The Second Sex, and then reread Beauvoir's idea of "gender as act" as "social performance" in performance theory. Moreover, she extended Beauvoir's argument of denaturalizing sex, referring to Gayle Rubin's study of kinship, Monique Wittig's theory of sex, and Esther Newton's analysis of Drag Queen. Thus, her performative theory is found not only in the context of speech act theory, but also in contexts of feminist/ queer theory and performance theory. From this genealogical perspective, this article seeks to rethink gender performativity.