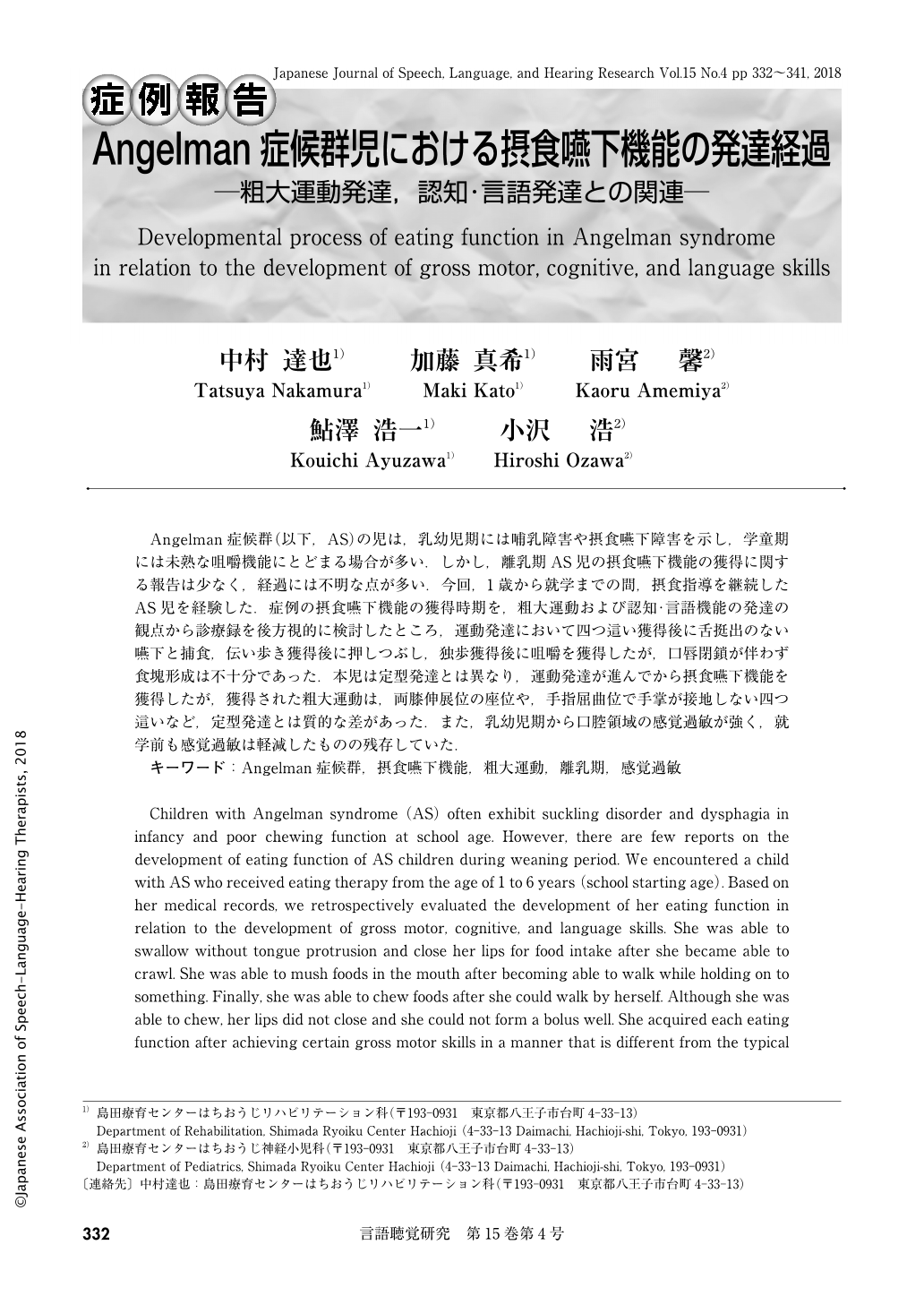6 0 0 0 OA 難治性てんかん患者にケトン食を導入した症例について
- 著者
- 青山 有紀 雨宮 馨 星 博子 村越 孝次 輿水 三枝子
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.703-707, 2015 (Released:2015-04-20)
- 参考文献数
- 6
重度の脳性麻痺で難治性てんかん児へのケトン食療法を消化態栄養剤からエネルギー、水分量等を調整しながら徐々にケトンフォーミュラミルク®へ移行した。それと併せて、不足するビタミン・ミネラル類についてサプリメントを使用して、ケトン食療法を有効かつ安全に導入し、けいれん発作を軽減することができた2症例について報告する。
2 0 0 0 OA 神経発達症児における血清亜鉛値の検討
- 著者
- 井之上 寿美 河野 芳美 河野 千佳 白木 恭子 塩田 睦記 雨宮 馨 中村 由紀子 杉浦 信子 小沢 愉理 北 洋輔 小沢 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.356-358, 2022 (Released:2022-10-13)
- 参考文献数
- 10
神経発達症児の血清亜鉛値について健常児の参照値と比較検討した.血清亜鉛値を測定した学齢期の神経発達症児63名(男児49名,女児14名)を患者群とし,先行研究において年齢分布が一致する380名の健常児のデータを用いて解析を行った.その結果,患者群のうち19名(30%)が亜鉛欠乏症,また39名(62%)が潜在性亜鉛欠乏,亜鉛値正常は5名(8%)であり,血清亜鉛値は健常児の参照値と比較して有意に低値であった(p<0.001).患者群の診断内訳では,ADHD(36名,54%)と自閉スペクトラム症(22名,39%)の2疾患が大部分を占めたものの,血清亜鉛値は疾患間で有意な差はなく(p=0.32),性差も認められなかった(p=0.95).神経発達症児は亜鉛欠乏傾向にあると考えられ,疾患や性別による血清亜鉛値の明らかな違いはなかった.
2 0 0 0 OA 在宅での重症心身障害児者のアドバンス・ケア・プランニング
- 著者
- 雨宮 馨
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.238, 2018 (Released:2021-01-21)
重症心身障害児者(以下、重症児者)のアドバンス・ケア・プランニング(以下、ACP)は、がん患者と違い、急変の予測が困難であり行うべき適切な時期を見定めるのが難しい。成人在宅医療の現場でも、緩徐な進行をたどる神経疾患のACPは必ずしも行われていない現状がある。 しかし、実際に在宅療養している重症児者が急変し重篤な状態に陥ると、急性期病院で初めて会う医師から厳しい話を突然受けることになる。医師から事前に重篤な状態に陥る可能性を告げられていなかった場合、家族は「こんなことになるとは思わなかった」と当然混乱するであろう。急性期治療に従事する医師の負担感も大きく、「普段関わる医師が適切に病状を事前に伝えておいてほしい」といった希望が聞かれる。 重症児者の経過は乳幼児期の大変な時期を乗り越えると経過が緩徐であり、家族は身体に様々な問題のある状態を当たり前として受け入れながらともに生活していくため、家族の病識が薄れやすいといえる。ACPと構えて行うことは医療者にとって負担感のあることかもしれないが、重症児者のACPとして大切な一歩は、まず患者の現在の病状について家族と共有することである。 重症児者のACPの課題として、代理意思決定の問題が存在する。在宅医療では自宅に訪問するため、患者本人の病状のみならず、本人の療養環境や家族背景、教育や福祉の介入状況などが把握でき、それらを交えて関わるので、家庭の中での「○○くん/ちゃんとは」という患者の存在を共有しやすい。この子とどう過ごしたいかといった親の実際の希望を聞くことも多く、周囲の状況を交えながら、患者にとっての最善の利益を考えながら診療に反映することが可能といえる。ただ、患者の存在について共有するには時間が必要であり、在宅期間が短い乳幼児はACPが非常に難しいといえる。 家族が介護する中で抱える希望や不安に触れる機会も多い。在宅医療の依頼を受ける重症児者は医療的ケアが多く、介護者である親は子どもが急にSpO2が下がり顔色が悪くなったといったような命の危機を感じさせられる経験することも多い。自宅では実際に急変に家族のみで対応しなくてはいけないため、心肺停止といった状態に至った場合は実際に対応は困難といえる。在宅医療では終末期の緩和も含め自宅での看取りに対応することも可能であり、家族と関係をある程度築き情報提供した上で、実際にわが子が死に直面する状況に至った場合にどのようにしたいか、入院してどのような治療を受けたいのか、自宅で穏やかに過ごしたいのかといった方向性をある程度確認することも努力している。ACPとして、①本人の病状とそれに対し今後起こりうることと対応方法、②死に直面した状態の際には自宅でできる終末期の緩和方法や心肺蘇生についてといった内容を具体的に説明し、親の子どもに対する人生観や死生観、希望を踏まえ、どのような医療を望み、医療を受けどう生きてほしいのかをともに考えていく必要がある。 外来診療でのACPは、患者が肺炎等で入院し回復した後や知り合いの死などをきっかけに行っている。重症者の場合は長い年月を患者と過ごしており、介護している家族も年齢を重ねているため、適切な医療情報を提供すれば本人にどう生きてほしいかを語ってくださる方が多い。急変時は他院に運ばれることになるため、家族が悩んだ末に侵襲的な高度医療を望まないという場合には、十分に患者の病状を理解した上で家族が選択したことがわかるような意思表示の書類やカードを家族とともに作成し、急変の際に少しでも意向が反映されるよう支援している。 セミナーでは上記のことを踏まえ、①実際のACPのタイミングや方法について、②ACPの実際の難しさ、③DNARの意思表示支援カードについて、④ACPを事前に行い急変に至った事例等についてお話する予定である。 略歴 新潟大学医学部卒業 小児科専門医 東京大学医学部付属病院小児科、亀田総合病院小児科、都立小児総合医療センター神経内科等勤務後、島田療育センターはちおうじ(島はち)で障害児医療に従事し、現在はさいわいこどもクリニック在宅診療部で小児在宅診療を行い、島はちの療育外来で診療を行っている。
- 著者
- 冨田 直 生田 陽二 三山 佐保子 雨宮 馨
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.242, 2016
はじめにオピオイドは非癌患者の呼吸困難に対しても効果があるとされる。今回、呼吸苦緩和および呼吸負荷軽減の治療の両方の目的でモルヒネを使用し、治療困難な肺炎から回復した症例を経験したので報告する。症例症例は8歳男児。原病は脳性麻痺・慢性肺疾患。在胎23週出生体重572gの超低出生体重児と脳室内出血による後遺症で大島分類1の重症心身障害児となった。1歳1カ月で新生児病棟退院後、呼吸不全を伴う下気道炎を繰り返し5歳時に単純気管切開を施行されている。その後、主治医と家族で急変時の対応について話し合い、人工呼吸器装着はしない方針となった。今回RSV感染による最重度の呼吸不全を伴う肺炎を発症し入院。事前の決定事項を家族に再度確認の上、方針に従いステロイド投与、RTXレスピレーター、肺理学療法、持続吸入等最大限の治療を行った。しかし、低酸素血症の進行を認め、治療継続による回復は困難と判断。入院4日目にICUに入室し、集中治療科の協力を得て治療と緩和両方の目的でモルヒネ持続点滴(0.4mg/kg/day)を開始した。病状はその後も進行し開始3日目にはSaO2のベースが40-60%台となり尿量も低下したが、それ以上の悪化はない状態が3日間持続。その後、ゆっくりと呼吸状態が改善、開始8日目にはモルヒネ減量開始でき、9日目に中止。入院71日で退院した。考察呼吸困難に対するオピオイドの効果は苦痛緩和以外に呼吸数低下による呼吸仕事量低下、肺血管抵抗低下による心負荷軽減などがある。RSV肺炎に対しては特異的な治療がなく、対症療法を行い回復を待つことになる。今回の症例ではモルヒネが直接最重度の肺炎を治療したわけではないが、呼吸困難による負担を軽減することで回復を助ける役割をしたと考えている。結語急性の呼吸困難時、オピオイドの使用は呼吸苦をとるだけでなく回復を支える治療的な効果を得られる可能性がある
- 著者
- 中村 達也 加藤 真希 雨宮 馨 鮎澤 浩一 小沢 浩
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.332-341, 2018-12-15
Angelman症候群(以下,AS)の児は,乳幼児期には哺乳障害や摂食嚥下障害を示し,学童期には未熟な咀嚼機能にとどまる場合が多い.しかし,離乳期AS児の摂食嚥下機能の獲得に関する報告は少なく,経過には不明な点が多い.今回,1歳から就学までの間,摂食指導を継続したAS児を経験した.症例の摂食嚥下機能の獲得時期を,粗大運動および認知・言語機能の発達の観点から診療録を後方視的に検討したところ,運動発達において四つ這い獲得後に舌挺出のない嚥下と捕食,伝い歩き獲得後に押しつぶし,独歩獲得後に咀嚼を獲得したが,口唇閉鎖が伴わず食塊形成は不十分であった.本児は定型発達とは異なり,運動発達が進んでから摂食嚥下機能を獲得したが,獲得された粗大運動は,両膝伸展位の座位や,手指屈曲位で手掌が接地しない四つ這いなど,定型発達とは質的な差があった.また,乳幼児期から口腔領域の感覚過敏が強く,就学前も感覚過敏は軽減したものの残存していた.