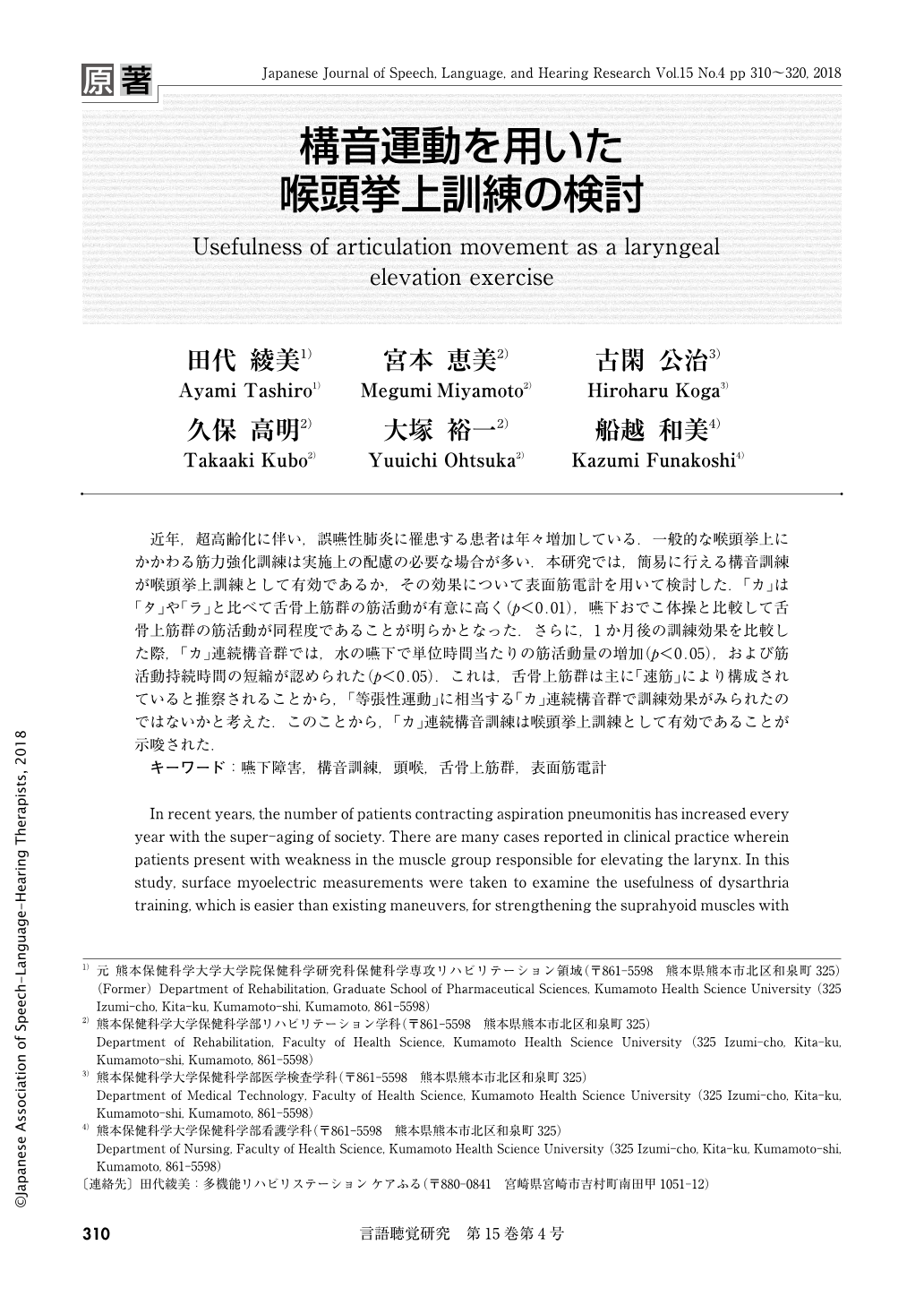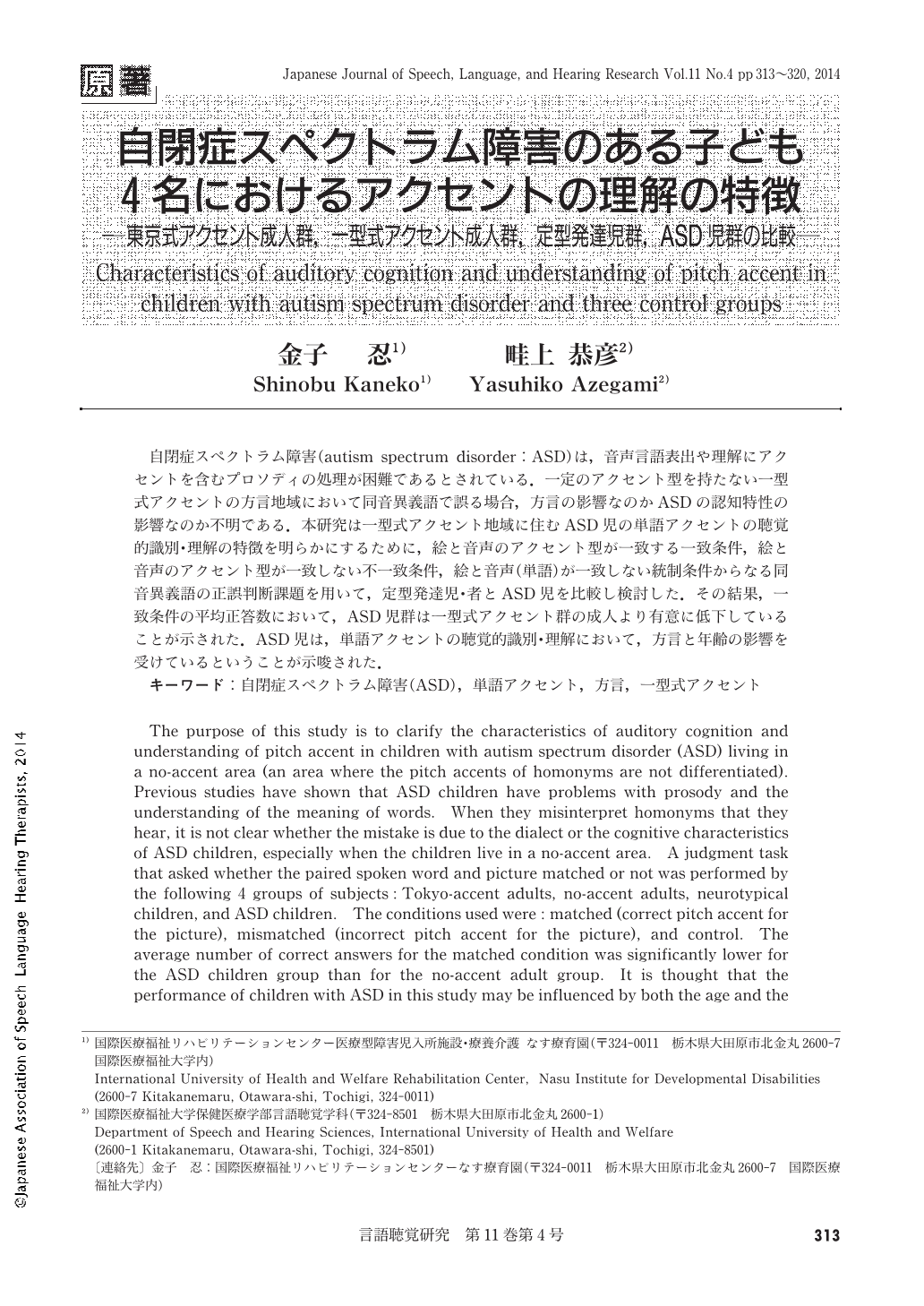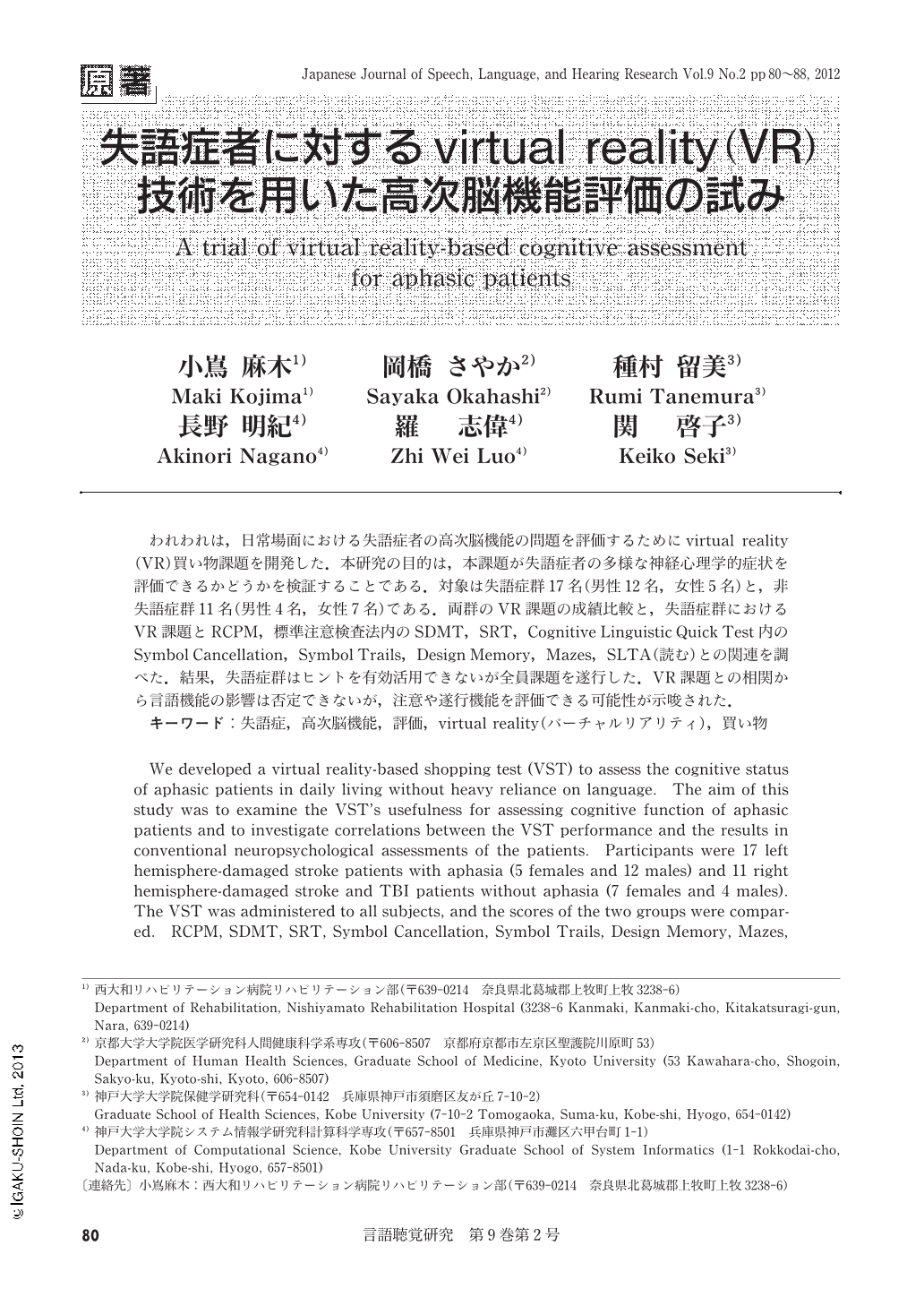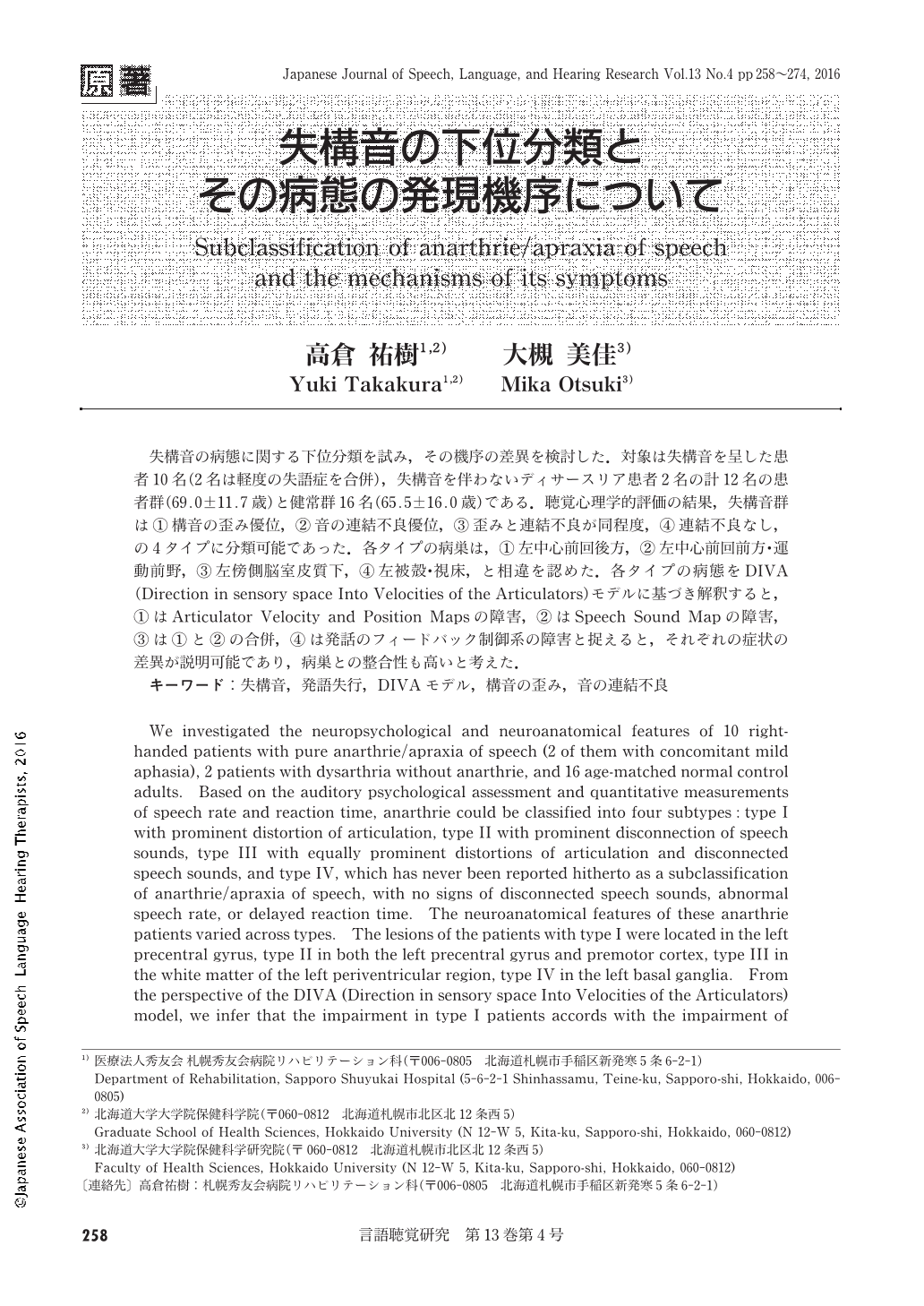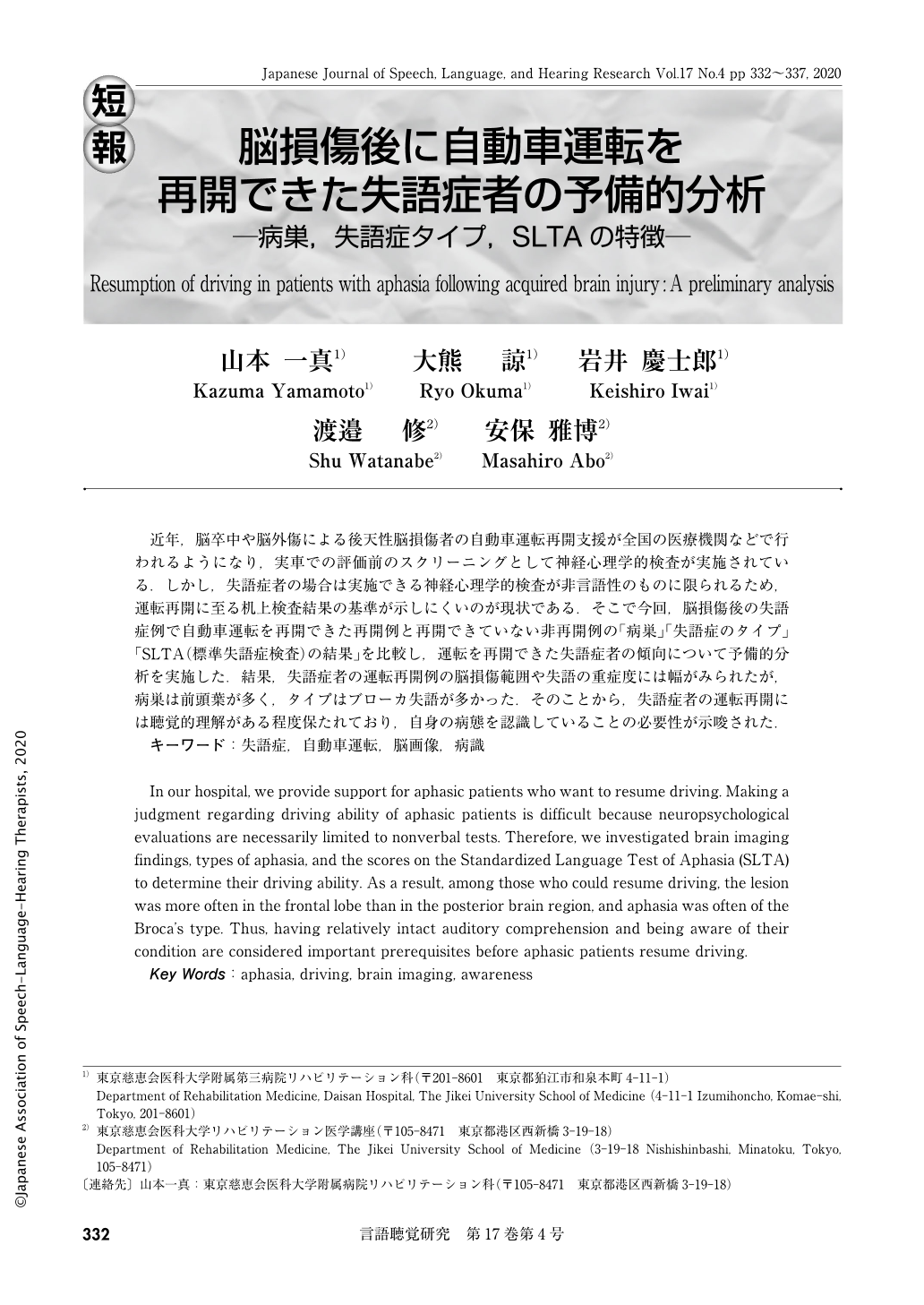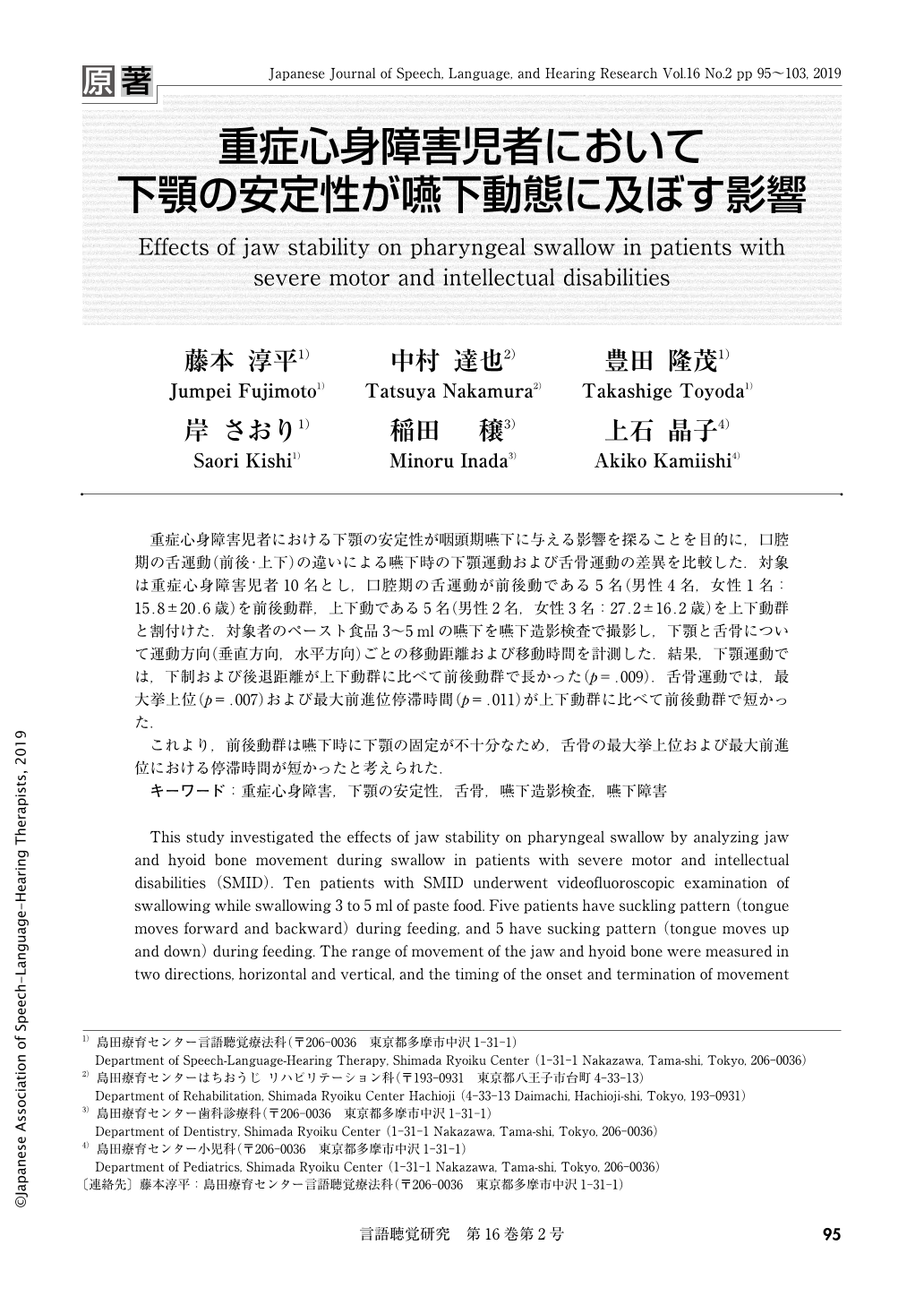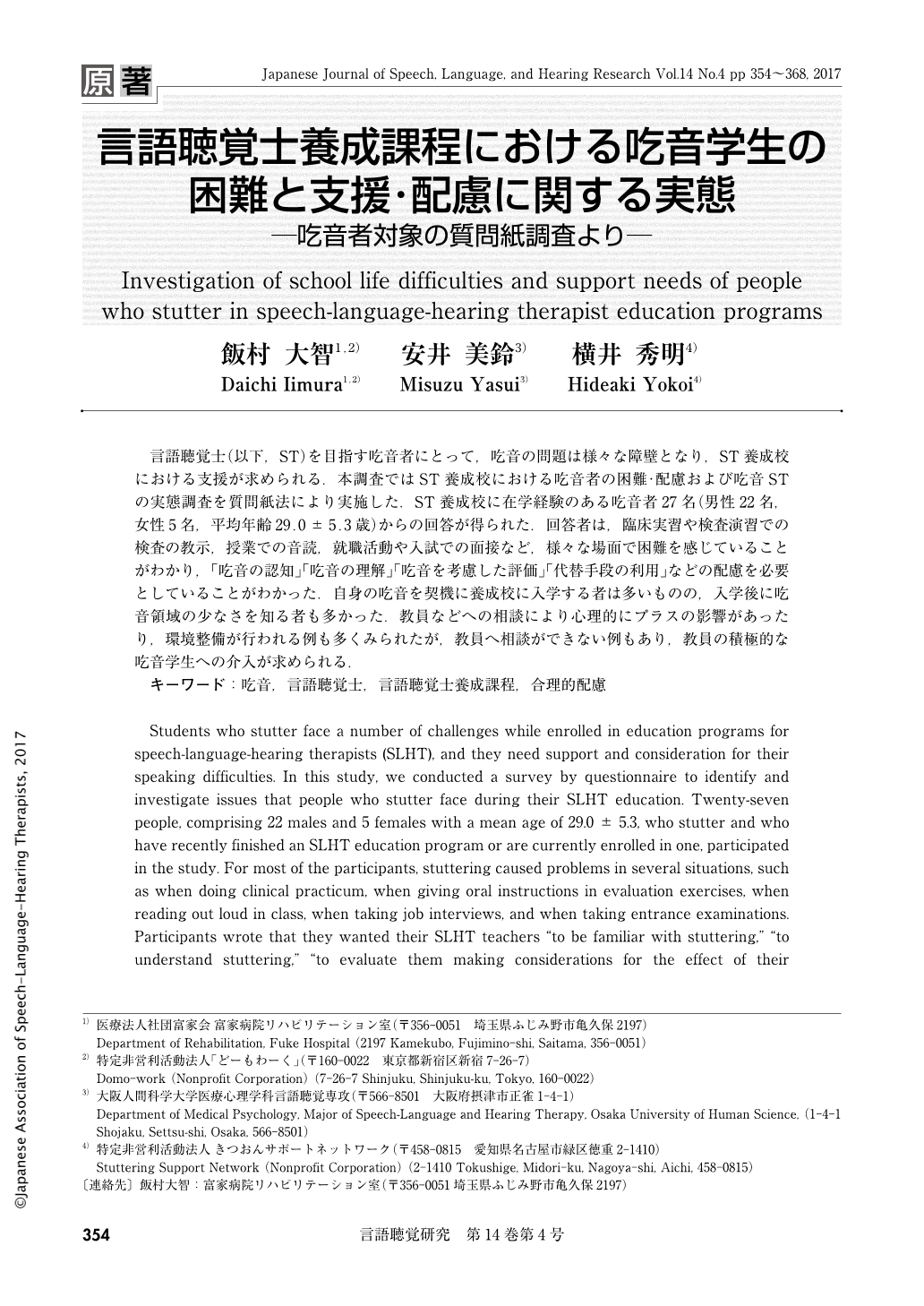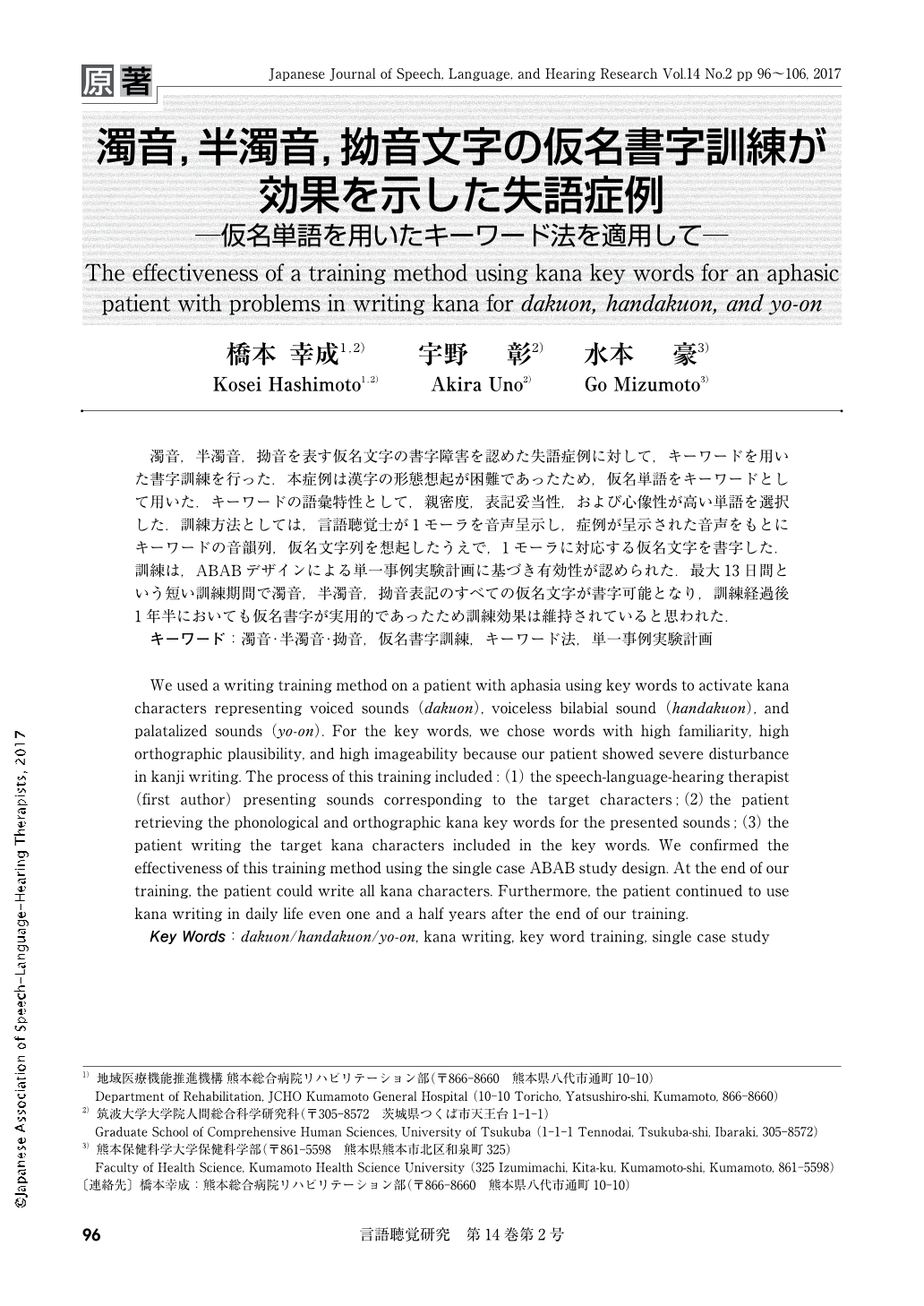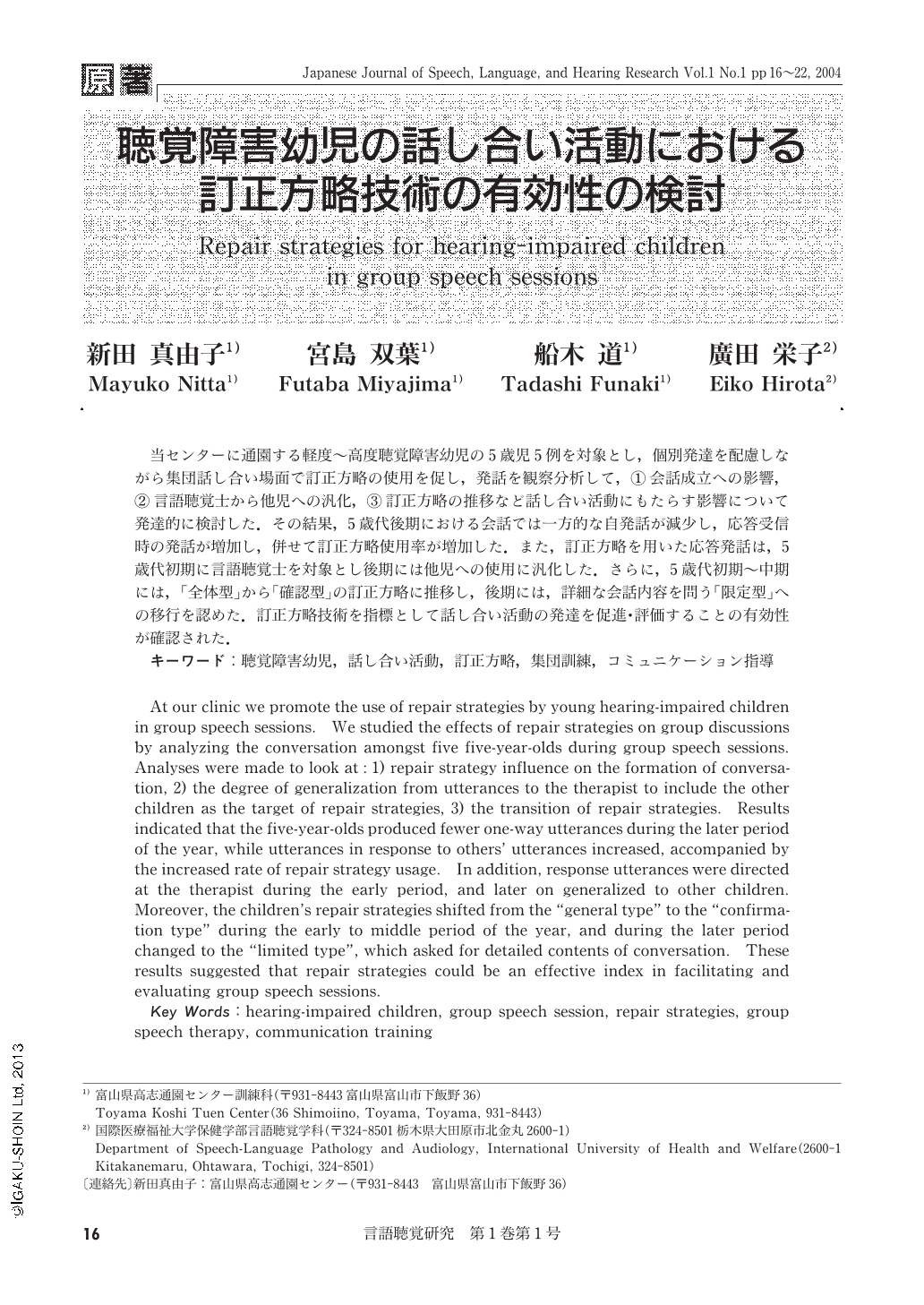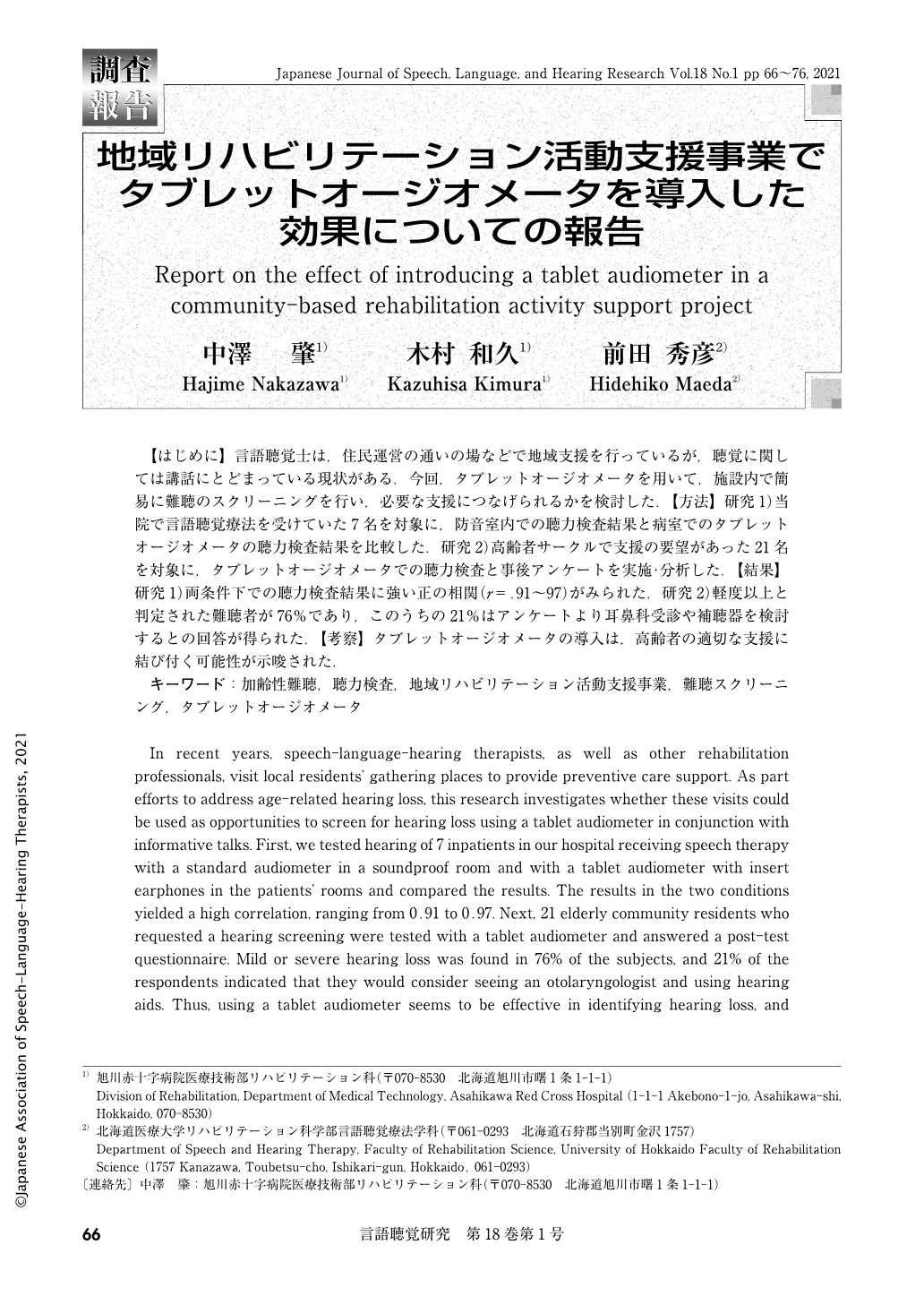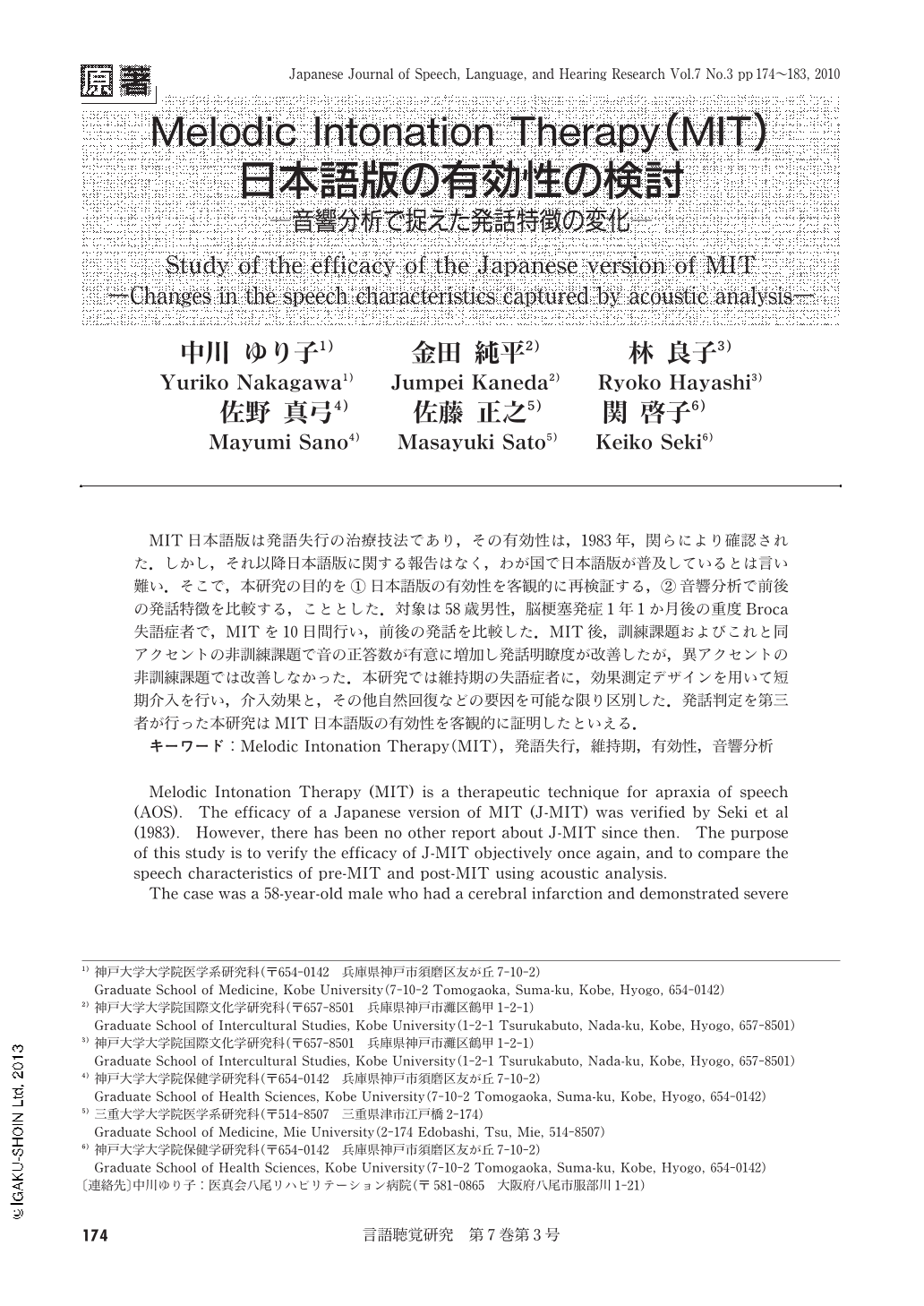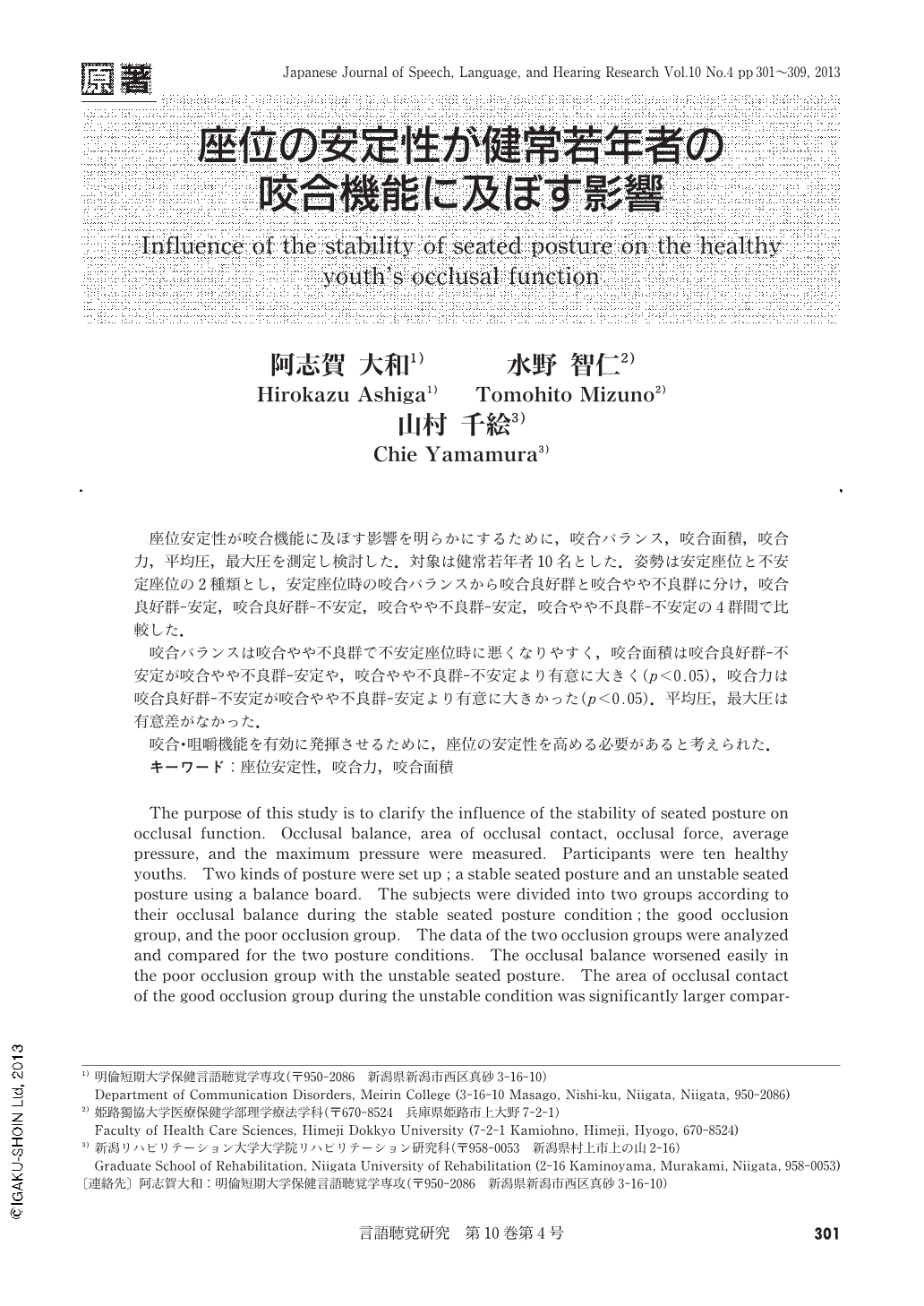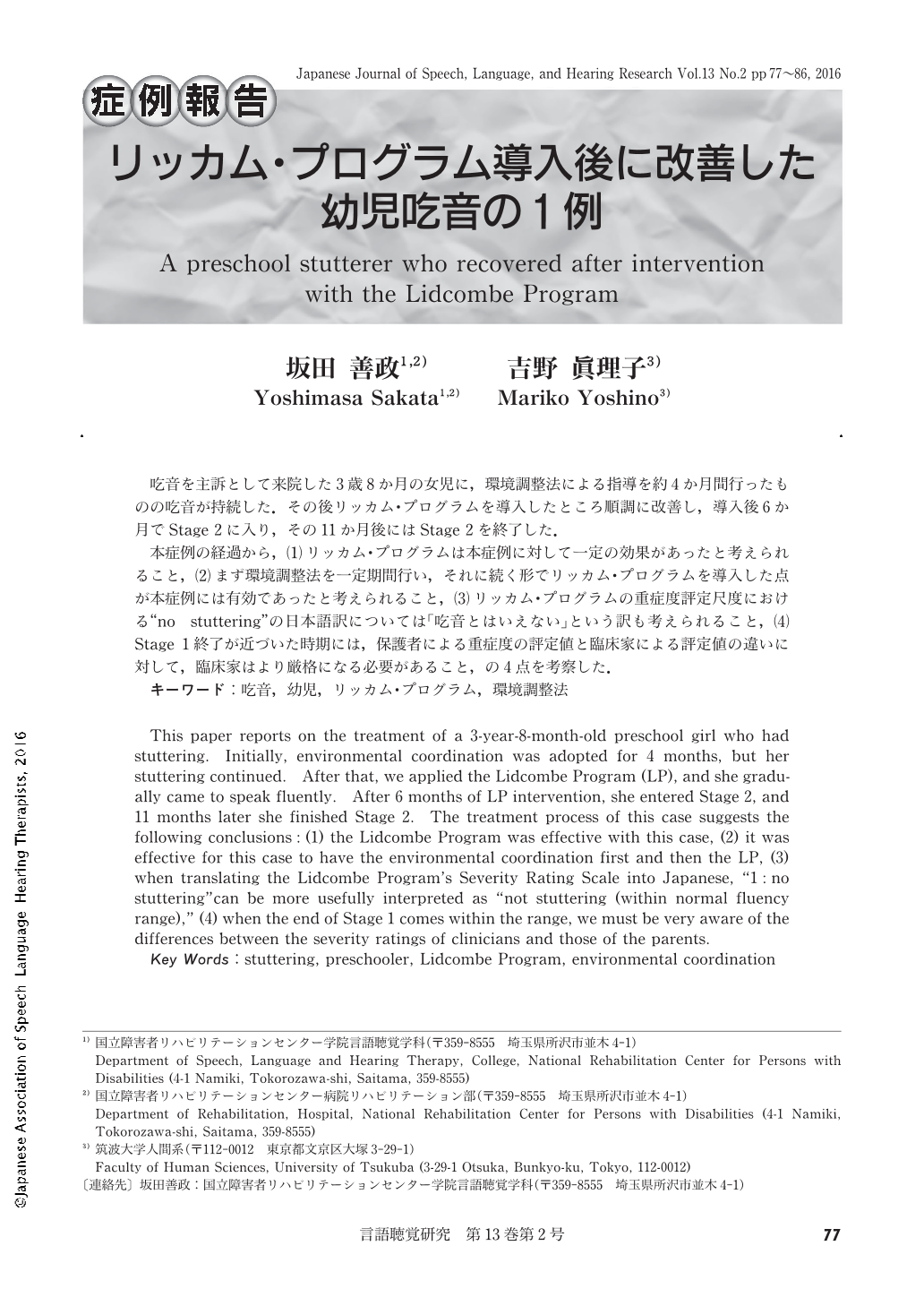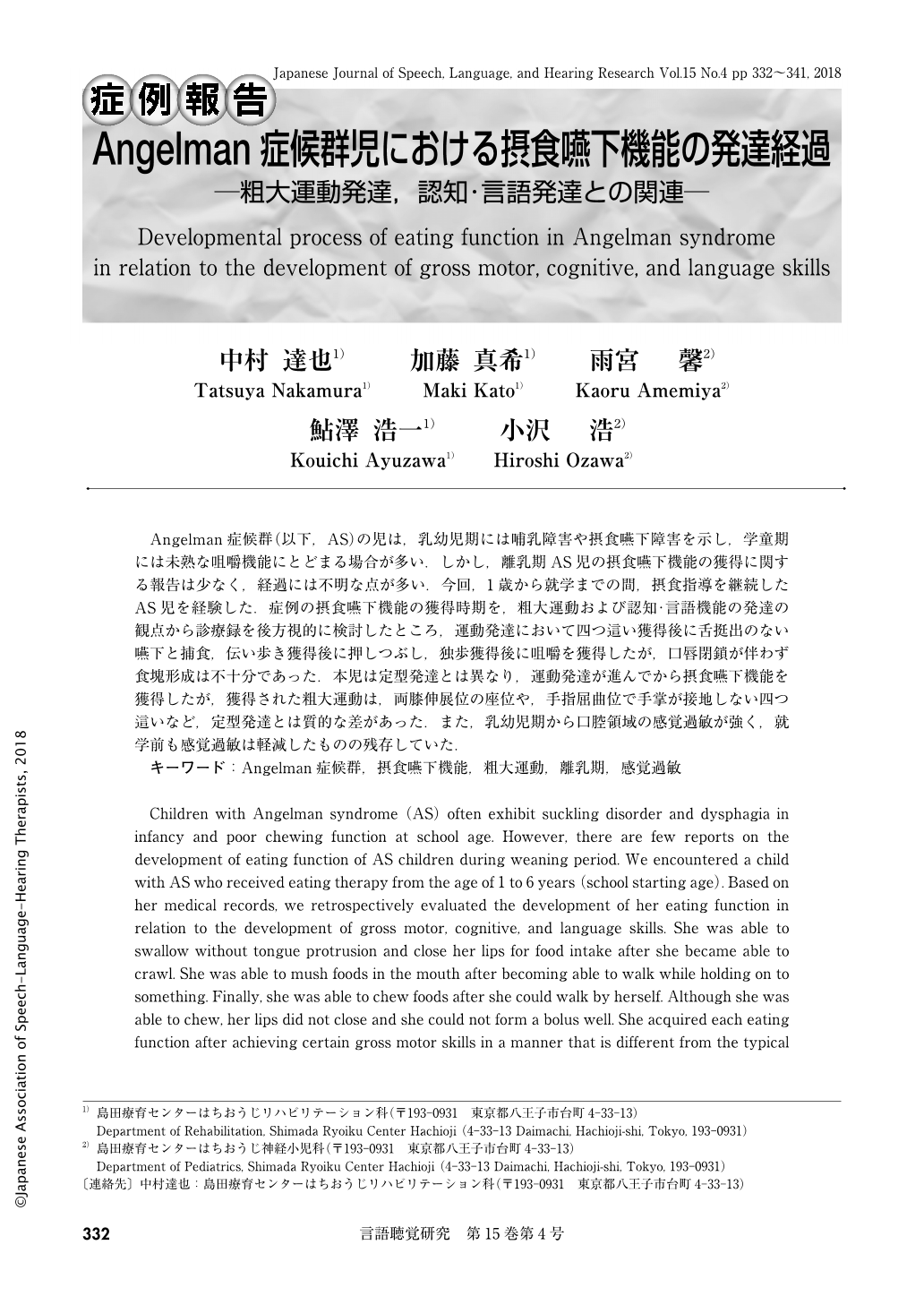9 0 0 0 構音運動を用いた喉頭挙上訓練の検討
近年,超高齢化に伴い,誤嚥性肺炎に罹患する患者は年々増加している.一般的な喉頭挙上にかかわる筋力強化訓練は実施上の配慮の必要な場合が多い.本研究では,簡易に行える構音訓練が喉頭挙上訓練として有効であるか,その効果について表面筋電計を用いて検討した.「カ」は「タ」や「ラ」と比べて舌骨上筋群の筋活動が有意に高く(p<0.01),嚥下おでこ体操と比較して舌骨上筋群の筋活動が同程度であることが明らかとなった.さらに,1か月後の訓練効果を比較した際,「カ」連続構音群では,水の嚥下で単位時間当たりの筋活動量の増加(p<0.05),および筋活動持続時間の短縮が認められた(p<0.05).これは,舌骨上筋群は主に「速筋」により構成されていると推察されることから,「等張性運動」に相当する「カ」連続構音群で訓練効果がみられたのではないかと考えた.このことから,「カ」連続構音訓練は喉頭挙上訓練として有効であることが示唆された.
自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder:ASD)は,音声言語表出や理解にアクセントを含むプロソディの処理が困難であるとされている.一定のアクセント型を持たない一型式アクセントの方言地域において同音異義語で誤る場合,方言の影響なのかASDの認知特性の影響なのか不明である.本研究は一型式アクセント地域に住むASD児の単語アクセントの聴覚的識別・理解の特徴を明らかにするために,絵と音声のアクセント型が一致する一致条件,絵と音声のアクセント型が一致しない不一致条件,絵と音声(単語)が一致しない統制条件からなる同音異義語の正誤判断課題を用いて,定型発達児・者とASD児を比較し検討した.その結果,一致条件の平均正答数において,ASD児群は一型式アクセント群の成人より有意に低下していることが示された.ASD児は,単語アクセントの聴覚的識別・理解において,方言と年齢の影響を受けているということが示唆された.
4 0 0 0 右側頭-頭頂葉に局所脳血流量の低下を示した聴覚情報処理障害小児例
- 著者
- 小嶌 麻木 岡橋 さやか 種村 留美 長野 明紀 羅 志偉 関 啓子
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.80-88, 2012-07-15
われわれは,日常場面における失語症者の高次脳機能の問題を評価するためにvirtual reality(VR)買い物課題を開発した.本研究の目的は,本課題が失語症者の多様な神経心理学的症状を評価できるかどうかを検証することである.対象は失語症群17名(男性12名,女性5名)と,非失語症群11名(男性4名,女性7名)である.両群のVR課題の成績比較と,失語症群におけるVR課題とRCPM,標準注意検査法内のSDMT,SRT,Cognitive Linguistic Quick Test内のSymbol Cancellation,Symbol Trails,Design Memory,Mazes,SLTA(読む)との関連を調べた.結果,失語症群はヒントを有効活用できないが全員課題を遂行した.VR課題との相関から言語機能の影響は否定できないが,注意や遂行機能を評価できる可能性が示唆された.
3 0 0 0 失構音の下位分類とその病態の発現機序について
失構音の病態に関する下位分類を試み,その機序の差異を検討した.対象は失構音を呈した患者10名(2名は軽度の失語症を合併),失構音を伴わないディサースリア患者2名の計12名の患者群(69.0±11.7歳)と健常群16名(65.5±16.0歳)である.聴覚心理学的評価の結果,失構音群は①構音の歪み優位,②音の連結不良優位,③歪みと連結不良が同程度,④連結不良なし,の4タイプに分類可能であった.各タイプの病巣は,①左中心前回後方,②左中心前回前方・運動前野,③左傍側脳室皮質下,④左被殻・視床,と相違を認めた.各タイプの病態をDIVA(Direction in sensory space Into Velocities of the Articulators)モデルに基づき解釈すると,①はArticulator Velocity and Position Mapsの障害,②はSpeech Sound Mapの障害,③は①と②の合併,④は発話のフィードバック制御系の障害と捉えると,それぞれの症状の差異が説明可能であり,病巣との整合性も高いと考えた.
2 0 0 0 失語症患者の排泄訓練における言語聴覚士の役割
近年,脳卒中や脳外傷による後天性脳損傷者の自動車運転再開支援が全国の医療機関などで行われるようになり,実車での評価前のスクリーニングとして神経心理学的検査が実施されている.しかし,失語症者の場合は実施できる神経心理学的検査が非言語性のものに限られるため,運転再開に至る机上検査結果の基準が示しにくいのが現状である.そこで今回,脳損傷後の失語症例で自動車運転を再開できた再開例と再開できていない非再開例の「病巣」「失語症のタイプ」「SLTA(標準失語症検査)の結果」を比較し,運転を再開できた失語症者の傾向について予備的分析を実施した.結果,失語症者の運転再開例の脳損傷範囲や失語の重症度には幅がみられたが,病巣は前頭葉が多く,タイプはブローカ失語が多かった.そのことから,失語症者の運転再開には聴覚的理解がある程度保たれており,自身の病態を認識していることの必要性が示唆された.
2 0 0 0 重症心身障害児者において下顎の安定性が嚥下動態に及ぼす影響
- 著者
- 藤本 淳平 中村 達也 豊田 隆茂 岸 さおり 稲田 穣 上石 晶子
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.95-103, 2019-06-15
重症心身障害児者における下顎の安定性が咽頭期嚥下に与える影響を探ることを目的に,口腔期の舌運動(前後・上下)の違いによる嚥下時の下顎運動および舌骨運動の差異を比較した.対象は重症心身障害児者10名とし,口腔期の舌運動が前後動である5名(男性4名,女性1名:15.8±20.6歳)を前後動群,上下動である5名(男性2名,女性3名:27.2±16.2歳)を上下動群と割付けた.対象者のペースト食品3〜5mlの嚥下を嚥下造影検査で撮影し,下顎と舌骨について運動方向(垂直方向,水平方向)ごとの移動距離および移動時間を計測した.結果,下顎運動では,下制および後退距離が上下動群に比べて前後動群で長かった(p=.009).舌骨運動では,最大挙上位(p=.007)および最大前進位停滞時間(p=.011)が上下動群に比べて前後動群で短かった. これより,前後動群は嚥下時に下顎の固定が不十分なため,舌骨の最大挙上位および最大前進位における停滞時間が短かったと考えられた.
- 著者
- 飯村 大智 安井 美鈴 横井 秀明
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.354-368, 2017-12-15
言語聴覚士(以下,ST)を目指す吃音者にとって,吃音の問題は様々な障壁となり,ST養成校における支援が求められる.本調査ではST養成校における吃音者の困難・配慮および吃音STの実態調査を質問紙法により実施した.ST養成校に在学経験のある吃音者27名(男性22名,女性5名,平均年齢29.0±5.3歳)からの回答が得られた.回答者は,臨床実習や検査演習での検査の教示,授業での音読,就職活動や入試での面接など,様々な場面で困難を感じていることがわかり,「吃音の認知」「吃音の理解」「吃音を考慮した評価」「代替手段の利用」などの配慮を必要としていることがわかった.自身の吃音を契機に養成校に入学する者は多いものの,入学後に吃音領域の少なさを知る者も多かった.教員などへの相談により心理的にプラスの影響があったり,環境整備が行われる例も多くみられたが,教員へ相談ができない例もあり,教員の積極的な吃音学生への介入が求められる.
1 0 0 0 クリニカル・クラークシップによる言語聴覚療法臨床実習の試み
Ⅰ.はじめに 近年,理学療法士(physical therapist:PT)および作業療法士(occupational therapist:OT)分野では臨床実習のあり方について様々な議論がなされており,言語聴覚士(speech therapist:ST)にとっても関心の高い内容であると考えられる.2018年10月には,理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則が改正され,新たに示された養成施設指導ガイドラインにおいて「評価実習と総合臨床実習については,実習生が診療チームの一員として加わり,臨床実習指導者の指導・監督の下で行う診療参加型臨床実習が望ましい」とされた1). 診療参加型臨床実習(clinical clerkship:CCS)とは,「学生が診療チームの一員として診療業務を分担しながら,職業的な知識・思考法・技能・態度の基本的な内容を学習し,実際の診療業務に必要とされる思考力(臨床推論)・対応力などを養うことを目的とした実習形態」2)のことであり,「教育者や実習施設を保護しながらも,臨床実習を可能にするコンプライアンス遵守のためのシステム」3)でもある.一方で,従来型の臨床実習とは,明確な定義はないが「実習施設にて学生自身が患者を担当し評価から治療までの過程を経験する」という“患者担当型”の指導形態が代表的な例3)であり,CCSのような学習理論4)に基づく明確な指導方法やコンプライアンス遵守のためのシステムは存在しない.また,その実施方法は学校養成施設や臨床実習施設によって様々であるとされる5).2017年のPT,OTの学生・卒業生を対象としたアンケート調査6)では,約8割が患者担当型実習を経験したと回答している.この従来の患者担当型実習の問題点として,臨床実習で学生が行う行為の違法性阻却のための条件7)が整備されていないという課題3)や,対象者に触れない見学中心の臨床実習であることなどにより療法士の臨床能力の低下につながっている課題8)が示されている.また,レポート中心の指導となっている実態やその弊害も報告されており9-11),これらの問題を解決するための新たな臨床実習のあり方としてCCSが求められている. 上記の背景から,当院リハビリテーション部では臨床実習のあり方に関する議論を重ねてきた.2018年度にはPT,OTは臨床実習を全面的にCCSへと移行し,STでは移行期間を定め,複数の養成校の協力を得ながらCCSによる臨床実習指導体制の整備を図ってきた.今回は,そのうちの学生1名の実践を報告する. なお,本報告に関して,当院臨床研究倫理審査委員会の承認を得た(承認番号433).その後,学生と養成校の担当教員に口頭および書面にて説明し同意を得た.
濁音,半濁音,拗音を表す仮名文字の書字障害を認めた失語症例に対して,キーワードを用いた書字訓練を行った.本症例は漢字の形態想起が困難であったため,仮名単語をキーワードとして用いた.キーワードの語彙特性として,親密度,表記妥当性,および心像性が高い単語を選択した.訓練方法としては,言語聴覚士が1モーラを音声呈示し,症例が呈示された音声をもとにキーワードの音韻列,仮名文字列を想起したうえで,1モーラに対応する仮名文字を書字した.訓練は,ABABデザインによる単一事例実験計画に基づき有効性が認められた.最大13日間という短い訓練期間で濁音,半濁音,拗音表記のすべての仮名文字が書字可能となり,訓練経過後1年半においても仮名書字が実用的であったため訓練効果は維持されていると思われた.
- 著者
- 水野 奈緒美 川崎 聡大 後藤 多可志
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会 ; 2004-
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.150-158, 2012
1 0 0 0 聴覚障害幼児の話し合い活動における訂正方略技術の有効性の検討
当センターに通園する軽度~高度聴覚障害幼児の5歳児5例を対象とし,個別発達を配慮しながら集団話し合い場面で訂正方略の使用を促し,発話を観察分析して,①会話成立への影響,②言語聴覚士から他児への汎化,③訂正方略の推移など話し合い活動にもたらす影響について発達的に検討した.その結果,5歳代後期における会話では一方的な自発話が減少し,応答受信時の発話が増加し,併せて訂正方略使用率が増加した.また,訂正方略を用いた応答発話は,5歳代初期に言語聴覚士を対象とし後期には他児への使用に汎化した.さらに,5歳代初期~中期には,「全体型」から「確認型」の訂正方略に推移し,後期には,詳細な会話内容を問う「限定型」への移行を認めた.訂正方略技術を指標として話し合い活動の発達を促進・評価することの有効性が確認された.
【はじめに】言語聴覚士は,住民運営の通いの場などで地域支援を行っているが,聴覚に関しては講話にとどまっている現状がある.今回,タブレットオージオメータを用いて,施設内で簡易に難聴のスクリーニングを行い,必要な支援につなげられるかを検討した.【方法】研究1)当院で言語聴覚療法を受けていた7名を対象に,防音室内での聴力検査結果と病室でのタブレットオージオメータの聴力検査結果を比較した.研究2)高齢者サークルで支援の要望があった21名を対象に,タブレットオージオメータでの聴力検査と事後アンケートを実施・分析した.【結果】研究1)両条件下での聴力検査結果に強い正の相関(r=.91〜97)がみられた.研究2)軽度以上と判定された難聴者が76%であり,このうちの21%はアンケートより耳鼻科受診や補聴器を検討するとの回答が得られた.【考察】タブレットオージオメータの導入は,高齢者の適切な支援に結び付く可能性が示唆された.
MIT日本語版は発語失行の治療技法であり,その有効性は,1983年,関らにより確認された.しかし,それ以降日本語版に関する報告はなく,わが国で日本語版が普及しているとは言い難い.そこで,本研究の目的を①日本語版の有効性を客観的に再検証する,②音響分析で前後の発話特徴を比較する,こととした.対象は58歳男性,脳梗塞発症1年1か月後の重度Broca失語症者で,MITを10日間行い,前後の発話を比較した.MIT後,訓練課題およびこれと同アクセントの非訓練課題で音の正答数が有意に増加し発話明瞭度が改善したが,異アクセントの非訓練課題では改善しなかった.本研究では維持期の失語症者に,効果測定デザインを用いて短期介入を行い,介入効果と,その他自然回復などの要因を可能な限り区別した.発話判定を第三者が行った本研究はMIT日本語版の有効性を客観的に証明したといえる.
1 0 0 0 失語症の長期経過—外来訓練の意義
失語症状の長期経過を明らかにする研究の一環として,右手利き左大脳半球一側損傷後に失語症を呈した270例の病巣別回復経過と,その中で言語機能に低下を示した37症例のSLTA総合評価法得点各因子の機能変遷の既報告を俯瞰した.次に,2年以上適切な言語訓練を行った失語症121例について,SLTA総合評価法得点に影響を及ぼす要因を調査した.その結果,1)失語症状の回復は損傷部位や発症年齢によって経過は大きく異なるが,少なくとも6か月以上の長期にわたって回復を認める症例が多いこと,2)言語訓練後に回復を示した機能は脆弱である可能性が高いこと,3)発症年齢,Wernicke領野を含む上側頭回の病変の有無,発症3か月時SLTA総合評価法得点などが予後に重要な因子であること,が示唆された. 以上のことから,失語症の訓練においては,1)長期にわたって変化しうる失語症状そのものに着目する必要があること,2)病院外来における訓練実施が望ましいこと,が考えられた.
1 0 0 0 座位の安定性が健常若年者の咬合機能に及ぼす影響
座位安定性が咬合機能に及ぼす影響を明らかにするために,咬合バランス,咬合面積,咬合力,平均圧,最大圧を測定し検討した.対象は健常若年者10名とした.姿勢は安定座位と不安定座位の2種類とし,安定座位時の咬合バランスから咬合良好群と咬合やや不良群に分け,咬合良好群-安定,咬合良好群-不安定,咬合やや不良群-安定,咬合やや不良群-不安定の4群間で比較した. 咬合バランスは咬合やや不良群で不安定座位時に悪くなりやすく,咬合面積は咬合良好群-不安定が咬合やや不良群-安定や,咬合やや不良群-不安定より有意に大きく(p<0.05),咬合力は咬合良好群-不安定が咬合やや不良群-安定より有意に大きかった(p<0.05).平均圧,最大圧は有意差がなかった. 咬合・咀嚼機能を有効に発揮させるために,座位の安定性を高める必要があると考えられた.
1 0 0 0 リッカム・プログラム導入後に改善した幼児吃音の1例
- 著者
- 坂田 善政 吉野 眞理子
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.77-86, 2016-06-15
吃音を主訴として来院した3歳8か月の女児に,環境調整法による指導を約4か月間行ったものの吃音が持続した.その後リッカム・プログラムを導入したところ順調に改善し,導入後6か月でStage 2に入り,その11か月後にはStage 2を終了した. 本症例の経過から,(1)リッカム・プログラムは本症例に対して一定の効果があったと考えられること,(2)まず環境調整法を一定期間行い,それに続く形でリッカム・プログラムを導入した点が本症例には有効であったと考えられること,(3)リッカム・プログラムの重症度評定尺度における“no stuttering”の日本語訳については「吃音とはいえない」という訳も考えられること,(4)Stage 1終了が近づいた時期には,保護者による重症度の評定値と臨床家による評定値の違いに対して,臨床家はより厳格になる必要があること,の4点を考察した.
- 著者
- 中村 達也 加藤 真希 雨宮 馨 鮎澤 浩一 小沢 浩
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.332-341, 2018-12-15
Angelman症候群(以下,AS)の児は,乳幼児期には哺乳障害や摂食嚥下障害を示し,学童期には未熟な咀嚼機能にとどまる場合が多い.しかし,離乳期AS児の摂食嚥下機能の獲得に関する報告は少なく,経過には不明な点が多い.今回,1歳から就学までの間,摂食指導を継続したAS児を経験した.症例の摂食嚥下機能の獲得時期を,粗大運動および認知・言語機能の発達の観点から診療録を後方視的に検討したところ,運動発達において四つ這い獲得後に舌挺出のない嚥下と捕食,伝い歩き獲得後に押しつぶし,独歩獲得後に咀嚼を獲得したが,口唇閉鎖が伴わず食塊形成は不十分であった.本児は定型発達とは異なり,運動発達が進んでから摂食嚥下機能を獲得したが,獲得された粗大運動は,両膝伸展位の座位や,手指屈曲位で手掌が接地しない四つ這いなど,定型発達とは質的な差があった.また,乳幼児期から口腔領域の感覚過敏が強く,就学前も感覚過敏は軽減したものの残存していた.