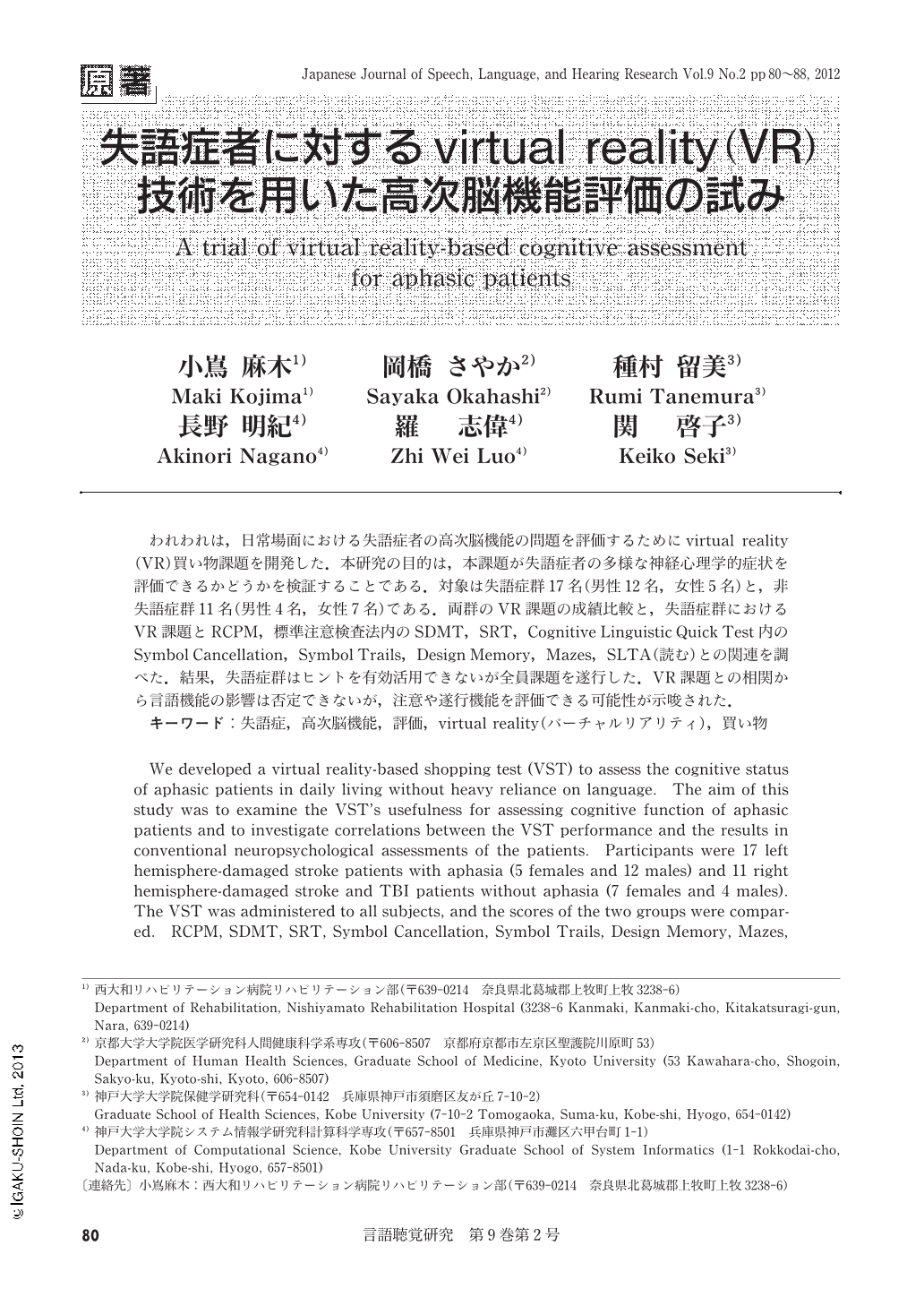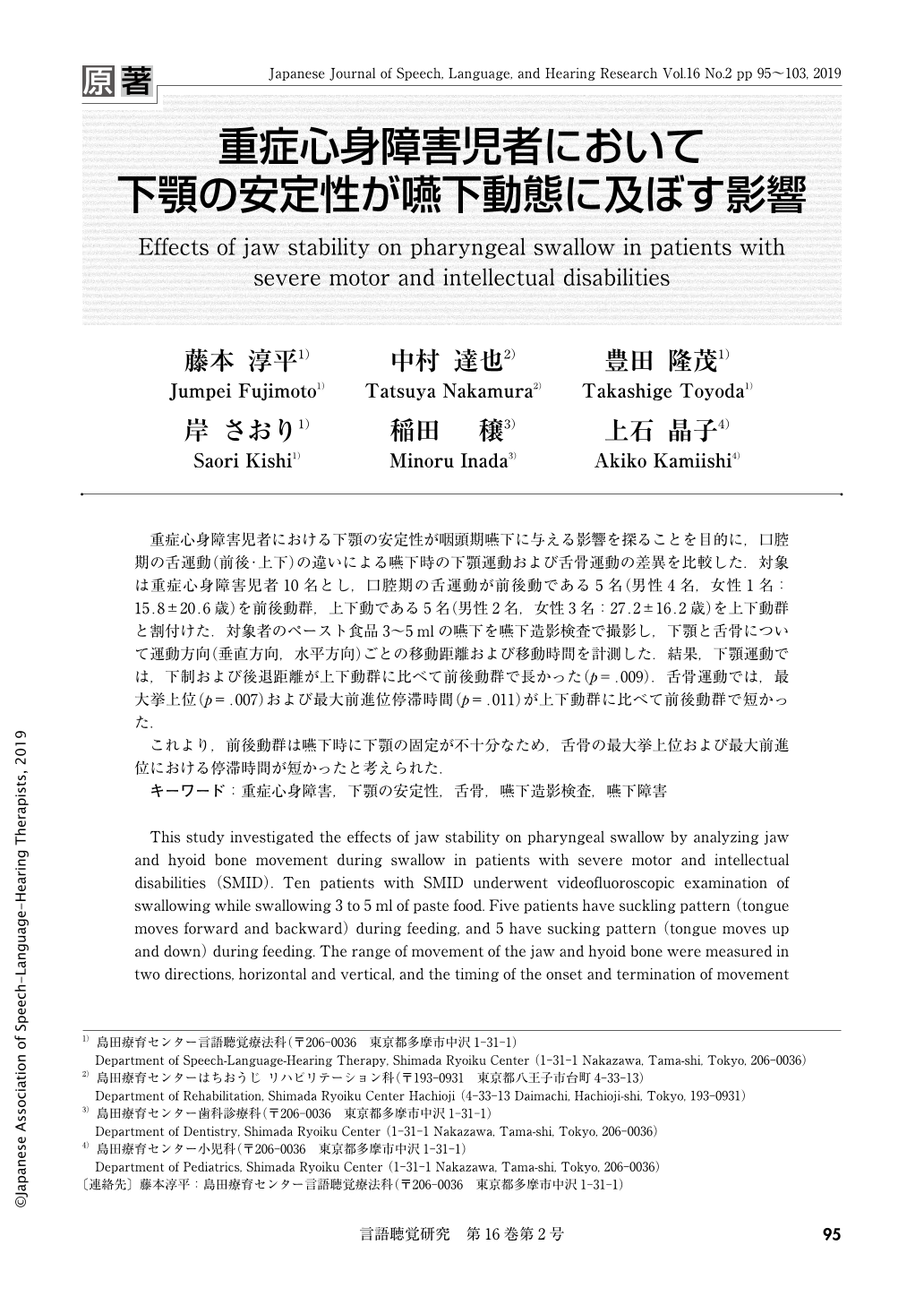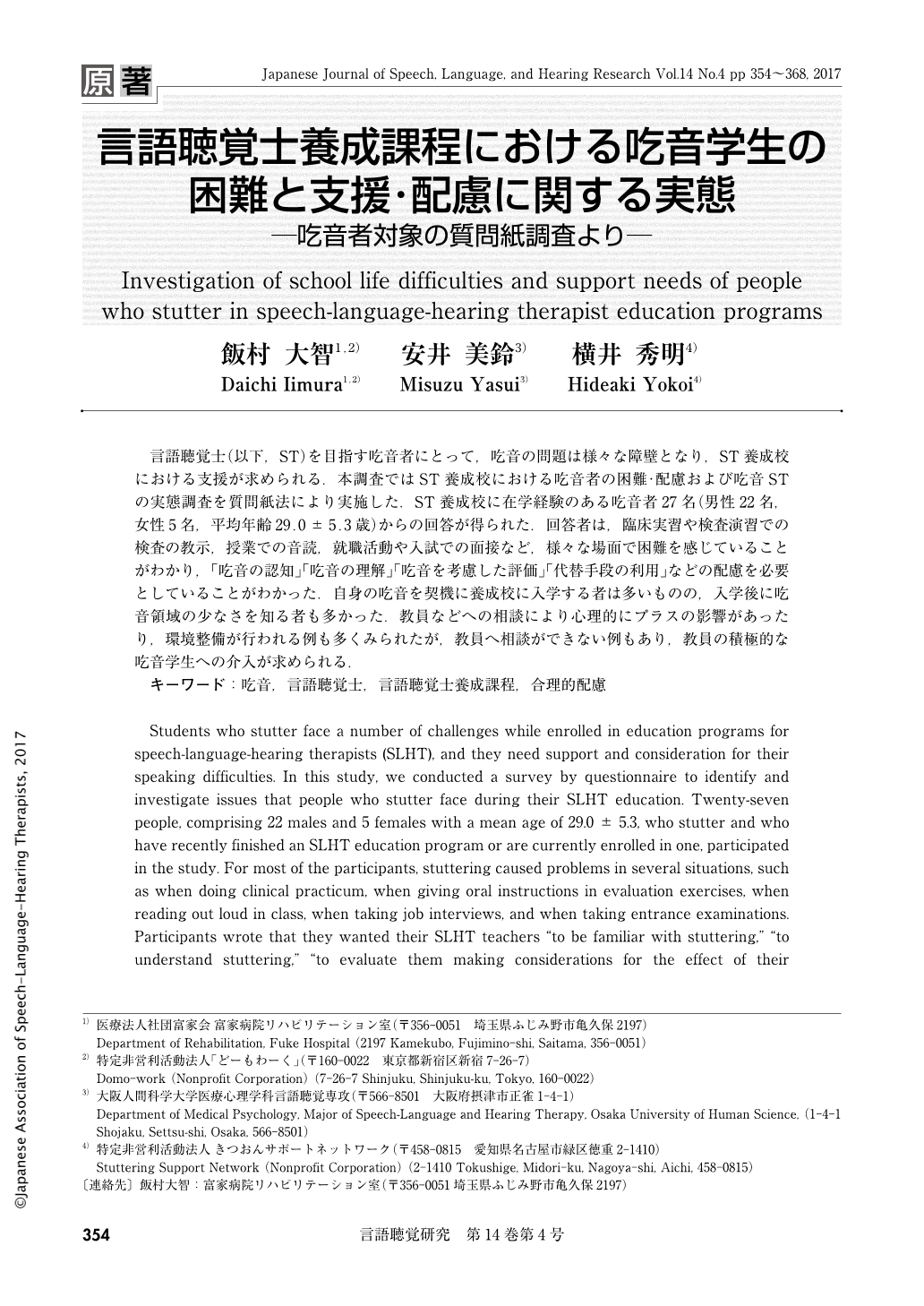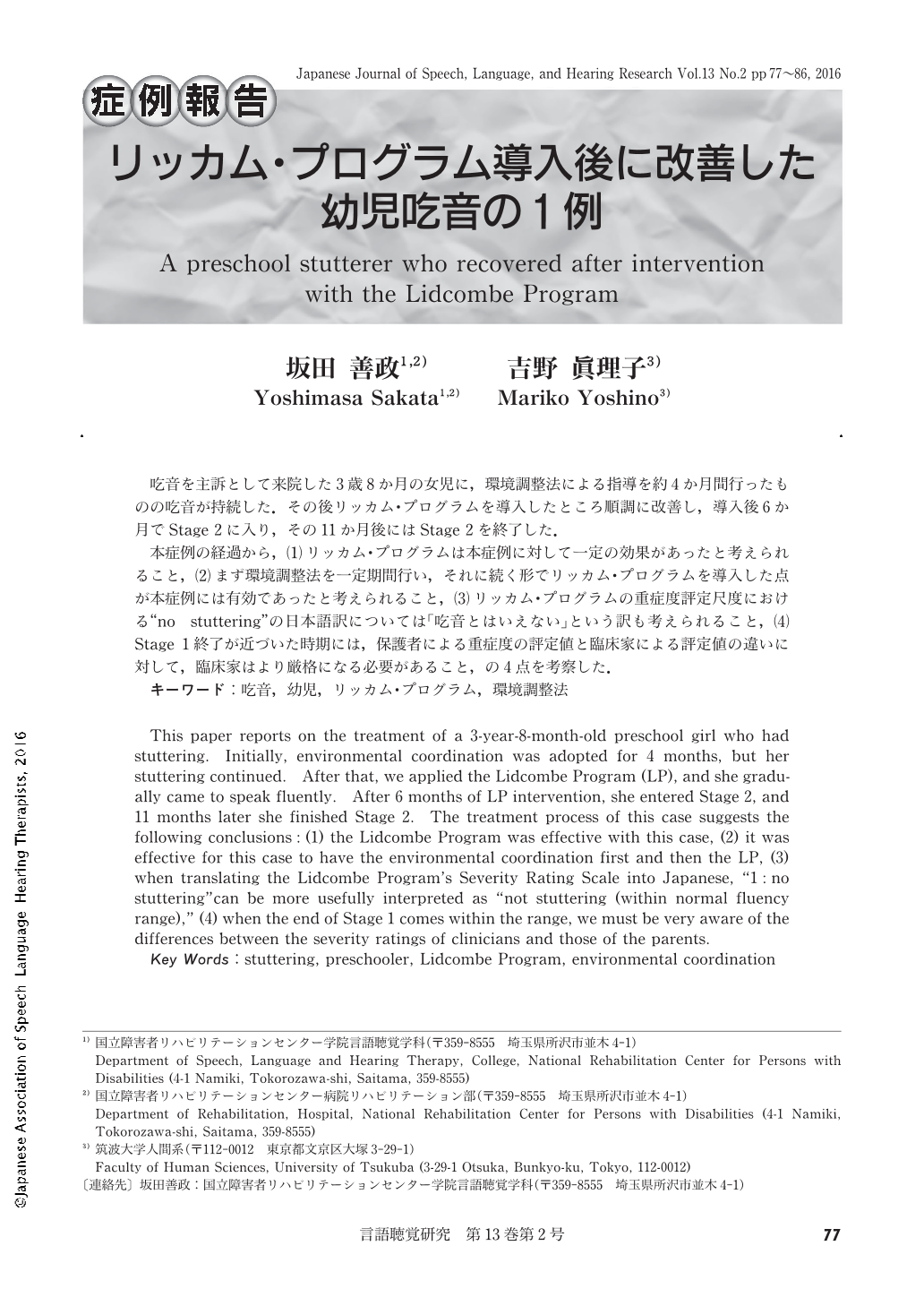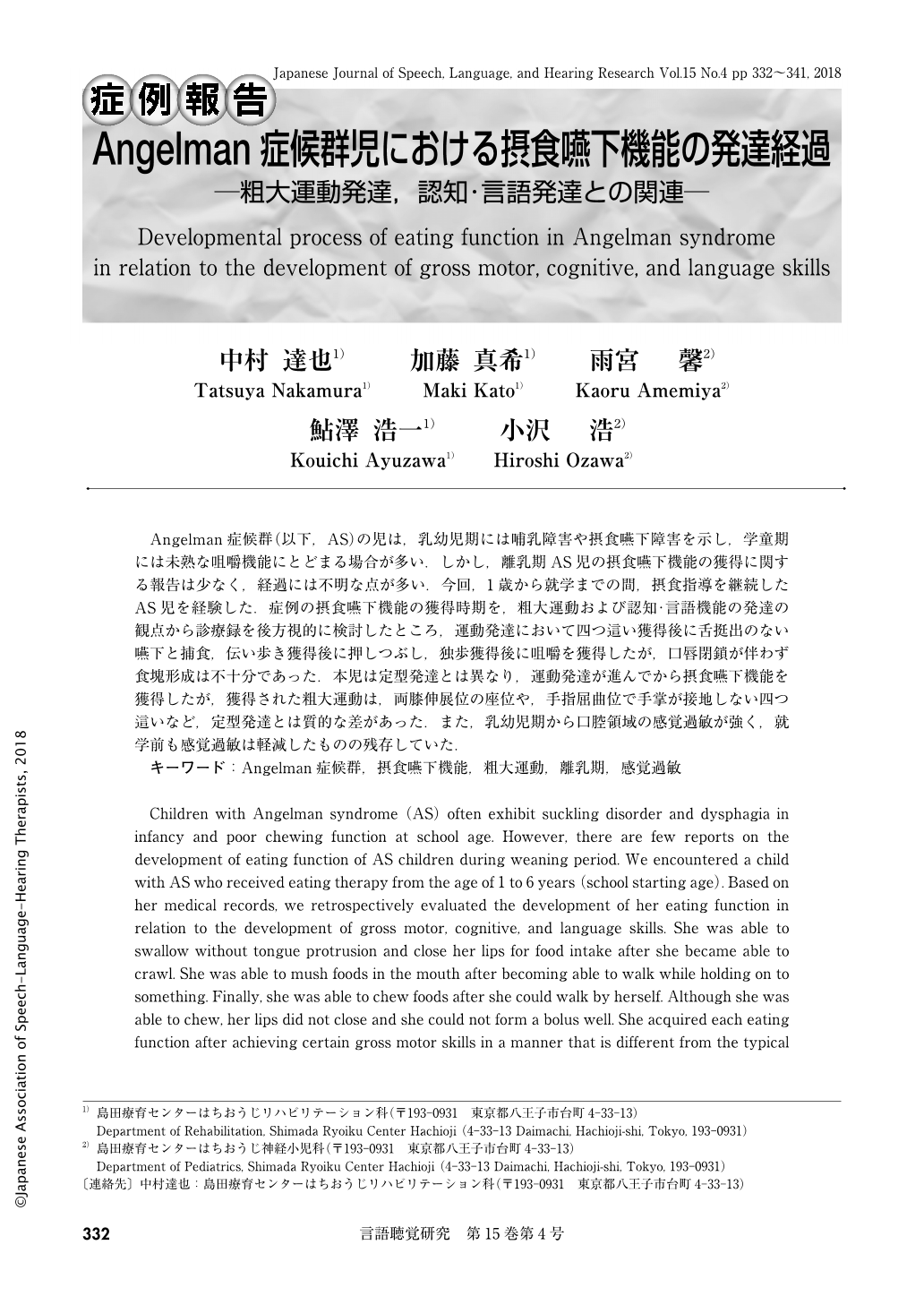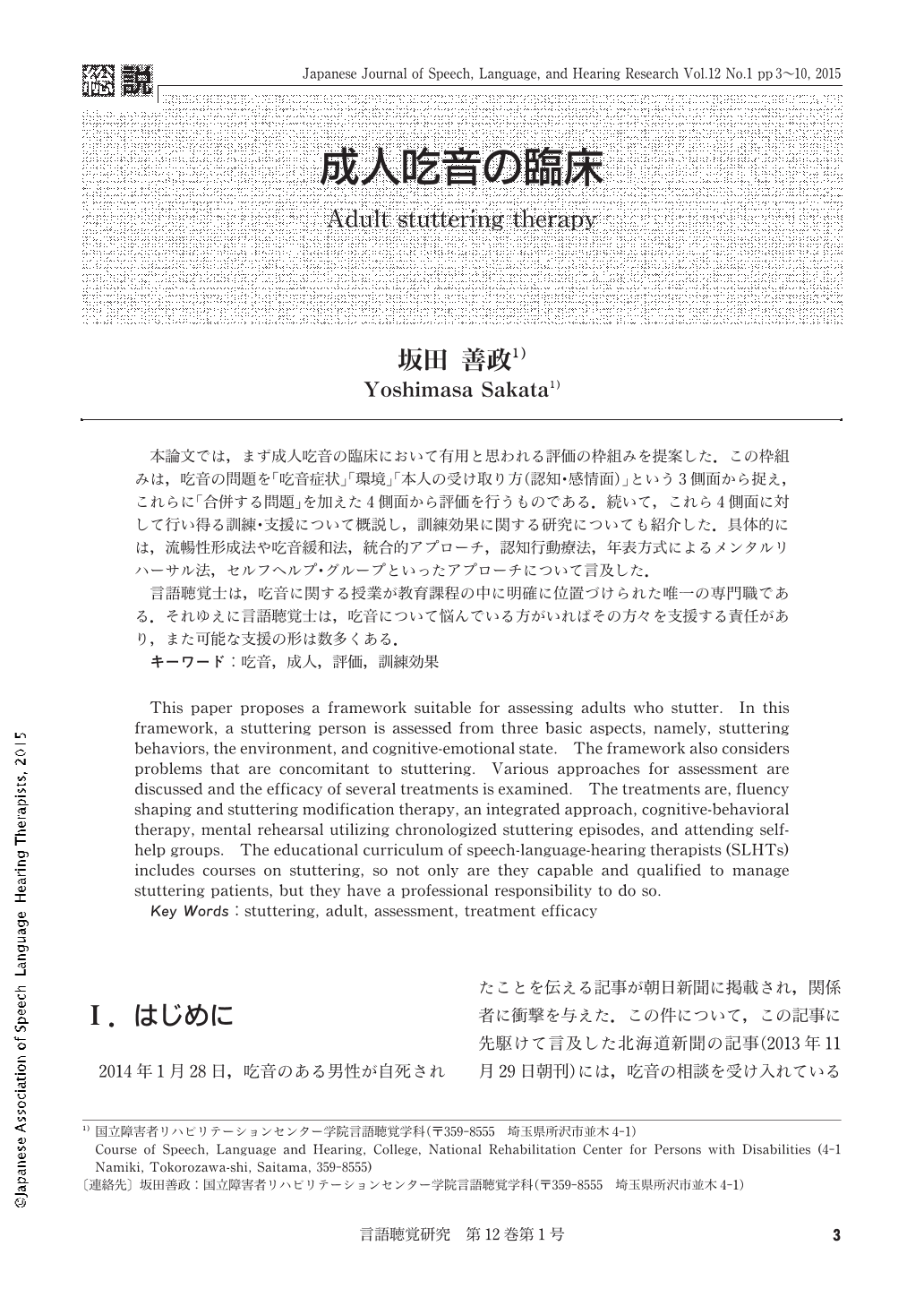4 0 0 0 右側頭-頭頂葉に局所脳血流量の低下を示した聴覚情報処理障害小児例
- 著者
- 小嶌 麻木 岡橋 さやか 種村 留美 長野 明紀 羅 志偉 関 啓子
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.80-88, 2012-07-15
われわれは,日常場面における失語症者の高次脳機能の問題を評価するためにvirtual reality(VR)買い物課題を開発した.本研究の目的は,本課題が失語症者の多様な神経心理学的症状を評価できるかどうかを検証することである.対象は失語症群17名(男性12名,女性5名)と,非失語症群11名(男性4名,女性7名)である.両群のVR課題の成績比較と,失語症群におけるVR課題とRCPM,標準注意検査法内のSDMT,SRT,Cognitive Linguistic Quick Test内のSymbol Cancellation,Symbol Trails,Design Memory,Mazes,SLTA(読む)との関連を調べた.結果,失語症群はヒントを有効活用できないが全員課題を遂行した.VR課題との相関から言語機能の影響は否定できないが,注意や遂行機能を評価できる可能性が示唆された.
2 0 0 0 失語症患者の排泄訓練における言語聴覚士の役割
2 0 0 0 重症心身障害児者において下顎の安定性が嚥下動態に及ぼす影響
- 著者
- 藤本 淳平 中村 達也 豊田 隆茂 岸 さおり 稲田 穣 上石 晶子
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.95-103, 2019-06-15
重症心身障害児者における下顎の安定性が咽頭期嚥下に与える影響を探ることを目的に,口腔期の舌運動(前後・上下)の違いによる嚥下時の下顎運動および舌骨運動の差異を比較した.対象は重症心身障害児者10名とし,口腔期の舌運動が前後動である5名(男性4名,女性1名:15.8±20.6歳)を前後動群,上下動である5名(男性2名,女性3名:27.2±16.2歳)を上下動群と割付けた.対象者のペースト食品3〜5mlの嚥下を嚥下造影検査で撮影し,下顎と舌骨について運動方向(垂直方向,水平方向)ごとの移動距離および移動時間を計測した.結果,下顎運動では,下制および後退距離が上下動群に比べて前後動群で長かった(p=.009).舌骨運動では,最大挙上位(p=.007)および最大前進位停滞時間(p=.011)が上下動群に比べて前後動群で短かった. これより,前後動群は嚥下時に下顎の固定が不十分なため,舌骨の最大挙上位および最大前進位における停滞時間が短かったと考えられた.
- 著者
- 飯村 大智 安井 美鈴 横井 秀明
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.354-368, 2017-12-15
言語聴覚士(以下,ST)を目指す吃音者にとって,吃音の問題は様々な障壁となり,ST養成校における支援が求められる.本調査ではST養成校における吃音者の困難・配慮および吃音STの実態調査を質問紙法により実施した.ST養成校に在学経験のある吃音者27名(男性22名,女性5名,平均年齢29.0±5.3歳)からの回答が得られた.回答者は,臨床実習や検査演習での検査の教示,授業での音読,就職活動や入試での面接など,様々な場面で困難を感じていることがわかり,「吃音の認知」「吃音の理解」「吃音を考慮した評価」「代替手段の利用」などの配慮を必要としていることがわかった.自身の吃音を契機に養成校に入学する者は多いものの,入学後に吃音領域の少なさを知る者も多かった.教員などへの相談により心理的にプラスの影響があったり,環境整備が行われる例も多くみられたが,教員へ相談ができない例もあり,教員の積極的な吃音学生への介入が求められる.
- 著者
- 水野 奈緒美 川崎 聡大 後藤 多可志
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会 ; 2004-
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.150-158, 2012
1 0 0 0 リッカム・プログラム導入後に改善した幼児吃音の1例
- 著者
- 坂田 善政 吉野 眞理子
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.77-86, 2016-06-15
吃音を主訴として来院した3歳8か月の女児に,環境調整法による指導を約4か月間行ったものの吃音が持続した.その後リッカム・プログラムを導入したところ順調に改善し,導入後6か月でStage 2に入り,その11か月後にはStage 2を終了した. 本症例の経過から,(1)リッカム・プログラムは本症例に対して一定の効果があったと考えられること,(2)まず環境調整法を一定期間行い,それに続く形でリッカム・プログラムを導入した点が本症例には有効であったと考えられること,(3)リッカム・プログラムの重症度評定尺度における“no stuttering”の日本語訳については「吃音とはいえない」という訳も考えられること,(4)Stage 1終了が近づいた時期には,保護者による重症度の評定値と臨床家による評定値の違いに対して,臨床家はより厳格になる必要があること,の4点を考察した.
- 著者
- 中村 達也 加藤 真希 雨宮 馨 鮎澤 浩一 小沢 浩
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.332-341, 2018-12-15
Angelman症候群(以下,AS)の児は,乳幼児期には哺乳障害や摂食嚥下障害を示し,学童期には未熟な咀嚼機能にとどまる場合が多い.しかし,離乳期AS児の摂食嚥下機能の獲得に関する報告は少なく,経過には不明な点が多い.今回,1歳から就学までの間,摂食指導を継続したAS児を経験した.症例の摂食嚥下機能の獲得時期を,粗大運動および認知・言語機能の発達の観点から診療録を後方視的に検討したところ,運動発達において四つ這い獲得後に舌挺出のない嚥下と捕食,伝い歩き獲得後に押しつぶし,独歩獲得後に咀嚼を獲得したが,口唇閉鎖が伴わず食塊形成は不十分であった.本児は定型発達とは異なり,運動発達が進んでから摂食嚥下機能を獲得したが,獲得された粗大運動は,両膝伸展位の座位や,手指屈曲位で手掌が接地しない四つ這いなど,定型発達とは質的な差があった.また,乳幼児期から口腔領域の感覚過敏が強く,就学前も感覚過敏は軽減したものの残存していた.
1 0 0 0 ペコぱんだ使用時における舌骨上筋群筋活動量の定量的評価
- 著者
- 大瀧 浩之 佐藤 新介 沖田 啓子 岡本 隆嗣
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会 ; 2004-
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.134-138, 2017
1 0 0 0 成人吃音の臨床
- 著者
- 坂田 善政
- 出版者
- 日本言語聴覚士協会
- 雑誌
- 言語聴覚研究 (ISSN:13495828)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.3-10, 2015-03-15
本論文では,まず成人吃音の臨床において有用と思われる評価の枠組みを提案した.この枠組みは,吃音の問題を「吃音症状」「環境」「本人の受け取り方(認知・感情面)」という3側面から捉え,これらに「合併する問題」を加えた4側面から評価を行うものである.続いて,これら4側面に対して行い得る訓練・支援について概説し,訓練効果に関する研究についても紹介した.具体的には,流暢性形成法や吃音緩和法,統合的アプローチ,認知行動療法,年表方式によるメンタルリハーサル法,セルフヘルプ・グループといったアプローチについて言及した. 言語聴覚士は,吃音に関する授業が教育課程の中に明確に位置づけられた唯一の専門職である.それゆえに言語聴覚士は,吃音について悩んでいる方がいればその方々を支援する責任があり,また可能な支援の形は数多くある.